GG(じいじい)です。
お盆も過ぎたら、少しずつ涼しくなってきた宮城です。
昨日、RS-1500の裏蓋を開け、カウンタのグリスアップと、
基盤の予防修理をしてみました。
(無理な体勢で作業をしたため、本日は、腰が痛いです。
これもGGだからでしょう・・・・)

早速、目についたのが、これ。
調整のところまでは印がありますが、
さすがに、検査後には、裏蓋まで再度開けないようですね・・・・。

いつものように、左上から右下の4枚を写真に撮ります。
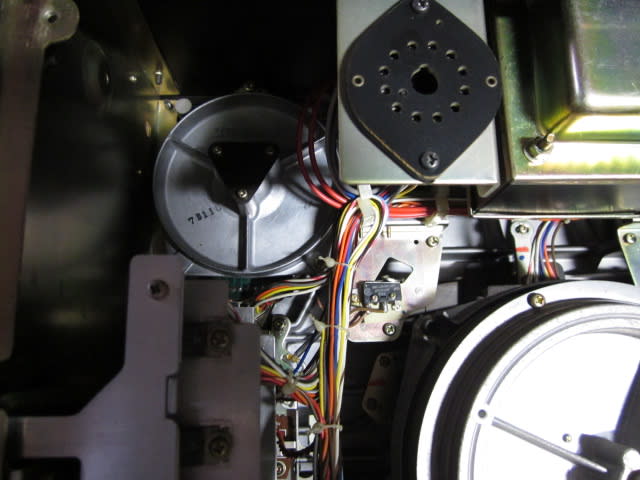
左下
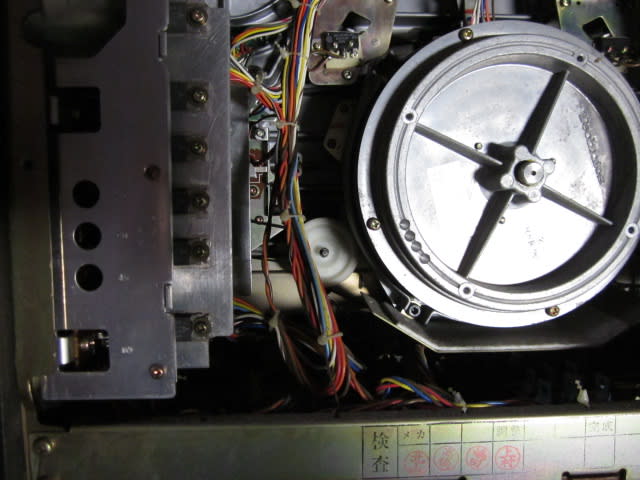
右上

右下
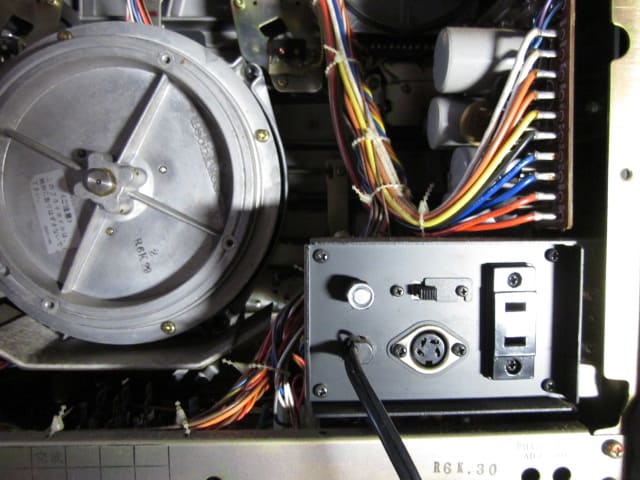
カウンタにたどり着くには、左側のPKGはずします。
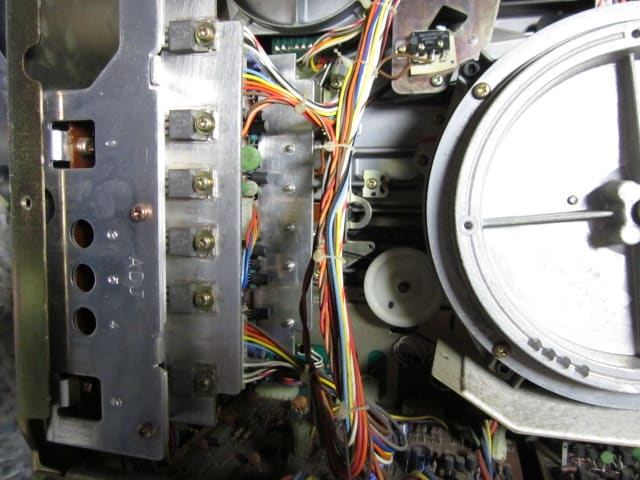
その奥に、このように鎮座しています。

ねじを4個はずすと、このように取り外しできます。
やはり、スカスカとなっています。
グリスを少し塗りましたが、その後、ギャーギャー音は出なくなりました。
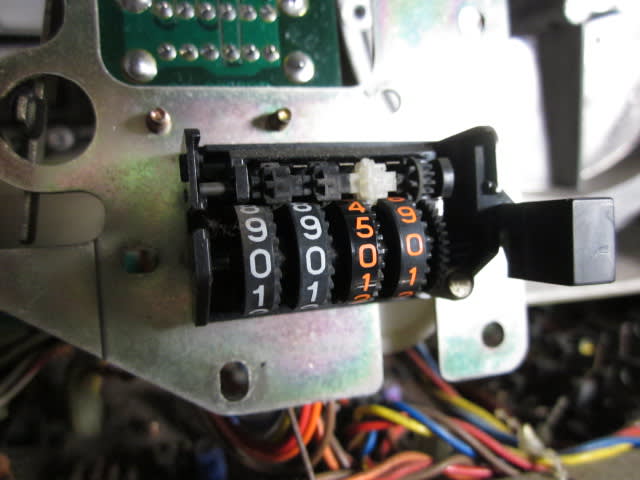
取り外したPKGを見ましたところ、
このように、メタボ状態の無極性コンデンサが
ありましたので交換しました。

●before
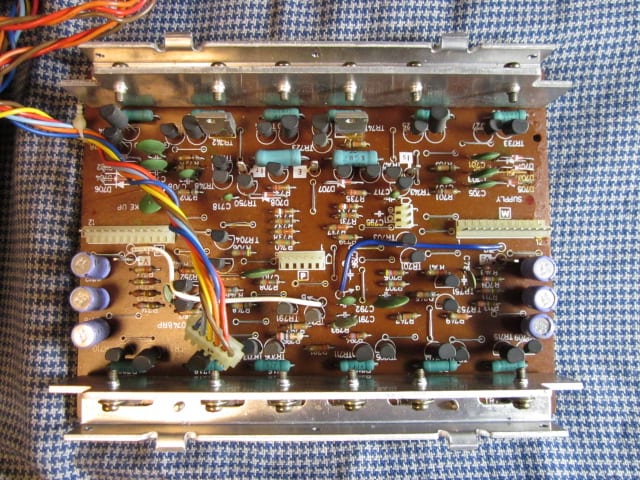
●after
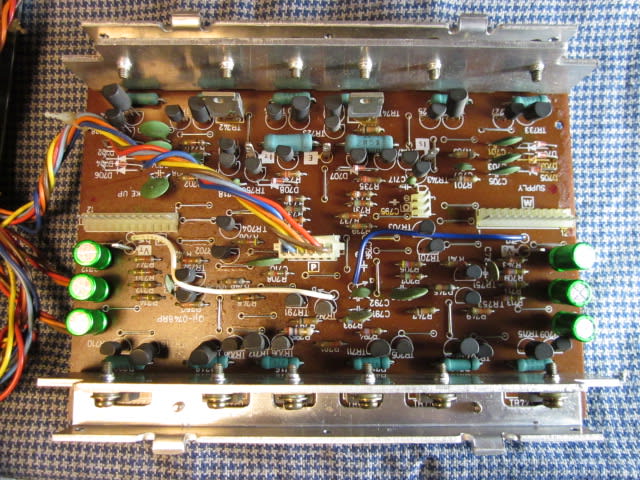
背中合わせになっている別なPKGも確認してみました。
こちらは、コンデンサが設計図と違っていましたので、
設計図どおりに、交換しました。
(基盤内の電解コンデンサを予防保全として、全部取り替えました)
設計図内のC892です。(実装47μ、設計図100μ)
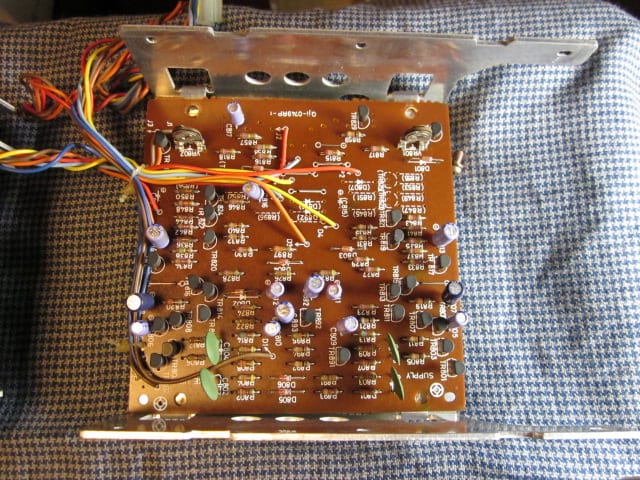
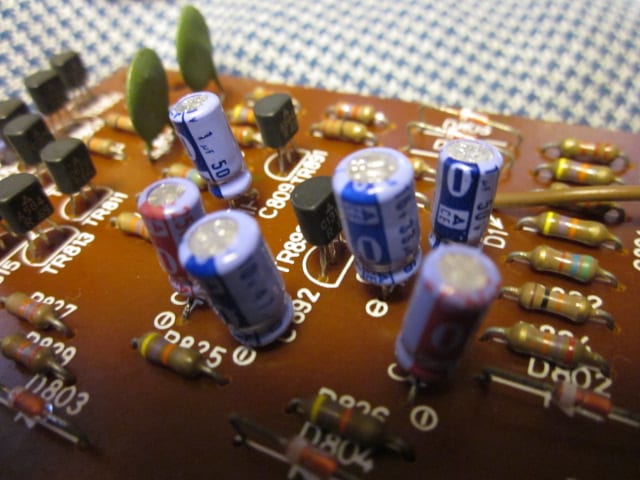

反対側(右側)にある電源PKGも確認してみました。
電解コンデンサを試しにはずして測定しましたが、
容量は問題ありませんでしたが、予防保全のため手持ちのものと交換しました。
(一番大きな、50V 2200μF以外、全て交換しました)
(35V 1000μF(2個)がなかったので、35V 2200μをつけておきました。)
●before

●after
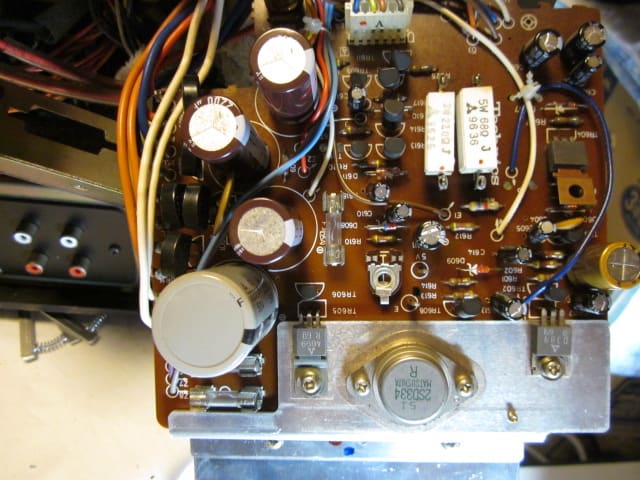
組み立て時に、カウンタユニットについている
CUE CUT用のスプリングを落としてしまいました。
買っておいた100円道具が威力を発揮しました。
(写真では見にくいですが、人目では探すことができました)
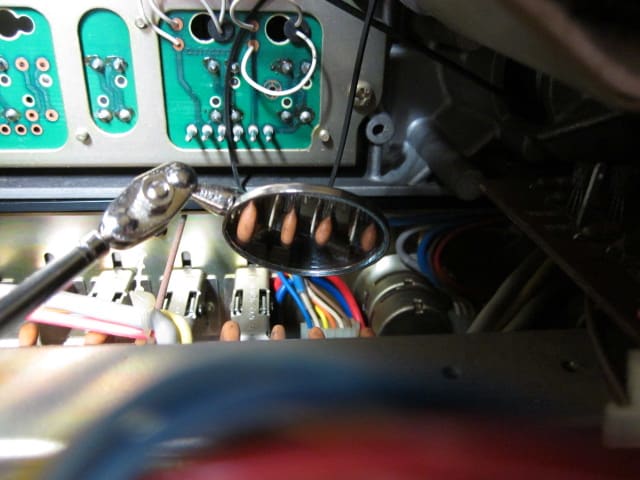
最後にタイラップで結束して終了。

久しぶりに大掛かりになってしましました。
このマシンですが、PKGを見ましたら、修理した履歴があるようで、
とてもきれいな状態でした。
(2、3回修理していると思われます)
雑感ですが、
①トランジスタはとてもキレイなので、そのまま使用。
(壊れたら、取り替える・・・)
②PKGの半田の状況は、クラックなど皆無の状態で心配なし。
③可変抵抗器もキレイで光っています。
④テスト用テープがないので、このまま使いますが、
やはり購入したいと思います。
(何か売らないと・・・・・)
※テープの音って、太くてずっしり聞こえるのでいいですね。
テープ、レコード、CDの順番でしょうか・・・・・。
(何の順番?? )
腰が痛い・・・。
-end-


















