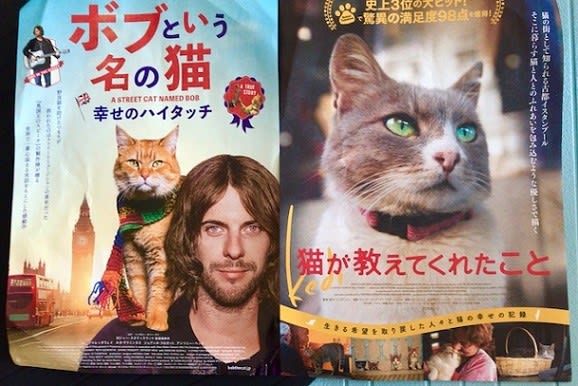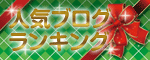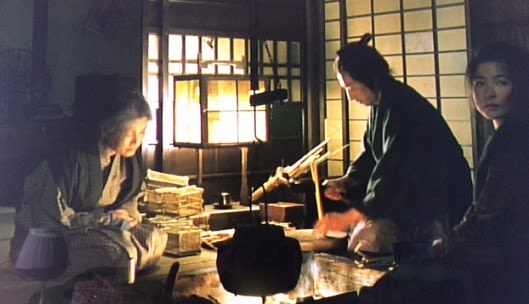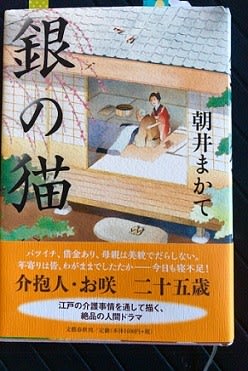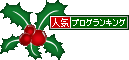4月6日
二週間限定の上映映画「クソ野郎と美しき世界」が公開された。
当日チケットは取れず、ようやく観れたのは公開11日目の月曜の夜。
平日の最終回なのに、最前列の席しか取れなかった。
映画の前評判は、なんだかパッとしてない感じ。
が、
映画っていうのは、
大きなスクリーンで、自分の目でシカと見届けると前評判と全然違ってた、、
なんてことが多々ある。
この映画は観ていくうちに、コレは映画だけど、、
ドキュメンタリー…と思えた。
稲垣吾郎・香取慎吾・草彅剛の三人のための。
4人の監督によるそれぞれの物語は、
観客に<オープンエンド>の結末をくれた。
観る側の想像力と察知能力に任せたメッセージのよう。
それは
とっても分かりずらい部分と凄く解りやすい部分と織り交ぜて、、ネ
多分、わざと。。。。。
◇トップバッターは園子温監督/稲垣吾郎 分かりずらさのカオス◇
エピソード1「ピアニストを撃つな!」
のっけからシバラクは、ヘンな園子温ワールド。
とにかく一貫して・・・・が続く。
観終わり、ホッとし、エピソード2~3に入ると、
エピソード1の??が、そういうこと!?という確信に変わる。
意味がないようで、煙に巻いた巧妙な揶揄か、、
そんな中で不変の稲垣吾郎。
金太郎飴のように切っても切っても、どこまでも吾郎ちゃんの存在。
コレは
敢えて分かりずらく仕上げてるとしか思えなかった。
観終わった後、なぜかエピソード1のナゾ謎に引きずられた。
まんまと園子温監督の罠にかかった。
◇エピソード2 山内ケンジ監督/香取慎吾◇
「慎吾ちゃんと歌喰いの巻」は今置かれてる現状を物語っていた。
警察の取調室で
自宅のアトリエで
そして街角で
香取君の表情が演技とはいえ、
SMAP解散の後遺症を抱えているようで、切なかった。
エピソード2は、
尾崎紀世彦「また会う日まで」と歌喰い女子のキーパーソン。
そして布石だらけ。
ここに沢山のメッセージを託し、ファンへ彼らの再生を誓っている。
そう感じたのは私だけではないはずだ。。
◇エピソード3 太田光監督/草彅剛◇
「光へ、航る」
草彅剛という人は、アップに耐えらえる数少ない役者だと知った。
巨大スクリーンいっぱいの草彅剛の表情は、映画を完全に支配していた。
眉に一本の白髪があることまでも、なぜか自然でカッコいい。。
SMAPの中で一番遅咲だった彼が、ダントツの実力を魅せた映画かもしれない。
◇エピソード4 児玉祐一監督/全員◇
「新しい詩(うた)」
元SMAPの三人のデモンストレーションと決意表明。。じゃないかと。
割り切れない気持ちは本人たちだけではなく、
二度と聴けない、、ファンにとって大きな穴に落ちた感じ。
あと一日で公開は終わる。
それもまた寂しいが、また会う日まで愉しみに待って居ようと思えた映画だった。