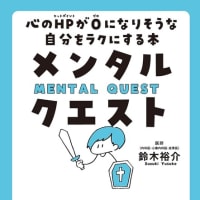今回の記事では、内科医である鈴木裕介先生が書かれた、「メンタル・クエスト 心のHPが0になりそうな自分をラクにする本」を紹介したいと思います。
ほんのつい最近に初めて読んだ本です。
鈴木裕介先生は高知大学医学部出身の医者です。

この本は「人生」への「攻略法」を説いているものですが、単なるハウツー本ではありません。
それはこの本に「決して『ラクして人生の困難を乗り越えるための方法』や『裏ルート』を紹介する意図はありません。」と書かれている通りです。
「生きづらさ」を抱える人の人生のコンパスのようなものにして欲しい、という「願い」を以て書かれた本である、という訳です。
この本の内容を詳細に紹介はしませんが、一部紹介します。
一番心に残った、というか心に刺さったのは「頭に巣食う『見えない敵』」の内の最大の敵・ラスボスとしてこの本に挙げられている「自己れんびん」という項目です。
自己れんびんとは「自分をかわいそうと思う気持ち」のことですが、もっとしっくりくる端的な表現は、「自己否定への酔い」です。「悲劇のヒロイン」という表現がありますが、自己否定にはアルコールやドラッグと同様の「酔い」の作用があります。
ものすごくつらい傷つき体験をした人が、その不幸さを呪いながら、不幸であることを自分のアイデンティティにしてしまう状態です。あまりにも不条理なことばかりが起こってきて、人生にポジティブな要素を何も見つけられない中での「私の不幸こそ、特別なものなのだ」という、ギリギリの自己肯定が自己れんびんなのです。
不幸のストーリーを生きることは、あらゆる不条理を回収してくれます。希望を持った状態から絶望の淵に叩き落されるよりも、絶望的な気持ちのまま不幸な出来事があったほうが、つらくないのです。不条理な出来事があるたびに、「ほうら、やっぱりね」とばかりに、自分は不幸であるというストーリーが強化されていきます。それが繰り返されれば、「自分の不幸は永遠に続く、特別なものである」と思うのも無理はありません。
つらすぎるから、「酔っていないとやってられない」ので、簡単にはやめられません。仮に不幸を抜け出せるような方法があったとしても、今の「不幸な生き様」を変えて生きていくことに不安があるため、飛びつけないのです。「常に不幸に片足を突っ込んでいるほうが安心する」と話してくれた人がいましたが、ある意味「不幸である必要があって、不幸でいる」という状態に近いかもしれません。それ以外の人生を生きたことがないのですから、他の生き方を想像することも難しいのでしょう。
と、このようなものですが、この「自己れんびん」によってあらゆる他の「頭の中の敵」が出現してしまい、それらが更にその人自身を、そして周囲のサポートしている人たちを酷く傷つける結果になってしまう、という訳です。
本人も周囲の人も全員が「一生懸命頑張っている」のにも関わらず、関わる人全員が不幸になってしまうというものです。
では、この「自己れんびん」の檻の中から抜け出すにはどうするか。
その問いに対して、この本では「セラピー」に対して正面から向き合う覚悟が必要になる、と書かれています。
「セラピー」とは「ケア(=回復魔法)」のような、表面的にも内包的にも「優しい」言葉とは異なり、「厳しさ」を前面に出しているけれども実は内包的には「優しい」接し方、と表現することができます。
この本では「黒魔法」のようなものである、と表現されます。
セラピーは、相手のために課題を指摘したりして、成長を促すような関わりです。課題と向き合い成長するには、この章で紹介している自分の中の「見えない敵」に気づき、自立のために戦うことが必要になります。そしてそこには、当然痛みを伴います。葛藤を前提としているからです。
すなわち、「自己れんびん」から抜け出すためにはこのセラピー・黒魔法を自分から引き受ける覚悟が必要になり、そしてそのためには「今、自分は本当に変わりたいと思っているのか」ということをしっかり考えて変わることが大切になります。
大事なのは、「これから、あなたがどうしたいか」ということだけです。
この「メンタル・クエスト」の本の紹介としては上記で終了とします。
非常に読みやすく、かつためになる本ですので、「生きづらさ」を感じている人にはぜひ読んでほしいものです。
さて、ここで私自身の話に少し移ります。
上記「自己れんびん」ですが、この本を読んで私にとても当てはまると思いました。
今まで何度も同じような間違いを繰り返しているのは、私の中に「変わりたくない」「過去の自分にすがりつく」「自分を変えられるはずがない」という想いが間違いなくあるのだ、と感じました。
この過去にすがりつく気持ちが私自身を苦しめていた元凶なのだと最近ついに気づいてしまった…。
さて、ここで少し「Re:ゼロから始める異世界生活」、通称「リゼロ」のアニメ第2期について少し書こうと思います。
「メンタル・クエスト」を読んで思い出したのが「リゼロ」第2期のアニメでした。
この第2期のテーマは「変わるということ」だと思います。
このリゼロ第2期のテーマについてはまた別の記事で書いてみようと思いますが、第2期には「変わっていく」人間の姿が描かれていると思います。
リゼロ第2期では大きくスバル⇒ガーフィール⇒エミリア⇒ロズワール・ベアトリスの順で変わっていきます。
それぞれ様々な問題を抱えている5人ですが、ガーフィールとロズワールは共に似ている「課題」を背負っていました。
ガーフィールは「変わることへの恐怖(作中では「外の世界への恐怖」と表現される)」を抱いており、一方でロズワールは「人は変わることができない、人間は弱いものだという信念」を抱いていました。
双方共に、「後ろ向きな姿勢」とも言えます。
過去にこだわる姿勢。
これは私自身のものと同じだと思います。
「変わることへの恐怖、人は変わることが出来ないという信念のようなもの」これは私が抱いている感覚そのものであると、「メンタル・クエスト」の本を読んで気づきました。
私は間違いなく、ガーフィールやロズワールと「同じ側の人間」であると気づきました。
今回は「メンタル・クエスト」の本を読んで感じたことをリゼロのアニメにも言及しながら書いておきました。
最後に、ガーフィールが「ロズワール側」から「スバル側」についた(寝返った?)理由としてガーフィール自身が言っている言葉を少し。
「弱い、弱い、そのまんまでいろ、って言われるより、お前は強い、必要だって言われる方につきたくなるのが当然だろうが」
と。
よく考えれば私は自分で自分を弱いままでいようと規定していたのかもしれない…そうも思いました。
では、今回の記事はこれで終了です。
またリゼロ第2期についてはいつか記事に書いてみようと思います。
今回も読んで下さりありがとうございました。