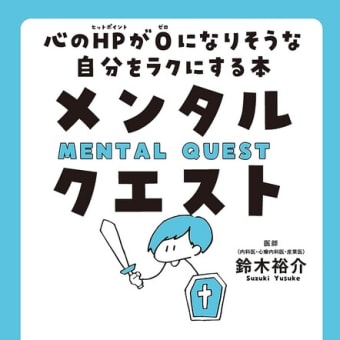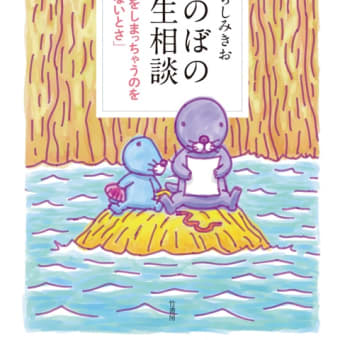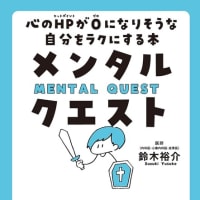前々から読もうとは考えてはいつつも、結局読んでいなかったものですが、今回年に100冊本を読むという計画を実行に移すに当たって、ようやく手にとって読んでみた、という訳です。
読んでみて、やはり有名な作品であるだけあって、名作であると感じました。
医学部に入ったのならもっと早くに読んでおくべきでした…。
もし医学部の学生でこの作品を読んでいないのなら、たとえ普段本を敬遠している人でも、ぜひ一読してみた方がよい、と思うような作品でしたよ。
テーマやあらすじなんかは言わずもがなでしょうし、知らない方はWikipediaでも見て頂いた方が僕の説明より分かりやすいと思うので詳しくは書きませんが、僕が最も感服したのはそのテーマ性もさることながら、作者の山崎豊子の徹底した取材力ともいえるものでした。
医学って、一般の方(医療従事者以外の人)にとっては非常に馴染み深いようで、馴染みのないものなので、そこにテーマを設定してあれだけの作品を書けたのは本当にすごいと思います。
まあ、古い作品なだけあって医療の常識は全く今とは異なるものだと感じましたが。
また、取材力以外にも、財前と里見という、対照的ともいえる生き方をしている二人をしっかりと描けている、という点でも「白い巨塔」はよくできているという風に感じました。
このような、社会的なメッセージ性が側面としてある作品というのは、文学作品としての意味を失って、その主張だけが前面に出てきて話が面白くなくなってしまう、ということがありがちなのですが、この「白い巨塔」はそうはなっておらず、純粋に作品として楽しめるという風に僕は思います。(中学生のころ、海堂尊の作品を追っかけて読んでいましたが、途中から作者の主張が前面に出てき始めて、それから読むのをやめてしまった記憶があります。今は医学生として、また読んでみたいとは思っているのですが。)
さて、「白い巨塔」のように、医者の世界がいまだに旧態依然としている…かどうかは僕のような(優秀ではない)医学生には到底解ることのなく、また関係のない処です。(今は医局制度ではなくなっているからこんな話はないのでしょうが。)
そして、今はそんなことを考えている前に目の前の勉強に集中すべきであり、また、その辺りの実態は後々知ればよいことなので当面のところはその点はそこまで興味はないです。
しかし、この作品を読んだ人に聞いてみたいことがあります。
それは、財前と里見、どちらがより好きか、ということです。
僕はちなみに財前でした…汗。
なんだか、里見は理想を語っているだけのように見えてしまい、なんだかその部分が、僕自身と重なってしまったのです。(もちろん、里見は僕のような学力の足りない人間などとは違って、勉強家であり、研究熱心でかつ臨床医としても優秀な人間であるので、重なったのはその部分「だけ」ですが)
それと比較して財前は、苦学をしつつ母親に仕送りをしながら、単に理想を求めすぎるのではなく現実に即した行動をしているように僕には見えたのです。(当然、里見の場合と同様、本当は僕なんぞと財前を比べてはいけないのだが、もうそこは勘弁してください。)
つまり、財前には自分にはないものを感じて憧れを抱いたのですが、里見には自分と同じ部分を感じて、嫌気がさしてしまった、という訳です。
僕にとっての一つの理想の人間像というのが、人に嫌われることは厭わず、自分の弱点は本当に自分の信頼する人だけに見せて生きていく、というものである(これは現実の僕がそうではないからですよ)ので、財前は僕には魅力的な人物に写ってしまったのかもしれません。
まあ、里見も芯がある人物であり、色々な面で魅力的な人間であるとは思うのですが。
このように考えて、僕はより財前に魅力を感じたのですが、みなさんはどうでしょうか?
それにしても、あの財前の最期は、本当に泣けます。
長くなりましたが、読んで下さりありがとうございました。
最新の画像もっと見る
最近の「本」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事