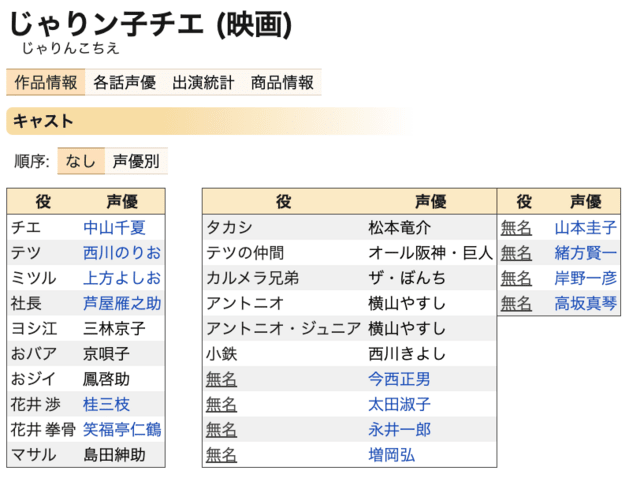徹底的な大阪弁と登場人物が常用する独白に笑わされ、大人より子どもが大人らしく、猫が人間より人間らしく、猫の目のように移り変わる視点が物語世界に奥行きを与えているこの作品は近来、出色の通俗・大衆・娯楽・滑稽小説のひとつと言い得よう
井上ひさし「見晴らしのよい叙事詩」(「文芸時評」『朝日新聞』)
ナカタは昔、とある大真面目な場で「最も影響を受けた本は」と質問され『じゃりン子チエ』だと即答したことがある。
『じゃりン子チエ』の世界──いったい誰がいちばん力を持っているのか、その関係図は「クラインの壺」のようにループし、この私たちの暮らす資本主義社会が「自転車を漕ぐようなモノ」と喩えた著名人がいたが、そこから最も遠くにある世界。
その著者、はるき悦巳先生が24年ぶりに、画を描き下ろされたという。しかも懐かしの「パインアメ」とのコラボで。

https://osaka.style/news/17252/?fbclid=IwAR2_3MvCsMnQIvUzzqTtlt2DplbgNWXLGjPhH_vfeAZwR91swbP8OCTQxT4
連載が終わったのは1997年のちょうど今頃。
広島で、末期癌で他界しようとしていた母親の病院に向かう道端の小さな本屋で、最終回の『アクション』を買った。
連載開始が1978年。ナカタが小学生になった頃。中学では本屋で万引きして連れ去られたヤツもいたし、高校では何人もの友達の家には、全巻が揃えられていた。わたしも同様。
大学時代には、関西での日常会話では必須である、話にオチを持ってくることのために、『チエちゃん』での有名なセリフを覚えておくことが、わたしたちの「教養」だった。
大学院時代には、関西以外の大学から入ってきたフレッシュ大学院生は、「どういった本をまず読んでおけばいいのですか」とまず読まされるのがこれだった。
博士課程を終えようとする頃、わたしにとっては長い長い下積み時代の終わりは、母親の人生の終わりの予感と、新たなこれからのモノ書きとしてのはじまりでもあり、連載終了はそれをシンボリックに色づける「事件」だった。広島大学附属病院で、もはや末期ガンでのモルヒネの打ち過ぎで意識のない、母親のベッドの横で、わたしはこの『じゃりン子チエ』の最終話を、映画のエンドロールを一行一行読むかのように、そこに至るさまざまな場面を思い出しながら、避けようのない終わりを噛みしめていた。