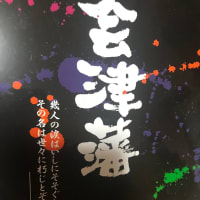住民集会型議会とは、
地方自治法89条では普通地方公共団体に議会を置く、と定めている。
町村は条例で第89条の規定にもかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設ける事ができる、94条前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する(95条)この法文を読めば分かるように都道府県や市では認められていないが、町村に限っては議会を置かず、有権者による町村総会で代用出来る、
とある。
西山村議が提唱した「住民集会型議会」構想は「超村議会」の一つの具体例と言えよう。すなわち現在の議会を廃止した上で、外部監査を置き、住民グループなどで組織する「住民集会型議会」で予算執行案などを、議論し、決定していく。
因みに、議会を置かず町村総会で代用していた例があるかどうか、総務省に問い合わせると、「現在はないが過去には2例ほどある」とのこと。神奈川県芦ノ湯村(合併して現在は箱根町)が、昭和22年まで、東京都宇津木村(同八丈町)が、昭和33年まで、それぞれ町村総会を設けていたのだという。
更にインターネット、ウィキペディアによると、長野県王滝村が財政危機を理由に、平成18年に、町村総会設置の動きがあったが、議会で否決されたため実現に至らなかった、と、言う記述がある。
ともかく制度上は町村に限って議会を廃止する事ができるのである。ただ、それを実現するには議会の可決が必要となり、「権益」と化している議会(議員)が自らその道を選ぶとは思えないから、かなり難しいだろう。それは王滝村の例を見れば明らか。しかし、西山村議がそれを承知でしかも現役議員でありながら、現在の議会を廃止するための勉強、運動を今後の議員活動の柱にしたいという。その意思の表れが本誌の寄稿というわけである。
本誌は県内の自治体の個々の各種事例を取り上げる中で、幾度となく地方議会を「無駄飯食い集団」と評してきた。もちろん、そうでない議会もあるが、いずれにしても「地方議会の報酬はそれだけでは生活できないくらいの金額が好ましい」というのが基本的な考えである。と、いうのは、議員専業だと落選したら「職」を失うことになり、その場合、生活に窮してしまうから、結果として次の選挙に不利になら内容、敵を作らないよう、当たり障りのない活動に終始する恐れがるからだ。
議会を廃止して住民総会を設置するというのは、そこから更に進化した形である。
王滝村のように、財政危機だからという後ろ向きの理由ではなく「自分たちが住む街の予算の使い道などを自分たちで審議する」という前向きな理由で実現に至れば、それが本当の住民自治となる。そういう意味では、同制度について議論してみる価値は大いにあるだろう。更にこうした議論が広がれば、現職議員は危機感を抱き、議会のあり方を、もう一度考え直すはずである。それだけでも大きな成果だ。
いずれにしても、地方議会のあり方を再度見詰め直す一つのきっかけになればと思う。
政経東北 2010 4月号