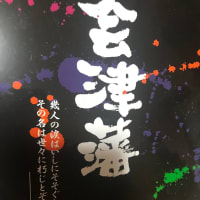(会津、鶴ヶ城)
恩讐を超えて、は因縁の戦いを繰り広げてきた、会津藩と長州藩のわだかまりを解き、お互いの憎しみその怨念を取り払い、和解を願うというものでした。
私は霊的感覚から、この怨念の波動が現界社会に良くない影響を与えていることを感じ、霊的和解の実現に向けて活動を始めたのです。
そのきっかけをいただいた山口にも足を運ぶその中で会津藩の頑なな心情が和解を阻んでいるのかもしれないと思い、新たな発見を求めて何度か会津、鶴ヶ城、飯盛山に向かいました。昨年11月鶴ヶ城近くのコンビニでコーヒーを求め、何気なく書棚を見ると、会津藩関係の書籍が、、、。
その中で、これだ!と思った一冊を求め早速目を通してみました。
偶然にして必然、否それは神に導かれた必然、、。この価格にしてこの内容、巷に並ぶ歴史書とは違って資料情報提供、協力先の公的機関の多さに、真実に近い会津藩史であると確信しました。
ザッと目を通して、
巷に流布されている会津藩史、戊辰戦争が如何に虚偽と偏見に満ちていたものかが分かり、
会津藩の怨念の深さは、国内外に言われなき朝敵の汚名を着せられ流布された事に対する悔しさが根本にあることを感じました。
世間一般には、何故、朝敵にされ官軍に追い詰められ開城に至ったのか、詳しくは知られていません。
白虎隊の悲劇が大きく取り上げられているその裏には、官軍にとって世間に知られたくない事実が隠されていました。
会津藩主は戦国時代から代々藩主が入れ替わっています。その中に伊達政宗もいますが、徳川家との微妙な関係から在任は長くはありませんでした。
その後徳川二代将軍の血を引く保科正之が(1643年)会津藩主となりました。
保科正之は教育にも熱心、神道、天文学、朱子学にも力を入れ「会津風土記」を作らせました。藩校を大拡張して「日新館」と名付け、この勉学熱心、真面目な侍の大集団として知られていきました。
黒船来航に露呈した徳川の弱体化で京の都は過激派の巣窟となっていた事で守護職を置く必要に迫られていました。
様々な角度から、勤勉で武士道に徹している会津藩が朝廷の守護職として信頼を得るに相応しいと、京都守護職に任ぜられました(1862年)。
当然、守護職より自藩を護って欲しいと反対の声もある中、
徳川宗家のために死を覚悟して京の地を踏んだのです。
時に徳川将軍家茂17歳、後見職一橋慶喜26歳、松平容保28歳。
28歳の若き会津藩主、松平容保は暗黒の都、京に入った。智略家達に翻弄されながらも一貫して「誠」を失わなかった。
新撰組の誕生もこの頃、、会津と新撰組の関係は微妙なものであったが守護職会津藩と新撰組は京都の治安維持に奔走しました。
京都という地は複雑怪奇、一筋縄ではいかない、守護職は多忙を極めていました。
薩摩、会津、長州、土佐藩、、
開国か、攘夷尊皇か、主導を巡り様々な思惑が入り乱れる中、慶応二年6月将軍家茂、12月光明天皇が亡くなります。
厚い信頼を寄せていた孝明天皇を失ったことは会津の悲劇の序章となりました。
慶応三年、幼い明治天皇を戴いて、いつの間にか薩長勢力が拡大して行く中、15代将軍となった徳川慶喜は自らが議長となって新しい議会政治を、との考えから大政を奉還する事になりました。
ところが、薩長ら反幕勢力は慶喜の想像を絶する謀略を考えていたのです。
岩倉具視主動の下に政権を幕府から切り離し、彼らの操る天皇の手に移す、というもので慶喜、容保の辞官納地を決定したのです。
会津藩士は憤慨、長州も憎いが友藩と思っていた薩摩の裏切りは更に憎く、会津藩士達は薩長の追い出しを進言しましたが慶喜は同意しなかったと言います。
そして慶喜は容保と定敬、老中を伴い大阪に向かったのです。
慶喜はその後をどのように考えていたのかはわかりませんが薩長は目的の為には手段を選ばない術に長けていました。
様々な事件が勃発、実は薩摩の計画通りに進んでいたと言います。その間坂本龍馬は襲われて亡くなっています。その後戊辰戦争に内戦が拡大していきます。
****** 孝明天皇毒殺説 *****
慶応二年(1866年)36歳で崩御。
孝明天皇の主治医の日記によると
慶応二年12月12日発熱、16日発疹、19日気脈(丘疹化)
命に別条なく24日、元気が出てきてあと数日でご回復。
25日朝の時点で疱瘡から殆ど快癒。
しかし、7つ刻(午後四時)天皇は急に苦しみだしました。
それ以降血便の下りつづける機械な症状に襲われ、午後十時崩御されました。
主治医の曾孫にあたるM氏は、この記述から
暗殺を図るものが「痘瘡によるご崩御にしたい、絶対失敗のない猛毒を入れた」と推理しています。
その実行犯は岩倉具視間接関係説が述べられています。
この毒殺説が定説となれば、
公武合体派の光明天皇を暗殺したグループが幼帝明治天皇をたてて薩長両藩に討幕の密勅(偽勅が証明されている)を与え暴走したというのが実態であった、と。
松平容保の悲劇は、京都守護職承認と同時に始動したと言って良い。
固く辞退する容保に対し将軍命令と称してほとんど強制的に就任させたのは
将軍後見職の慶喜と政治総裁職の松平春嶽である。
徳川慶喜公回想録の中で京都守護職は所司代などでは手に負えそうにない長州や薩摩を抑えるために設けたものであり、強大な兵力を持つ会津の容保を就任させた。
にも関わらず、「容保が会津が薩長両班に憎まれたのはその兵力が憎まれたのだ」などとまるで他人事のような口調で述べている。
誠実にして律儀な武人容保を、もはや身のかわしようもない悲劇の舞台ように強引に押し上げたものの心の痛みはなかったようだ。
京都における守護職松平容保は孝明天皇のから「その方精忠」との御製を賜るほどに信愛されたが帝の崩御を境にその運命が激変する。時勢は急転に次ぐ急転を続けた果て、慶応4年正月3日の鳥羽伏見戦争勃発となる。容保の不運はこの前後における最後の将軍慶喜の心理状態が不安定で振幅高低が甚だしかったことである。

(江戸城ー桜田門)
暮れ12月京都での薩長両藩の暴略に激怒した際も、二条城大広間で群臣を前に、
「必討」の気持ちを大書きしてみせ、断固戦う決意をしました。と思うとさっさと大阪へ退去してしまったし、今度もまた6日爆問総崩れの肺胞が向かう中で直ちに会津藩が反撃出動を要請したところ慶喜は自ら陣頭に立って反撃戦を挑むと宣言。
短期戦没しただ一樹となるも断じて充当にて止むべからずと激励したが、感奮した将兵が出撃の戦備に奔走している隙に信じ難い事をさっさとやってのけた。
なんと、それから数時間もたたない同夜、松平容保、定敬兄弟を殆ど詐術的に随従させ江戸に逃げ帰ってしまったのだ。そのために松平兄弟は藩臣を戦場に見捨てたという背信の思いに苦しまねばならなかった。そして新政府が自身の追封の大号令が下されたと知ると、松平兄弟の江戸城の登城禁止し、自分の身の安全を図ったという。
将軍に使い捨てにされ、追い詰められた容保は籠城する事一ヶ月、激闘の末ついに白旗を上げ落城した。
かって孝明天皇から「その方精忠」「頼みとするは会津のみ」とまで信愛された容保は朝敵の烙印を押されるとは夢想だにしなかったに違いない。
会津にとっての戦争は、第二次世界大戦ではなく戊辰戦争にあると言われています。
何故そこまでこだわるのか、
将軍に使い捨てにされ、朝敵の汚名を着せられ言われなき賊軍としての会津藩の処分があります。
ーーーーーー
戊辰戦争で、両軍に多数の戦死者が出て、この時官軍の将兵は丁寧に祀られたが、会津藩士及び一般の死体は戦争が終わってからも新政府民政局から「手を付けたものは厳罰」という令により無惨なまま捨て置かれ、鳥獣の食い荒らさすに任された。
この非情な取り扱いには武士道などまさに皆無であり、あまりの処置に多くの会津藩士は怒りに燃えた。
一部の藩士は民政局に戦死者の弔いを願い、明治2年2月、死体の埋葬がようやく許可されるが、これも普通の戦死者として扱う事は固く禁じられ埋葬地は古くからの罪人塚、作業にあたるのはやはり罪人の埋葬に当たってきた人々に限定された。
民政局は会津側の訴えを聞き埋葬地については阿弥陀寺と長命寺に変更するが遺体の扱いには厳然として口出しを許されなかった。
死体の扱いについては丁寧とは決して言えない有様だった。ムシロ、箱や風呂桶、戸棚などに一緒に押し込んだものをそのまま大きな穴に投げ捨てる。
作業にあたる人々にとっては望またる仕事でありさっさと終わらせてしまいたかったのであろう。丁重に埋葬してほしい会津藩主らはそう願った。
苦労の末、墓標が建てられたが、これも即刻撤去を命じられ、以後どんなに懇願しても許されなかった。戦死者の魂に香華をたむけることを禁じられたのである。
この時の怒りは怨念として永く生き続けていくのである。
時が幾重に過ぎても、昇華されない恨みを抱いて死んで行った旧会津藩士は多い。明治六年墓標を立てることを許されたが賊軍の墓という見方は依然として変わらず墓標は「戦死者」に限定された。
その三文字は西軍が会津に刻み込んだ苦衷の証として、今も変わらず残されている。
ーーーーー
新政府になって
四月、藩士その家族を伴いさいはての青森斗南の移住が始まった。
恐山近く斗南についた彼らは愕然とした。
そこは火山灰で覆われ荒涼とした風雪厳しい所、藩士らは流刑に近い処遇を思い知らされた。
******
以上は「会津藩」の中で述べられたほんの一部ですが、
最近になって、光明天皇暗、明治天皇すり替え説が定説となっています。
会津藩の抵抗を阻止する為掲げた錦の御旗は偽物、
明治維新は薩長のクーデター、という説もあり
最近になって歴史の見直しが盛んに言われています。
果たして、
明治維新の真実が明かされ、
会津藩の汚名の返上される時が来るのでしょうか?
2023 6/4