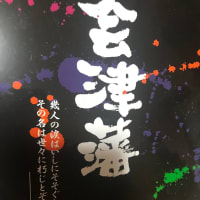さくら紀行(5)
夏の道ーー幻の軍医さんを訪ねて
陳先生、その後お元気でしょうか。
大学周辺の若葉も
初夏の日差しにひときわ美しく咲いていることでしょう。
そのような季節の中、不慮の事故で、
最愛のお母様を突然に亡くされました先生のご心情、
いかばかりかとご案じ申し上げます。
お母様が生涯かけて探し続けられました命の恩人、
元日本軍軍医さんのご存命とご所在が、
やっとわかる旬日前のご逝去は悲しみにて余りあります。
先生から送られてきましたご生前(2年前68歳)のお母様の写真、
気品のあるお顔、微笑まれている口元からは、
「編集長ありがとうございました」と、
今にも感謝の言葉がこぼれているような気がして、
私の悲しみもいっそう募ります。
しかし、いつまでも悲嘆に暮れていても、
かえってお母様の霊に報いることにはなりません。
私は3月22日兵庫県篠山町に、
前川元軍医さんをお訪ねすることにしました。
大阪から福知山線で約1時間、篠山口駅下車、
駅改札口まで迎えてくださった前川先生。
70歳とはとてもをお見受けできない、
背筋をしゃんとのばされた偉丈夫な、
元軍人らしい凛とした雰囲気の方でした。
前川先生は今も、お近くの湊川女子短期大学の教授として
日々ご活躍です。
朝早く起きられ10キロ余りのジョギングをこなされ
大学では若い女子学生といつも歓談されて、
健康維持に努めておられるとか。
先生よりずっと若い奥様が運転してくださるお車で
ご自宅に伺いました。
街外れの静かな田園の中にある瀟洒なお宅の庭には、
可憐な濃い紅色の緋桃の花と、五弁の丸まっちいボケの花がなまめかしく咲き誇っていました。
老鴬が一声澄んだ声で私を迎えてくれました。
「実は、、、」と申し上げながら、陳先生のお母様の不慮のご逝去のことが、
私にはなかなか前川先生に切り出せませんでした。
しばらくのためらいの後、
私の報告に、前川先生も奥様も、一様に驚かれ、
やがて一言「それは残念なことです」と、
おっしゃられたまま、三人の間に長い沈黙の時が流れました。
ややあって、
当時、義烏市近郊に駐屯されておられた部隊の、
たくさんの人のスナップ写真や
幹部軍人の記念写真を見せていただきました。
「これが幡本、これが、黒坪少尉です。楼美翠さんの手術をしたのは多分幡本中尉ではないでしょうか。どちらにしても、
楼さんがこの写真をご覧になれば執刀した軍医が
わかるはずですのに、本当に残念なことです」
陳先生、たとえ再会はずっと後になったとしても、
元軍医さんがこのようにお元気でしかも遠いあの頃、
あの日を懐かしく思い出されているとの事実を、お母様に、
一刻も早くお知らせしたかった。
やんぬることではありますが、今もなお私の脳裏には、
果てしない悔いの情念が渦巻いております。
陳先生、先生や私たちがお母様のご意志を引き継ぎ、
これから日中友好のためのいっそうの努力をすることが、
今となっては唯一救われる道ではないでしょうか?
「さぁ篠山今日はちょっとした城下町ですよ、
編集長、案内しましょう」
ややあって、重苦しい雰囲気を救ってくださった、
明るい奥様のお声で、私たちは三人で街へ出かけました。
兵庫県多気郡篠山町人口約2万余名。
多紀連山に囲まれ、町の中央に位置する篠山城跡、
古い建物が大切に保存された町並み、
町外れの美しい竹林などを案内してくださった後、
昼食に名物「箱鮨」を美味しくいただき、
列車の時間を気にしながら、後ろ髪引かれる思いで、
いつか陳先生とご一緒に再訪することをお約束しながら、
篠山町を後にしました。
さて、当時、御地に駐屯していた前川先生所属の部隊、
独立歩兵第一二四部隊の大隊長、田辺元中佐殿のことは、
作家伊藤恵一氏の著書「かかる軍人ありき」の本の中で詳細に書かれていることがわかりましたので、
その本を本日お送りします。
田辺中佐は大戦に疑問を持たれ、
さらに日本の敗戦を予見され、
中国民衆に親しく親しく接することを要望されていたのです。
実は伊藤恵一氏は本誌「ふるさと紀行」の東京担当の詩人江島先生の文学の師でいらっしゃると言うことがわかり、
早速、矢島先生のご紹介で、氏に
田辺中佐のその後の消息をお聞きすることができました。
その結果、田辺氏は去る昭和55年の7月78歳でご逝去、
今は東京市ヶ谷に永眠されておられました。
しかし、田辺氏ご婦人よりお手紙を頂戴する
幸運に恵まれました。
ご婦人は現在上尾市にお住まいです。
お二人にはお子様がおられず、
今はお一人でひっそりとお暮らしの様ご様子です。
房子様とはお便りいただきました後、お電話で、
るるお話を伺いました。
田辺氏は生前「ぜひ中国を訪ねたい、その時はお前も一緒に」と、話しておられたご様子、
氏のお人柄が忍ばれる思いがいたしました。
なお,田辺氏は広島県上下町のご出身であることがわかり,
私は早速同町の町役場にお電話しました。
同町で、田辺家は旧家であり、由緒ある家柄、
ただ、氏は幼少の頃にこの町を出られ氏の幼、少年時代を
ご存知の方がなく、引き続き氏に関する消息は
町役場の〇〇さんにお願いしておきました。
、、、、、時が往く、時が往ってしまった。
今、私は流れていった歴史の足音にじっと耳を傾けています。
そして、戦争と言う過酷な運命の中で織りなされた、
美しい人間模様に、
今一度胸が締め付けられる感動を覚えています。
7月12日、古く貴国、唐の岐王が砕けた玉片を竹林にかけて風を採った「古風鐸」の伝来と言われる風鈴の音に誘われて、
私は九州の博多に、端本元軍医さんをお尋ねするつもりです。
当時の陳先生のお母様のことをご記憶くださっていれば
どんなにか嬉しいことでしょう。
先生からの謝辞、私から充分にお伝えしましょう。
ご報告をどうかお待ち下さい。
ごきげんよう。さようなら。
(季刊ふるさと紀行平成4年夏の号掲載)