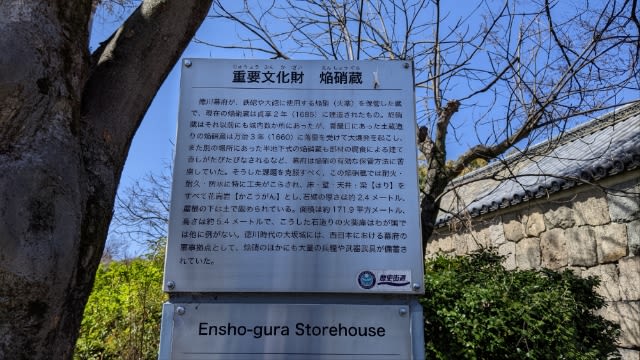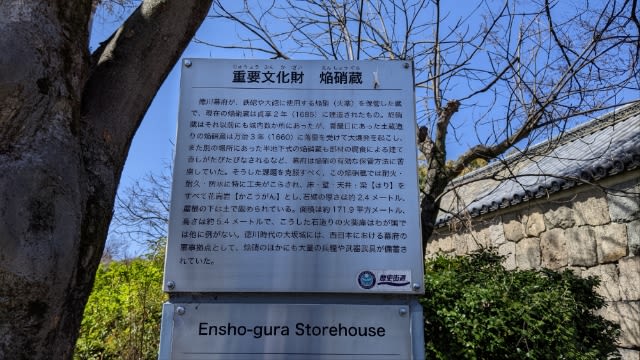そうそう。
 お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。
お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。
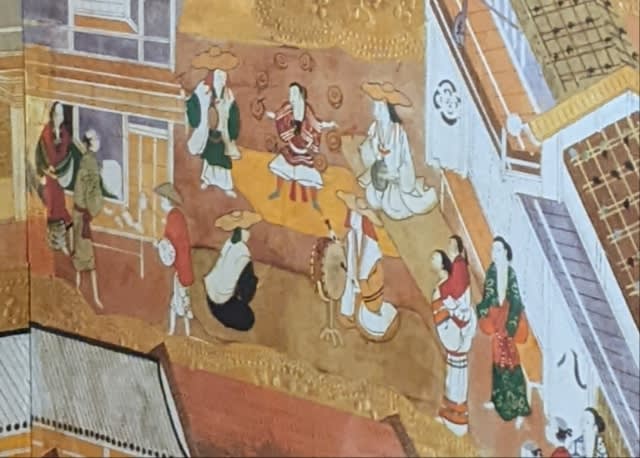 これ、何をしているんだろう?
これ、何をしているんだろう?
 左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?
左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?

お公家さん?となにかを運んでいる人夫さん。
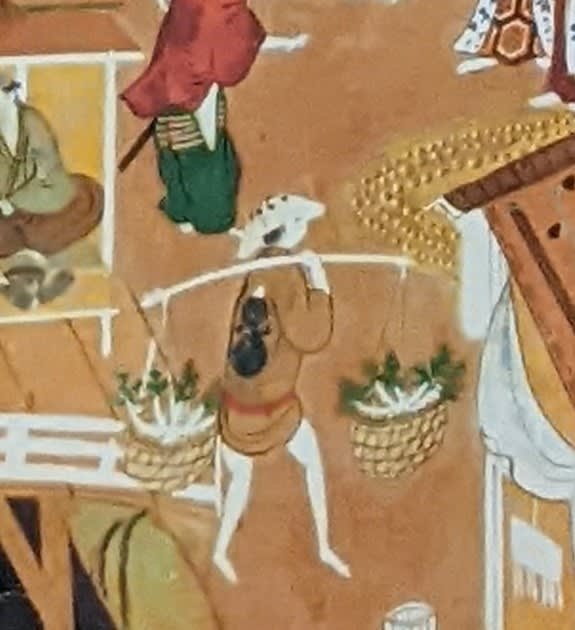
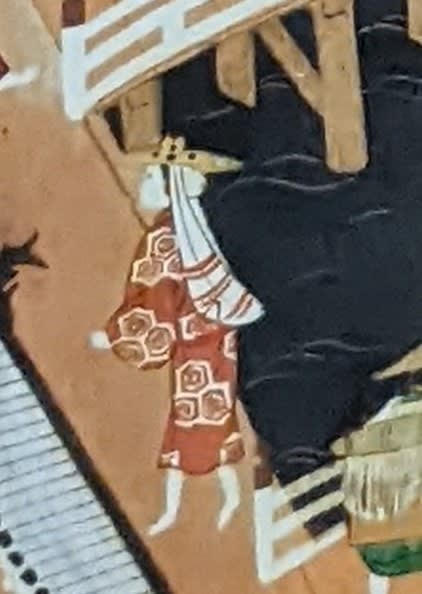 旅の女性?
旅の女性?
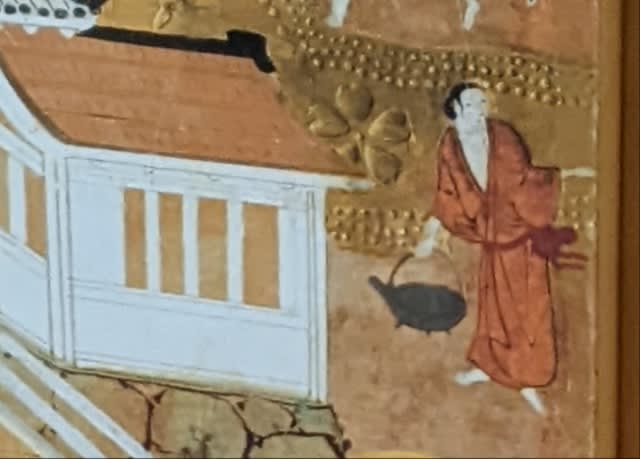 鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。
鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。 こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。
こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。
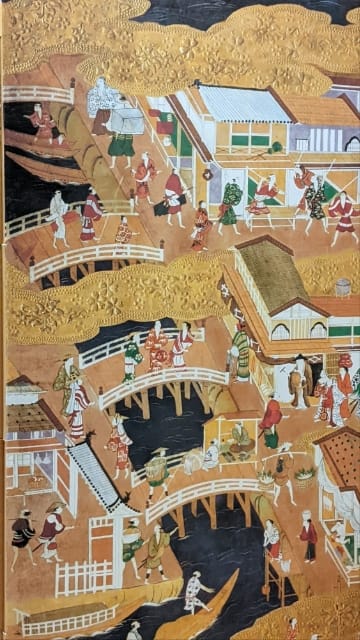
天守閣について書くのを忘れてた(笑)。
8Fからの眺めは良かったな!
あとは、大坂夏の陣の屏風。すごいな。細かくて。リアル。
歴史、あんまりわからないけど、わかりやすく説明が付いていて。
徳川と豊臣が戦っていて、豊臣方の大将が真田だったってことかな?
お城から担がれて逃げる、身分の高い女性。橋が落ちて、堀の中を渡って逃げようとする女性。
お城から、だいぶ離れたところまで兵がいて、いかに戦が広い範囲で行われたかがわかった。
戦って、お城だけですまないんだな。周りも巻き込まれる。
一方、オーストリアに渡っていた日本の屏風。
「豊臣期大坂図屏風」
これはコピーだけれど、十分きれい。城下町の様子がわかって楽しい。
 お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。
お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。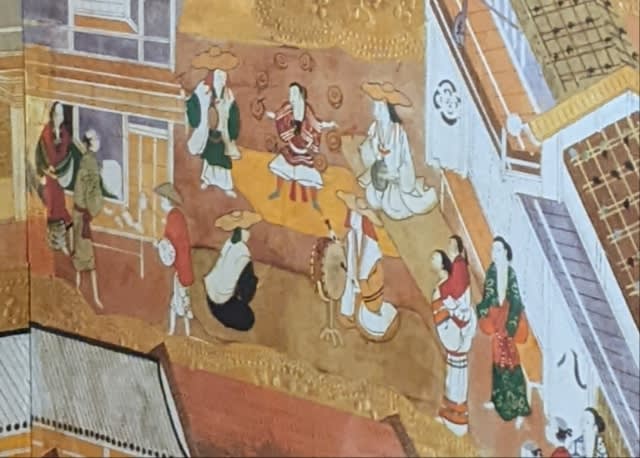 これ、何をしているんだろう?
これ、何をしているんだろう?太鼓叩いている人がいるんだけど。見世物?
 左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?
左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?
お公家さん?となにかを運んでいる人夫さん。
一番気になったのは、きもの。物売りとかはすごく短い丈のきものを着て、帯というより紐。
脚丸出し。通気性良さそう。
高温多湿の日本に最適!
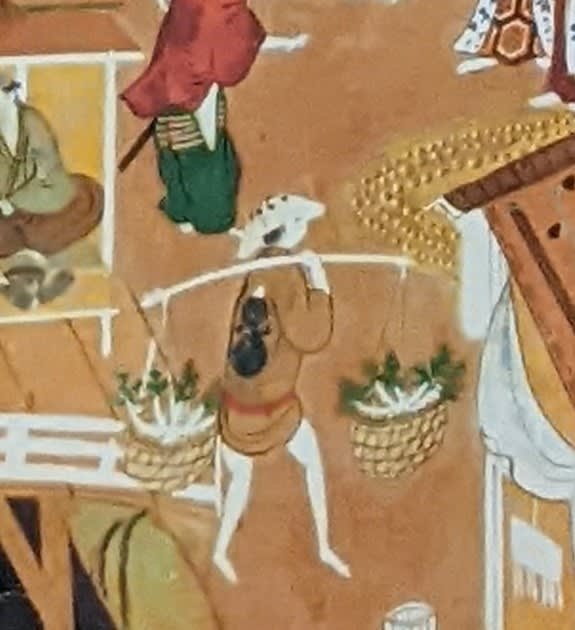
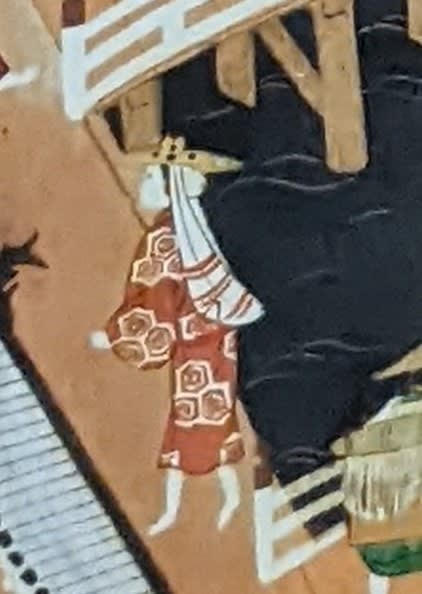 旅の女性?
旅の女性?きものの丈が短め動きやすそう。
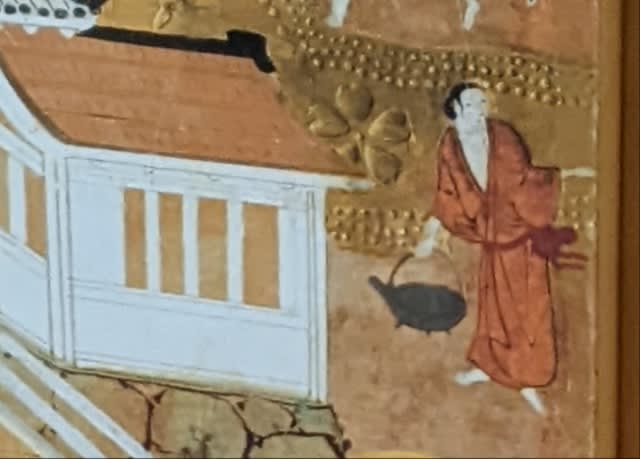 鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。
鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。かなりゆるい着かただと思う。腰の左で、かろうじて前がではだけないように紐で結んでいるように見える。
 こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。
こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。今のきものは、きゅうくつそうだけど、この時代のきものはいいなあ。
帯じゃなくて紐だし。
着かたもゆるゆる♪
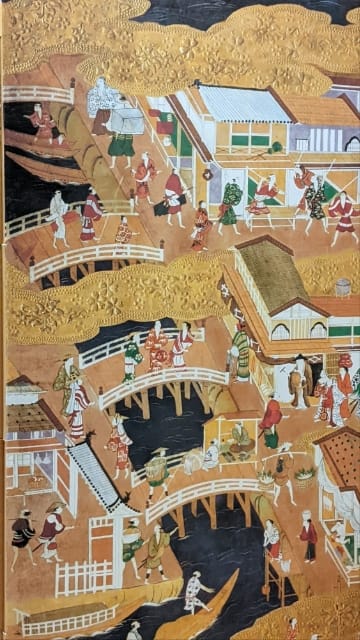
大阪城通い3日め。この日は京橋口から入った。


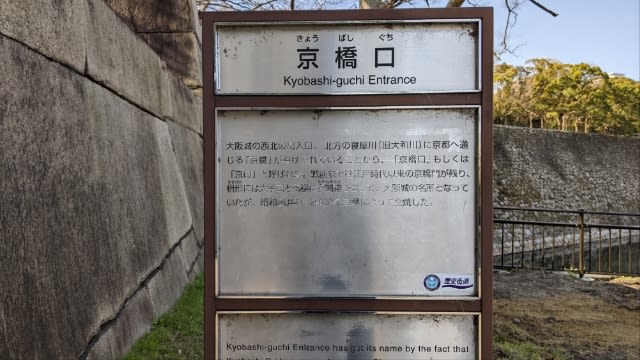
 京橋口から入って正面の石垣。
京橋口から入って正面の石垣。
 左側側面。
左側側面。

左側側面。

画面右側が正面。

 多聞櫓の石垣(たぶん)。
多聞櫓の石垣(たぶん)。
大手口枡形や桜門枡形にも負けない迫力の巨石。
因みに、初日は西外堀を通り、左手に乾櫓、千貫櫓を見ながら大手門から。
二日目は、大阪府警と大阪歴史博物館の間の通りから出て、南外堀と六番櫓を見てから大手門から。
さて、京橋口。


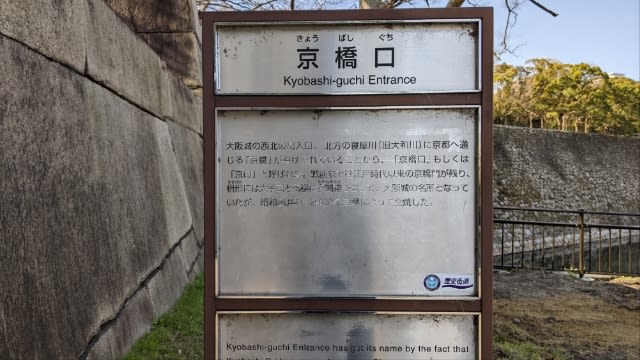
戦前までは門と多聞櫓が残っていたらしい。
見れないのが残念。
ここも枡形になっているのが、石垣を見るとわかる。
そして巨石も使われていて(鏡石と言うらしい)、壮観!
 京橋口から入って正面の石垣。
京橋口から入って正面の石垣。 左側側面。
左側側面。
左側側面。

画面右側が正面。

 多聞櫓の石垣(たぶん)。
多聞櫓の石垣(たぶん)。大手口枡形や桜門枡形にも負けない迫力の巨石。
力、入ってるな~!
ぐるっと見渡した動画を挿入したいのだが、できないのが残念。
それに今回は、青屋門と玉造門には行かなかった。
現存する櫓で見てないのは、一番櫓だけだが、
まだ見てない櫓跡も多い。
次回のお楽しみだね。
いや〜、正直、大阪城、こんなに楽しめるとは思ってなかったわ~!
今回の大阪城観光で興味をもったのが、仕切門。


天守下仕切門跡。ここも面白い。画面奥左側から、天守閣を目指して登ってくると正面に壁(石垣)!
特に
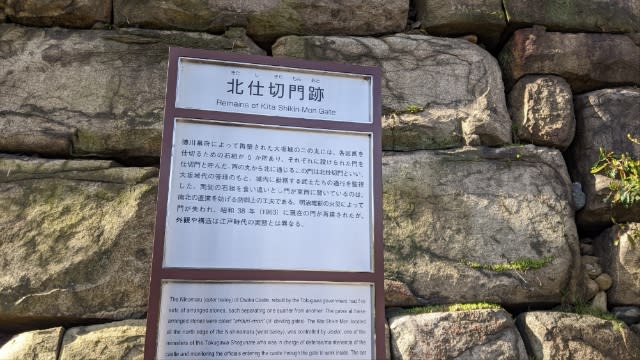
「門」のイメージって、その家の「格」を表すから、重厚な造りにするとか、目立つようにするものだ、と思っていた。

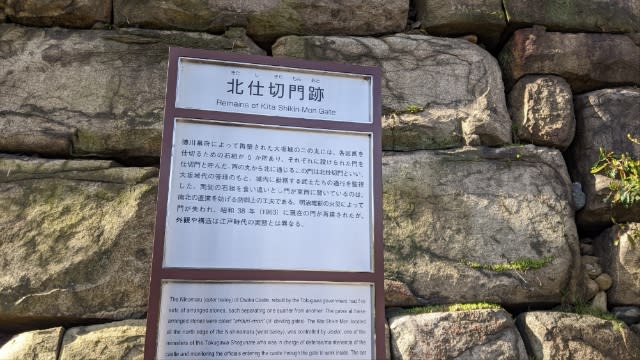
「門」のイメージって、その家の「格」を表すから、重厚な造りにするとか、目立つようにするものだ、と思っていた。
だけど、この北仕切門。道からちょっとそれたところにある。何気なく歩いていると、京橋口方向から来ても、極楽橋方向から来ても気が付かない。
私は、「何か道からそれたところで写真撮っている人がいるな~。なんだろう?」
と寄り道してみたら、門だった。
敵に見つかりにくくするため?
まるで門があるのを隠すかのような配置。
次に


天守下仕切門跡。ここも面白い。画面奥左側から、天守閣を目指して登ってくると正面に壁(石垣)!
行き止まり??
と思った。すると、右手に道(昔はここに門があったのだろう)。
しかも狭い。
(この写真は仕切門跡を通り抜けて、天守閣側から撮ったもの)
意地でも天守閣へ向かう敵を阻止するぞ、という意志が伝わってくる配置だね。
まっすぐには進ませない。
道が急に右に曲がれば、列も乱れるだろうし、門があればそこは渋滞するだろうし、仮にその門を突破したとしても道が狭くなればやっぱり渋滞する。そこを狙って天守閣から狙撃することも考えていたのだろう。
そんなことを、あれこれ空想させてくれた仕切門跡だった。
楽しい🎶
 重要文化財 金蔵(きんぞう)(または「かねぐら」「かなぐら」)
重要文化財 金蔵(きんぞう)(または「かねぐら」「かなぐら」) 床板の下は全面敷石にして、石と石の間は漆喰で固めて固定。
床板の下は全面敷石にして、石と石の間は漆喰で固めて固定。外壁は、なまこ壁。壁に貼りつける瓦と瓦の隙間を漆喰で盛り上げてある。防火、保温、防湿の効果。
窓は小さく、鉄格子がはめ込まれており、入口は三重で3回扉を開けないと中に入れないらしい。(「図説日本の城と城下町①大阪城」より)


 重要文化財 焔硝蔵(えんしょうぐら)
重要文化財 焔硝蔵(えんしょうぐら) つまり、火薬庫。
つまり、火薬庫。引火防止のため、壁・床・天井ともに花崗岩の切り石としっくいで固められた建物。窓はない。