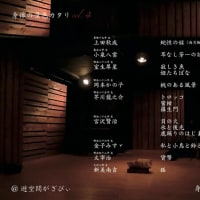六の宮の姫君の死の場面は朱雀門
朱雀門は 羅生門の対
北の朱雀門 南の羅生門(正確には羅城門)
また
六の宮の姫君の死の場面は晩秋
羅生門には初秋の季語キリギリスが出てくる
そして共に夕暮れ 雨止みという状況
秋の始まりと終わり
平安京 夕暮れ 雨
それぞれの門に雨止みをする者たち
南の羅生門で下人は
生きるため 盗人になり
北の朱雀門で姫君は
静かに 死を受け入れる
この対比…
この対比を「遊び」と表現してしまうのは軽薄であろうか
しかし姫君の死を朱雀門に置いた時
芥川の脳裏に羅生門との対比が軽やかに浮かんだように思える
「羅生門」は芥川が帝大在学中に書かれている
これから文壇をのし上がろうという野心さえタギル若き芥川(これは僕の想像)
その意気揚々たる心は下人に表れていると捉えることも出来よう
当時の失恋が影響しているらしいとの説もあるが…
「六の宮の姫君」が書かれたのは大正11年
芥川 自殺する5年前…
「或旧友へ送る手記」の中にある
『将来に対する唯ぼんやりとした不安』が忍び寄りはじめていたろうか
「或旧友へ送る手記」の中には こんな一節も出てくる
『我々人間は人間獣である為に動物的に死を怖れてゐる。所謂生活力と云ふものは実は動物力の異名に過ぎない。僕も亦人間獣の一匹である。しかし食色にも倦あいた所を見ると、次第に動物力を失つてゐるであらう』
この芥川の言葉は 僕の中で「六の宮の姫君」と深く結びつく
そう
姫には「生きる」という人間臭がない
精神の意思の有無云々より
そもそも肉体が希薄なのだろう
死への恐怖然り 食然り SEX然り…
細胞に刻み込まれた根源的衝動
この主題「更地」とも重なってくる
ふおぉぉ…
いやはや
いやはや
【語り 配信中】
珠玉の短編 声と音 想像力が織り成す豊かな物語を是非
⬇⬇⬇