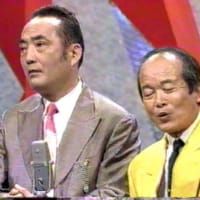ナスカの地上絵、、、懐かしい言葉が夕刊記事にありました。(^。^)
南米ペルーの世界遺産にも指定されており、世界の七不思議とも言われる古代の遺跡です。(^-^)
いったい誰が何の目的で、数十メートルから数百メートルにも及ぶ巨大な地上絵を描いたのか、、、٩( ᐛ )و
小学校の頃、図書館で読んだ「世界の七不思議」(だったかな?)なる本にあった、この地上絵に心を奪われてしまった身としては、夕刊記事に釘付けとなりました。m(__)m
記事は、現代らしく、最新のテクノロジーである「AI」を活用した解析結果で、驚くべき件数の新発見が掲載されていました。(^。^)
以下、ネットより引用しますと、、、
人工知能(AI)による航空写真の解析を基に、南米ペルーの世界遺産「ナスカの地上絵」を新たに303点発見したと、山形大などの研究チームが発表した。
過去1世紀で見つかった430点から大きく増え、その分布から地上絵の制作目的も明らかになってきた。論文が24日、米科学アカデミー紀要に掲載された。
同大によると、地上絵は東京23区の半分あまりの面積に相当するナスカ台地(約400平方キロ)に点在しており、人力で探すと膨大な時間がかかっていた。
そこで2018年からAIの活用を試み、地上絵の特徴を学習させたうえで航空写真を解析。これまでの実証実験で4点が新たに見つかっており、今回は1309か所で地上絵の候補が示された。
うち341か所を22年9月から約6か月かけて現地調査。1か所で複数の地上絵が確認されたり、候補地の付近でAIでは示されなかったものも見つかったりして、303点の発見につながった。発見までの時間が短縮され、調査研究が大幅に効率化された。
地上絵は紀元前100年頃~紀元後300年頃に作られ、地面に線状に描かれた「線タイプ」と、地表を削って凹凸をつけるなどした「面タイプ」がある。代表的な「ハチドリ」や「クモ」などの地上絵は線タイプで、50点が確認されている。大きさは平均約90メートルと、大型なのが特徴だ。
一方、今回見つかったのは全て面タイプだった。大きさは平均約9メートルと比較的小さく、これまで発見が難しかったとみられる。
人の形や頭部を模したとみられるものが約8割を占め、ラマのような家畜や、「ナイフを持ったシャチ」(写真)のような地上絵もあった。
チームの坂井正人教授(考古学)は「今回の地上絵は、(住民が日常的に使う)小道沿いに多く分布している。当時は文字を持っていなかったため、儀式や家畜に関する『掲示板』のような情報共有の役割を果たしたのではないか」と分析している。
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
世界の七不思議、、、当時の記憶では、ナスカの地上絵のほか、イースター島のモアイ像、魔のバミューダ海域、インカ帝国の滅亡、ムー大陸の謎、などがあったと思います。(^。^)
しかし、かつては科学技術の粋を集めても解き明かせなかった地上絵の謎が、人工知能によって明らかになってくるとは、、、テクノロジーの威力に脱帽ですね!!(◎_◎;)
「AIに正体訊くや枯れ芒」 祖谷馬関
(注)枯れ芒は冬の季語。「幽霊の正体見たり枯れ尾花(芒)」と言われる。枯れ尽くした芒。葉も穂も枯れ果て、茎の部分が風に揺れる姿は寂寥感の極み。枯れ尽くした芒も野原一面に群れると美しくもある。雪や風の中に見るのも風情がひとしお。芒は秋の季語。
南米ペルーの世界遺産にも指定されており、世界の七不思議とも言われる古代の遺跡です。(^-^)
いったい誰が何の目的で、数十メートルから数百メートルにも及ぶ巨大な地上絵を描いたのか、、、٩( ᐛ )و
小学校の頃、図書館で読んだ「世界の七不思議」(だったかな?)なる本にあった、この地上絵に心を奪われてしまった身としては、夕刊記事に釘付けとなりました。m(__)m
記事は、現代らしく、最新のテクノロジーである「AI」を活用した解析結果で、驚くべき件数の新発見が掲載されていました。(^。^)
以下、ネットより引用しますと、、、
人工知能(AI)による航空写真の解析を基に、南米ペルーの世界遺産「ナスカの地上絵」を新たに303点発見したと、山形大などの研究チームが発表した。
過去1世紀で見つかった430点から大きく増え、その分布から地上絵の制作目的も明らかになってきた。論文が24日、米科学アカデミー紀要に掲載された。
同大によると、地上絵は東京23区の半分あまりの面積に相当するナスカ台地(約400平方キロ)に点在しており、人力で探すと膨大な時間がかかっていた。
そこで2018年からAIの活用を試み、地上絵の特徴を学習させたうえで航空写真を解析。これまでの実証実験で4点が新たに見つかっており、今回は1309か所で地上絵の候補が示された。
うち341か所を22年9月から約6か月かけて現地調査。1か所で複数の地上絵が確認されたり、候補地の付近でAIでは示されなかったものも見つかったりして、303点の発見につながった。発見までの時間が短縮され、調査研究が大幅に効率化された。
地上絵は紀元前100年頃~紀元後300年頃に作られ、地面に線状に描かれた「線タイプ」と、地表を削って凹凸をつけるなどした「面タイプ」がある。代表的な「ハチドリ」や「クモ」などの地上絵は線タイプで、50点が確認されている。大きさは平均約90メートルと、大型なのが特徴だ。
一方、今回見つかったのは全て面タイプだった。大きさは平均約9メートルと比較的小さく、これまで発見が難しかったとみられる。
人の形や頭部を模したとみられるものが約8割を占め、ラマのような家畜や、「ナイフを持ったシャチ」(写真)のような地上絵もあった。
チームの坂井正人教授(考古学)は「今回の地上絵は、(住民が日常的に使う)小道沿いに多く分布している。当時は文字を持っていなかったため、儀式や家畜に関する『掲示板』のような情報共有の役割を果たしたのではないか」と分析している。
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
世界の七不思議、、、当時の記憶では、ナスカの地上絵のほか、イースター島のモアイ像、魔のバミューダ海域、インカ帝国の滅亡、ムー大陸の謎、などがあったと思います。(^。^)
しかし、かつては科学技術の粋を集めても解き明かせなかった地上絵の謎が、人工知能によって明らかになってくるとは、、、テクノロジーの威力に脱帽ですね!!(◎_◎;)
「AIに正体訊くや枯れ芒」 祖谷馬関
(注)枯れ芒は冬の季語。「幽霊の正体見たり枯れ尾花(芒)」と言われる。枯れ尽くした芒。葉も穂も枯れ果て、茎の部分が風に揺れる姿は寂寥感の極み。枯れ尽くした芒も野原一面に群れると美しくもある。雪や風の中に見るのも風情がひとしお。芒は秋の季語。