
こんにちは、中川香須美です。これまで2年間にわたってブログでカンボジアの子どもたちについて紹介させていただきましたが、今回はわたしが書くブログの最終回になります。最後のしめくくりとして、カンボジアの子どもたちがNGOに寄せる期待と憧れを紹介します。
5月に、ある仕事の一環で、私はへき地の女子高校生を集めて話を聞く機会を得ました。地方都市から車で2時間ほどでこぼこ道を行ったところにある村の高校です。本題は女性に対する暴力についての情報収集でした。でも若い女子高校生と話していて一番印象に残ったのは、彼女たちのNGOに対する強い憧れの気持ちです。その地区ではこれまでNGOがほとんどまったく活動していません。女子高生も、NGOの職員に会ったのは、私と一緒に同行した数名の若いカンボジア人たちが初めてだったそうです(実際はNGOとして行ったのではないのですが)。彼女たちは、NGOの職員が自分たちと話に来るということで、嬉しくって楽しみにして待っていたと言うのです。
彼女たちは、こちらがインタビューして意見を聞くのを知っていたので、最初は一生懸命質問に答えてくれました。でも、こちらからの質問が終わって、「もし質問があればどうぞ」と彼女たちに投げかけると、水を得た魚のように次々と質問が出てきました。その理由は、NGOには知り合いがいないけれど、将来はNGOの職員になって社会のために役立ちたいという強い希望を持っているからでした。高校まで進学はしたけれど大学に行かなくてもNGOで働けるのか、プノンペンにいけばNGOで働く機会はあるのか、どういう能力がNGO職員として必要なのか、次々と質問されました。NGOという名前が、テレビやラジオなどを通じて広く知られていて、かっこいいという印象を彼女たちに与えているようです。また同時に、社会に貢献できるような仕事をするには、ぜひNGOで仕事をしたいと考えているのです。
カンボジアは内戦が終結した後、政府がさまざまな政策を作って国家の発展を進めているものの、予算や人材不足から行政サービスが住民に十分に行き届いていないのが実情です。そのような状況の中、NGOが政府の役割を側面支援する形で、さまざまな分野で活動しています。子どもの権利普及活動についても、国際子ども権利センターをはじめとして多くのNGOが教育省に現場で協力しながら二人三脚で実施しています。高校生にとっては、行政官や自治体職員といっても身近に接することもなく、むしろメディアなどで報道されるNGOなどの活躍に注目がいっているようです。
政府職員であってもNGO職員であっても、カンボジアの将来をよりよくしていきたいと思う若い世代が育っているのは、とても心強いです。カンボジアは人口の半数以上が子どもです。将来を担っていく子どもたちに、できるだけ学ぶ機会を提供し、将来の夢が持てるような環境をつくっていくのは、わたしたち大人全ての責任だと思います。暴力から自由な社会、悲しみから自由な社会、個人が自由に生きられる社会、国境を越えてそういった社会を作っていくのは、わたしたち、大人の責任です。国際子ども権利センターの活動を通じて、またブログを通じて、日本人の間でもそういった意識が高まることを期待しています。
最後になりますが、これまでわたしが書くブログを読んでくださった皆様、コメントをくださった皆様、本当にありがとうございました。長年住んでいるカンボジアから日本向けに情報を発信していきたいと思っていた時に、国際子ども権利センターの甲斐田万智子さんからお誘いいただき、これまで細々と情報発信ができる機会をいただけて本当にありがたく思っています。
なお、わたしは6月28日から2年間、国際協力機構(JICA)のジェンダー主流化プロジェクトの専門家として、カンボジアの女性省に派遣されることになりました。今後はどういった形になるか分かりませんが、引き続きカンボジアからさまざまな情報発信をしていきたいと思っています。
写真は、子どもの人身売買防止ネットワークで活動する女子中学高校生
5月に、ある仕事の一環で、私はへき地の女子高校生を集めて話を聞く機会を得ました。地方都市から車で2時間ほどでこぼこ道を行ったところにある村の高校です。本題は女性に対する暴力についての情報収集でした。でも若い女子高校生と話していて一番印象に残ったのは、彼女たちのNGOに対する強い憧れの気持ちです。その地区ではこれまでNGOがほとんどまったく活動していません。女子高生も、NGOの職員に会ったのは、私と一緒に同行した数名の若いカンボジア人たちが初めてだったそうです(実際はNGOとして行ったのではないのですが)。彼女たちは、NGOの職員が自分たちと話に来るということで、嬉しくって楽しみにして待っていたと言うのです。
彼女たちは、こちらがインタビューして意見を聞くのを知っていたので、最初は一生懸命質問に答えてくれました。でも、こちらからの質問が終わって、「もし質問があればどうぞ」と彼女たちに投げかけると、水を得た魚のように次々と質問が出てきました。その理由は、NGOには知り合いがいないけれど、将来はNGOの職員になって社会のために役立ちたいという強い希望を持っているからでした。高校まで進学はしたけれど大学に行かなくてもNGOで働けるのか、プノンペンにいけばNGOで働く機会はあるのか、どういう能力がNGO職員として必要なのか、次々と質問されました。NGOという名前が、テレビやラジオなどを通じて広く知られていて、かっこいいという印象を彼女たちに与えているようです。また同時に、社会に貢献できるような仕事をするには、ぜひNGOで仕事をしたいと考えているのです。
カンボジアは内戦が終結した後、政府がさまざまな政策を作って国家の発展を進めているものの、予算や人材不足から行政サービスが住民に十分に行き届いていないのが実情です。そのような状況の中、NGOが政府の役割を側面支援する形で、さまざまな分野で活動しています。子どもの権利普及活動についても、国際子ども権利センターをはじめとして多くのNGOが教育省に現場で協力しながら二人三脚で実施しています。高校生にとっては、行政官や自治体職員といっても身近に接することもなく、むしろメディアなどで報道されるNGOなどの活躍に注目がいっているようです。
政府職員であってもNGO職員であっても、カンボジアの将来をよりよくしていきたいと思う若い世代が育っているのは、とても心強いです。カンボジアは人口の半数以上が子どもです。将来を担っていく子どもたちに、できるだけ学ぶ機会を提供し、将来の夢が持てるような環境をつくっていくのは、わたしたち大人全ての責任だと思います。暴力から自由な社会、悲しみから自由な社会、個人が自由に生きられる社会、国境を越えてそういった社会を作っていくのは、わたしたち、大人の責任です。国際子ども権利センターの活動を通じて、またブログを通じて、日本人の間でもそういった意識が高まることを期待しています。
最後になりますが、これまでわたしが書くブログを読んでくださった皆様、コメントをくださった皆様、本当にありがとうございました。長年住んでいるカンボジアから日本向けに情報を発信していきたいと思っていた時に、国際子ども権利センターの甲斐田万智子さんからお誘いいただき、これまで細々と情報発信ができる機会をいただけて本当にありがたく思っています。
なお、わたしは6月28日から2年間、国際協力機構(JICA)のジェンダー主流化プロジェクトの専門家として、カンボジアの女性省に派遣されることになりました。今後はどういった形になるか分かりませんが、引き続きカンボジアからさまざまな情報発信をしていきたいと思っています。
写真は、子どもの人身売買防止ネットワークで活動する女子中学高校生



















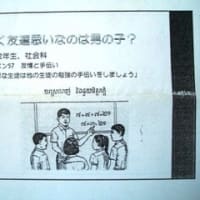
中川さんが講演した昨年末の大阪セミナーに参加させていただいた、日本福祉大学の松林です。
カンボジアだより、楽しく読ませていただきました。ありがとうございました。
今後は女性省に勤務されるのですね。ご活躍をお祈りしております。
わたしも今年6月から、これまでやってきたことをすべて捨てて、がんばってやっていこうとおもっております。
女性省ですか。
初めのうちは慣れない中でのお仕事、体調崩さないように、これまで以上のご活躍を祈念しております。
これまで本当にありがとうございました、
&
これからも中川さんらしさを存分に発揮してかんばってくださいね!