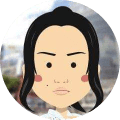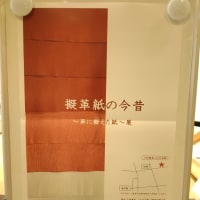この小学校には本格的な紙漉き専用の部屋があり、紙漉き舟や簀桁は勿論、圧搾台まであります。下は排水も考えられていて水がたまらない。いいなあ、私もこういう工房が欲しい。。
各学年!1回から2回紙漉きの授業があり、手すき組合員が手分けして指導に行きます。
一年生はハガキ作り。
まだ小さくて簀桁が持てないので、枠にひしゃくで紙料を流し込み作ります。
二年生から流し漉き
でもまだまだ力がなくて簀桁を持てないし、小さいので、一緒に漉きます。
三年生は少し大きくなり、少し力がついてきたので、横から簀桁を支えながら紙漉き。流れを覚えてもらいます。
四年生は和紙について学ぶ授業もあり、失敗しても自分の力で漉けるよう指導します。
五年生は大分経験値もあがり、紙漉きだけでなく、紙をたねて布を被せるところまで。全部自分で出来るように。
六年生は集大成。今までの経験をいかして卒業証書を造ります。この卒業証書は特別。
何が特別かって、漉き流し、引っかけ、流し込み、漉き合わせと紙漉きの技術がふんだんに、ここぞとばかりに、盛り沢山使われているのです。
和紙の里会館でも出来ない技術ばかり。



模様は山と川と片栗の花。
ここまで手の込んだ卒業証書は他にないでしょう。指導する側も力が入ります。
何回漉いていても、やはり簡単ではない紙漉き。慣れてくると「裏水」をしてしまうのです。これは、簀の裏(下)から水が入ることで、表面の繊維が浮いてしまうこと。
簀桁を水に入れるだけと思うなかれ、入れる角度、スピード、水の量、方向など複雑なのです。
裏水がついたらやり直し。
良い紙で卒業してほしいし、
地元にはこんな伝統工芸があったんだと覚えていてほしい。
そして大人になって、自分の育った町、伝統を誇りに思って貰えると良いな。