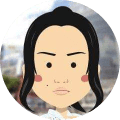最近、作ったモノを「作品」と呼んでいただくことが多くなっています。
凛九で活動してるからかな?
伝統工芸と一言で言っても様々。
作品として仕上げてそのままエンドユーザーへというモノ、素材として作られているモノ、作品を作るための道具、とか色々あります。
どれも伝統工芸。
和紙は、、素材かな。
和紙を使って何かを作る、和紙に描いたり、補強したり。使ってみないとわからない。
素材を作っているので、自分の思いを形にしたものではないし、世界に一つでもありません。
ただ、求められている紙を作れるように経験を積む。様々な注文に応じられること、また同じ品質の紙を作れること、そんな紙漉き職人になりたくて、精進しています。
価格に関してはここでは触れず遙か彼方の方へ置いといて…

その紙を使うことで、良い仕事が出来たり、能率が上がったり、作家さんの表現の幅が広がったり、創造性豊かになったりすることが紙漉き職人としての喜びです。
(格好よく言ったけど、実は絵心全くない)
ただ和紙を作る人も様々ですし、紙も様々あります。造形としての紙作りや、加工がうまい人もいます。繊維をよく知りうまく扱ってるんですよね。みんなそれぞれ。それは作品になるかも?
素材として作っている和紙を作品としてしまうと、その作品に絵を描いた作品、、と訳が分からなくなってしまいますね。
時々漉いた紙を加工して商品を作ったりしてますが、それが作品と思ったことはないです。
あくまで商品かな。こういうとこ頑固です。
作家さんは作品が売れることを「お嫁に行く」なんて表現したりしますが、私は「旅立ち」と言っています。
伝統工芸の多くは用途が決まっていて、その為に作られるんですが、和紙って用途が決まってない。同じ日に作られた沢山の紙が、別の場所に行き、形を変えそれぞれの人生「紙生」をおくる。
本になったり、糸になったり、
絵を描かれたり、絵の一部になったり
作品を支えたり、動力の一部になったり。
どうなっても、その先で懸命に生きて欲しい。
この和紙、どうやって使おうか?
大人も子供も男も女もない。
自分の創造力を目一杯働かせ、
自分の中にインプットしたものを
形としてアウトプットできるもの。
小学生の夏休み、工作大変だったの思い出します。出来上がると、上手に作れなくても大作じゃなくても、自分を出し切った。
そんな達成感や充実感が残りました。
人と比べることない、
自分なりの楽しみ方が出来る。
和紙ってそんな所が面白いんです。
人生と紙生、何だか似てますね。