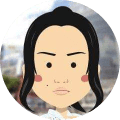研修の話
私は美濃手すき和紙協同組合の組合員ですが、本美濃紙保存会というところにも入っていて、本美濃紙の技術を学んでいます。
段階的に会員、研修者、研修生といまして、
私は今年度から研修者となりました。
夏は全体研修。
皆で集まって、一人一貫ずつ配られた楮を各々作業をして紙を作ります。
秋冬は個人研修。二貫の那須楮を配られ、指定の厚さの紙にして提出。報告書や写真も提出します。
この研修プログラムがとても良いと、文化庁の方が紹介してくれたり、和紙の他産地の方々が見学に見えたりします。
しかし皆そのストイックさに顔をしかめ恐れおののき「美濃じゃなくて良かった」「怖すぎる」と口にし飛んで帰るのです…ヒィィィ
その内容とは…
主に冬の個人研修なのですが、
提出した紙を会員が全検査、良品(厚口、中口、薄口)、傷物と分別し表にし、講評を書いたモノを全員分まとめ配布。それを見ながら各々の紙を見て回ります。
この人は耳が厚いのね、この人はちり取りが甘い、こっちの人は地合いが悪い、そっちの人は厚さが揃ってない等々。
それを皆してどれどれと持ち上げて透かしたり横から見たりしながら、どうしてこうなったか話し合うのです。
公開処刑みたいなものですね…
しかし逆に素晴らしい紙を漉けば感嘆の声があがり飲めや歌えの大騒ぎに(なりません)。
初めて見るキズもあります。
そんな時は何故こうなったかと皆で意見を出し合い話し合います。こんな時はこうだった、アレをしたらああなった等々失敗談が飛び交い中々面白いです。
ここの「情報の共有」がとても画期的なのです。私が和紙の世界に入った頃なんかは他所の工房に行くことは御法度。紙や技法について聞くのは勇気がいったものです。
これが変わったのはユネスコ無形文化遺産登録。後継者育成が何より必須と保存会が動いたのです。
この技術を後世にどう繋げていくか?今までは
家庭内工業のため家族間で繫いできていましたが、現存する工房に後継者はおらず。しかし他所から入ってきた紙漉き職人はいる。と言うことで情報を共有し底上げを図り、後継者育成に力をいれようと皆が意識を変えたのです。
それはもうほんと凄いこと。
あり得ないことでした。
「本美濃紙の技術を残す」ということを何より優先して個々の工房の垣根を越えて、それぞれの工房の仕事の仕方を明かしたのです。
それぐらいの気持ちを持って後継者育成に取り組んでるんだもん、厳しくなりますよね。
と、いうわけで鬼も逃げ出す厳しい研修を積極的に受けているのです。(泣)
長くなるので、個人研修の様子は次回に書くことにします