
平の高房字に14時過ぎに入った小生であるが、正規のチェックインは15時からであり、さすがに・・・ということで、毎回訪れている「平家の里」に出掛けてきた。


平の高房からは徒歩で10分くらい。冬のかまくら祭りの会場になるし、途中には河原のミニかまくらが並ぶ川がある。
この施設は平家の落人伝説にちなむ「平家塚」を中心にし、かやぶきの家に平家にちなむ展示などを並べたもの。
平家ゆかりの神社なども祭られている。こちらに来たのは紅葉が真っ盛りと聞いたため。細かい話は別にして、紅葉は予想以上に見事であった。
冬には真っ白な世界であるが、この季節の色は素敵である。上右写真の「平家塚」は、この里に逃げのびた平家の先祖が、いずれ再興のチャンスもあろうかと宝や武具を埋めたところという伝説が残っている。



そのチャンスのないまま、子孫がこちらの里の温泉を見つけたときにたまたま発見し、先祖の思いに涙したと伝えられているそうな。
さて、同行者と平家について話していたところ、「平家物語は知っているが、全部『盛』でわけわかんない」と。
そこで小生思ったのは「実家の伊豆は源氏ゆかりのところでもあり、歴史の授業でもなんとなく、源氏が正義で平氏が悪みたいな印象があった」こと。
冷静に振り返ってみよう。「平氏にあらずんば人にあらず」なんて言葉が独り歩きしているし、平清盛といえば、悪の権化のようなイメージがある。
だが、福原や大和田の泊(神戸)の開発をベースにした海運・貿易の振興は評価されてしかるべきだろうし、結果論だが源氏を根絶やしにはしなかった。
一方で頼朝が取った政策は、平氏を根絶やしにするもの・・・いや、それどころか木曽義仲や源義経など源氏の身内ですらも根絶やしにするものだった。


鎌倉は首都というよりも、防御のための逃避地であり、平氏の取った経済政策に逆行するものであった。
歴史に「たられば」はないが、平氏を滅ぼした源氏が鎌倉幕府を作り、すぐに平氏系の北条氏が実権を取った。
その後、源氏系の足利氏が室町幕府を作り、平氏系の織田信長が天下に迫る。そして秀吉をはさみ、源氏系の徳川の時代になる。
まさに源平の交代劇が日本の歴史に連なっている・・・歴史は常に勝者のもの。その点でいうと、平氏についてはもっと評価を上げてやっても・・・と。

























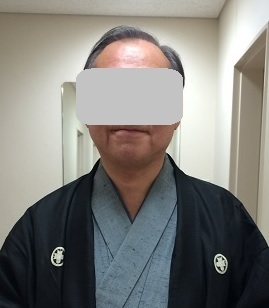

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます