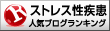うつ解消マニュアル
(脳及び心疾患並びに認知症及び更年期障害予防)
第21回目(2008・12・14作成)
(マニュアルは第1回目にあります。常に最新版にしています。)
「解消法、1から3までの解説」
グー(2007.7.1開設)のブログに開設中
http://blog.goo.ne.jp/kenatu1104

今回は、解消法の解説をします。
数が多いので、
何回かに分けてお話しします。
ブログ立ち上げの時から、
解説というか説明はしなくてはならない
と思っていたのですが、
中々する機会がありませんでした。
何時でも出来るという気持ちと、
平易に説明することの難しさが禍いしました。
どうしても専門用語が並ぶことになるし、
それぞれの項目毎に
括弧の中にヒントを書いておいたので
興味のある人は
自分で調べるだろうと思っていたのです。
でも、よーく考えてみると、
何故そうすると良いのか
ということが分かっていなければ、
効果も半減します。
やはり、脳は「何故なのか」を求めています。
納得したがっているのです。
出来るだけ、簡単に書いてみます。
この解消法には自信があるのですが、
実行して貰わなければ意味がありません。
病気になれば、心は地獄、体は悲鳴をあげます。
是非、活用して下さい。

(北海道旭川市、上野ファーム・「風のガーデン」のガーディナー)
(解消法1~3)
1 朝の起きる時間を一定にする事。
(夜、何時に寝ても起きる時間は、
必ず同じ時間にする。
セロトニンを出易くする。
体内時計のリセット。)
2 朝日は必ず浴び、朝食は必ずとる事。
(カーテンを薄地にするか、全くしない。
セロトニンを出易くする。
体内時計のリセット。)
3 23時から2時までの3時間は、
出来るだけ眠っている事。
黄金の眠りと言われている。消灯の事。
(成長ホルモンが最も出る時間帯。
疲れをとる等。メラトニンと関連。)
(生体リズム・・・サーカディアン・リズム)
私たちの生体リズムは、
地球の自転に合わせて約24時間
《概日周期(がいじつしゅうき)、
サーカディアン・リズムともいいます》です。
この生体リズムを司っているのが、
体内時計です。
この体内時計は、
以前は脳だけにしかないと
思われてきたのですが、
肝臓や筋肉・肺・心臓といった
臓器及び皮膚などの細胞にも
あることが分かっています。
しかも、周期は約25時間。
一般的には、昼行性動物が
25時間、夜行性動物は23時間ですが、
もっと詳しく言うと、
ヒトの場合では成人の平均値で
24.5~25.5時間です。
このまま25時間だと、
毎日1時間づつズレますから、
12日後には昼夜が逆転します。
私達は仕事や学校という社会的要因もあって、
生体リズムの24時間で
生活しているわけですから、
これでは日常生活が送れなくなります。
そこで、
体内時計をもっと詳しく説明します。
(体内時計・・・
主要時計・末梢時計・時計遺伝子)
脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)にある
体内時計を「主要時計」、
その他を「末梢時計」といいます。
「末梢時計」は長期間リズムをつくれないので、
普段は「主要時計」に支配されています。
朝の光を浴びると、
視交叉上核にある体内時計は
時間のズレをリセットして、
自律神経を交感神経優位に切り替えます。
この時
コルチゾールというホルモンが出て、
全身の「末梢時計」を
「主要時計」に合わせます。
つまり、
25時間を24時間にリセットします。
一日の始まりです。
ところで、数年前、「末梢時計」の中に
「主要時計」と同じくらい重要な時計がある
ことが分かったのです。
肝臓にある時計遺伝子です。
ネズミの実験なのですが、
本来なら寝ている時間帯に食事を与えたところ、
昼夜が逆転してしまったのです。
つまり、
食事という要素が
大きく時計を狂わせてしまったのです。
だから、
朝起きる時間を同じにすること、
そして朝の食事が重要なのです。
朝になっても起きないとか、
朝食を抜くとかは、
絶対にしてはならないのです。
(朝の光・・・セロトニン・メラトニン)
そして、
朝の光を浴びると、目からの視神経は、
視交叉上核にある「主要時計」のリセットをし、
松果体(しょうかたい)で
トリプトファン(セロトニンをつくる物質)から
セロトニン(心を安定させ、明るくする神経伝達物質)
をつくらせるのです。
一方、視交叉上核への刺激は、
脳幹の縫線核(ほうせんかく)という
セロトニン神経細胞でも
セロトニンをつくらせます。
だから、朝の光を遮断してはならないし、
むしろ積極的に朝の光を窓のそばまで行って、
浴びなければならないのです。
ところで、
逆に夜中に
強い光(パソコンの光もそうですよ)を浴びると、
体内時計は
朝と間違えてしまいますので要注意です。
セロトニンは、
なんと夜になって暗くなると、
メラトニン(睡眠を促し、免疫力を高め、心臓の働きを
良くするホルモンです)になります。
暗くないと、メラトニンに変化しませんので、
くれぐれも電気を点けっぱなしで寝ないようにして下さいね。
つまり、夜グッスリ眠るためには、
睡眠導入効果のあるメラトニンが
必要になりますから、
昼間は光に良く当たって、
セロトニンを沢山つくって
おかなければなりません。

(北海道旭川市、花菜里ランド)
(体温)
ところで、体温を考えてみます。
午後4~7時にもっとも高くなりその後低下し、
早朝の4~7時に最低となって再び上昇します。
なんと、昼と夜の明暗サイクルに一致します。
このことは、
私達の生活にとって
とても好都合なことです。
朝、目が覚めて行動するためには、
エネルギーが必要です。
つまり、朝の起床に向けて、
体の準備をしていてくれたということですよね。
(睡眠・・・レム睡眠・ノンレム睡眠)
次は睡眠について、説明します。
ノンレム睡眠とレム睡眠を合わせて
約90分を一周期として、
朝起きるまで
この周期を4~5回程度繰り返します。
一周期の中身は、
ノンレム睡眠からレム睡眠へと移行します。
睡眠時間全体の割合は、
ノンレム睡眠80%、レム睡眠20%です。
ノンレム睡眠は、
浅い眠りから深い眠りまで4段階あり、
若いほど質の良い深い眠りである
ステージ4が多く出現します。
レム睡眠は、所謂、夢を見ている睡眠です。
ノンレム睡眠は、
脳は休んでいるが
体は休んでいない状態です。
レム睡眠は、
これとは逆で
脳は休まずに働いていますが、
体は休んでいますので、
全身の筋肉はだらりと弛緩した状態です。
6時間睡眠の場合、90分周期で4回ですが、
睡眠の前半部分はノンレム睡眠優位で、
睡眠後半部分はレム睡眠が優位になります。
つまり、入眠後の数時間の方が
質の良い眠りが出来るのです。
だから、23時から翌2までの時間が
一番深い眠りが出来る時間帯なので、
昔から「黄金の眠り」
と言われているのです。
「この時間さえ眠っていれば
睡眠時間が短くても問題がない」
という学者もいるくらいです。
因みに私は、この意見には賛成です。
優しい看護婦さんも夜勤明けは不機嫌だし、
私の経験からも病気になる人は、
何故かこの時間に起きていた人が多いのです。
レム睡眠時は、眼球が動く事から名づけられたのですが、
夢を見ているのだと考えると納得しますね。
そして、朝に向かって、
レム睡眠である浅い眠りが増えていきますから、
爽やかな朝を迎えることが出来るのです。
ここで大事なことは、
90分周期だということです。
決して、途中で起こさないこと、
起きないことです。
深い眠りの時間帯に起こされた日は、
一日中気分が悪い筈です。
起きる時間から90分周期で逆算して、
寝る時間を決めましょう。
従って、起きる時間は、
90、180、270、
360、450分後のどれかにしましょう。
うつ状態の人に共通しているのは、睡眠障害
(入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒など)です。
また、睡眠障害が原因で、
高血圧や心臓・脳疾患、癌や糖尿病、
果ては認知症になる危険
さえあると言われています。
解は、
良質な睡眠にあると言っても
過言ではありません。
睡眠薬とかお酒で得られる眠りは、
精々、ステージ3なのだそうです。
やはりそうだったのかと、
思い当たる人は多いのではないでしょうか。

(北海道旭川市、上野ファーム・「風のガーデン」のガーディナー)
それでは、確認します。
起床時間は、例えば6時と決め、
必ず、同じ時間に起きること。
そして、朝の光を存分に浴びること。
しかも、朝食を決して欠かさず、
光の中を出来る限り歩き
(歩行・運動・昼食時間の有効利用等)、
夜は出来るだけ10時には床に着き、真っ暗にして眠ること。
夜寝る時間がいくら遅くなっても、
起床時間には必ず、起きること。
起きる時間から逆算して、
90分の倍数の時間で眠ること。
ところで、これは余談なのですが、
ジョギングしている時に
爽やかに挨拶をくれた農家の人の話です。
その人の話は、次のとおり。
「不思議なんだけど、
朝日の当たらない所の畑の作物は、
育ちが悪いし味も落ちるんだよね。」
何か、妙に納得してしまう話ではありませんか。
やはり、
朝の光にはとてつもない力があるんですよね。
さて、
今日の説明はちょっと難しかったですか。
上手く、説明出来たでしょうか。
また次回、
出来るだけ早い時期に続きを書きます。
皆さん、どうもお疲れ様でした。
(脳及び心疾患並びに認知症及び更年期障害予防)
第21回目(2008・12・14作成)
(マニュアルは第1回目にあります。常に最新版にしています。)
「解消法、1から3までの解説」
グー(2007.7.1開設)のブログに開設中
http://blog.goo.ne.jp/kenatu1104

今回は、解消法の解説をします。
数が多いので、
何回かに分けてお話しします。
ブログ立ち上げの時から、
解説というか説明はしなくてはならない
と思っていたのですが、
中々する機会がありませんでした。
何時でも出来るという気持ちと、
平易に説明することの難しさが禍いしました。
どうしても専門用語が並ぶことになるし、
それぞれの項目毎に
括弧の中にヒントを書いておいたので
興味のある人は
自分で調べるだろうと思っていたのです。
でも、よーく考えてみると、
何故そうすると良いのか
ということが分かっていなければ、
効果も半減します。
やはり、脳は「何故なのか」を求めています。
納得したがっているのです。
出来るだけ、簡単に書いてみます。
この解消法には自信があるのですが、
実行して貰わなければ意味がありません。
病気になれば、心は地獄、体は悲鳴をあげます。
是非、活用して下さい。

(北海道旭川市、上野ファーム・「風のガーデン」のガーディナー)
(解消法1~3)
1 朝の起きる時間を一定にする事。
(夜、何時に寝ても起きる時間は、
必ず同じ時間にする。
セロトニンを出易くする。
体内時計のリセット。)
2 朝日は必ず浴び、朝食は必ずとる事。
(カーテンを薄地にするか、全くしない。
セロトニンを出易くする。
体内時計のリセット。)
3 23時から2時までの3時間は、
出来るだけ眠っている事。
黄金の眠りと言われている。消灯の事。
(成長ホルモンが最も出る時間帯。
疲れをとる等。メラトニンと関連。)
(生体リズム・・・サーカディアン・リズム)
私たちの生体リズムは、
地球の自転に合わせて約24時間
《概日周期(がいじつしゅうき)、
サーカディアン・リズムともいいます》です。
この生体リズムを司っているのが、
体内時計です。
この体内時計は、
以前は脳だけにしかないと
思われてきたのですが、
肝臓や筋肉・肺・心臓といった
臓器及び皮膚などの細胞にも
あることが分かっています。
しかも、周期は約25時間。
一般的には、昼行性動物が
25時間、夜行性動物は23時間ですが、
もっと詳しく言うと、
ヒトの場合では成人の平均値で
24.5~25.5時間です。
このまま25時間だと、
毎日1時間づつズレますから、
12日後には昼夜が逆転します。
私達は仕事や学校という社会的要因もあって、
生体リズムの24時間で
生活しているわけですから、
これでは日常生活が送れなくなります。
そこで、
体内時計をもっと詳しく説明します。
(体内時計・・・
主要時計・末梢時計・時計遺伝子)
脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)にある
体内時計を「主要時計」、
その他を「末梢時計」といいます。
「末梢時計」は長期間リズムをつくれないので、
普段は「主要時計」に支配されています。
朝の光を浴びると、
視交叉上核にある体内時計は
時間のズレをリセットして、
自律神経を交感神経優位に切り替えます。
この時
コルチゾールというホルモンが出て、
全身の「末梢時計」を
「主要時計」に合わせます。
つまり、
25時間を24時間にリセットします。
一日の始まりです。
ところで、数年前、「末梢時計」の中に
「主要時計」と同じくらい重要な時計がある
ことが分かったのです。
肝臓にある時計遺伝子です。
ネズミの実験なのですが、
本来なら寝ている時間帯に食事を与えたところ、
昼夜が逆転してしまったのです。
つまり、
食事という要素が
大きく時計を狂わせてしまったのです。
だから、
朝起きる時間を同じにすること、
そして朝の食事が重要なのです。
朝になっても起きないとか、
朝食を抜くとかは、
絶対にしてはならないのです。
(朝の光・・・セロトニン・メラトニン)
そして、
朝の光を浴びると、目からの視神経は、
視交叉上核にある「主要時計」のリセットをし、
松果体(しょうかたい)で
トリプトファン(セロトニンをつくる物質)から
セロトニン(心を安定させ、明るくする神経伝達物質)
をつくらせるのです。
一方、視交叉上核への刺激は、
脳幹の縫線核(ほうせんかく)という
セロトニン神経細胞でも
セロトニンをつくらせます。
だから、朝の光を遮断してはならないし、
むしろ積極的に朝の光を窓のそばまで行って、
浴びなければならないのです。
ところで、
逆に夜中に
強い光(パソコンの光もそうですよ)を浴びると、
体内時計は
朝と間違えてしまいますので要注意です。
セロトニンは、
なんと夜になって暗くなると、
メラトニン(睡眠を促し、免疫力を高め、心臓の働きを
良くするホルモンです)になります。
暗くないと、メラトニンに変化しませんので、
くれぐれも電気を点けっぱなしで寝ないようにして下さいね。
つまり、夜グッスリ眠るためには、
睡眠導入効果のあるメラトニンが
必要になりますから、
昼間は光に良く当たって、
セロトニンを沢山つくって
おかなければなりません。

(北海道旭川市、花菜里ランド)
(体温)
ところで、体温を考えてみます。
午後4~7時にもっとも高くなりその後低下し、
早朝の4~7時に最低となって再び上昇します。
なんと、昼と夜の明暗サイクルに一致します。
このことは、
私達の生活にとって
とても好都合なことです。
朝、目が覚めて行動するためには、
エネルギーが必要です。
つまり、朝の起床に向けて、
体の準備をしていてくれたということですよね。
(睡眠・・・レム睡眠・ノンレム睡眠)
次は睡眠について、説明します。
ノンレム睡眠とレム睡眠を合わせて
約90分を一周期として、
朝起きるまで
この周期を4~5回程度繰り返します。
一周期の中身は、
ノンレム睡眠からレム睡眠へと移行します。
睡眠時間全体の割合は、
ノンレム睡眠80%、レム睡眠20%です。
ノンレム睡眠は、
浅い眠りから深い眠りまで4段階あり、
若いほど質の良い深い眠りである
ステージ4が多く出現します。
レム睡眠は、所謂、夢を見ている睡眠です。
ノンレム睡眠は、
脳は休んでいるが
体は休んでいない状態です。
レム睡眠は、
これとは逆で
脳は休まずに働いていますが、
体は休んでいますので、
全身の筋肉はだらりと弛緩した状態です。
6時間睡眠の場合、90分周期で4回ですが、
睡眠の前半部分はノンレム睡眠優位で、
睡眠後半部分はレム睡眠が優位になります。
つまり、入眠後の数時間の方が
質の良い眠りが出来るのです。
だから、23時から翌2までの時間が
一番深い眠りが出来る時間帯なので、
昔から「黄金の眠り」
と言われているのです。
「この時間さえ眠っていれば
睡眠時間が短くても問題がない」
という学者もいるくらいです。
因みに私は、この意見には賛成です。
優しい看護婦さんも夜勤明けは不機嫌だし、
私の経験からも病気になる人は、
何故かこの時間に起きていた人が多いのです。
レム睡眠時は、眼球が動く事から名づけられたのですが、
夢を見ているのだと考えると納得しますね。
そして、朝に向かって、
レム睡眠である浅い眠りが増えていきますから、
爽やかな朝を迎えることが出来るのです。
ここで大事なことは、
90分周期だということです。
決して、途中で起こさないこと、
起きないことです。
深い眠りの時間帯に起こされた日は、
一日中気分が悪い筈です。
起きる時間から90分周期で逆算して、
寝る時間を決めましょう。
従って、起きる時間は、
90、180、270、
360、450分後のどれかにしましょう。
うつ状態の人に共通しているのは、睡眠障害
(入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒など)です。
また、睡眠障害が原因で、
高血圧や心臓・脳疾患、癌や糖尿病、
果ては認知症になる危険
さえあると言われています。
解は、
良質な睡眠にあると言っても
過言ではありません。
睡眠薬とかお酒で得られる眠りは、
精々、ステージ3なのだそうです。
やはりそうだったのかと、
思い当たる人は多いのではないでしょうか。

(北海道旭川市、上野ファーム・「風のガーデン」のガーディナー)
それでは、確認します。
起床時間は、例えば6時と決め、
必ず、同じ時間に起きること。
そして、朝の光を存分に浴びること。
しかも、朝食を決して欠かさず、
光の中を出来る限り歩き
(歩行・運動・昼食時間の有効利用等)、
夜は出来るだけ10時には床に着き、真っ暗にして眠ること。
夜寝る時間がいくら遅くなっても、
起床時間には必ず、起きること。
起きる時間から逆算して、
90分の倍数の時間で眠ること。
ところで、これは余談なのですが、
ジョギングしている時に
爽やかに挨拶をくれた農家の人の話です。
その人の話は、次のとおり。
「不思議なんだけど、
朝日の当たらない所の畑の作物は、
育ちが悪いし味も落ちるんだよね。」
何か、妙に納得してしまう話ではありませんか。
やはり、
朝の光にはとてつもない力があるんですよね。
さて、
今日の説明はちょっと難しかったですか。
上手く、説明出来たでしょうか。
また次回、
出来るだけ早い時期に続きを書きます。
皆さん、どうもお疲れ様でした。