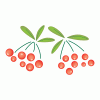先日、テレビで、うつ病治療のドキュメンタリー番組を見た。うつ病患者に処方される薬を長年、または大量に飲み続けて、病気が治らないばかりか副作用によって悪化した、というような事例がいくつか取り上げられていた。また、まるで医療機関のお金儲けのためのように、何種類もの薬を処方されたなどの体験を語る元患者たちが出演していた。「先生から薬の説明はされましたか?」と、司会者が質問すると、「いいえ、1度も説明されたことありません」と、まるで被害者みたいな口調で元患者が答えた時は、驚かされた。元患者たちは、まるで主治医を疑ってるみたいで、何の薬か聞けないと話していた。質問したら、機嫌を悪くされたことがあると答えた出演者もいた。
私がこの番組を見て思ったことは、病院や医師に対する認識が、私とあまりにも違うということだった。もう、驚きの連続だったと言っていい。その番組に出演していた元患者たちや大学病院の医師は、今後は医師が淘汰されていくから未来は明るいみたいなことまで語っていた。
この番組を、多くの医師たちは、どんな思いで見ただろうと想像しないではいられなかった。まるで、世の中には、うつ病患者を食い物にするお金儲け主義の悪徳医師が少なくなく、オフィス街には心療内科の看板を掲げたクリニックが急増している、とそれらの看板が映し出され、皆さん、気をつけましょう、みたいなムードだったのである。
『うつ』に限らず、体調が悪くなって受診すると、患者は信頼と尊敬をこめて医師を「先生」と呼ぶ。けれど、なかなか病気が治らなかったり、かえって悪化したりすると、薬ばかり多く出して儲け主義とか、無能とか腕が悪いとか人格がどうのとか、感情的な批判をして、最初の信頼と尊敬が、不信と軽蔑に一変し、「あの医者」と侮蔑的な口調になったりする。
医師は神様ではないのだと、私はいつも思う。ところが、医師は神様だと思っている人が多いような気がする。受診して、処方された薬を飲んで、手術したりして、それまでの病苦から解放され、病気は完治する、医師は神様だから治せないはずがないと、理論ではなく感情的にそう思い込んでいる人が少なくないような気がする。
実際、私の周囲で、病院に車で送迎している知人の肉親の、〈経過観察〉の病気の話の時。私が質問するたびに、答えられなかったり曖昧な答え方をしたりし、「先生にお任せしているから」という言葉が何度も出てくるのだった。
(どうして主治医に聞かないの? 病気は主治医のものではなく、自分の身体に起きた自分のものでしょう?)
そう言いたかったが、人それぞれのやり方があるし、気を悪くさせるような気がし、私は言葉を呑み込んだ。
私の少ない経験や、見聞したりテレビで見たりする限り、概して、医師は病気の特定に慎重である。薬剤師のように自信ありげな口調で話したりしない。それは、医師はあらゆる病気を想定するからではないかと思う。
医師だって病気になるのだ。開業医の友人は、インフルエンザの時期に次々来院する患者を加療しているうちに、感染してインフルエンザに罹ってしまったことを開業医の宿命と、手紙に書いてあった。
持病のある医師もいるし、『医者が癌にかかったとき』(竹中文良・著)という体験記を読んだこともある。もし、医師が神様なら、自分は病気にならないし、なってもすぐに治るはずである。
そう言えば、以前、建築デザイナーの知人女性は、病院へ行くのが昔から好きだと言っていた。何故、好きかと聞いたら、体調の悪いのが良くなるからだと。そういう人にとっては、<お医者さんは神様>と思っていていいのかもしれない。
けれど、報道番組やドキュメンタリー番組で見る限り、神様である医師が病気を治してくれない、お金ばかりかかる、かえって悪化した、こんなに被害を受けた、神様どころか冷酷無残な人間、お金の亡者、と言わんばかりに主張する人が目立ち過ぎると思う。
もっとも、テレビ番組というのは、こんないいお医者さんに出会えて病気を治して貰ったという話より、こんな悪徳医師に出会ってこんな被害体験をしたという話のほうがインパクトがあると言えるかもしれない。
けれど、その夜の番組を見終わった時、明日から、『うつ』以外の診療科でも医師たちは薬を出しにくいのではないかと、私は思った。薬の効果や副作用は個人差があると思うし、現代医療には限界というものがなくはなく、たとえベテラン医師でも実際は手探りというか半ば迷いながら患者に薬を処方している、ということがないとは言えないかもしれない。医師は、先生と呼ばれ、社会的地位も収入もあるように思われる職業だけれど、その能力や腕や人格について何人もの他人から毎日毎日、評価を受けているようなものと私には感じられる。レベルの高い特殊な知識と能力を持つ自信と誇りと、人知れず自信喪失と迷いと焦りと後悔と、諦めや絶望や無力感や憤りや虚無感など、さまざまな想いをかかえて仕事しているように見える。普通の神経で生きて行けるとは思えないと言っていいくらいだ。しかも、あのようなドキュメンタリー番組で、医師不信というか医療不信というか、薬の副作用や恐怖を視聴者たちにイン・プットされてしまっては──。
それとも、うつ病という病気に限定されることであり、薬が乱用されがちと言われるのは抗うつ剤だけということなのだろうか。薬と言えば厚生労働省とか製薬会社の責任はないのだろうか。うつ病の人たちやその家族たちは、あの番組を見て、どう思い、どう感じただろうと私は想像した。
それに、何種類もの薬を処方され、治ると思い込んで、毎日きちんと飲み、治った人だって少なくないかもしれない。私自身、そう思い込んで、何種類もの薬を飲もうとしたことがある。もう、ずっと以前のことだが、夜中に咳で目が覚める気管支炎のような風邪をひいた時だった。市販の風邪薬を長期に飲んで治らないまま、こじらせたのだと思う。すすめられて近所の内科医院へ行った。風邪で内科へ行くのは、15年ぶりぐらいのこと。23歳の時に、風邪と思って内科医院へ行ったが治らず、病院で麻疹(はしか)と診断された時以来である。その後、風邪をひかなかったわけではなく、たいてい市販薬で治っていたので、内科医院へ行くことはなかった。
久しぶりに行った内科医院。何故か、ワクワクした気分も少しあった。熱はないが、咳が激しく出るという症状を話すと、聴診器を当てられた後、2種類の風邪薬を処方されて、一週間飲んだ。治らないので、別の内科医院へ行った。レントゲンを撮って、肺には問題なく、3種類の薬が一週間分出て、飲んだ。治らないので、3軒目の医院で、やはりレントゲンでは異常ないけれど、5種類の薬が処方された。この時のドクター・ショッピングは決して医師不信ではなく、よく効く薬を出してくれる医院への期待と、徒歩圏内に内科医院が何軒もあったため、あちらへ行き、こちらへ行き、というのが新鮮で少しは楽しかったのである。
(5種類の薬を飲むのは大変だけど、我慢して、一生懸命、これだけの薬を飲めば治るかもしれない)
そんな気持ちで帰宅した。当時、半同居していた家人は何でもよく知っている人で、少しでもわからないことや自信のない答えはすぐ百科事典で調べるような人だった。私が処方されて来た5種類の薬のローマ字や記号を確認しながら、『病院で貰った薬がわかる本』という本を見て調べ、解熱剤などの不要と思われる薬を除いてくれた。5種類の薬を飲むのは身体に悪いと言われ、他の処方された2種類の薬を飲んだが、治らない。連日の咳でさすがに食欲も落ちて、作って貰った卵おじやとお味噌汁とりんごとみかんだけの食事で、もう死にそうと思うくらい体力も気力も落ちてしまった。その後、それまで1度も飲んだ経験がなかった漢方薬を家人にすすめられた。家人が漢方薬局店で、私の症状を薬剤師に話し、買って来てくれた五虎湯という漢方薬だった。夕食前に1袋飲んだら、その夜は咳で目が覚めることはなく、翌日にはもう咳の発作がおさまっていて、嘘みたいと驚いた。1箱3日分の薬を飲み終える前に、苦しい咳は消え、風邪は完治したのである。それまで半信半疑だった漢方薬との初めての出会いだった。
それから、さらに十数年後に、就寝時の呼吸困難が起き、インターネットで漢方薬を処方する医療機関を調べて、近所の診療所を受診した。血液検査、レントゲン、心電図に異常がなく、医師は病名を告げない。原因がわからないから病名を告げられないのか、想像はついていて、うかつに告げられないのか。私はネットで調べた漢方薬の名前をメモして行って主治医に見せ、「その薬を処方して下さい。飲んでみたいので」と言って、処方して貰った。医師はその薬が効くとも効かないとも言わなかったが、あまり効かないかもしれないと言われた言葉は印象に残っている。プラセボ効果ではないが、この薬は効くかもしれないと医師から言われたら、暗示にかかりやすい私は、効いていたかもしれないという気がしなくもない。
その薬を1週間飲んで効かなかったので、ふたたび、その医療機関へ行き、ネットで調べた別の漢方薬の名前をメモして行って医師に見せ、「その薬を処方して下さい。飲んでみたいので」と言って、処方して貰った。こんな患者は初めてと医師は内心、呆(あき)れていたかもしれない。
また、耳鼻咽喉科で喉の検査をすることをすすめられ、ネットで調べた近所の2軒の耳鼻咽喉科へ検査に行った。最初に行った耳鼻咽喉科の医師が、横柄な感じの悪い医師だったので、検査の途中で、「やめます」と言い、中断して帰って来た。中断でも高額の検査費用を請求された時は、内心、腹立たしかった。翌日、2軒目に行った耳鼻咽喉科の医師は、信頼できる感じの良い医師でホッとした。検査の結果は異常なしだった。5日分の薬を処方されたが、薬の名前をネット検索したら、何と〈睡眠導入剤〉の薬だった。睡眠薬は長期服用の薬という先入観と、何度もあくびが出るほど眠いのに〈睡眠導入剤〉を飲む必要があるとは納得できず、漢方薬ではなく化学薬品への怖さも感じたりで、薬は飲まずに捨てた。処方薬が5日分というのは初めてで、風邪の時など多くの医療機関は1週間分か2週間分なので、化学薬品のダメージを考えてのことかもと思った。
次回、かかりつけの医師に、耳鼻咽喉科の検査の結果は異常なしだったことを記録したメモを見せたら、「えっ、耳鼻咽喉科へ行ったの?」と小さな驚きの口調。「だって、耳鼻咽喉科へ喉の検査に行くようにって、前回、先生に言われましたから」と言うと、「ああ」の後、医師が何か言ったか言わなかったか記憶にないが、私はコケた。内心、(行かなくても良かったのオ!?)と呟いたが、信頼できる医師だから、患者に言った言葉を忘れても、非難する気にはならなかった。
就寝時の連日のような呼吸困難といっても、全く息が吸えないというわけではなく、正確に言えば、息が吸いにくいという感じで、横向きになったり、外出日や来客のある日の夜は、神経が疲れるせいか不思議と症状が起こらないのである。漠然と、私は年齢的または精神的な原因、よく聞く不定愁訴ではないかと自己診断していた。
または、枕に原因があるのかもしれないと思い、デパートへ枕を買いに行き、いくつも試して比較的ラクなのを買った。それから、家電量販店へ行ってパソコン・ソフトを買い、その近くに漢方薬局店があるのをネットで見て知っていたので、そこに入った。
症状のメモを読み終えた熟年薬剤師が、
「西洋医学的に言えば自律神経失調症、婦人科的に言えば更年期障害、東洋医学的に言えば血の道症だと思いますよ」
と言ったが、私の自己診断と、〈当たらずといえども遠からず〉のような気もした。ただ、自律神経失調症という言葉が気になった。仕事がハードな従兄が数年前に自律神経失調症で数か月間、入院したため、興味が湧き、書店で自律神経失調症の本を2冊買って来て読んだ。
その薬局で薬剤師にすすめられて買って来た『半夏厚朴湯』という漢方薬が効いたので、かかりつけの診療所へ行き、それと同じ漢方薬を処方して下さいと言った時、
「市販薬より、処方して貰う薬のほうが成分が強くて、効き目も強いのでしょう?」
そう質問したら、
「若干(じゃっかん)ね」
医師がそう答え、私はその言葉が今でも忘れられないほど印象に残っている。
偽薬、プラセボという薬に関して、ネット記事で読んだことがある。本物の薬に見えるが実際は偽物。新薬の治験でプラセボ薬と本物の薬とで比較して、効果を調べたりするらしい。
あの3か月間の<漢方薬服用迷走>は何だったのだろうと、今でも思う。本当に効果のある漢方薬だったのか、プラセボ効果みたいにきっと効く、きっとこれで治る、と信じ込んだ私の精神状態が、案外効果的なだけだったかもしれないと、そんな気がしなくもないからである。
先日のドキュメンタリー番組で、大量の薬を処方されたとか、薬の説明はなかったとか、まるで被害者意識にとらわれているみたいな発言には、私はあまり同情できない。薬についての認識が違い過ぎるからだ。1種類の薬でも数種類の薬でも、信頼できる医師ならその医師を信頼して、きっと効く、きっと治ると信じて飲めば効くことが多いと言えるのではないだろうか。やはり、病気を治すのは本人であり、医師と薬は補助してくれるものという考え方をしたいと私は思う。
私がこの番組を見て思ったことは、病院や医師に対する認識が、私とあまりにも違うということだった。もう、驚きの連続だったと言っていい。その番組に出演していた元患者たちや大学病院の医師は、今後は医師が淘汰されていくから未来は明るいみたいなことまで語っていた。
この番組を、多くの医師たちは、どんな思いで見ただろうと想像しないではいられなかった。まるで、世の中には、うつ病患者を食い物にするお金儲け主義の悪徳医師が少なくなく、オフィス街には心療内科の看板を掲げたクリニックが急増している、とそれらの看板が映し出され、皆さん、気をつけましょう、みたいなムードだったのである。
『うつ』に限らず、体調が悪くなって受診すると、患者は信頼と尊敬をこめて医師を「先生」と呼ぶ。けれど、なかなか病気が治らなかったり、かえって悪化したりすると、薬ばかり多く出して儲け主義とか、無能とか腕が悪いとか人格がどうのとか、感情的な批判をして、最初の信頼と尊敬が、不信と軽蔑に一変し、「あの医者」と侮蔑的な口調になったりする。
医師は神様ではないのだと、私はいつも思う。ところが、医師は神様だと思っている人が多いような気がする。受診して、処方された薬を飲んで、手術したりして、それまでの病苦から解放され、病気は完治する、医師は神様だから治せないはずがないと、理論ではなく感情的にそう思い込んでいる人が少なくないような気がする。
実際、私の周囲で、病院に車で送迎している知人の肉親の、〈経過観察〉の病気の話の時。私が質問するたびに、答えられなかったり曖昧な答え方をしたりし、「先生にお任せしているから」という言葉が何度も出てくるのだった。
(どうして主治医に聞かないの? 病気は主治医のものではなく、自分の身体に起きた自分のものでしょう?)
そう言いたかったが、人それぞれのやり方があるし、気を悪くさせるような気がし、私は言葉を呑み込んだ。
私の少ない経験や、見聞したりテレビで見たりする限り、概して、医師は病気の特定に慎重である。薬剤師のように自信ありげな口調で話したりしない。それは、医師はあらゆる病気を想定するからではないかと思う。
医師だって病気になるのだ。開業医の友人は、インフルエンザの時期に次々来院する患者を加療しているうちに、感染してインフルエンザに罹ってしまったことを開業医の宿命と、手紙に書いてあった。
持病のある医師もいるし、『医者が癌にかかったとき』(竹中文良・著)という体験記を読んだこともある。もし、医師が神様なら、自分は病気にならないし、なってもすぐに治るはずである。
そう言えば、以前、建築デザイナーの知人女性は、病院へ行くのが昔から好きだと言っていた。何故、好きかと聞いたら、体調の悪いのが良くなるからだと。そういう人にとっては、<お医者さんは神様>と思っていていいのかもしれない。
けれど、報道番組やドキュメンタリー番組で見る限り、神様である医師が病気を治してくれない、お金ばかりかかる、かえって悪化した、こんなに被害を受けた、神様どころか冷酷無残な人間、お金の亡者、と言わんばかりに主張する人が目立ち過ぎると思う。
もっとも、テレビ番組というのは、こんないいお医者さんに出会えて病気を治して貰ったという話より、こんな悪徳医師に出会ってこんな被害体験をしたという話のほうがインパクトがあると言えるかもしれない。
けれど、その夜の番組を見終わった時、明日から、『うつ』以外の診療科でも医師たちは薬を出しにくいのではないかと、私は思った。薬の効果や副作用は個人差があると思うし、現代医療には限界というものがなくはなく、たとえベテラン医師でも実際は手探りというか半ば迷いながら患者に薬を処方している、ということがないとは言えないかもしれない。医師は、先生と呼ばれ、社会的地位も収入もあるように思われる職業だけれど、その能力や腕や人格について何人もの他人から毎日毎日、評価を受けているようなものと私には感じられる。レベルの高い特殊な知識と能力を持つ自信と誇りと、人知れず自信喪失と迷いと焦りと後悔と、諦めや絶望や無力感や憤りや虚無感など、さまざまな想いをかかえて仕事しているように見える。普通の神経で生きて行けるとは思えないと言っていいくらいだ。しかも、あのようなドキュメンタリー番組で、医師不信というか医療不信というか、薬の副作用や恐怖を視聴者たちにイン・プットされてしまっては──。
それとも、うつ病という病気に限定されることであり、薬が乱用されがちと言われるのは抗うつ剤だけということなのだろうか。薬と言えば厚生労働省とか製薬会社の責任はないのだろうか。うつ病の人たちやその家族たちは、あの番組を見て、どう思い、どう感じただろうと私は想像した。
それに、何種類もの薬を処方され、治ると思い込んで、毎日きちんと飲み、治った人だって少なくないかもしれない。私自身、そう思い込んで、何種類もの薬を飲もうとしたことがある。もう、ずっと以前のことだが、夜中に咳で目が覚める気管支炎のような風邪をひいた時だった。市販の風邪薬を長期に飲んで治らないまま、こじらせたのだと思う。すすめられて近所の内科医院へ行った。風邪で内科へ行くのは、15年ぶりぐらいのこと。23歳の時に、風邪と思って内科医院へ行ったが治らず、病院で麻疹(はしか)と診断された時以来である。その後、風邪をひかなかったわけではなく、たいてい市販薬で治っていたので、内科医院へ行くことはなかった。
久しぶりに行った内科医院。何故か、ワクワクした気分も少しあった。熱はないが、咳が激しく出るという症状を話すと、聴診器を当てられた後、2種類の風邪薬を処方されて、一週間飲んだ。治らないので、別の内科医院へ行った。レントゲンを撮って、肺には問題なく、3種類の薬が一週間分出て、飲んだ。治らないので、3軒目の医院で、やはりレントゲンでは異常ないけれど、5種類の薬が処方された。この時のドクター・ショッピングは決して医師不信ではなく、よく効く薬を出してくれる医院への期待と、徒歩圏内に内科医院が何軒もあったため、あちらへ行き、こちらへ行き、というのが新鮮で少しは楽しかったのである。
(5種類の薬を飲むのは大変だけど、我慢して、一生懸命、これだけの薬を飲めば治るかもしれない)
そんな気持ちで帰宅した。当時、半同居していた家人は何でもよく知っている人で、少しでもわからないことや自信のない答えはすぐ百科事典で調べるような人だった。私が処方されて来た5種類の薬のローマ字や記号を確認しながら、『病院で貰った薬がわかる本』という本を見て調べ、解熱剤などの不要と思われる薬を除いてくれた。5種類の薬を飲むのは身体に悪いと言われ、他の処方された2種類の薬を飲んだが、治らない。連日の咳でさすがに食欲も落ちて、作って貰った卵おじやとお味噌汁とりんごとみかんだけの食事で、もう死にそうと思うくらい体力も気力も落ちてしまった。その後、それまで1度も飲んだ経験がなかった漢方薬を家人にすすめられた。家人が漢方薬局店で、私の症状を薬剤師に話し、買って来てくれた五虎湯という漢方薬だった。夕食前に1袋飲んだら、その夜は咳で目が覚めることはなく、翌日にはもう咳の発作がおさまっていて、嘘みたいと驚いた。1箱3日分の薬を飲み終える前に、苦しい咳は消え、風邪は完治したのである。それまで半信半疑だった漢方薬との初めての出会いだった。
それから、さらに十数年後に、就寝時の呼吸困難が起き、インターネットで漢方薬を処方する医療機関を調べて、近所の診療所を受診した。血液検査、レントゲン、心電図に異常がなく、医師は病名を告げない。原因がわからないから病名を告げられないのか、想像はついていて、うかつに告げられないのか。私はネットで調べた漢方薬の名前をメモして行って主治医に見せ、「その薬を処方して下さい。飲んでみたいので」と言って、処方して貰った。医師はその薬が効くとも効かないとも言わなかったが、あまり効かないかもしれないと言われた言葉は印象に残っている。プラセボ効果ではないが、この薬は効くかもしれないと医師から言われたら、暗示にかかりやすい私は、効いていたかもしれないという気がしなくもない。
その薬を1週間飲んで効かなかったので、ふたたび、その医療機関へ行き、ネットで調べた別の漢方薬の名前をメモして行って医師に見せ、「その薬を処方して下さい。飲んでみたいので」と言って、処方して貰った。こんな患者は初めてと医師は内心、呆(あき)れていたかもしれない。
また、耳鼻咽喉科で喉の検査をすることをすすめられ、ネットで調べた近所の2軒の耳鼻咽喉科へ検査に行った。最初に行った耳鼻咽喉科の医師が、横柄な感じの悪い医師だったので、検査の途中で、「やめます」と言い、中断して帰って来た。中断でも高額の検査費用を請求された時は、内心、腹立たしかった。翌日、2軒目に行った耳鼻咽喉科の医師は、信頼できる感じの良い医師でホッとした。検査の結果は異常なしだった。5日分の薬を処方されたが、薬の名前をネット検索したら、何と〈睡眠導入剤〉の薬だった。睡眠薬は長期服用の薬という先入観と、何度もあくびが出るほど眠いのに〈睡眠導入剤〉を飲む必要があるとは納得できず、漢方薬ではなく化学薬品への怖さも感じたりで、薬は飲まずに捨てた。処方薬が5日分というのは初めてで、風邪の時など多くの医療機関は1週間分か2週間分なので、化学薬品のダメージを考えてのことかもと思った。
次回、かかりつけの医師に、耳鼻咽喉科の検査の結果は異常なしだったことを記録したメモを見せたら、「えっ、耳鼻咽喉科へ行ったの?」と小さな驚きの口調。「だって、耳鼻咽喉科へ喉の検査に行くようにって、前回、先生に言われましたから」と言うと、「ああ」の後、医師が何か言ったか言わなかったか記憶にないが、私はコケた。内心、(行かなくても良かったのオ!?)と呟いたが、信頼できる医師だから、患者に言った言葉を忘れても、非難する気にはならなかった。
就寝時の連日のような呼吸困難といっても、全く息が吸えないというわけではなく、正確に言えば、息が吸いにくいという感じで、横向きになったり、外出日や来客のある日の夜は、神経が疲れるせいか不思議と症状が起こらないのである。漠然と、私は年齢的または精神的な原因、よく聞く不定愁訴ではないかと自己診断していた。
または、枕に原因があるのかもしれないと思い、デパートへ枕を買いに行き、いくつも試して比較的ラクなのを買った。それから、家電量販店へ行ってパソコン・ソフトを買い、その近くに漢方薬局店があるのをネットで見て知っていたので、そこに入った。
症状のメモを読み終えた熟年薬剤師が、
「西洋医学的に言えば自律神経失調症、婦人科的に言えば更年期障害、東洋医学的に言えば血の道症だと思いますよ」
と言ったが、私の自己診断と、〈当たらずといえども遠からず〉のような気もした。ただ、自律神経失調症という言葉が気になった。仕事がハードな従兄が数年前に自律神経失調症で数か月間、入院したため、興味が湧き、書店で自律神経失調症の本を2冊買って来て読んだ。
その薬局で薬剤師にすすめられて買って来た『半夏厚朴湯』という漢方薬が効いたので、かかりつけの診療所へ行き、それと同じ漢方薬を処方して下さいと言った時、
「市販薬より、処方して貰う薬のほうが成分が強くて、効き目も強いのでしょう?」
そう質問したら、
「若干(じゃっかん)ね」
医師がそう答え、私はその言葉が今でも忘れられないほど印象に残っている。
偽薬、プラセボという薬に関して、ネット記事で読んだことがある。本物の薬に見えるが実際は偽物。新薬の治験でプラセボ薬と本物の薬とで比較して、効果を調べたりするらしい。
あの3か月間の<漢方薬服用迷走>は何だったのだろうと、今でも思う。本当に効果のある漢方薬だったのか、プラセボ効果みたいにきっと効く、きっとこれで治る、と信じ込んだ私の精神状態が、案外効果的なだけだったかもしれないと、そんな気がしなくもないからである。
先日のドキュメンタリー番組で、大量の薬を処方されたとか、薬の説明はなかったとか、まるで被害者意識にとらわれているみたいな発言には、私はあまり同情できない。薬についての認識が違い過ぎるからだ。1種類の薬でも数種類の薬でも、信頼できる医師ならその医師を信頼して、きっと効く、きっと治ると信じて飲めば効くことが多いと言えるのではないだろうか。やはり、病気を治すのは本人であり、医師と薬は補助してくれるものという考え方をしたいと私は思う。