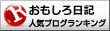今年の大河は「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」あのTUTAYAのご先祖さんかいな?て思われるでしょうばってんが血筋的には関係ありません。
戦国物好きのおいしゃんではありますばってんが今回のも守備範囲であります、て言うとも舞台が吉原ですけんね。この吉原、お江戸小説には頻繁に出てきますけん吉原内の見取り図もおいしゃん大概頭の中に入っとります。日本堤やら五十間道、見返り柳、大門、鉄漿どぶやら、初回に出て来た「くろすけ稲荷」やらはお江戸小説にもたびたび出てきます。
特に「吉原裏同心」はまさに舞台は吉原ですけんね。食は人の天なりの「みおつくし料理帖」も女料理人と花魁の友情物語です。その橋渡しするとが女郎宿の料理人「又次」でした。
この色里、裏社会ではあるばってんが現在でちゃソープやらデリヘルやら法の解釈かいくぐって堂々と存在するっちゃけん庶民とは昔から切っても切れん部分ではあります。昭和の売春禁止法前までは日本各地に赤線・青線て言われる色里がありました。博多にも古くは柳町やら春吉に存在しとりました。博多の今の古ノ二辺りも青線て言われる色里がありました。
昔の吉原は一つの生活圏で全部その中で完結しますけん住人もおるしお店もあります。外部からもの売りに来る商売人もおったようです。当然そこで生まれ育ったものも多くおって外の生活は知らずに生きていくものも多くおりました。ばってんが吉原は女郎以外は出入りは自由で女性も手形ば持って入れば出入りでけました。
ばってんが女郎たちはこの吉原の大門から外に出るとは一部の花魁ばのぞけばでけません。出入口は大門一つでぐるりはネズミ返しが付いた塀で囲まれその内側は鉄漿(おはぐろ)どぶて言われる濠で囲われておりました。唯一火事が起こったら再建まで市中での営業が許可されるけん女郎たちはその時だけは外の暮らしがでけました。今回も外に出たいばっかりに初回に火つけばした女郎が登場しましたね。
お江戸の華は火事と喧嘩て言うくらいでお江戸は火事が多くてこの吉原も最初は日本橋にあったとが明暦の大火ばきっかけに町中から離れた場所に移され浅草田甫の中にポツンと作られた塀に囲まれた町です。吉原の地、今ではソープ街になっとるみたいですが昭和の中期まで存在しとったゲナです。当然明治以降では官許や無かったろうばってん。見返り柳は現在も残こされとるみたいです。
ちなみにこの明暦の大火は江戸の市街地の大半ば焼き尽くし、この時、江戸城の天守閣も焼失しその後再建されませんでした。明暦の大火以降江戸の町は延焼ば防ぐためにあちこちに火除け地て言われる空地ができそこで昼間は露店が出てにぎわったそうです。
今回のべらぼうは吉原が浅草田甫に移って全盛期になる少し前からの物語のようです。顔ぶれも田沼意次やら長谷川平蔵、平賀源内、鳥山検校(けんぎょう)とバラエティに富んで面白くなりそうです。
長谷川平蔵は「鬼平犯科帳」になる前の若き平蔵が登場しましたばってんがこれはどうもイメージは合いませんでしたやね。優男すぎます(>_<)。田沼意次も歴史上では賄賂の権化のごと言われて久しいですばってんが最近ではそうやなかったて言う説もあり今回は後者の意次の扱いみたいです。鳥山検校、検校とは盲官(盲人(あんま)の役職)の最高位であって社寺や荘園の監督役職名で大金持ちで通ってます。時代劇でも大概悪者ででてきますもんね。
いずれにしたっちゃ今回は戦国物でも前回の貴族の物語とも違うて庶民が舞台の物語やけん面白そうです。他の時代劇では花魁は高貴で近寄りがたい存在として描かれとることが多かとですが今回は普段の素顔の生活が出てくるけん親しみやすいですね。
吉原には最初の頃は江戸詰めの地方武士や大名も多く通うたようですばってんが江戸も中期になってきたら生産性の無か武士たちは将軍家しかり金繰りに困り、羽振りの良か商人たちが頻繁に通うごとなります。
この吉原は花魁がおるとこばっかりやのうて金のない庶民もそこそこの値段で遊べよりました。その底辺が良く出てくる羅生門河岸やら言う「ひと切り何文」て言う最下級の女郎がおる見世です。当時蕎麦の値段が十六文の時代です。大店で歳とった女郎たちは最後にこげな河岸に落ちぶれて死んでいくとです。これも今回、初回で出てきました。
制作者によるとこげな影の部分も摂りれて制作していきたいて言われよりました。それとメインは浮世絵師やら作家のお話。日本が世界に誇る浮世絵が登場してきた時代の物語です。中には春画て言ういやらしか絵も庶民の間で流行りますばってんがあれ見て何が興奮するとか現代人のおいしゃんはわからんばってんが、日本でちゃヌード写真や如何わしい動画が平気で見られるごとなったとはごく最近のことで写真もない時代はあれで想像掻き立てられよったとでしょうね。日本でも戦後は逆さまにしたら女の人が裸になるボールペンやらありました。ばってんがもろ出しはまだご法度でおいしゃん家にも親父が後生大事にして「見つかったら捕まるけん」て言う博多人形のあります。

※大事なところはかくして映しました(>_<)
あそこの部分まで精密に描写した「春人形」て言いますか戦後生活のために裏で売り買いように作られた博多人形です。桐箱に入れて今もおいしゃんの手元にあるっちゃけど、こげんとメルカリに出すこともでけんめぇけん博物館に寄付しょうて思うた時期もあったばってんが未だに持ってますと(>_<)これおいしゃんが死んで子供たちが見たら「親父の変な趣味」て思われんか心配です(^^♪
そげなこげな庶民の今回の大河今年も一年楽しめそうです
ちゃんちゃん