飾り山公開ば待つだけになりました。
朔日に御神入されてご神体となります。
ほとんどの舁き山は七月に入ってからの棒締めが多かですが
引き出し山(飾山の台ば舁山と共有する)の中州流は昨日
舁山・飾り山の準備も終えました・・・・・・・・・
ここまでいろいろな工程が山大工の手によって行われ
八文字掛けや棒締めやらは良う紹介されますばってんがそれ以外に
いろいろな作業ば経てここまで作り上げられます。
今回はちょこっとそこんとこば紹介しますね・・・・
通年は解体しとった山台の組み立てから・・・・・
一番山ば期に山台新調する流は大工が本職の山大工が制作します。
新調するとき、流の希望によって舁棒の間隔や高さの調整して新調します。
良く山笠は釘一本も使わず組み立てられるって言いますばってんが
これは山台のことです。
込み栓や鼻栓で隙間ば埋め、八文字掛けで台ば固定します。
山台は舁く時のショックに耐えるごと余裕ば持って作られとります。
現在の走りぐっちょの山ならではの先人の山大工の知恵です。
山台は突っかけた時のために本体は後ろにわずかに傾けて作られとります。
それば八文字て言う縄かけで山台ば固定します。
そのあと装飾ば兼ねて方杖やら丸束に小縄巻し
山足の四隅の補強に番線ば巻きつけます。
番線はショックアブソーバーの役割ば務めますったいぃ・・・
そのあと杉壁やら杉壁に装飾する麦束の準備ばします。
麦束は台上がりが手にする鉄砲やら杉壁の装飾に飾る麦束に多量に使います。
ここまではほとんど大工仕事ではなく「山大工」や「ヒヨカタ」のお仕事です。
杉壁に使う縦笛や横笛の篠竹の装飾や杉壁に使う大竹や杉の葉の調達も
山大工の仕事です。
流にもよりますばってんが大黒流の場合はこの材料の調達までほとんどが
当番町のお仕事になります。
山台ができたら棒締めして完成です。
ここからは人形師の指図で飾り付けが始まりここからは大工さんのお仕事。
矢切の取り付けから人形の飾りつけ。
最後にしなえの取り付け台幕の取り付け、赤熊(しゃぐま)や大弓(だいきゅう)の
取付、標題板の取り付けして完成です。
旧来から山笠飾りのタブーとされてきた題材があります。
武田信玄・川中島・竜神・大蛇・高師直等です。
昔の人は演技担いで災難や事故が起こった時の人形と結び付けて
考えたけんです。
これにあえて迷信に挑戦したとが名人小島与一さんです。
それ以来この迷信にとらわれず昨今は龍やらはたびたび登場します。
今年の櫛田神社の山笠には「八俣遠呂智(やまたのおろち)
中洲の舁き山には「龍鬼願安寧(りゅうきあんねいをねがう)」と
それは大きな龍がとぐろ撒いとります。
竜神・大蛇を飾ると水害が起こるて言われますばってんが
山の時期は梅雨でただでさえ雨が多い時期やけん昔からたびたび
水害も起こりよったんでしょうね・・・
さぁ明日早朝からヤマが始まります!!
ランキングに参加中です。
見るたびにクリックしてつかあさい!
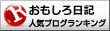
最新の画像もっと見る
最近の「山笠・博多の事」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事














