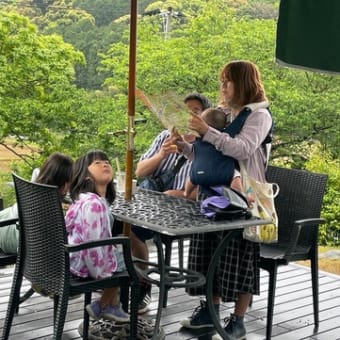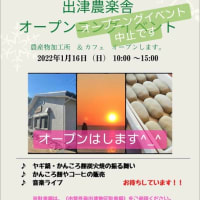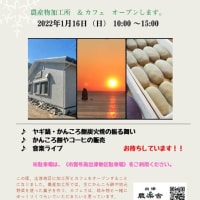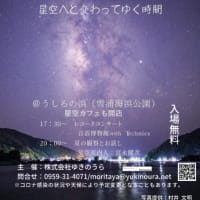昨日は、雪浦観光ガイドの下見 兼 実地練習ということで、雪浦一帯を、ガイドのシナリオに沿って、歩きまわりました。

毎日歩いている雪浦なのに、あたらしい発見がたくさん。
雪浦の見どころを、ちょっとまとめてみました。


雪浦のあちこちにある通り名プレート。昔から通りについていた名前を,復活させました。
このプレートは、ウィークのメンバーが作り、タナカタカシさんが、文字を書きました。趣があり、雪浦の小路の雰囲気にぴったりです。
さて、通りの後ろにある♯19や♯15の意味、知っていますか?・・・・これは、♯19だったら、「この通りの起点から、190メートルの位置です」という意味です.
矢印がありますが、なんだか知っていますか?・・・・これは、この通りの起点が、矢印の方向にあるという意味です。

「小路」とありますが、これは雪浦では、「しゅうじ」と読みます。
このプレートから分かることは、「中小路」という通りの基点が、矢印の方向・右側にあり、その起点からここが、220メートルのところである・・・ということです。

これは、十膳寺通りの名前の由来となった薬師如来堂跡。井戸の跡が残っています。通りから、ちょっと入ったところにあります。

これは、山水をあつめているところ。


これは、山から水を引いていて、蛇口をひねると、冷たい山水が出てきます。大正10年に設置されました。今でも、生活水として活用されています。


雪浦の石垣は、結晶片岩。きれいに割れるので、石垣に適しています。特に、雪浦の石垣は美しいです。
この石垣が、山の中に入ると、たくさん見られます。今は、草木で覆われてしまっていますが、昔は、田んぼや畑だった名残です。
イノシシ除けの「ししがき」も、このような結晶片岩で作られていて、70キロメートルにわたり、山の中に続いています。
西彼杵半島の万里の長城とも言われます。

雪浦診療所のあたりは、清水と呼ばれています。


診療所のすぐ近くにこのように山水が湧いているところがあります。飲めるそうです。清水という地名の由来ですね。
雪浦一帯には、遺跡や貝塚が何か所も見つかっています。この辺りは、清水遺跡。
1998年、雪浦診療所の建設と河川改修工事を行った際に、土器や石鍋、陶磁器などが出土したそうです。
時代は、縄文前期、後期、弥生。

「じばとおり」と読みます。

1789年から1795年まで、森伊平衛(もり いひょうえ)さん監督のもと、干拓工事が行われ、この水路の右側が水田、左側が塩田となりました。この干拓がおこなわれる前は、診療所から先の今の田んぼ一帯が、住宅地だったとのことです。

この一帯が、塩田があったところです。
雪浦の歴史は面白いく、遺跡や名所まだまだあるんです。
一歩踏み入れてみるだけで、これまでとは、ちょっと違った雪浦が見えてきます。
雪浦の魅力は、豊かな自然と、町並みに眠る歴史、そしてそこに住む人々。
今回は、「町並みに眠る歴史編 その1」・・・でした。