
前回記事の続きになります。
はじめての方はそちらからどうぞ。
前記事で述べた
世界の歴史を変える事実
とは何か。 ズバリ言うと
世界最古の往復航海が日本で行われていたこと
です。
これまで、人類が確かな航海技術をもって(漂流して流れ着いた、とかではなく)海上を往復した記録は、東南アジアのインドネシアからオーストラリア、ニューギニアへの渡航(約2万年弱前)などが言われていました。
日本でこれまで見つかっている一番古い遺跡は、約3万8千年前辺りまで遡る、後期旧石器時代と呼ばれる時代のものです。この年代に同じような特徴を持った遺跡が複数見つかっています。そして、これより前の遺跡は現在見つかっておらず、この年代以降に遺跡数が増えていくことから、この頃に日本列島に人類がやってきたと現在は考えられています。
そんな遺跡の一つである静岡県沼津市の井出丸山遺跡で、黒曜石でできた石器が多数見つかりました。それを分析してみたところ、そのうちの幾つかが神津島の黒曜石であることが判明しました。
ここで少し歴史に詳しい方は、静岡県と伊豆諸島なら、距離的には近いし、旧石器時代は海水面が低かったから陸続きだったんじゃないの?と考えるかもしれません。
しかし、研究によると、当時の海水面は今より100mほど低かったものの、間にある海峡が深かったため、伊豆諸島と伊豆半島は陸続きになっていなかったと考えられています。しかも、現在と変わらない、あるいはもっと強い黒潮海流が間に流れていたとされています。

約3万8千年前の関東、伊豆諸島の地形 参考元:海部陽介『日本人はどこから来たのか?』より
つまり、
当時の人々が舟(どのような舟かは不明ですが)を用い、黒潮を横切り、神津島に渡って本土に帰った(往復した)
ということを、神津島の黒曜石が証明したのです。
正に探偵もので言うところの「物的証拠」というわけです。
そして、これはそれだけのことをするための「高度な航海技術」を、当時の人々が持ち合わせていたことを示唆します。
これは、日本列島にやってきた人類が、対馬海峡や南西諸島、シベリア、サハリン(こちらは陸続きだったようですが)から「海を越えてやってきた」とする最近提唱された有力な学説を強力に補佐するものとして、国内だけでなく海外でも注目され、現在、学会での発表や海外有名誌での論文紹介が盛んにおこなわれています。
さらに、上野にある国立科学博物館の研究チームが、当時の海上渡航を、当時の技術だけで行おうという壮大な実験を行い、去年、遂に台湾から与那国島への丸木舟による海上渡航を成功させました。
ここまで話せば、何となく分かっていただけるかもしれません。
私が何故、わざわざ離島に移住してまで黒曜石を追っかけているのか。
それは
神津島の黒曜石が、太古の人類が持っていた技術の超重要な手掛かりを持っているから
なのです。
これだけのことを証明した神津島の黒曜石。研究を続ければまだまだ色々なことが分かってくるに違いありません。で、せっかく研究をするなら、現地で直接黒曜石を集めながらやった方が効率がいいわけです。ちょくちょく島外から黒曜石の研究目的で著名な学者先生方もいらっしゃるので、現地島民としてその方々と交流、サポートもできて一石二鳥。色々都合がいいわけです。
まぁ、なんだかんだ長々と書き連ねましたが、とどのつまりぶっちゃけますと
追い続けたい研究の対象に四六時中触れ合いたいから
ということです。
これが、私が離島に移住した理由。
・・・こうやって書くと、改めてヘンタイ感ありますね。参ったなコリャ。(完)















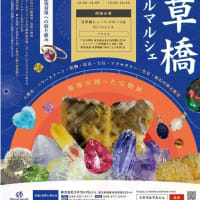




林さんの探究心と行動力本当に尊敬します!
「追い続けたい研究の対象に四六時中触れ合いたいから」これシンプルで最強の答えですね!
これができるのも、周りの皆様が色々と良くしてくださっているおかげであります。ありがたいです。