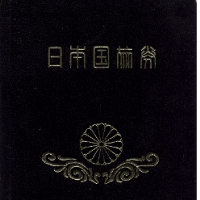4時起床、起床時間の乱調子になれてしもて、このところのように略4時前後で安定してると、何で?と思うてしまうね。
”治にいて乱を忘れる”では無く”乱にいて治を忘れる”という事もあるんかいな?ですなぁ、治を忘れとうは無いなぁ。
昨日は1日中インチキ植木屋をしてたんですが、同じ樹上でも作業位置が低かったのと、脚立での仕事も結構有ったんです。
その為もあってか、連休中の作業である程度体が慣れたのか、筋肉痛等は全く起きず、至極快調ですわ。
剪定を終えたマツを見ると、一生懸命サボらずしてたのに、何で2日も掛かったんやろ?と思いますなぁ。
掃除や修理というのは、やった経験の無い人ほど簡単に思いがちで、割りに軽視する傾向があるんとちゃいます?
確かに、最近の製品は修理時の作業性を配慮してない物が多いし、新品価格が下がったんで相対的に修理費が高う感じる。
壊れたら修理などせず新品を買うのが当たり前、修理依頼したら不思議な顔をされる、旧型人間は釈然とせん事が多いね。
朝一にカミさんは近所の某オアシスへ”あきたこまち”、私は1駅宝塚寄りの某オアシスへヨーグルトを買いに一っ走り。
一旦帰宅して、お次は国立民族学博物館ウィーク・エンドサロンへ、今回の話題はカミさん好み。
11時37分岡町駅発に乗り十三駅乗換えで山田駅下車、デュウ山田の「とりプロ」で空揚げ甘酢餡かけ弁当を購入。
自然文化園に入ると西大路に人が一杯、キラキラ光ってるのは楽器?どうやら吹奏楽のイベントがあるみたいでした。
中津道から北口へ迂回して万博記念公園のバラ園レストハウスに13時着、デッキで昼食後民博へ。
開場までの間に、先日説明パネルが入れ違って無いか訊ねた二・三・四胡を見に行ったら正しい組み合わせになってました。
そういえば、5月2日にジャガーナウトの前で三尾民博准教授と話してたら「あれ?説明パネルが逆だ。」いうてはったね。
さて、今日の”ウィーク・エンドサロン、研究者と話そう”は、
染織の伝統と現代―新しくなった南アジア展示場
南アジアの刺繍や染め、織りなどの染織文化は、多様な自然環境からうまれる繊維素材や染材などに支えられてきました。現代のグローバル化においてこれらの染織文化はどのように変容しているのでしょうか。新しくなった展示場で染織文化の伝統と現代にてついて紹介します。
話者:上羽陽子(国立民族学博物館准教授)
【以上、参照及び引用元:国立民族学博物館HP】
ナビ広場で話を聞いた後、皆んなで展示場へ移動して、現物を見ながらお話を聞きました。
何というても、現物が持ってる力は映像とは比べ物になりません、まして民博は触ってもOKな展示が多意のが魅力ですなぁ。
特に民族学の場合は現場、現物主義、地図を見るより現地を観よ、写真を見るより現物を触れ、が大事やねぇ。
帰り道の十三駅構内阪急そば”若菜”でオリジナルメニューのチャンポンうどんで夕食。
同じホームの551蓬莱でアイスキャンディのフルーツとアズキを5本づつ買ったらお姉さんが「箱にもう2本入りますよ。」。
人間が素直やから2本追加、しかし551蓬莱はエエ社員教育してる!ホッキョクグマも寄付してくれたし、益々惚れるねぇ。