立春大吉はシンメトリー
春の縁起の良い言葉、立春大吉を紹介します。
立春とは、古来の季節を表す言葉「二十四節気」の最初の時季。
2021年では、2月3日が立春の日です。
この立春の早朝、禅寺では、魔除けや厄除けの意味を込めて『立春大吉』と書いた紙やお札を門に貼る習慣があるのです。
- 魔除け
- 厄除け
- 幸運を呼び込む
四柱推命や風水等では、節分までは前年で立春をもって新しい年が始まると考えられています。
節分の豆撒きは大晦日にあたり、厄を祓って、翌日の立春から新しい年の幸運を呼び込むしきたりだったのです。
では何故禅寺で『立春大吉』と書いた紙や札が貼られるようになったのでしょうか。
禅寺でも曹洞宗のお寺でこの習慣を実践しているところが多く、お寺だけではなくそのお寺の檀家となっている家にも配られる『立春大吉』の札ですが、縦書きにした『立春大吉』という文字をよく見てみてください。
シンメトリー、左右対称になっているのにお気づきでしょうか?
この熟語は大変珍しくも、シンメトリーになっている言葉なのです。
つまり、和紙に墨字で「立春大吉」と書くと、表から見ても裏から見ても立春大吉と読めることが、こんなエピソードを生みました。
節分で祓われた鬼が、再び災厄を持ち込もうとその家の門をくぐりました。
その家の門には、立春大吉と書かれた紙が貼られてありました。
門をくぐった鬼がふと振り向くと、くぐったはずの門に再び立春大吉の文字が書かれてある紙が貼られてあるのが見えます。
鬼は「あれ?くぐったつもりがまだ門をくぐってなかったのか?」
鬼は勘違いして、門の外へと出ていってしまいました。
こうして禍を避けることが出来た。笑
なんて頭の悪い鬼・・・きっと、もっと深い話なのでしょうけど、表面的にはこうした話です。
しかし、なぜに鬼は振り返ったのか?疑問が残ります・・・
門の外に出て、また振り返れば、紙がそのままであるのに気づき、
再びうちに入れたのではないのか?
そして、また振り返り、また戻り、さらに、、、(この話は永遠にループ)
何だかよくわからない逸話ですが、昔の人が如何にして縁起を担ごうとしたのかがわかるエピソードということにしましょう。
このことから「立春大吉」は、鬼を払う力があると信じられているのです。
立春の日の太陽の光には、いつもの倍以上もパワーがあります。
そんな太陽の日差しに財布をかざすことで、1年金運が上昇すると言われております。
春に買う「春財布」は、(お金をパンパンに)張る財布とも言われ、縁起がいいことで知られています。
お財布に限らず立春に合わせて新しいものを使い始めることで良い運気を呼ぶことが出来るのでお薦めです。
禅語をテーマに日々の思いをブログにしています→良かったら、こちらにもおこし下さい

















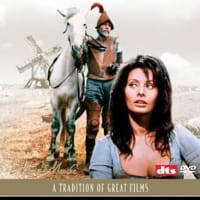

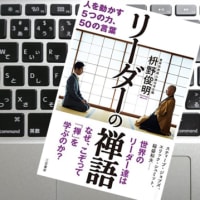
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます