
誰よりも穂高を愛し、穂高に暮らし、仲間とともに多くの遭難者を救助。漫画『岳』の宮川三郎のモデルとなった熱血漢。穂高岳山荘元支配人・宮田八郎の遺稿集。
第1章 穂高に生きる―山小屋暮らし三〇年の日々(一〇代で穂高の小屋番に
はじめて出動した遭難現場
憧れと修業と研鑽の日々 ほか)
第2章 遭難救助の現場から―人を助けるのは当たり前(子供のはずが…予想外の事態の救出劇
スタッフ総出で救助救命に奔走した一夜
奥穂高岳「間違い尾根」のハプニング ほか)
第3章 わが師、わが友―その誇りと英知と死(穂高の守り手たち
映像で描く串田さんの言葉
「アルパインクライマー」という矜持 追悼・今井健司 ほか)
穂高のこれまでの遭難死亡者は世界一ですらあるかもしれません。
谷川岳が累積死亡者数800余人で世界一の「魔の山」だが、
穂高は長野と岐阜の両県にまたがるためその正確な死亡者数の記録はありません。
僕の実感では、少なくとも毎年10人以上の方が穂高で亡くなっています。
2014年、15年はなんと年間20人以上が穂高で遭難死しているのです。
はじめてのレスキュー現場は白出(しらだし)沢でした。
現場である白出沢のセバ谷付近から山荘までは標高差で500m。
小屋のすぐ裏手から飛騨側の右股谷へ向かって1直線に落ち込む白出沢は、穂高岳山荘の歩荷道であり、小屋番にとっては「通勤路」ともいうべき登山道です。
35kgの荷を背負って標高差1500mの雪渓あり岩場ありの白出沢を登るのは。いかに自分を鍛えてくれたことか。いまでは通算100回以上もたどって歩き慣れたこの山道も、当時のぼくには歩荷にひたすら喘ぐ地獄のような道のりでした。
東邦航空の篠原秋彦氏;山岳高性能ヘリ「ラマ」「遭難救助基金」
これは東邦航空という民間会社のヘリを救助に使用する場合、当事者からその費用負担の承諾を得ないことにはダメだったものを、現場の判断のみでヘリを動かせるようにした画期的なものでした。
「生活必需品」
倉本聡の「富良野塾」では「1水、2火、3ナイフ、4食べ物、5衣類」
東京では「1お金、2ケイタイ、3テレビ、4車、5家」
穂高岳山荘では雪渓から水を得ています。
「天命水」と名づけられた水は、急斜面の雪渓の底に流れる水を200mのホースで小屋に引き入れています。水平に雪の穴を掘っていった14m先に「天命水」の水源がある。
行方不明となる登山者の90%以上は単独行者です。
そんな単独での遭難を題材にした映画で『127時間』という海外の映画があります。
登山者の義務(登山届け)に加えて「覚悟」という言葉を思い出します。
「私は以前、鑑識課にいたことがあります。
そこで仕事柄さまざまなご遺体を拝見してきました。
しかしこの高山署に赴任して、山から下りてくるご遺体を目にすると、その悲惨なこと甚だしい。山小屋のみなさんは民間人でありながら、よくぞそうした方々のお世話をしてくださる」
あらぬ方向に曲がってしまった手足、石がのめり込んだ皮膚、中のものが出てしまった胴体、そして血まみれで半分ないような顔・・・。
篠原秋彦氏;現場は鹿島槍ヶ岳東尾根一の沢ノ頭
「認知・予測・判断・行動」のキーワード
いま自分がおかれている状態を知り、これからその状況がどう変化あるいは持続していくのかを予測し、それからどうした行動をすべきなのかを考え、そして実行に移すというプロセスを踏むことがよくわかります。
そこに存在するリスクを「知ること」
そもそも山に登るという行為は、そこに存在する危険を受容すること。
登ってきた登山者とすれ違うために先生は「どうぞ」と谷側によけたそうです。その直後、先生の姿は音もなく乳白色の霧の中に消えてしまったとのこと。現場の路肩にあたるその部分には、岩がそっくり抜けたバケツほどの穴の跡が残っていました。
それが登りであれば、踏んだその一歩の支えが抜けたとしてもこらえることができたかもしれません。しかし下りで、しかも道を譲ろうと踏み出した足元が崩れれば、成すすべはありません。
ザイテングラートのどこにでもありそうなその地形は、いったん踏みはずしてしまえば谷底へと1直線で、人の体を止めてくれるものはありません。
登山道ですれ違うとき、下る人は谷側へよけてはいけません。
下る人が山側によけて、登る人が路肩に注意しながらすれ違ってもらうべきです。
下りでバランスを失うと致命的な結果となるのです。
奥穂高岳~西穂高岳縦走雑感
およそ地図に載っている登山道としてはおそらく日本一の難路ともいわれるこの縦走路。
この場合、その積算標高差は1200mとも1600mともいわれ、しかもその間に1000m以上を下降するという、実は非常な体力ルートであるということです。
奥穂→西穂と西穂→奥穂ではこれまで思っていた以上に難易度に差があるのではないか。
西穂→奥穂のほうがかなり大変なのではないか。
その大きな要因は天狗のコルとジャンダルムの標高差です。
西穂から奥穂へと向かった場合は、天狗のコルからのキツイ登りのあとに縦走路中のハイライトともいえるジャンダルム~ロバの耳~馬の背を迎えます。
これはやはり体力的に「くる」のではないかと思います。
もっとも奥穂→西穂も、ジャンダルムからの長い下りで足が疲れたあとに天狗ノ頭、間ノ岳、西穂と越えていくわけで、西穂の下り(とりわけピラミッドピーク付近)で事故が多いのもそれが原因かもしれません。
所要時間でいうと間違いなく西穂→奥穂のほうが時間がかかると思います。
ちなみに大キレットは「槍(南岳)→北穂」が有利で、逆コースは難所がモロに下りとなって難しくなります。
個人的には、この縦走路中でもっとも難しいのは、ジャンダルムからロバの耳の小尾根を乗り越し、飛騨側にほぼ垂直の岩場をクライミングダウンする個所ではないと思っています。
往きの登りはともかく、帰りの下りに「なんでココに鎖がないのん?」と思っていました。
逆に事故が多発するのは、たとえばロバの耳と馬ノ背のあいだの名もないピークの斜面であり、西穂の下りの何でもなさそうな岩場であったりします。
つまり事故は危険とは見えない場所でこそ起きているのです。
心がけていることとして、登りではあまりゼーハーゼーハならないように呼吸に気をつけるくらいで基本的にはリラックス、逆に下りでは危険察知アンテナを全開にして緊張感を持つようにしています。
最後の難所;馬ノ背
さて、このルートを最初に歩くならベストシーズンは9月の初・中旬ではないかと思います。
ベルグラ;簿氷
決して軽々しく人に勧めることはできない場所ですが、ロバの耳からジャンダルムあたりのあの圧倒的な岩の感じは、ぼくはあれこそ「穂高オブ穂高」と思っています。
山を畏れること
山に謙虚になること
山の経験を積むとは臆病を重ねることでありましょう
冬の涸沢岳西尾根の落とし穴
涸沢岳西尾根は、冬穂高へのメインルートとされています。
およそ無雪期には登られることのないこの尾根が、なぜ冬期のメインルートとされているのか?
それはひとえに「雪崩の危険回避のため」といえるでしょう。
奥穂高岳へ登る場合、夏には一般的である涸沢、岳沢、白出沢という「沢」の名のつくルートは、冬期には雪崩の巣となり使えないとされています。
少なくともぼく個人は、冬の西尾根を「安全」とはとうてい思うことはできません。
むしろ隠されたリスクの非常に多い、かなりシビアなルートであると思っています。
このルートで命を落とした人は決して少なくありません。
しかもそのほとんどが山の実力者ばかりです。
両雪疵
F沢
蒲田富士付近の雪稜での雪疵の踏み抜き事故は、単純な雪疵への不注意から生じるのではなく、時に複雑な張り出し方をしている雪疵へのルート取りの難しさによるものと考えられます。
涸沢岳西尾根は、起点の新穂高温泉から換算すると標高差2000m。
なぜ「間違い尾根」なのか
奥穂山頂から穂高岳山荘までの歩行距離は647mです。
このほんのわずかともいえる下降路で、過去何人もの人が命を落としています。
さらに山荘寄りの支尾根に迷い込んだ末に滑落し、白出沢で発見された人も1人や2人ではありません。
ワイヤネットの網の目の間隔は、じつは人が通り抜けてしまうくらいの幅があるのです。もうちょっと狭くしたほうがエエかなぁと思案していたところ、山荘のボス、今田英雄さんが言いました。「あの隙間をくぐり抜けて落ちていくようなヤツは、ハナから生きる意志のないヤツやから、あのままでエエ」
ご注意ください。
「馬ノ背」のナイフリッジを平均台よろしく駆け下りると「ブタの背」と呼ぶ台地に差しかかります。奥穂高岳~ジャンダルム間にある通称「ブタの背」
岳沢ヒュッテのヘリポート
いったん涸沢岳の山頂を北穂側へ過ぎると、ほどなく稜線はスッパリ切れ落ち、涸沢槍周辺は難しい悪場となります。
「D沢のコル」とは涸沢岳と涸沢槍の鞍部で、自分たちの戦力をリスクを考えるとそこが限界であろうと判断したのです。
穂高岳のある白出のコル
「ワっ、ワタシもついでに助けてもらえまへんかっ!」
「イヤァー~三日ほど前に前穂のほうから来ましてん」
「ほんでここらあたりで何にも見えんようになって、こらアカン思て雪穴掘って寝てましてん」
「ほんで食べモンもなくなるし、寒いし、もうどないしょ?思てたんですわ」
「ほんでおたくはんらの声がしまっしゃろ?こら助かったァ思てね!」
と、コテコテの関西弁でまくしたてるではないですか。
それが、出動した救助現場でまったく関係のない別の人からその場で直接に救助依頼を受けるなんてことは前代未聞、そんなの見たことも聞いたこともありません。
その一連の行動は、なんだか凍っていた脳が少しずつ解凍していくかのようでありました。
上高地の玄文沢ヘリポート
すると前穂北尾根3峰フェースのやや右上、ほとんど壁としかみえない岩場の中に必死で手を振る人の姿がありました。
(「うへぇー、あんなトコかよ!)
およそロープも使わずによくぞまぁあんなところへ行けたものだという絶壁の中に、その遭難者はいたのです。そしてそのテラスは人が1人立てるかどうかというほどの広さしかありません。
さてこのレスキューには後日談があって、要救助者から「オレのあのザックをどうしてくれるんだ!回収してこい!」というクレームがあったというのです。
「あなたがあそこでザックを捨ててくれなければ、あなたの命は(そして、もしかしたらぼくの命も)いまごろなかったかもしれませんよ」と。
標高3000mでは空気の密度は2/3
ヘリは3割減のパワーしか出せない。
山の世界でヘリコプターが有効に使われるとはあまり考えられていなかったのです。
ところが、それを覆したのが昭和38年の薬師岳における愛知大山岳部の大量遭難事故でした。
正月に薬師岳を目指した学生13人が消息を絶ちました。
その安否の焦点は太郎小屋となります。
大型ヘリをチャーターした朝日新聞の本多勝一記者が直接小屋へと強行着陸し、
「来た、見た、いなかったーー太郎小屋に人影なし」のスクープを放った一件が一躍ヘリコプターの山岳フライトを注目させたのです。
「ラマ」;正式名称 アエロスパシアルSA315B「Lama」
この機種は1972年に12,440mに到達というヘリコプターによる絶対高度記録を樹立し、その記録は初フライトから半世紀近くが経った現在でさえいまだ破られていません。
2009年に「若鮎Ⅱ号」は、岐阜防災航空隊による救助活動中に「ロバの耳」にて墜落。
隊員3名が殉職するという痛ましい事故が起きています。
トウホウには彼らにしか成し得ない救助方法「長吊り(センタースリング)」があった。
通常、警察や防災あるいは自衛隊でも、レスキュー活動となると「ホイスト」と呼ばれる救助用巻上げウインチを用います。この方法は機内に要救助者を収容できるというメリットがあるものの、隊員が降下して収容できるのは基本的には1名のみです。そしてヘリがホバリングしている時間が長く、また多人数の場合、何回もホイストを上げ下げしなければならないため時間がかかります。
ぼくは東日本大震災や茨城の河川氾濫災害の際に、建物に取りのこされた人々をヘリコプターが懸命に救助する映像を見て、「あぁ、もしもあれをラマを使った長吊りでやれば、短時間にもっと救えるのに!」と地団駄を踏んだことがあります。
実際、東日本大震災の折などは、もう居ても立ってもいられずに東邦航空松本営業所の所長に電話して「小松サンっ、オレにラマ貸してくれ!長吊りであの人たちを救おう!」と言ったのですが、小松さんに「バカ言ってんじゃねーよ!そのラマが仙台空港で流されたんだヨっ!」
あれは普段から「ラマ」で物資の荷揚げで山を飛びまくっていた東邦航空であったからこそ成し得たワザであったのです。
よく「県警ヘリはお金がかからない」
この世の中にタダで空を飛べるヘリは存在しません。
「ラマ」の場合であれば、状況による他の経費などは除外して1時間あたり50万円。
岐阜県警の使う「ベル412」は80万円。
個人的には山岳遭難救助にかかる費用というものは、すべからず「受益者負担」つまり遭難者本人(あるいは家族)が全額を負担すべきものであろうと思います。
現場に駆けつける救助隊員にも官と民の違いがあるのです。
われわれ民間の救助隊員の出動にあたっては「出動費」という名目の救助費用の請求があります。隊員1人あたり一日2~4万円ほど。
なんと近頃ではその支払いを拒否する輩が出現してきています。
奥穂高岳山頂を踏んで、これから下山される方々へ!
まだ奥穂登山は終わっていません。
ここから先、ザイテングラートの下りこそが
奥穂登山の核心です。
無事に下山してこその山頂です。
ほんの少し踏み外せば、
この先の下りは重大事故につながります。
「涸沢常駐隊」
穂高における遭難救助の最前線。
民間による山岳救助隊が毎夏組織されます。
串田孫一;「雪は宇宙の匂いを伝達する」
映像作品『光の五線譜』
「アルパインクライマー」としての矜持;追悼 今井健司
常々ぼくは「アルパインクライマー」という存在に深い憧憬と尊敬を抱いています。
彼らには、都会のオシャレなレストランでの最上級のステーキよりも、風雪の岩壁に張りつきながら啜る一杯のスープのほうがはるかに価値あるものなのです。
トップレベルのアルパインクライミングというのは、おそらく人間が行う行為の中でもっとも死に近い領域に踏み込むものであり、強靭な肉体と精神とで挑む究極の冒険行為です。
己の能力の限界近くでなければ感じえないものを求め続けることは、この上なくヤバい世界です。そこには死という究極のリスクが存在します。それを承知の上でなお登る「アルパインクライマー」という者たちは、どうしようもない業の中にいるといえます。
ヒマラヤのチャムラン;7319mにて遭難 享年33
笑顔の旅人 追悼 谷口けい
笑顔の人
元気の人
勇気の人
まっすぐな人
ひたむきな人
好奇心の人
前向きの人
ワクワクドキドキの人
エネルギッシュな人
溌剌な人
パワフルな人
天真爛漫な人
これまで出会ったなかで、彼女ほどまわりの者をしあわせにする人を知りません。
胸の中に爽やかな風が吹き、あたたかな思いがして、いつのまにか勇気を与えられていました。
そして何より、いつも元気いっぱいのあの笑顔は、およそ「山での死」からはいちばん遠い存在であるように思えたのです。ぼくは谷口けいに山での死の匂いをいささかも感じることはありませんでした。
映像作品「星々の記憶」










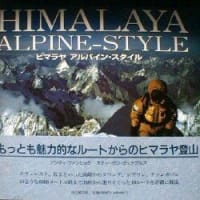
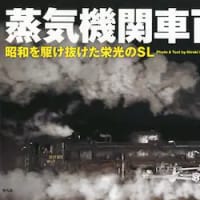
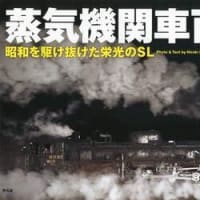
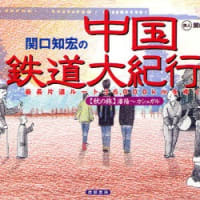
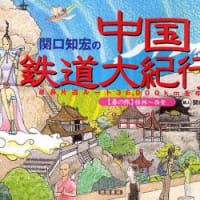
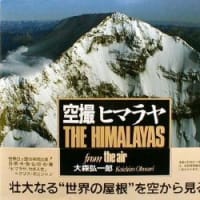

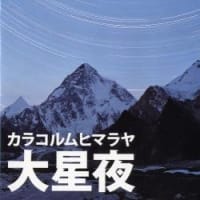
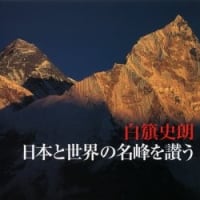
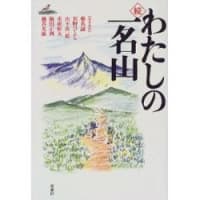
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます