神戸から飛び出して名古屋での勉強会は、6月8日の間際になって、発表をお願いしていた細川恵利さんが急な校務が入って出席できなくなり、参加を楽しみにしておられた方が前日に関東地方を襲った大雨の影響で欠席を余儀なくされたり、いろいろ予期せぬ出来事もありましたが、いつものメンバーに加えて、初めて参加してくださった学校図書館関係者、半年以上もたって更新した私のブログをたまたま見て参加してくださった方など、多彩な顔ぶれで活発な話し合いが行なわれ、無事に終えることができました。
椙山女学園大学のLCは、図書館を入ってすぐ左手に広がる開放的な空間だ。一階フロアの三分の一ほどを占めているだろうか。その規模は同志社大学のLCとは比べものにならないが、広々と感じられる。ガラス張りの壁面から自然光をふんだんに取り込んで明るく、外の空や樹木にも目をやることができる。可動式の机、椅子、ホワイトボードなど、白を基調とした家具は詰め込まずにゆったりと配置されていて、圧迫感がない。それらを自由に組み合わせ、タブレットPCやプロジェクターも使って、人数や目的に合わせて使い勝手のいい空間を自分たちでつくることができる。カフェスペースもある。天野さんに聞くと、やはり開放感や広がりを意識されたそうだ。「学習しろっ」という感じをださないで、思考をまとめるために少し漂えるような空間、余白のような空間を求めたという。
一階中央にある階段を下りると地下は二層になっていて、すべて開架。仕切りのついた机もあって、膨大な本に囲まれてひとり集中して調べものや思索に没頭できる。2階はゆったりと読書ができるエリア。絵本コーナーもある。3階に上がると、サイズの異なるグループ学習室が4室あり、それぞれのドアがグリーン、ブルー、レッド、オレンジに色分けされている。
仲間とアクティブに学べる空間からひとり静かに過ごせる空間まで、変化に富んだ図書館全体を活用すれば、学生は、自分で発想し、考え、議論し、知識を獲得し、探究を重ねる学びのプロセスのそれぞれの局面に適した学習環境を、そのつど自分たちで創っていくことができるだろう。
椙山のLCは、学びに必要な三つのキーワード、idea(考え)、intelligence(知能)、inquiry(探究)の頭文字をとった“i”と、共通の問題意識をもった学生が議論を交わす“Circle”を重ねてiCircleと呼ばれる。
スライド:椙山女学園大学ラーニング・コモンズiCircleの紹介(天野由貴)
5月に訪問した同志社大学のLCも開口部が多くて外の景色を眺めることができたが、外部の自然光をとくに感じることはなかった。面積や規模には圧倒されたけれども、広々とした感じや開放感をとくに意識することはなかった。それよりも、一時の訪問者としての私が目を奪われたのは、技術の粋を尽くした学習環境のなかで多くの学生が自分たちの活動に集中し、作業に没頭している姿だった。そこは、また、ネットワークをとおして世界とつながっている。図書館や国際交流・留学部門、PBL推進支援センターなど学内各部署とのネットワークはもちろん、職員が出向して学生の相談に応じるなどの連携をはかっていて、ラーニング・ハブとしての役割も果たしている。だが、図書館との空間的なつながりはない。その点でも、図書館と一体化された椙山のLCとは、きわめて対照的だ。
スライド:同志社大学ラーニング・コモンズ見聞記(山本敬子)
(写真は省いてありますので、下記でごらんください)
良心館ラーニング・コモンズHP
案内パンフレット
この日の発表を終えた後、山本さんはフェイスブックに以下のように書いておられる。
|
なぜ同志社はLCと図書館を全く別の建物、組織として設置したのか、時間が経つにつれて気になって気になって仕方がなかったので、井上真琴氏の論文などを時間の許す範囲でかき集めて読んでみた。井上氏といえば、著書『図書館に訊け!』に表れているように、選書・レファレンス・アカデミックスキル育成などを通じ、大学図書館で積極的な学習支援を展開してきた図書館人でもあった。関係の論文や講演も多数。普通に考えると、図書館とLCをつなげて考えてよさそうだが…? 同志社LC設置までの経緯、井上氏の異動の様子と論文・報告資料、教育開発センターレポート、それらを時系列にざっと眺めていくと、なんとなく見えてくるものがあり… |
山本さんと天野さんの話は、どちらも図書館職員の教育にたいする意識のあり方や関わり方にまで踏み込んで、考えさせる内容だった。
こうして、わたしたちは椙山女学園大学LCの居心地のいい空間に身をおいて、時間が経つのも忘れて幅広く活発な話し合いをし、充実した思考の時間を過ごすことができました。はじめて参加された方からも「とても刺激的な勉強会でした。自分の立場、役割、できること、すべきこと、いろいろと考えさせられた、あっという間の数時間」だったとメールをいただきました。豊かな学びを生み出す条件は、かならずしも面積や設備の規模とは直接的な関係がないのかもしれません。
つぎは、この経験をふまえて「場所」と「場」について考えようと思います。










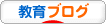

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます