▽『清水義範の作文教室』
『言語表現技術ハンドブック』
『書ける大学生に育てる』
『国語教科書の闇』
という本を連続で読んだ。
一カ月くらい前の話だけど。
そこで考えた国語という教科について。
▽上3冊が文章表現の重要性について、一番下が小説教材の問題点について取り扱った本。
まぁ、この偏り方じゃあ今の文章理解中心の国語の授業については批判的になるよね。
いや、もともと文章を書かせなさすぎとは思っていたんだけど、
その根拠づけをしていただいたというか。
▽現在の私の周りに文章に対する苦手意識を持った人のなんと多いことか。
書きたいことが書けない。
書きたいことがわからない。
書いても意味が通じない。
意味は通じるけど面白味が出ない。
とかとか。
相手に伝わる文章を書く指導が圧倒的に足りていないと思う。
小学生の頃、作文を書いた事はあったけど、誰かに伝えようとして書いていた覚えはないし。
そもそも何を目的に作文書いていたのかを覚えていない。
記憶の整理?
まぁせいぜいそのくらいの役にしかたってなかった。
自分の中であぁ、あれに感動したんだったなぁと思い出すためのツール。
だから断片的な事しか書いてなかった。それを読めばそれを書いた自分は思い出せるから。
何のことを言っているかわかるから。
「すごいと思った」の言葉にすべてを込めることができる。
他の人が読むことなんて全く考えてなかった。
▽メールも大学に入ってようやく体裁とかを覚えた。
最初はインターネットで「メールの書き方」のページを見ながらじゃなきゃ書けなかった。
これこそ社会に出る前に「一回聞いたことある」程度じゃなくって何の迷いもなく書けるくらいにしとかないと困るものなんだろうけど、
高校卒業までに身につけておくべきだな、と思った事はなかった。
▽自分は幸い中2からブログを始めていたから、
読む人を意識したリズムで文章を書くことはできる。(読みやすい文章が書けているとは言わない。けど、意識は間違いなくしてる。)
けど大学に入って読む友人の文章は読みづらいものが多かった。
入試で「小論文」を課されない限り、高校では人に読ませる文章を書く練習をしないという人も多いんだろう。
▽逆に、小説を中学生とか高校生になってあそこまで繰り返し読む必要はあるんだろうか?
社会に出てからの読書ってそんな同じところを何度も何度も読まないのに、
やれ修辞がどうだ、心情がどうだと問われるたびに何度も何度も同じ文章に目を通す。答えを探す。
小説ってそうしなきゃ楽しめないものか?
わかったらわかったで楽しいだろうけど、それは社会に出て必要か?
その教育方法で文学好き以上の文学嫌いを生んではいないか?
小説を読む時は書かれていない情報をいかに読み取るかが大事、ってことを延々やっていたら、
生徒たちは人の言動の裏を常に考えるような人にならないか?
そして小説の詳細を読む方に時間を費やして自分の意見をわかりやすく表現することは練習していないから
コミュ障と呼ばれる人たちはそうやって生まれてくるんじゃないか?
なにかの論文だったり評論だったりは要点を掴むために何度も読み返す必要性があるにしても、
小説まで同じような読み方をするのは違うのではないだろうか。
▽たしかに作文は絶対的な評価がしづらい。
逆に小説から読み取れることを聞くのは正否がはっきりしていて点をつけやすい。
けれど、表現の場をもっと作るべきだと思う。
▽大学はいまや社会のニーズに答えるための就職予備校になっていて、
普通科高校は大学に入るための予備校と大差ない状態で、
小学校・中学校は教育委員会からの縛りがきつそうで、
結局、自分の教育観と今の(今までの)学校が求める教育観がまるで違うことに気が付いたので
教員は目指さないことにしました。
次の春から文学部で学ばせていただくことになります。
7年間大学に通わせてもらえる情けなさとありがたさ。
『言語表現技術ハンドブック』
『書ける大学生に育てる』
『国語教科書の闇』
という本を連続で読んだ。
一カ月くらい前の話だけど。
そこで考えた国語という教科について。
▽上3冊が文章表現の重要性について、一番下が小説教材の問題点について取り扱った本。
まぁ、この偏り方じゃあ今の文章理解中心の国語の授業については批判的になるよね。
いや、もともと文章を書かせなさすぎとは思っていたんだけど、
その根拠づけをしていただいたというか。
▽現在の私の周りに文章に対する苦手意識を持った人のなんと多いことか。
書きたいことが書けない。
書きたいことがわからない。
書いても意味が通じない。
意味は通じるけど面白味が出ない。
とかとか。
相手に伝わる文章を書く指導が圧倒的に足りていないと思う。
小学生の頃、作文を書いた事はあったけど、誰かに伝えようとして書いていた覚えはないし。
そもそも何を目的に作文書いていたのかを覚えていない。
記憶の整理?
まぁせいぜいそのくらいの役にしかたってなかった。
自分の中であぁ、あれに感動したんだったなぁと思い出すためのツール。
だから断片的な事しか書いてなかった。それを読めばそれを書いた自分は思い出せるから。
何のことを言っているかわかるから。
「すごいと思った」の言葉にすべてを込めることができる。
他の人が読むことなんて全く考えてなかった。
▽メールも大学に入ってようやく体裁とかを覚えた。
最初はインターネットで「メールの書き方」のページを見ながらじゃなきゃ書けなかった。
これこそ社会に出る前に「一回聞いたことある」程度じゃなくって何の迷いもなく書けるくらいにしとかないと困るものなんだろうけど、
高校卒業までに身につけておくべきだな、と思った事はなかった。
▽自分は幸い中2からブログを始めていたから、
読む人を意識したリズムで文章を書くことはできる。(読みやすい文章が書けているとは言わない。けど、意識は間違いなくしてる。)
けど大学に入って読む友人の文章は読みづらいものが多かった。
入試で「小論文」を課されない限り、高校では人に読ませる文章を書く練習をしないという人も多いんだろう。
▽逆に、小説を中学生とか高校生になってあそこまで繰り返し読む必要はあるんだろうか?
社会に出てからの読書ってそんな同じところを何度も何度も読まないのに、
やれ修辞がどうだ、心情がどうだと問われるたびに何度も何度も同じ文章に目を通す。答えを探す。
小説ってそうしなきゃ楽しめないものか?
わかったらわかったで楽しいだろうけど、それは社会に出て必要か?
その教育方法で文学好き以上の文学嫌いを生んではいないか?
小説を読む時は書かれていない情報をいかに読み取るかが大事、ってことを延々やっていたら、
生徒たちは人の言動の裏を常に考えるような人にならないか?
そして小説の詳細を読む方に時間を費やして自分の意見をわかりやすく表現することは練習していないから
コミュ障と呼ばれる人たちはそうやって生まれてくるんじゃないか?
なにかの論文だったり評論だったりは要点を掴むために何度も読み返す必要性があるにしても、
小説まで同じような読み方をするのは違うのではないだろうか。
▽たしかに作文は絶対的な評価がしづらい。
逆に小説から読み取れることを聞くのは正否がはっきりしていて点をつけやすい。
けれど、表現の場をもっと作るべきだと思う。
▽大学はいまや社会のニーズに答えるための就職予備校になっていて、
普通科高校は大学に入るための予備校と大差ない状態で、
小学校・中学校は教育委員会からの縛りがきつそうで、
結局、自分の教育観と今の(今までの)学校が求める教育観がまるで違うことに気が付いたので
教員は目指さないことにしました。
次の春から文学部で学ばせていただくことになります。
7年間大学に通わせてもらえる情けなさとありがたさ。














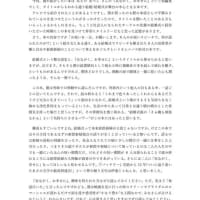
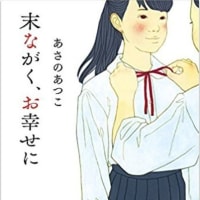
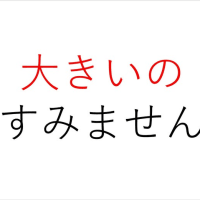
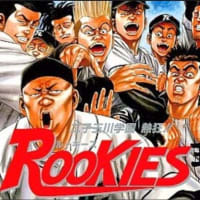


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます