▽今日が仕事納めという人も多かったのではないでしょうか。
年末の「よいお年を」ってなかなか不思議な挨拶ですよね。
言及しているのは一年という長いスパンなのに
そういって別れた人とは年始にすぐ会ったりする。
そして特に違和感はない。
なぜよいお正月をー。とかよい年末年始をー。
とかにならないのだろうか。
▽教えて!gooにもよいお年をについて疑問を持った人がいた(2003年)ようで、
「martinbuho#2」さんがなかなかに納得のいく説を投稿していらした。
以下引用
昔の日本では大晦日(おおみそか、12月31日のこと)を迎えるまでには沢山のしなければならないことがありました。(一部は今でも残っています)
1.支払い。昔は日用品をつけ(クレジット)で買い年末に清算していた。この支払いが出来るかどうかが庶民にとっては一番の心配ごとだった。
2.大掃除
家中のチリを払い、障子を張替え、畳を干す。最後に神棚や仏壇の拭き掃除。
3.すべてが終わると年越しそばを食べて一年の無事を喜びあい、新しい年が無事迎えられることを神仏に感謝しお酒を飲んだ。
年末に外出先で知人に会ったとき、これらのすべてのことを念頭に「今年もいよいよ終わりですね。大晦日を迎えるまでいろいろ大変でしょうが、お互いにがんばりましょう。どうぞ良いお年を(無事大晦日が迎えられますように、夜逃げなどしなくて済むように)」と挨拶したわけです。
こうして庶民は大変な思いをして新年を迎えたので
「明けましておめでとう」の挨拶に喜びと神仏への感謝の気持ちが込められていました。新年には何をさておいても、無事年を取ったことを氏神様に報告していたのが、現在の元旦の初参りの習慣の始まりです。
西欧でもHappy New Yearの挨拶はほとんど日本と同じです。本当に新年になってからはこの挨拶は使いません。年末最後に友人と別れるときに使います。1月2日に学校や会社で使う人もいますが少数派です。
以上引用
▽なるほどですね。
みなさんは「よいお年をー」と言って仕事を納められたでしょうか。
忘れていた人、年明けの初出勤を終えて帰るときに言ってみてください。
ややウケだと思います。
どんな反応が来ようと責任は負いかねますが。
年末の「よいお年を」ってなかなか不思議な挨拶ですよね。
言及しているのは一年という長いスパンなのに
そういって別れた人とは年始にすぐ会ったりする。
そして特に違和感はない。
なぜよいお正月をー。とかよい年末年始をー。
とかにならないのだろうか。
▽教えて!gooにもよいお年をについて疑問を持った人がいた(2003年)ようで、
「martinbuho#2」さんがなかなかに納得のいく説を投稿していらした。
以下引用
昔の日本では大晦日(おおみそか、12月31日のこと)を迎えるまでには沢山のしなければならないことがありました。(一部は今でも残っています)
1.支払い。昔は日用品をつけ(クレジット)で買い年末に清算していた。この支払いが出来るかどうかが庶民にとっては一番の心配ごとだった。
2.大掃除
家中のチリを払い、障子を張替え、畳を干す。最後に神棚や仏壇の拭き掃除。
3.すべてが終わると年越しそばを食べて一年の無事を喜びあい、新しい年が無事迎えられることを神仏に感謝しお酒を飲んだ。
年末に外出先で知人に会ったとき、これらのすべてのことを念頭に「今年もいよいよ終わりですね。大晦日を迎えるまでいろいろ大変でしょうが、お互いにがんばりましょう。どうぞ良いお年を(無事大晦日が迎えられますように、夜逃げなどしなくて済むように)」と挨拶したわけです。
こうして庶民は大変な思いをして新年を迎えたので
「明けましておめでとう」の挨拶に喜びと神仏への感謝の気持ちが込められていました。新年には何をさておいても、無事年を取ったことを氏神様に報告していたのが、現在の元旦の初参りの習慣の始まりです。
西欧でもHappy New Yearの挨拶はほとんど日本と同じです。本当に新年になってからはこの挨拶は使いません。年末最後に友人と別れるときに使います。1月2日に学校や会社で使う人もいますが少数派です。
以上引用
▽なるほどですね。
みなさんは「よいお年をー」と言って仕事を納められたでしょうか。
忘れていた人、年明けの初出勤を終えて帰るときに言ってみてください。
ややウケだと思います。
どんな反応が来ようと責任は負いかねますが。














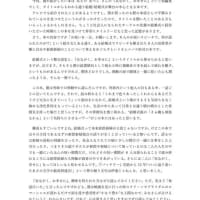
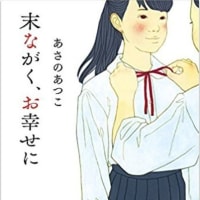
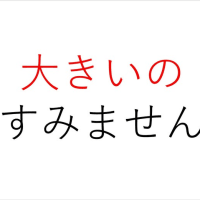
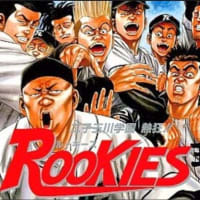


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます