早いもので気付くと今年もあと1年。
年末というと日本ではベートーベンの第九ですね。
大学時代にドイツ語の授業でこの文を勉強した覚えがあります。
内容は忘れましたが・・・
わが大学の交響学団は関西で初めて第九を演奏した楽団です。
年末第九をやるようになったのはN響(旧日本交響楽団)が最初とか。
今でも毎年N響は第九を演奏しますね。
アマチュア合唱団が第九を手がけるようになったのはまだ俺が大学時代の頃かな。
大阪城ホールで一万人の第九がありましたね~。
今年もあるみたいですよ。
京都ではコバケンの炎の第九があったり、よく聞きにいったものです。
一度歌いたいとは思ったのですが、練習スケジュールに合わなくって・・・
年末はもう一つ自分的にはバッハも聞きたいのです。
12/23にいずみホールでクリスマス・オルガンコンサートがあります。
同ホールで12/24にはモーツァルト室内管弦楽団スペシャルコンサート「今宵バッハとクリスマス2006」が、
そして、翌日12/25は青少年オーケストラベートーヴェン「第九の夕べ」が。
これは前半バッハ、後半第九という、おいしそうなプログラムです。
あとは年末と言えば南座の顔見世ですね。
仁左衛門の俊寛、勘三郎の娘道成寺、藤十郎の雁のたよりと見所たっぷりです。
ただでさえ物入りなのに、財布が大変。













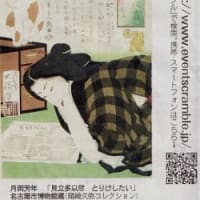
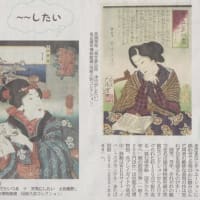





都会はいいですね、聴こうと思えば生の音楽が身近にあって。
田舎暮らしは缶詰ばかりです。
都会に住んでいた学生時代が懐かしい。(相当なオヤジっすね。)
私はバッハ派ですが、腰据えてベートーヴェンもいいですね。
友人のへたくそ第九(失礼!)を聴かされるのはかなわんけど・・。
「おお、友よ!この響きではない…」
何度歌っても、何度聞いても最後のフロイデで涙が出ます。
そう言えば、今年の一万人の第九、誰と行こうか…(汗)
初めまして。
自分も大学に行くまでは山奥に住んでいたため、
生の音楽とは縁がありませんでした。
唯一触れる事ができるのは、雑音の混じるNHKFMでした。
レコード店には流行の流行歌だけ。
それが京都の大学に行ってから、そして大阪で働いてから、
多くの生の音楽に触れる事ができるようになりました。
やっぱりバッハですかね。
どうしてもベートーベンって構えてしまいますよね。
>伊右衛門さん
一万人の第九、昔は山本直純さんでしたね~。
いつの間にか、佐渡さんに代わりました。
第一回、ウィーン室内合唱団が「アヴェ・ヴェルム・コンプス」を演奏した時、平井堅がゲストに来た時、
ミシャ・マイスキーがゲストに来た時、の4回聴きに行きました。
音響的には?なところありますけど、あの迫力。
日本人のベートーベン好きなところに圧倒されます。