いやー、まるで三月場所。
またまたお借りしちゃいます(笑)。
ひとのフン○シで相撲をとらせていただきます。
ホントにいつもありがとうございます~♪
3月17日に開催された、片岡愛之助×友吉鶴心トークショー
「京都から見る伝統芸能」~平家物語の世界から読み解く
に参加された瑠衣さまの詳細レポがコメント欄に届きまし
たので、ご本人さまの許可を得て掲載させていただきます。
同時にご自分の視点での感想もしっかりとお書きくださっ
ています。(瑠衣さま、早々ととても詳しいレポを本当に
ありがとうございました。)
なお、当日の新聞記事と写真がここに♪
>> 読売新聞3月18日 愛之助さん「上方芸能守る」
----<片岡愛之助×友吉鶴心トークショー>----
最初に友吉鶴心氏が紹介され登場。現在の某国営放送大河
ドラマ「平清盛」も含め、大河ドラマの芸能面の時代考証
や指導に携わってこられた方で、薩摩琵琶の奏者。
先ず琵琶の演奏をされ『平家物語』の序章「祇園精舎の鐘
の聲 諸行無情の響あり」を語られ、『敦盛』に入られ
「ここに熊谷次郎直実は 名ある武将を討たばやと うか
ごう内に渚の方・・・ 中略 太刀に哀れや 磯千鳥 鳴
くも悲しき須磨の浦」までを語られた。
ライブで琵琶の演奏を聞くのは初めてだったが、強弱の響
きがズンと胸を撃ち、お声も素晴らしい語りだった。多分
南座で「熊谷陣屋」が上演されているので選ばれた演目だ
ろう。
ここで南座から大慌てでかけつけた愛之助さんが登場。
友吉鶴心氏が手首を見られて「急がれたのですね、ここに
まだお白粉が残っていますよ」と目ざとく指摘されていた。
綱豊卿を演じられていた名残の化粧である。
そこからお二人の会話があり、又それぞれの分野のお話を
された。
司会者が「薩摩琵琶」の歴史につて問われると「薩摩琵琶
としては約150年の歴史です。琵琶は、法師琵琶が一番
古く、あとは筑前琵琶もあります。薩摩琵琶は、元々薩摩
藩の武士が都から流れて来た法師や公家に琵琶の演奏を習
い、武士のたしなみとして演奏出来る者が多かった。明治
維新後、薩摩武士の多くは海軍の軍人が多く、集まりなど
で琵琶を奏じて聞かせる事が多かったので、薩摩琵琶と称
されるようになった」と話された。
友吉鶴心氏は話もお上手なら、セッションする相手への配
慮もおありで「愛之助さんの芝居は数年前に東京の浅草公
会堂で『封印切』を見まして、小さな劇場なのに、それを
感じさせない、歌舞伎座で見る芝居のような芸が良くて、
3回も見に行きました」と持ち上げられていた。
愛之助さんも気分良く、我々が何回も聞いた出自の話から
上方歌舞伎について語られたが、友吉鶴心氏が琵琶の語り
でも昔は言葉を語る間が長く「お~~~~~ご~~~~~
~れる~~~~」と語るので現代人には分からない。「今、
私は、お~~~ご~~れる、くらいの間で語る」と話され
ると、愛之助さんも「歌舞伎の基本は義太夫で、義太夫も
はやり言葉の間が長く」と話されたあと、実際の義太夫の
節で違いを示された。
今までは「う~~~と言ってるのは苦しんでるのと違いま
す、次の音をしっかり聞けばわかる」と話されていたが、
これは友吉鶴心氏効果だろう。
お二人で今の古典芸能の起こりは殆どが上方であると同調
されていた。「今は歌舞伎と言うと東京だと思っている方
が多いが、上方から江戸へ下っていったもの。是非、上方
の地で毎月歌舞伎の興行を実現したい」という愛之助さん
の話に友吉鶴心氏も頷かれていて「琵琶にしろ、歌舞伎に
しろ基本の言葉は上方言葉です」と言って居られた。
「すし屋」でも現在、本行(文楽)に近い演じ方が出来る
のは仁左衛門丈と愛之助さんだけである事は愛之助さんが
言って居られる。「江戸風も間違いでは無い。江戸弁の
権太もすてきですが」と愛之助さんは仰るが、如何なもの
だろうか?
(レポート by 瑠衣さま) ---------------------
またまたお借りしちゃいます(笑)。
ひとのフン○シで相撲をとらせていただきます。
ホントにいつもありがとうございます~♪
3月17日に開催された、片岡愛之助×友吉鶴心トークショー
「京都から見る伝統芸能」~平家物語の世界から読み解く
に参加された瑠衣さまの詳細レポがコメント欄に届きまし
たので、ご本人さまの許可を得て掲載させていただきます。
同時にご自分の視点での感想もしっかりとお書きくださっ
ています。(瑠衣さま、早々ととても詳しいレポを本当に
ありがとうございました。)
なお、当日の新聞記事と写真がここに♪
>> 読売新聞3月18日 愛之助さん「上方芸能守る」
----<片岡愛之助×友吉鶴心トークショー>----
最初に友吉鶴心氏が紹介され登場。現在の某国営放送大河
ドラマ「平清盛」も含め、大河ドラマの芸能面の時代考証
や指導に携わってこられた方で、薩摩琵琶の奏者。
先ず琵琶の演奏をされ『平家物語』の序章「祇園精舎の鐘
の聲 諸行無情の響あり」を語られ、『敦盛』に入られ
「ここに熊谷次郎直実は 名ある武将を討たばやと うか
ごう内に渚の方・・・ 中略 太刀に哀れや 磯千鳥 鳴
くも悲しき須磨の浦」までを語られた。
ライブで琵琶の演奏を聞くのは初めてだったが、強弱の響
きがズンと胸を撃ち、お声も素晴らしい語りだった。多分
南座で「熊谷陣屋」が上演されているので選ばれた演目だ
ろう。
ここで南座から大慌てでかけつけた愛之助さんが登場。
友吉鶴心氏が手首を見られて「急がれたのですね、ここに
まだお白粉が残っていますよ」と目ざとく指摘されていた。
綱豊卿を演じられていた名残の化粧である。
そこからお二人の会話があり、又それぞれの分野のお話を
された。
司会者が「薩摩琵琶」の歴史につて問われると「薩摩琵琶
としては約150年の歴史です。琵琶は、法師琵琶が一番
古く、あとは筑前琵琶もあります。薩摩琵琶は、元々薩摩
藩の武士が都から流れて来た法師や公家に琵琶の演奏を習
い、武士のたしなみとして演奏出来る者が多かった。明治
維新後、薩摩武士の多くは海軍の軍人が多く、集まりなど
で琵琶を奏じて聞かせる事が多かったので、薩摩琵琶と称
されるようになった」と話された。
友吉鶴心氏は話もお上手なら、セッションする相手への配
慮もおありで「愛之助さんの芝居は数年前に東京の浅草公
会堂で『封印切』を見まして、小さな劇場なのに、それを
感じさせない、歌舞伎座で見る芝居のような芸が良くて、
3回も見に行きました」と持ち上げられていた。
愛之助さんも気分良く、我々が何回も聞いた出自の話から
上方歌舞伎について語られたが、友吉鶴心氏が琵琶の語り
でも昔は言葉を語る間が長く「お~~~~~ご~~~~~
~れる~~~~」と語るので現代人には分からない。「今、
私は、お~~~ご~~れる、くらいの間で語る」と話され
ると、愛之助さんも「歌舞伎の基本は義太夫で、義太夫も
はやり言葉の間が長く」と話されたあと、実際の義太夫の
節で違いを示された。
今までは「う~~~と言ってるのは苦しんでるのと違いま
す、次の音をしっかり聞けばわかる」と話されていたが、
これは友吉鶴心氏効果だろう。
お二人で今の古典芸能の起こりは殆どが上方であると同調
されていた。「今は歌舞伎と言うと東京だと思っている方
が多いが、上方から江戸へ下っていったもの。是非、上方
の地で毎月歌舞伎の興行を実現したい」という愛之助さん
の話に友吉鶴心氏も頷かれていて「琵琶にしろ、歌舞伎に
しろ基本の言葉は上方言葉です」と言って居られた。
「すし屋」でも現在、本行(文楽)に近い演じ方が出来る
のは仁左衛門丈と愛之助さんだけである事は愛之助さんが
言って居られる。「江戸風も間違いでは無い。江戸弁の
権太もすてきですが」と愛之助さんは仰るが、如何なもの
だろうか?
(レポート by 瑠衣さま) ---------------------














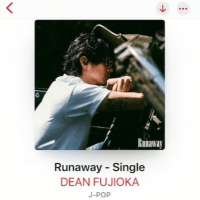
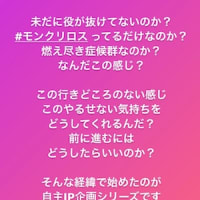
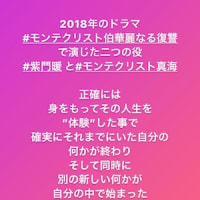


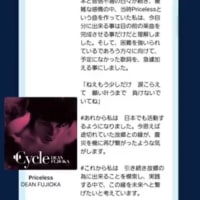













とても内容の濃い、勉強になるトークショーだったのですね。
琵琶の演奏をナマで聴ける機会なんてホントに貴重!
そのうえお話もお上手とは。
琵琶の語りと義太夫・・・どちらも言葉の間を長くとる話、
面白いですね。やはり通じるところがあるのでしょうね。
愛之助さんもいつもと少し違うお話ができて新鮮だった
かもしれませんね。
松嶋屋さんの場合、できるだけ義太夫狂言に近い形で
見せてくださっているのでしょうか。
私の場合、他のお家の舞台を拝見して初めて、その違いに
気づくことがあります。「熊谷陣屋」しかり。
お江戸で生まれた演目は江戸風に、義太夫狂言は上方風に、
というのが観ていて自然な気がします。
座禅堂にこもる夫、右京様に怖い妻は言います、
一回目、獅童さんの 妻 玉乃井
『一晩だけですよッ』
二回目は愛之助さん
『ふたよ(2夜)とはなりませぬ』
ガ~ン、なんて美しいのでしょう、上方の言葉は・・・。
まったく日本の精神は畿内からはじまったのでしょうね、素敵な古い文化も言葉も尊敬します。
7年前から、上方舞(山村流)を東京で習っていますが、踊りとの違いがわかってきました。
江戸でもっと上方舞は盛んになってほしいものです。 愛之助さん(楳茂都扇性さん)の活躍期待しています。
権太も浅草で観ましたが、愛之助さん、お江戸に気を遣ってくださっていますね、優しいかたです。
> 『ふたよ(2夜)とはなりませぬ』
鈴の助さまはここにガーンとこられたわけですね。
その違いを感じられる鈴の助さまの感受性も
素晴しいと思います。
さきほど仁左衛門丈のスペシャル番組を見たところ
なのですが、東京の役者、大阪の役者じゃなく、
私は日本の役者でありたい、と。
両方を兼ねられる仁左衛門丈ならではのお言葉ですね。
そういえば「上方歌舞伎」という言葉自体がヘンですよね。
上方がいい、江戸がいい、ではなく
歌舞伎の演目にはその成り立ちがあると思いますので
私はまずオリジナルに近い形を知りたいですね。
なので義太夫狂言の権太はやっぱり、上方がいいです(笑)。
> 7年前から、上方舞(山村流)を東京で習っています
きゃあ、すごいですね。
関西に住んでいるだけではわからない上方のこころを
舞のお稽古を通じて会得されているのですから。
本当に大事なことは決して出身地や現住所ではなく
(当たり前ですが)そうやって求めようとする人に
継承されていくということでしょうね。
扇性さん、そちらも活躍していただかねば・・・。