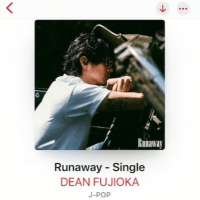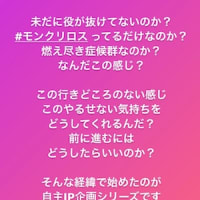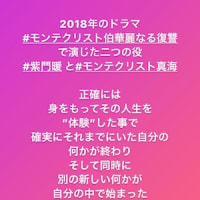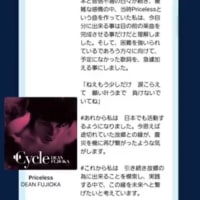公演名 投影と踏襲~文楽と落語・舞踏のあやしい関係~
日時 3月17日(土)
第一部 12:30~14:45
第二部 15:00~17:00
アフタートーク
会場 ジーベックホール(神戸ポートアイランド)
文楽のこういう催しには過去に2回参加させて頂いたことがある。
今回は勘十郎さんによるエア人形のパフォーマンスも観られる!
というので、この日を心待ちにしていた。
神戸のジーベックホールは定員300名の小さな劇場。文楽関係の
催しなのにロビーにはある人物のモノクロポスターが2枚掲げら
れている。
1枚は髪は長く、頬はこけ、眼だけは鋭く、まるでどこかの教祖
のような風貌をした男の写真。もう1枚は、和服姿で髪を後ろに
束ねた男が晩年の阿部定の横にちょこんと正座して撮った写真。
それが「舞踏」の創始者、土方巽だった。
雀松さんが冒頭の挨拶で「ようこそ、秘密クラブへ」と笑いをとっ
ておられたが、開演前からアヤシサじゅうぶん120%超え~♪

第一部 上方の芸 落語と文楽のあやしい関係
<落語・文楽それぞれのワークショップ(体験)>
初っ端。桂雀松さんが出囃子ではなく、文楽の野崎詣りの三味
線で登場。落語の約束事や楽しみ方についてお話された。
上方落語と文楽は昔から関係が深く、文楽をモチーフにした噺
がけっこうあるそうだ。そのために雀松さん自身も義太夫のお
稽古をしているとのこと。
で、義太夫がわかりにくいのは言葉を伸ばすからで、日本語は
伸ばすとすべて母音になる(実演入り)。だから結局母音しか
思い出せないのだと、言い当てられて笑ってしまった。
文楽のワークショップでは、希大夫さんが文楽について解説。
語りの一部を観客全員で一斉に語る体験をさせていただいた。
~あーらわれーいでたるー たけちーいぃ みつぅぅひでっ!~
「みつぅぅ」までは隠れていて「ひでっ」で姿を現す。その感じを
声で表現するのだ。
発声してみてわかった。「会話」以外の語りは伴奏や効果音に
もなるのでうまく音程がとれないと聴く人がツライ。
短い時間だったけれど初めての体験は楽しかった。
三味線ワークショップは清公さん。客席から二人が選ばれて舞
台上で体験レッスン。お二人とも二の糸だけを弾くことができ、
ほめられていた。ちなみに、若手の人が弾いておられる三味線
は猫ではなく犬の皮。力のあるうちは固いものを使うのだそう。
<落語 どうらんの幸助>
出演:桂雀松
文楽の桂川連理柵「帯屋の段」を題材にしたオハナシ。
いやー、笑った笑った。
二人の男が他人からタダ酒をせしめるくだりから始まり、いっ
たいどんなふうに「帯屋」につながるのかと思いながら聴いて
いたら、ナルホロ~。そういうオチですか♪
それにしても落語のネタに使われるくらいだから、作られた当
時は文楽がいかにポピュラーだったかがわかるし、正式な
演目は知らなくても「お半長」といえば老若男女がわかる。
落語と文楽の深くてアヤシ~イ関係とは、上方ならではの素敵
このうえない関係のことだった。
<文楽 桂川連理柵 帯屋の段>
浄瑠璃:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友
人形(長吉):桐竹勘十郎 ほか
舞台上にしつらえた床には、英大夫さんと清友さん。
三味線から語りへ、そこに登場したのは丁稚の長吉。
え! そうきますか~。チャリ場の長吉にズーム・イン。
もう何が可笑しいって、いきなり青ッパナですよ。2つの鼻の
穴からツーと2本の青洟が伸びてきて、長吉が洟をすするたび
にズルッと穴の中に吸い込まれる。
ツーツー&ズル♪ ツーツー&ズル♪
これ、以前に観た時は全然気づかなかった。
いやん、文楽人形楽しすぎるやん!
この時、床のお二人は舞台奥に。舞台前方には手摺も書割もな
く、人形遣いの3人の姿がまるまる見えていた。
私たちをツーツー&ズルで笑わせながらも、勘十郎さんはポーカ
ーフェイス。しかも、全身の動きはときおり舞を舞っておられる
ように見えることにしばし感動・・・。
舞台転換のため少しの待ち時間があり、そのままダーッと
第二部に突入。誰一人帰ることなく全員通しで臨むようだ。
ムム、アツイぜ!
つづきは(2)へ。
日時 3月17日(土)
第一部 12:30~14:45
第二部 15:00~17:00
アフタートーク
会場 ジーベックホール(神戸ポートアイランド)
文楽のこういう催しには過去に2回参加させて頂いたことがある。
今回は勘十郎さんによるエア人形のパフォーマンスも観られる!
というので、この日を心待ちにしていた。
神戸のジーベックホールは定員300名の小さな劇場。文楽関係の
催しなのにロビーにはある人物のモノクロポスターが2枚掲げら
れている。
1枚は髪は長く、頬はこけ、眼だけは鋭く、まるでどこかの教祖
のような風貌をした男の写真。もう1枚は、和服姿で髪を後ろに
束ねた男が晩年の阿部定の横にちょこんと正座して撮った写真。
それが「舞踏」の創始者、土方巽だった。
雀松さんが冒頭の挨拶で「ようこそ、秘密クラブへ」と笑いをとっ
ておられたが、開演前からアヤシサじゅうぶん120%超え~♪

第一部 上方の芸 落語と文楽のあやしい関係
<落語・文楽それぞれのワークショップ(体験)>
初っ端。桂雀松さんが出囃子ではなく、文楽の野崎詣りの三味
線で登場。落語の約束事や楽しみ方についてお話された。
上方落語と文楽は昔から関係が深く、文楽をモチーフにした噺
がけっこうあるそうだ。そのために雀松さん自身も義太夫のお
稽古をしているとのこと。
で、義太夫がわかりにくいのは言葉を伸ばすからで、日本語は
伸ばすとすべて母音になる(実演入り)。だから結局母音しか
思い出せないのだと、言い当てられて笑ってしまった。
文楽のワークショップでは、希大夫さんが文楽について解説。
語りの一部を観客全員で一斉に語る体験をさせていただいた。
~あーらわれーいでたるー たけちーいぃ みつぅぅひでっ!~
「みつぅぅ」までは隠れていて「ひでっ」で姿を現す。その感じを
声で表現するのだ。
発声してみてわかった。「会話」以外の語りは伴奏や効果音に
もなるのでうまく音程がとれないと聴く人がツライ。
短い時間だったけれど初めての体験は楽しかった。
三味線ワークショップは清公さん。客席から二人が選ばれて舞
台上で体験レッスン。お二人とも二の糸だけを弾くことができ、
ほめられていた。ちなみに、若手の人が弾いておられる三味線
は猫ではなく犬の皮。力のあるうちは固いものを使うのだそう。
<落語 どうらんの幸助>
出演:桂雀松
文楽の桂川連理柵「帯屋の段」を題材にしたオハナシ。
いやー、笑った笑った。
二人の男が他人からタダ酒をせしめるくだりから始まり、いっ
たいどんなふうに「帯屋」につながるのかと思いながら聴いて
いたら、ナルホロ~。そういうオチですか♪
それにしても落語のネタに使われるくらいだから、作られた当
時は文楽がいかにポピュラーだったかがわかるし、正式な
演目は知らなくても「お半長」といえば老若男女がわかる。
落語と文楽の深くてアヤシ~イ関係とは、上方ならではの素敵
このうえない関係のことだった。
<文楽 桂川連理柵 帯屋の段>
浄瑠璃:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友
人形(長吉):桐竹勘十郎 ほか
舞台上にしつらえた床には、英大夫さんと清友さん。
三味線から語りへ、そこに登場したのは丁稚の長吉。
え! そうきますか~。チャリ場の長吉にズーム・イン。
もう何が可笑しいって、いきなり青ッパナですよ。2つの鼻の
穴からツーと2本の青洟が伸びてきて、長吉が洟をすするたび
にズルッと穴の中に吸い込まれる。
ツーツー&ズル♪ ツーツー&ズル♪
これ、以前に観た時は全然気づかなかった。
いやん、文楽人形楽しすぎるやん!
この時、床のお二人は舞台奥に。舞台前方には手摺も書割もな
く、人形遣いの3人の姿がまるまる見えていた。
私たちをツーツー&ズルで笑わせながらも、勘十郎さんはポーカ
ーフェイス。しかも、全身の動きはときおり舞を舞っておられる
ように見えることにしばし感動・・・。
舞台転換のため少しの待ち時間があり、そのままダーッと
第二部に突入。誰一人帰ることなく全員通しで臨むようだ。
ムム、アツイぜ!
つづきは(2)へ。