公演名 二月花形歌舞伎
劇場 松竹座
観劇日 2012年2月5日(日)と18日(土)
座席 3階
夜の部は初めてではない演目が2つ。
2週間ぶりの2月18日、舞台は確実に進化していた。
「すし屋」のほうは出演者全員の呼吸、間がぴったり合っており、
その分愛情や苦痛、悲しみが深く感じられた。
「研辰の討たれ」のほうは客席と舞台が完璧に一体化。観客が手
を叩いて喜ぶ爆笑喜劇になっていてビックリした。
平日は手がグッタリ。ほんとに毎日数行ずつしか書けないので、
ナントもう公演が終わってしまうよ~~~(泣&笑)。

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら) すし屋
いがみの権太:愛之助 弥助実は三位中将維盛:染五郎
梶原平三景時:獅童 娘お里:壱太郎
若葉の内侍:米吉 弥左衛門女房お米:吉弥
鮓屋弥左衛門:歌六
<あらすじ>
下市村の釣瓶すし屋は連日大勢の客で溢れている。店を営む弥左
衛門は、その昔、助けてもらった平重盛への旧恩から、その子息
の維盛を使用人の弥助として匿っている。しかしこれが源頼朝の
重臣の梶原景時に知れ、維盛の首を差し出すように命じられてい
た。一方、弥助に恋していた弥左衛門の娘のお里は、ある晩訪ね
てきた親子が維盛の御台所若葉の内侍と、一子六代である事実を
知り三人を逃がす。しかし、弥左衛門の息子で放蕩者の権太はそ
の想いを裏切り、維盛詮議に来た景時に、褒美欲しさに維盛の首
と縄にかけた内侍親子を突き出す。怒った弥左衛門は思わず権太
を刺すが、その時若葉の内侍と六代が現れる。驚く弥左衛門達に
権太が明かす、隠された真実とは...
(歌舞伎美人 サイトより抜粋引用)
谷太夫さんの出語りが一気に義太夫狂言の世界へと誘う。
ええやん、ええやん~♪
浅草の舞台を観ていないので、愛之助さんの権太はこれが初見。
しかも上方版といえば、2回の巡業で拝見した仁左衛門さんのお
手本権太がつねに目の前にちらつく。
とはいえ、上方一(ファン目)のセクシー大腿筋&上腕二頭筋の
持ち主♪ 風貌的には愛之助さんの権太はイメージぴったり。
開幕4日目に観て気になったのが、鎌倉方に差し出した若葉の内
侍と六代君(実は権太の妻子)との別れの場面。「下市村茶店の
場」がないので妻子への想いはここですべて見せるしかない。
前回は「褒美の金たのんまっせー!」と舞台中ほどで叫んでおり、
本当に褒美が目的かと思わされたが、今回はちゃんと花道まで走
り出て褒美のことを叫びながらも、二人の背中を見送る途中で膝
からガクッとくずおれ、泣いていた。もう断然このほうがいい!
立ったまま涙があふれていた仁左衛門さんとも若干違う表現だ。
権太の最期。皆に見送られつつ、手は前で合掌し、寄り目のまま
何度もヒクッ、ヒクッとなりながら幕切れとなったのが前回。
今回は寄り目でヒクッヒクッとなりながらも、幕が閉まりかける
と光の中で権太の表情がやわらいでいるのが見えた。いい顔だ。
言いたいことを伝えることができた安堵の笑み、だろうか。忠義
の証、父への愛情・・・すべて入り混じっているのかもしれない。
余韻のある権太の幕切れにようやく満足~♪
染五郎さんの弥助は優男風だがぴしっと通った気品があり、他の
演目で見せるコミカルな所作との切り替えが見事。弥左衛門と二
人、主従関係が入れ替わる場面にも納得。出演者中、染五郎さん
が一番起伏の激しい1日だと思うがそこが見応えにもなっている。
壱太郎さんのお里は弥助LOVEなそぶりがほんとに可愛い。前回は
夫指南の場面でまだ遠慮があるように見えたが、18日にはお手本
を演じる時と、自分に戻って恥じらう時の落差がくっきり。面白
みが増していた。権太の最期の場面でも情の細やかさを感じる。
吉弥さんはいつもの艶っぽさを完全に消して権太の母になりきっ
ており、小悪党の息子の嘘にころっと騙されるところに、母親な
らではの弱さ、断ち切れない無償の愛情が伝わる。
父親としての想いと忠義の心を複雑に絡めながら、一番泣かせて
くれるのが弥左衛門の歌六さん。18日はさらに権太への愛情、孫
への想いが強く感じられた。やっとほめてもらえると嬉しそうに
振り返る権太を刺すタイミングも、権太が真実を明かしてゆく場
面での受け入れ方も、愛之助さんとの呼吸がぴたっと合って安心
して泣ける。

研辰の討たれ (とぎたつのうたれ)
守山辰次:染五郎 平井九市郎:愛之助
平井才次郎:獅童 八見伝介:亀鶴
小平権十郎:松也 宮田新左衛門:宗之助
中間市助:薪車 湯崎幸一郎:錦吾
粟津の奥方:高麗蔵 平井市郎右衛門:友右衛門
吾妻屋亭主清兵衛/僧良観:翫雀
<あらすじ>
粟津城中の侍溜りの間には、泰平の世をもてあます大勢の若侍が
所在なげにしていた。その中には、殿様や家老の刀を研いだのが
縁で、先ごろ町人から侍に取り立てられた研屋の辰次もいた。う
まく取り入り侍となったものの、根っからの町人根性は抜けず、
媚びやお追従を並べたてる辰次に、周りの侍たちは我慢を堪えて
いた。聡明な家老の平井市郎右衛門は、余りに鼻持ちならないの
で、皆の前で辰次を激しく罵倒し、唾をはきかけ去っていく。悔
しくてならない辰次は、市郎右衛門を待ち受け、だまし討ちで斬っ
てしまう。平井の長男九市郎と次男の才次郎が駆けつけ、敵討ち
を恐れる辰次は逃げ去り、九市郎と才次郎は敵討ちの旅に出るの
であった―
(歌舞伎美人 サイトより抜粋引用)
「野田版 研辰の討たれ」は私を歌舞伎に引き入れたお芝居。
初めて松竹座の敷居をまたいだ思い出深い演目だ。勘三郎さんの
人気もあり、またチケットの買い方もわからず、満席の劇場の
3階3列辺りで見たと思う。
(あの時は3階席で見ても楽しい演出があった♪)
面白いな~!なんて面白いんだろう、これが歌舞伎というものな
のか、それならもっと見たい、と心に決めたのだった。
なので歌舞伎版オリジナルがどれほど面白いのか、またあの時、
自分が見たものは歌舞伎だったのか演劇だったのか、そんな検証
をするのも今回の観劇の目的だったりする。
さて、ここで問題です。
「野田版と歌舞伎版の違い。粟津城の家老、平井市郎右衛門の直
接の死因は何だったでしょう?」
正解は、野田版では脳卒中。辰次の仕掛けたからくり殺人人形を
見て仰天、そのまま息絶えたのを、死因がそれでは家名に傷がつ
くからと辰次に斬り殺されたことにしたのが敵討ちの発端。
(辰次は脳卒中のことは知らずに敵討ちによって死んでしまう。
そこがあのホロリとさせる余韻につながるのだと思う。)
今回の歌舞伎版では辰次が直接殺めていた。落とし穴の横に取っ
てあった大きな石で頭を殴打し、その後何度か刀で斬っていた。
なので、敵討ちといえども、しょせんただの人殺しじゃないか!
という意味合いは野田版のほうが強く、歌舞伎版では辰次に同情
の余地はないように思えた。
ということで、最後の芝居的落としどころはあまり気にせずテン
ポのよさ、ばかばかしさを楽しむことにした。
本水をつかったり、今でいうリフトのような篭が登場したり、目
を見張る演出もある。(そのために犠牲になる場面転換の待ち時
間と回数の多さは改善希望。)
媚びへつらいながら、たとえみっともないと言われようが、死ぬ
のが怖い~!と言ってしまう辰次の醜態を、染五郎さんが面白可
笑しく演じている。2週間の間に命乞いの場面は進化してかなり
しつこくなっているように感じた。
平井兄弟の九市郎役の愛之助さん、才次郎役の獅童さんは、辰次
を追いかけて客席を走り回ったり、息を切らして台詞が言いづら
くて笑ってしまったり。そんなこんなもすべてひっくるめて巧み
に(?)客席を巻き込むことに成功している。
18日はあまりの可笑しさに別の意味の拍手が何度も起きていた。
2月5日はカーテンコールがあったが、18日にはなかった。
楽日はどうなるのだろう?














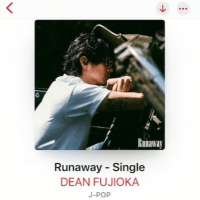
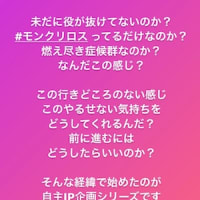
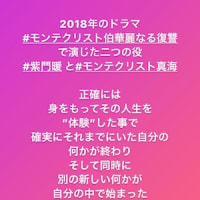


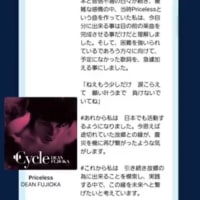












愛之助さんは満員の御礼と「次はこの座組みで5月に新橋でやりますのでよろしくお願いします」獅童さんは毎日が楽しい芝居が出来た事のお礼を言われていたと思います。
確かに今回は歌舞伎初心者が多い客席だったように思いますので、観客を増やす意味ではこのような芝居もアリかな?とは思いますが、団体さんが多いと言う事は大入りでも・・・
その中から一人でも多く本当の歌舞伎ファンが増えて下さる事を願います。
あのノリですからね、静かに帰らされると辛いものが(笑)。
私も千秋楽に行ってきました。
野田版でも勘三郎さんの辰次が3階席に現れてキャーキャー
言ったのを思い出しました。
今回は3階→2階→1階とくまなく走り回っていたので
3人は相当息切れしたと思います。
獅童さんは今回は同級生が多くて、子役の頃からいっしょに
舞台に立ってきた彼らといっしょに芝居を造れたことが
うれしい!と。声を震わせてウルウルしてたのでこちらまで
胸がいっぱいになりました。意外でした。
> その中から一人でも多く本当の歌舞伎ファンが増えて下さる事を願います。
たしかに! 今回の試みが新しい観客の獲得につながって、
このままどんどん定着していってほしいですよね。
そして関西での興行を継続していってほしいです。