初めて見てぶったまげました。
システィーナ歌舞伎の名前の通り、カタカナ文化と日本文化が混じ
り合った不思議な舞台。歌舞伎の荒唐無稽なところを自在に取り入
れながらも伝統美はたっぷり味わえて、しかもどこを切ってもエン
ターテインメント精神にあふれた、贅沢で素敵な公演だった。
出演者どうしの異種格闘なのはもちろん、場面ごとに切り替わる音
楽も賛美歌、長唄、フラメンコ、義太夫、バロック音楽・・・とい
うフツウでは考えられない取り合わせ。なのに妙にマッチしてるん
ですよーこれが。
ふと目をやれば、あの藤間勘十郎さんが効果音の鐘や太鼓を叩いて
いたりしておられるのが楽しくて♪
システィーナ礼拝堂の一部を模したホールはつねに壁画が見えてお
り、見上げれば天井画!
舞台はアリーナスタイル。つまり中央に舞台がドーンとあって、私
たち観客はそれを四方から取り囲むようにすわっている。アリーナ
奥と前方にはそれぞれ花道がつき、サイドからは階段ですばやく出
入りできるようになっていた。
天井画や壁画は上演中ずっと視界に入ったまま芝居が進行してゆく。
以下、感想&備忘録。場面タイトルはプログラムから引用。
それを見ながら思い出して書いたので、タイトルと内容が一致して
いるかどうかは不明。
第三回システィーナ歌舞伎
新作歌舞伎 和と洋のコラボレーション
GOEMON 石川五右衛門
~片岡愛之助宙乗りにて つづら抜け相勤め申し候~
劇場 大塚国際美術館 システィーナ・ホール
観劇日 2011年11月12日(土)夜 11月13日(日)昼
座席 椅子席

<スタッフ・キャスト>
作・演出:水口一夫
石川五右衛門:片岡愛之助 出雲の阿国:中村壱太郎
友市(子供時代の五右衛門):上村 吉太朗
石田局:上村吉弥 豊臣秀吉:石田太郎
カルデロン神父:伊礼彼方
特別出演:小島章司(フラメンコ舞踊家)
<あらすじ>
五右衛門は、明智光秀の重臣四王天但馬守の娘、石田局とイス
パニアの神父カルデロンとの間に生まれた混血児。ところが、
時の権力者、秀吉の出した切支丹禁止令・伴天連追放令によっ
て父は追放。母は秀吉のもとへ呼ばれるが目の前で自害する。
成人して天下を騒がす大盗賊となった五右衛門は、父と母の共
通の敵である天下人、秀吉への恨みを晴らすべく、その機会を
虎視眈々とうかがっている。
ある時、秀吉の命で聚楽第へと連れ去られた出雲の阿国。いや
いや舞を披露する阿国を救出したのが五右衛門だった。その後、
阿国が芸に行き詰まったときに、五右衛門は子供の頃に父に教
わったフラメンコを伝授する。二人の間に芽生える恋心。しかし、
阿国には名古屋山三 という大事なひとが。
とはいえ、秀吉の捕手に追われる身となった五右衛門には恋を
成就させる時間もなく。
やがて、南禅寺の山門の上に立つ五右衛門の姿が。そして、つ
いに父の待つイスパニアへと船出するのだった。

●第一部
<プロローグ 京都大聖堂>
会場の照明が落とされるとすぐ賛美歌が聴こえてきた。
ホール奥の壁画に十字架のシルエットがくっきり投影されている。
冒頭から厳かで清冽な空気が満ち、期待が高まる。
<第一場 大聖堂礼拝堂>
四方から大聖堂にポツポツと集まってくるキリシタンの老若男女たち。
(群衆の衣装は、黒のTシャツ&パンツ&小さな編笠だけで表現。)
舞台奥から現れたのはイスパニア人のカルデロン。伴天連の神父だ。
一段高くなった中央の舞台で行なわれているのは、神父と信者たちと
のいつものミサの光景なのだろう。
(カルデロン神父役の伊礼彼方さん。きれいなお顔でしかも小顔。
が、布教の使命に燃える若き神父はいかにも過ちを犯しそうな素敵
オーラを発しているぞ♪)
賛美歌が日本語の歌に変わる。(長唄の方が唄っておられるのだろ
うか、恨みがナントカって、詞も曲調も歌謡曲っぽい。)
ほらほら、言わんこっちゃない。
着物姿の妖し気なご婦人が登場。人目をしのんで来た風情ありあり。
頭には白の総レースのベール、手にはロザリオを持ち、思い詰めた
表情でひざまずき、祈りを捧げる。
苦悩をにじませた白い横顔が美しい。
(吉弥さん、お祈りをしている姿は息を飲む美しさだった。着物の下
半分には明智の家紋である桔梗の花が描かれている。)
この女性こそ明智光秀の重臣四王天但馬守の娘、石田局。
彼女に「神父さま」と呼ばれて驚き、うろたえるカルデロン神父。聖
職者の身でありながら自分は罪を犯した、悪魔に魂を売った、忘れて
ほしい、もうここには来ないでほしい、と頑に彼女を拒絶する。
秀吉を恨むことよりも神の教えを信じるようになったのは神父様の
おかげ。そして、いま私のお腹にはあなたの子供がいる、と石田局。
するとカルデロンはさらに驚き、こんどは愛ある眼差しで彼女を見つ
め、近づいて抱擁する。心が通じ、喜び合う二人。
最後にいっしょに十字を切り、カルデロンは石田局の体を気遣いつ
つ、二人手を取り合って大聖堂を後にする。
<第二場 南蛮寺の片隅 カルデロン住居>
ここで裃をつけて純也さんが登場。
とざい、とーざい!(隅々まで響き渡る声が心地いい。)
続けて口上。
以上が石川五右衛門の出生にまつわる発端であります。カルデロン
は神父をやめて通訳となり、親子三人仲良く暮らしておりました。
「それから7年が経ったのでございます」と口上を結ぶ。
(舞台奥と手前に向かってそれぞれ座礼して退場。)
秀吉の家臣が二人登場し、「切支丹禁止令」のお触れを出して回る。
カルデロンの住まいにやってきた家臣たち、伴天連のカルデロンに
国外追放を命じ、そのうえ秀吉の命として石田局を聚楽第へと召す。
聚楽第へ参内する前の親子3人の場面。
友市はイスパニア人とのハーフなので赤毛。そのことでいじめられ
る上に一人ぼっちにするのは耐えられない、と父が言う。
秀吉の命で親子が別れねばならないことを友市に話す母、石田局。
ここ、別れの場面は義太夫狂言で、たっぷりの見せ場。
(会場の土地柄、人形浄瑠璃の「傾城阿波鳴門」を思い出した。)
なんといっても友市を演じる吉太朗くんがたまりません。
声といい仕草といい、健気で父や母を慕う表情のかわゆらしいこと。
母子の別れは本当に見応えがあった。
母は友市に「秀吉は敵。明智の血を引く者としてお前がいつか敵を
とってくれ」と語ってきかす。さらに自害する覚悟であると話す母
に、死んでくださるな母上、とすがる友市。
出てゆく母の前に回り両手をそろえて引き止める姿のいじらしさ。
子を振り切って出ていく母親の後ろで、エエエエエという我が子の
泣き声が。両手で耳をふさぎながら逃げるように走り去る石田局。
この場面、吉弥さんは本当に泣いておられた。
父子の別れの場面は独特だ。
出てゆく前にカルデロンは友市に伴天連の秘術「空中飛行」を授け
る。(くうちゅうひぎょう、と言っていたのでこの漢字であろうと
思う。当然、その後のつづら抜けを想定しての前振りと思われる。)
父と子、両手を取り合って顔を見交わし、義太夫狂言の見本のよう
な別れの表現もある。(外国人の顔立ちの伊礼さんがこれをやるの
で奇妙な感覚におそわれつつも、なぜか見いってしまう。)
「強く生きていってくれ」と言う父に「お帰りはいつですか? それ
なら私もいっしょに行きとうございます」などと返す友市が不憫で
泣ける。振り切って出てゆく父。
友市はその場に倒れ込み、しばらく伏せた状態でいる。
<第三場 バロックの輝き>
光が射し、ゆっくり目を上げ起きる友市。
荘厳なバロックの演奏が聴こえている。
光のほう(舞台前方)を見上げ「あ、父上!」と。
「はい、いつまでもお帰りを待っています」「イスパニアはどんなと
ころでございますか?」などと、頬を輝かせ父に話しかけている。
(キュンとくるいいシーンでございます。)
友市と入れ替わりで、フラメンコ舞踊の小島章司さんが登場。
ん? フラメンコギターと歌も生演奏なのか。素晴らしい!
ダンサーは上下白の衣装で、男性だが下にはスカートをまとっている。
歌舞伎の女形をダンスに取り入れた演出なのではないかと思う。
長い髪を後ろに束ね、男性なのに時おり女性の顔に見えたりするのは
メイクのせいか、照明ゆえか。もの悲し気な歌と呼応するダンサーの
悲壮感ある眼差しに、気持ちが引っ張られてゆく。手拍子の連打が、
強い踏み込みのステップが、見ている私の気持ちをかき乱す。
芝居に直接絡むのではなく、イメージとしてのダンスが場の空気を熱
く、より濃密なものにしてゆく感じだ。
<第四場 聚楽第>
聚楽第の部屋。秀吉が家臣たちを従えて座している。
そこに呼ばれて入ってくるのは石田局・・・。
舞台前方の花道を女性が歩いてくる。
能の舞を見せる趣向のようだ。
上半身が鱗紋になった着物、顔には般若のお面、手には打ち状。
(『葵上』後シテ鬼相の六条御息所の衣装だと思うが、「八大竜王」
という台詞があったので演目わからず・・・。)
<2013/2/10追記>2013年の再演で能「春日龍神」だと判明!
舞いながら秀吉に向かって進み、打ち状を突きつける。親の敵である
ばかりか、夫と自分にまでこんな仕打ちをしたにっくき秀吉!と言わ
んばかりに。(ここ、演奏との相乗効果でかなりスリリングな場面。)
途中で足がふらつくので、様子がおかしいと家臣がお面を取り去ると、
石田局の口から血が吹き出ていた。陰腹していたのだ。顔色も青い。
「自害しおったか」と家臣たちが騒ぐ中、秀吉に近づき、この柔肌は
自由にはさせぬ、と秀吉に一太刀浴びせようとする。
が、家臣たちに止められ、ついに倒れ、こと切れる石田局。
(ふう~、激しい。けどカッコイイわ、石田局さん。片岡十二集にあ
る「石田の局」も見たくなった。)
「聞きしにまさる美しい女だ。このままいうことを聞いておれば一生
悠々と暮らせるものを。ばかなやつだ!」と秀吉が吐き捨てる。
(石田太郎さん、いい声。歌舞伎の発声とは違うが、ばかなやつ、と
大きくゆっくり言う響きに天下人の威厳がある。)
会場の照明が消え、緑色の火の玉がフワリ、フワリ。
浮かび上がる顔は石田局。魂はまださまよっているのか。
死んでも秀吉のことは決してゆるすまじ、という強い意志を感じる。
(やはり六条御息所か?)
<第五場 ややこ踊り>
見物衆の前で踊る10人ほどの若き女たち。
出雲の阿国とその芸人一座たちはすっかりまちの人気者なのだ。
ここからはショータイム。群舞は華やかだし、壱太郎さんは若さの中
にも色気が漂い、私も見物衆の一人になった気分。
(阿国の初期の頃の踊りは「ややこ踊り」と呼ばれていたらしい。)
そこへ秀吉の一行が通りがかり・・・。
しばらくしてなんと阿国が連れ去られてしまった!!!
傘をかぶった男が奥の花道から登場。黒の衣装で傘を取ると、赤毛~♪
(やっとだよ。ひゅうひゅう、待ってました、松嶋屋っ。にしても赤毛
の五右衛門なんて初めて。ついつい頭に目がいってしまう。)
「母を奪い、女を盗み、秀吉は大泥棒」。
(はは、笑っちゃう。大泥棒の石川五右衛門に言われてらぁ~。)
「この友市が五右衛門と名をあらためての盗っ人稼業。秀吉に報わんが
ため」。(名乗りの台詞回しはお腹に響く低い声でゆっくり。ちょこっ
との登場ですごい存在感。愛之助さん、堂々とした大泥棒ぶりだわ。)
<第六場 秀吉の寝所>
秀吉に見染められ連れてこられた阿国、すでに聚楽第にいる。
嫌々参内した阿国はバシッとひとこと。
「芸は売っても体は売らず!」
(石田局にも同じようなことを言われてたよね> 女好きの秀吉!)
その言葉に秀吉は笑い出す。「実に面白い女だ。では踊れ。舞え!」
阿国が舞っている途中に乱入者あり。
舞台奥から登場したの赤や緑のド派手衣装の赤毛男。
阿国に向かって「石川五右衛門、盗賊さ。驚かなくていい。秀吉の鼻
をあかしたいだけだ」と。ここからは救出劇。
捕り手が集まってきて五右衛門との派手な立ち回りが始まる。
12日夜と13日昼の部ではここの演出が変更になっていた。
(理由は後述。最後の最後に。)
捕り手たちの上に乗ったり、捕り手たちが高く掲げたハシゴの上で
見得を決めた後、ピョンと舞台に飛び降りたりしていたのは12日。
13日はハシゴの上に腰をかけてポーズを決め、ハシゴをそっと下にお
ろしてから足をついていた。花道の出と引っ込みも、13日は極力花道
を使わず直接出入りするやり方に変更されていた。それでも13日に初
めて見た人には全く違和感のない演出変更だったと思う。
秀吉が五右衛門の持っていた刀の秘密に気づく。「鞘から抜いただけ
で雷鳴が轟く刀があると聞く。さては五右衛門は明智の血筋か?」
大立ち回りの後、煙幕が張られ、印を結んで五右衛門が消えた。
カンカンカンと鐘の音が響いて、舞台右奥の天井につづらが!
つづらの戸が開いて、中からナント五右衛門が~っっっ。
「つづらしょったら可笑しいか! ばーかーめー!」と見得をキメる。
(うっうっ、そら可笑しいワ。なんて人を喰った台詞。なんて楽しげ。)
手を引き上げていく所作から、空中を踊って渡る動作に。
初めて見る愛之助さんの宙乗り。ワイヤーは舞台右後方から左前方へ
と対角線にナナメに横断。どの角度からも見えるように、五右衛門は
つづらといっしょにクルクルクル。足は自転車をこいでるカンジ・・・
近くに来たときに見上げたら裸足だった♪
途中で止まってつづらに言う。
「おっとあぶない。阿国、あばれるんじゃないよ」
大興奮の宙乗り。いやはや、盛り上がりました!!
(ここで10分の休憩)

・・・・・・書けたら書くぞ、第二部!(指しだい)
●このブログ内の関連記事
~第三回システィーナ歌舞伎「GOEMON 石川五右衛門」(2)
システィーナ歌舞伎の名前の通り、カタカナ文化と日本文化が混じ
り合った不思議な舞台。歌舞伎の荒唐無稽なところを自在に取り入
れながらも伝統美はたっぷり味わえて、しかもどこを切ってもエン
ターテインメント精神にあふれた、贅沢で素敵な公演だった。
出演者どうしの異種格闘なのはもちろん、場面ごとに切り替わる音
楽も賛美歌、長唄、フラメンコ、義太夫、バロック音楽・・・とい
うフツウでは考えられない取り合わせ。なのに妙にマッチしてるん
ですよーこれが。
ふと目をやれば、あの藤間勘十郎さんが効果音の鐘や太鼓を叩いて
いたりしておられるのが楽しくて♪
システィーナ礼拝堂の一部を模したホールはつねに壁画が見えてお
り、見上げれば天井画!
舞台はアリーナスタイル。つまり中央に舞台がドーンとあって、私
たち観客はそれを四方から取り囲むようにすわっている。アリーナ
奥と前方にはそれぞれ花道がつき、サイドからは階段ですばやく出
入りできるようになっていた。
天井画や壁画は上演中ずっと視界に入ったまま芝居が進行してゆく。
以下、感想&備忘録。場面タイトルはプログラムから引用。
それを見ながら思い出して書いたので、タイトルと内容が一致して
いるかどうかは不明。
第三回システィーナ歌舞伎
新作歌舞伎 和と洋のコラボレーション
GOEMON 石川五右衛門
~片岡愛之助宙乗りにて つづら抜け相勤め申し候~
劇場 大塚国際美術館 システィーナ・ホール
観劇日 2011年11月12日(土)夜 11月13日(日)昼
座席 椅子席

<スタッフ・キャスト>
作・演出:水口一夫
石川五右衛門:片岡愛之助 出雲の阿国:中村壱太郎
友市(子供時代の五右衛門):上村 吉太朗
石田局:上村吉弥 豊臣秀吉:石田太郎
カルデロン神父:伊礼彼方
特別出演:小島章司(フラメンコ舞踊家)
<あらすじ>
五右衛門は、明智光秀の重臣四王天但馬守の娘、石田局とイス
パニアの神父カルデロンとの間に生まれた混血児。ところが、
時の権力者、秀吉の出した切支丹禁止令・伴天連追放令によっ
て父は追放。母は秀吉のもとへ呼ばれるが目の前で自害する。
成人して天下を騒がす大盗賊となった五右衛門は、父と母の共
通の敵である天下人、秀吉への恨みを晴らすべく、その機会を
虎視眈々とうかがっている。
ある時、秀吉の命で聚楽第へと連れ去られた出雲の阿国。いや
いや舞を披露する阿国を救出したのが五右衛門だった。その後、
阿国が芸に行き詰まったときに、五右衛門は子供の頃に父に教
わったフラメンコを伝授する。二人の間に芽生える恋心。しかし、
阿国には名古屋山三 という大事なひとが。
とはいえ、秀吉の捕手に追われる身となった五右衛門には恋を
成就させる時間もなく。
やがて、南禅寺の山門の上に立つ五右衛門の姿が。そして、つ
いに父の待つイスパニアへと船出するのだった。

●第一部
<プロローグ 京都大聖堂>
会場の照明が落とされるとすぐ賛美歌が聴こえてきた。
ホール奥の壁画に十字架のシルエットがくっきり投影されている。
冒頭から厳かで清冽な空気が満ち、期待が高まる。
<第一場 大聖堂礼拝堂>
四方から大聖堂にポツポツと集まってくるキリシタンの老若男女たち。
(群衆の衣装は、黒のTシャツ&パンツ&小さな編笠だけで表現。)
舞台奥から現れたのはイスパニア人のカルデロン。伴天連の神父だ。
一段高くなった中央の舞台で行なわれているのは、神父と信者たちと
のいつものミサの光景なのだろう。
(カルデロン神父役の伊礼彼方さん。きれいなお顔でしかも小顔。
が、布教の使命に燃える若き神父はいかにも過ちを犯しそうな素敵
オーラを発しているぞ♪)
賛美歌が日本語の歌に変わる。(長唄の方が唄っておられるのだろ
うか、恨みがナントカって、詞も曲調も歌謡曲っぽい。)
ほらほら、言わんこっちゃない。
着物姿の妖し気なご婦人が登場。人目をしのんで来た風情ありあり。
頭には白の総レースのベール、手にはロザリオを持ち、思い詰めた
表情でひざまずき、祈りを捧げる。
苦悩をにじませた白い横顔が美しい。
(吉弥さん、お祈りをしている姿は息を飲む美しさだった。着物の下
半分には明智の家紋である桔梗の花が描かれている。)
この女性こそ明智光秀の重臣四王天但馬守の娘、石田局。
彼女に「神父さま」と呼ばれて驚き、うろたえるカルデロン神父。聖
職者の身でありながら自分は罪を犯した、悪魔に魂を売った、忘れて
ほしい、もうここには来ないでほしい、と頑に彼女を拒絶する。
秀吉を恨むことよりも神の教えを信じるようになったのは神父様の
おかげ。そして、いま私のお腹にはあなたの子供がいる、と石田局。
するとカルデロンはさらに驚き、こんどは愛ある眼差しで彼女を見つ
め、近づいて抱擁する。心が通じ、喜び合う二人。
最後にいっしょに十字を切り、カルデロンは石田局の体を気遣いつ
つ、二人手を取り合って大聖堂を後にする。
<第二場 南蛮寺の片隅 カルデロン住居>
ここで裃をつけて純也さんが登場。
とざい、とーざい!(隅々まで響き渡る声が心地いい。)
続けて口上。
以上が石川五右衛門の出生にまつわる発端であります。カルデロン
は神父をやめて通訳となり、親子三人仲良く暮らしておりました。
「それから7年が経ったのでございます」と口上を結ぶ。
(舞台奥と手前に向かってそれぞれ座礼して退場。)
秀吉の家臣が二人登場し、「切支丹禁止令」のお触れを出して回る。
カルデロンの住まいにやってきた家臣たち、伴天連のカルデロンに
国外追放を命じ、そのうえ秀吉の命として石田局を聚楽第へと召す。
聚楽第へ参内する前の親子3人の場面。
友市はイスパニア人とのハーフなので赤毛。そのことでいじめられ
る上に一人ぼっちにするのは耐えられない、と父が言う。
秀吉の命で親子が別れねばならないことを友市に話す母、石田局。
ここ、別れの場面は義太夫狂言で、たっぷりの見せ場。
(会場の土地柄、人形浄瑠璃の「傾城阿波鳴門」を思い出した。)
なんといっても友市を演じる吉太朗くんがたまりません。
声といい仕草といい、健気で父や母を慕う表情のかわゆらしいこと。
母子の別れは本当に見応えがあった。
母は友市に「秀吉は敵。明智の血を引く者としてお前がいつか敵を
とってくれ」と語ってきかす。さらに自害する覚悟であると話す母
に、死んでくださるな母上、とすがる友市。
出てゆく母の前に回り両手をそろえて引き止める姿のいじらしさ。
子を振り切って出ていく母親の後ろで、エエエエエという我が子の
泣き声が。両手で耳をふさぎながら逃げるように走り去る石田局。
この場面、吉弥さんは本当に泣いておられた。
父子の別れの場面は独特だ。
出てゆく前にカルデロンは友市に伴天連の秘術「空中飛行」を授け
る。(くうちゅうひぎょう、と言っていたのでこの漢字であろうと
思う。当然、その後のつづら抜けを想定しての前振りと思われる。)
父と子、両手を取り合って顔を見交わし、義太夫狂言の見本のよう
な別れの表現もある。(外国人の顔立ちの伊礼さんがこれをやるの
で奇妙な感覚におそわれつつも、なぜか見いってしまう。)
「強く生きていってくれ」と言う父に「お帰りはいつですか? それ
なら私もいっしょに行きとうございます」などと返す友市が不憫で
泣ける。振り切って出てゆく父。
友市はその場に倒れ込み、しばらく伏せた状態でいる。
<第三場 バロックの輝き>
光が射し、ゆっくり目を上げ起きる友市。
荘厳なバロックの演奏が聴こえている。
光のほう(舞台前方)を見上げ「あ、父上!」と。
「はい、いつまでもお帰りを待っています」「イスパニアはどんなと
ころでございますか?」などと、頬を輝かせ父に話しかけている。
(キュンとくるいいシーンでございます。)
友市と入れ替わりで、フラメンコ舞踊の小島章司さんが登場。
ん? フラメンコギターと歌も生演奏なのか。素晴らしい!
ダンサーは上下白の衣装で、男性だが下にはスカートをまとっている。
歌舞伎の女形をダンスに取り入れた演出なのではないかと思う。
長い髪を後ろに束ね、男性なのに時おり女性の顔に見えたりするのは
メイクのせいか、照明ゆえか。もの悲し気な歌と呼応するダンサーの
悲壮感ある眼差しに、気持ちが引っ張られてゆく。手拍子の連打が、
強い踏み込みのステップが、見ている私の気持ちをかき乱す。
芝居に直接絡むのではなく、イメージとしてのダンスが場の空気を熱
く、より濃密なものにしてゆく感じだ。
<第四場 聚楽第>
聚楽第の部屋。秀吉が家臣たちを従えて座している。
そこに呼ばれて入ってくるのは石田局・・・。
舞台前方の花道を女性が歩いてくる。
能の舞を見せる趣向のようだ。
上半身が鱗紋になった着物、顔には般若のお面、手には打ち状。
(『葵上』後シテ鬼相の六条御息所の衣装だと思うが、「八大竜王」
という台詞があったので演目わからず・・・。)
<2013/2/10追記>2013年の再演で能「春日龍神」だと判明!
舞いながら秀吉に向かって進み、打ち状を突きつける。親の敵である
ばかりか、夫と自分にまでこんな仕打ちをしたにっくき秀吉!と言わ
んばかりに。(ここ、演奏との相乗効果でかなりスリリングな場面。)
途中で足がふらつくので、様子がおかしいと家臣がお面を取り去ると、
石田局の口から血が吹き出ていた。陰腹していたのだ。顔色も青い。
「自害しおったか」と家臣たちが騒ぐ中、秀吉に近づき、この柔肌は
自由にはさせぬ、と秀吉に一太刀浴びせようとする。
が、家臣たちに止められ、ついに倒れ、こと切れる石田局。
(ふう~、激しい。けどカッコイイわ、石田局さん。片岡十二集にあ
る「石田の局」も見たくなった。)
「聞きしにまさる美しい女だ。このままいうことを聞いておれば一生
悠々と暮らせるものを。ばかなやつだ!」と秀吉が吐き捨てる。
(石田太郎さん、いい声。歌舞伎の発声とは違うが、ばかなやつ、と
大きくゆっくり言う響きに天下人の威厳がある。)
会場の照明が消え、緑色の火の玉がフワリ、フワリ。
浮かび上がる顔は石田局。魂はまださまよっているのか。
死んでも秀吉のことは決してゆるすまじ、という強い意志を感じる。
(やはり六条御息所か?)
<第五場 ややこ踊り>
見物衆の前で踊る10人ほどの若き女たち。
出雲の阿国とその芸人一座たちはすっかりまちの人気者なのだ。
ここからはショータイム。群舞は華やかだし、壱太郎さんは若さの中
にも色気が漂い、私も見物衆の一人になった気分。
(阿国の初期の頃の踊りは「ややこ踊り」と呼ばれていたらしい。)
そこへ秀吉の一行が通りがかり・・・。
しばらくしてなんと阿国が連れ去られてしまった!!!
傘をかぶった男が奥の花道から登場。黒の衣装で傘を取ると、赤毛~♪
(やっとだよ。ひゅうひゅう、待ってました、松嶋屋っ。にしても赤毛
の五右衛門なんて初めて。ついつい頭に目がいってしまう。)
「母を奪い、女を盗み、秀吉は大泥棒」。
(はは、笑っちゃう。大泥棒の石川五右衛門に言われてらぁ~。)
「この友市が五右衛門と名をあらためての盗っ人稼業。秀吉に報わんが
ため」。(名乗りの台詞回しはお腹に響く低い声でゆっくり。ちょこっ
との登場ですごい存在感。愛之助さん、堂々とした大泥棒ぶりだわ。)
<第六場 秀吉の寝所>
秀吉に見染められ連れてこられた阿国、すでに聚楽第にいる。
嫌々参内した阿国はバシッとひとこと。
「芸は売っても体は売らず!」
(石田局にも同じようなことを言われてたよね> 女好きの秀吉!)
その言葉に秀吉は笑い出す。「実に面白い女だ。では踊れ。舞え!」
阿国が舞っている途中に乱入者あり。
舞台奥から登場したの赤や緑のド派手衣装の赤毛男。
阿国に向かって「石川五右衛門、盗賊さ。驚かなくていい。秀吉の鼻
をあかしたいだけだ」と。ここからは救出劇。
捕り手が集まってきて五右衛門との派手な立ち回りが始まる。
12日夜と13日昼の部ではここの演出が変更になっていた。
(理由は後述。最後の最後に。)
捕り手たちの上に乗ったり、捕り手たちが高く掲げたハシゴの上で
見得を決めた後、ピョンと舞台に飛び降りたりしていたのは12日。
13日はハシゴの上に腰をかけてポーズを決め、ハシゴをそっと下にお
ろしてから足をついていた。花道の出と引っ込みも、13日は極力花道
を使わず直接出入りするやり方に変更されていた。それでも13日に初
めて見た人には全く違和感のない演出変更だったと思う。
秀吉が五右衛門の持っていた刀の秘密に気づく。「鞘から抜いただけ
で雷鳴が轟く刀があると聞く。さては五右衛門は明智の血筋か?」
大立ち回りの後、煙幕が張られ、印を結んで五右衛門が消えた。
カンカンカンと鐘の音が響いて、舞台右奥の天井につづらが!
つづらの戸が開いて、中からナント五右衛門が~っっっ。
「つづらしょったら可笑しいか! ばーかーめー!」と見得をキメる。
(うっうっ、そら可笑しいワ。なんて人を喰った台詞。なんて楽しげ。)
手を引き上げていく所作から、空中を踊って渡る動作に。
初めて見る愛之助さんの宙乗り。ワイヤーは舞台右後方から左前方へ
と対角線にナナメに横断。どの角度からも見えるように、五右衛門は
つづらといっしょにクルクルクル。足は自転車をこいでるカンジ・・・
近くに来たときに見上げたら裸足だった♪
途中で止まってつづらに言う。
「おっとあぶない。阿国、あばれるんじゃないよ」
大興奮の宙乗り。いやはや、盛り上がりました!!
(ここで10分の休憩)

・・・・・・書けたら書くぞ、第二部!(指しだい)
●このブログ内の関連記事
~第三回システィーナ歌舞伎「GOEMON 石川五右衛門」(2)














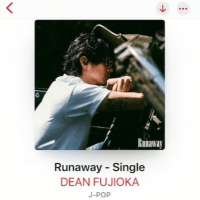
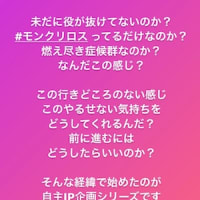
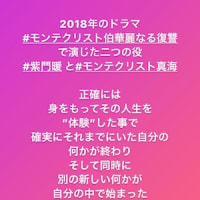


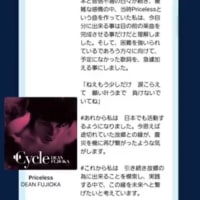












私なんて
永楽館の感想がまだ終わってなくて
毎晩うなされそうなんですけど(笑)
いつもながら
詳細なレポに感動!(^^)!です。
システィーナ歌舞伎3度目ですが
回を重ねるごとに進化しているなあ
と感嘆しています。
2回の観劇をご一緒できて
(観劇後のおしゃべりも)
大変光栄です!
またたくさんお話を聞かせてくださ~い。
安心してこちらを書きかけたんですけどね。
システィーナは1回と2回を見ていないので
進化の具合がわからないのですが、とにかく
会場の特性や魅力を最大限に生かす演目、
演出の工夫に拍手ですね。
第2部も少しずつ書き足していければいいのですが。
観劇後の長い長いおしゃべりも楽しかったです!
またね~♪