先週の日曜日に京都南座で顔見世観劇。
師走の南座の前は何度も通っているというのに、中に入るのは全く初めて。
なので、まずはゆっくりまねき見物をしてから劇場へ。
ここに掲げられた役者さんのお名前とお顔が半分以上一致しないことが、なによ
りも歌舞伎ビギナーぶりを証明している。
ざっと見渡したところ、中村とつくお名前が半分以上。
私が歌舞伎を観るきっかけになった勘三郎さんのまねきは上段のほぼ真ん中に。
なんといっても襲名披露の主役ですから。
向かって左側には勘三郎さんの舞台で拝見して覚えた役者さんたちが。
橋之助さん、勘太郎さん、七之助さんたちは勘三郎さんと同じく上段に。
右側には上方歌舞伎の役者さんたち。(そういう表現でいいのかな。)
今年の壽初春大歌舞伎の「十六夜清心」で初観劇し、ついウットリしてしまった
仁左衛門さんは下段の右端に構えている。そのすぐ上に、上方歌舞伎の復興に長
年努めてこられ、今年1月に四代目を襲名した坂田藤十郎さんのお名前が。
秀太郎さんは仁左衛門さんと同じ下段の真ん中に。その右隣りには孝太郎さん。
今年3つ目の公演を観ることになった愛之助さんは上段の右から3番目。
もっと早くから観ていればよかったと思う役者さんがこの1年でずいぶん増えた。
 |
|
●平家女護島 俊寛(しゅんかん)
<配役>
俊寛僧都:仁左衛門 丹波少将成経:秀太郎 海女千鳥:孝太郎
平判官康頼:愛之助 瀬尾太郎兼康:段四郎 丹左衛門尉基康:我當
平家転覆を企てた咎で、俊寛らが薩摩鬼界島に流されたという「鹿ヶ谷の陰謀」
のその後のお話。
高僧としてではなく、人間俊寛の苦しみ、口惜しさ、憎悪、悲しみ、切なさと
いったマイナスの感情を次から次へと見せつけてくれる仁左衛門さんを、思いっ
きり堪能いたしました。俊寛はまだ30代なんだから、あきらめきれない、捨てき
れない思いがあって当然。自分だけが赦免にならないとわかった時に着物の袖を
咬む仕草がたまらなくて。客席でもこの瞬間に拍手が起きたので、やはりこれは
仁左衛門さんの見せ場だったみたい。(なにぶん初俊寛なもので。)
自分の代わりに千鳥を船に乗せ、さも俊寛は良い人だった、めでたしめでたし、
で終わらないのが近松モノなのだそう。(←イヤホンガイドの解説より)
「思い切っても凡夫心」の場面で船が離れた後に海に入って追いかけてゆく姿は
3階席から観ていても迫力じゅうぶん。
最後、小高い場所に上り船を見届けながら動かなくなるところ。まるで岩になっ
てしまったかのようで、俊寛はあのままあの場所で島の草木となって朽ち果てて
しまったのだと思わせられるものがあった。
で、千鳥といっしょになるのは愛之助さんじゃなく秀太郎さんだったんだ~。
千鳥役の孝太郎さん。俊寛と使者の瀬尾が争っている時に、助っ人に入ろうと物陰
から様子をうかがっている姿が上から丸見えで、妙にかわいらしくてツボでした。
そして段四郎さん演じる使者、瀬尾太郎兼康の衣装に目が釘付け! 歌舞伎って
ホントになんてクリエイティブなんだろう~♪
●十八代目中村勘三郎襲名披露 口上
<出演>勘九郎改め勘三郎 幹部俳優
夏に見られなかった勘太郎さん。南座には初お目見えとのこと。口上のときの襖絵
が金子國義画伯によるものであるというひとことも添えてくれました。
勘三郎さん。今回夜の部で踊る「京鹿子娘道成寺」を、お隣りにすわっている岳父
の芝翫さんに逐一教わったとのこと。
仁左衛門さん。「小さな頃から脚光を浴びていたけれど、今までずっと脚光を浴びっ
ぱなし。それも勘三郎さん自身の並々ならぬ努力の賜物」と。
とにかく華のある役者さんたちがいっぱい並んだ楽しい口上だった。
●京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ) 道行より押戻しまで
<配役>
白拍子花子 勘三郎
大館左馬五郎照秀 我當
京鹿子娘道成寺には二つの代表的な流派があるらしい。
今回の「京鹿子~」は血筋的に二つの流派の合流点にあたる勘三郎さんならではの
やり方で踊るとのこと。(流派についてはイヤホンガイドで聴いた事がウロ覚えで、
ワケがわからなくなったので削除しました。)
そういうことまでわかるようになれば歌舞伎がもっと楽しくなるんだろうな。
ムズカシイことはともかく、勘三郎さんは今までに私が見たことのないような顔で、
間違いなくきれいな若い女という表情で、延々と踊り続けた。
(前回見たのがいがみの権太だから、ギャップありすぎ!)
道成寺の鐘供養に現れた若い女、白拍子の花子。清姫の怨霊らしく、恋に身をやつ
す女の執念をところどころで見せ、ときどき鐘を睨みつける目がこわかった。
歌舞伎座でもやっていたけれど、お化粧をする時に使った紙をぽいと客席に投げる
演出に、勘三郎さん、やっぱりエンターテイナーだなあと思う。
個人的に昼の部のチケットが買えなくて、勘三郎さんの源九郎狐をナマで見損なっ
たのが残念。(大晦日にTVでさっそく会えるけれど、いつかきっとナマで見たい!)
白拍子の花子を境内に入れるときに、道成寺の所化(お坊さん)たちが全員で
「お入りなさい」の代わりに「来なこもち、来なこもち」というのがおかしくて。
しばらく耳にこびりついていた。
●雁のたより(かりのたより)
髪結三二五郎七:藤十郎 愛妾司:扇雀 若殿前野左司馬:愛之助
下剃の安:亀鶴 乳母お光:竹三郎 若旦那万屋金之助:翫雀
家老高木治郎太夫:段四郎 花車お玉:秀太郎
お話の舞台が有馬だし、台詞も話し言葉のような関西弁だし、親しみやすかった
のだけれど、3階席からは何人かの役者さんの台詞があまり聞こえなかったのが
残念!! イヤホンガイドのボリュームを上げて聴くのが疲れてしまった~。
最後は歌舞伎らしいオチがあって、ナルホドなお話だった。
愛之助さんの若殿は司に全く相手にされず、お金はあっても心までは買えなかった
というなさけない役。金打(きんちょう)という武士ならではの儀式を行っていた
のはこの役だったと思うんだけど。
●乗合船恵方萬歳(のりあいぶねえほうまんざい)
万歳:翫雀 才造:橋之助 門礼者:進之介 女船頭:孝太郎
大工:愛之助 通人:勘太郎 芸者;七之助 子守:鶴松
田舎侍:弥十郎 白酒売:扇雀
今から船に乗ろうとする人たちが自己紹介を兼ねて順番に舞うという、なんとは
なしにおめでたい演目。乗り込む人物を七福神に見立てるという趣向。
翫雀さんと橋之助さんがにこやかな顔で歌って語る昔の萬歳が珍しかった。
勘太郎さんの<通人>が不思議な雰囲気を持っていたのと、愛之助さんの大工さん
がビジュアル的に美しかったのが印象的。
今回の顔見世で名前と顔が一致する役者さんがまた少しふえたよ♪
「古典はともだち歌舞伎セミナー」第一部だけ(このブログ内の関連記事)














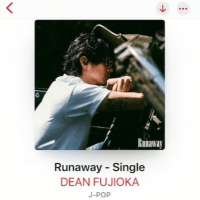
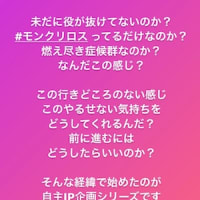
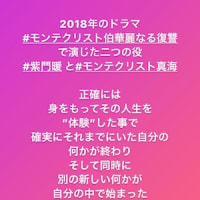


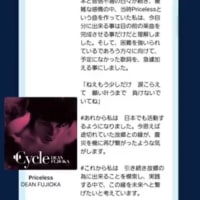












いや、私的にかもしれないけど・・・。
『俊寛』は今年の7本の指に入るかも・・・という
感動ものでしたね・・・。
今年も何本かいい作品に出会えてよかった♪
その内でもムンバリさんといくつかご一緒させていただき、
とてもよかったわあ~♪
来年もどうぞよろしくです♪・・って、まだ残すところ数日有るし・・・(笑)
私、源九郎狐の勘三郎さんを見てないのが心残りで、昼の部も観たかずりんさんがうらやましいです。
「俊寛」は噂には聞いてたけど、仁左衛門さんで観られてよかったわぁとほんとに思います。もう一度観てみたい!
こちらこそ、今年初めて会ったにしては前々からのともだちのようで(笑)、いろいろいっしょに観られて楽しかったですよー。かずりんさんほどは観てないけど、私も良い舞台に巡り逢えました。来年はまず「アレ」で逢いましょう!!