第二部は凝った構成だった。
まず、舞踏に関するレクチャー。
続いて、文楽「日高川入相花王 渡し場の段」を人形なしで上演
し、それを舞踏手が引き継ぎ、舞踏のパフォーマンスを披露。
最後に人形を入れて「日高川~」をもう一度見せる。
文楽と舞踏のコラボが感覚的に楽しめる演出にワクワク。

第二部 舞踏の源流・文楽
<講演 土方巽と芸術家たち>
建畠 哲(詩人・京都市立芸術大学学長)
文楽ファンの人たちといっしょに「舞踏」の映像を見て、土方巽
の話を聞く。かなり奇妙な感覚だった。
その日に見る映像に関して男性(お名前わからず)の解説が入る。
最初の映像は1968年の「肉体の反乱」から若き土方巽のずいぶん
挑発的でエロティックな舞台。つづく1970年代の映像は「疱瘡譚」
から。病や肉体的弱者の体の動きに着目したパフォーマンスという
ことだった。(白塗り、肌の露出、局部の誇張、空中移動、等々が
あるかと思えば、躍動とは対局にある奇異な身体表現もある。私が
持っているDVDは1973年の「夏の嵐 燔犧大踏鑑」なので、それ以
外の舞台映像が見られたのがウレシかった。)
伝統芸能との関係でいえば、音楽に義太夫や津軽三味線を使用した
ことがあった、とのこと。
彼の最後のパフォーマンスに間に合ったという建畠哲さんによれば、
人類は「土方巽を見たか否か」の2種類に分かれるそうだ♪
当時の熱狂的な観客の目線や熱気が話の端々から伝わってくる。
土方は三島由紀夫、細江英公、横尾忠則、澁澤龍彦、高橋睦郎ら
ジャンルを越えた芸術家、文化人たちと交流があったという。
細江英公と土方巽のコラボ写真集『鎌鼬』(かまいたち)からの
写真も数枚紹介された。
1965年に横尾忠則がデザインした暗黒舞踏の公演「バラ色ダン
ス―A LA MAISON DE M. CIVECAWA」のポスターもあった。
(こちらで見られます )
それまでの横尾忠則の作風が一変するきっかけとなったポスター
だと聞く。二人の出会いによって生まれた時代の落とし子的作品。
CIVECAWAとは澁澤龍彦のことだそうで、公演の出演者の中には
大野一雄・大野慶人の名前も見られる。
建畠さんの高尚な解説を勝手に噛み砕いてメチャクチャ平たく言
うとこうなるだろうか?
文楽は<人形>に人間を憑依させることによって人間以上に生々
しい存在になる。一方、土方の舞踏はオブジェとしての体、不自
由な肉体を意識することより結果として生々しいものを表現して
みせた。文楽と舞踏、そこに通じるものがあるのではないか。
(舞踏はいわば、自分で自分の体を人形の体のように客観的に扱っ
た、ということだろうか? 間違っていたらすみません。。。)
「舞踏」の表現の根本にある理論を「文楽」と結びつけて説明し
てくださったおかげで今までわからなかったことが感覚的にわかっ
たような気がする。
<創作と新演出による「舞踏と文楽のコラボレーション」>
●日高川入相花王 渡し場の段(人形なし)
浄瑠璃:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友、鶴澤清公
出演:桐竹勘十郎 ほか
舞台上に床が置かれ、浄瑠璃と三味線による出語り。
やはり、手摺や書割等のないシンプルな舞台。
下手から3人の人形遣いが全員黒衣姿で登場してくる。
黒ずくめで人形を持たないので、黒い長袖の先の露出した肌色
だけが目立っている。
人形を脱いで露になった勘十郎さんの左手、裸の指にゴクリ♪
一瞬、なんだか見てはいけないものを見てしまった気がした。
(やっぱり秘密クラブかもしれない。)
が、すぐにSな気持ちが打ち勝って、そこから先はほとんど舐め
るように見ていたと思う。
あ、これか。これなのか。
見てはいけないものを見てしまったー!という感覚は、白虎社
(舞踏集団)を初めて観た時の衝撃と興奮に通じる。
ところが、そんなヘナチョコな思いはすぐに吹き飛んだ。
勘十郎さんはじめ3人の人形遣いによる本物の力というか、伝統
芸能の持つ圧倒的なエネルギーに打ち砕かれた。
勘十郎さんの左手は胴串を握った形をしている。親指が上方に
開いて、人差し指は細やかに滑らかに動き、握り方がゆるんだり
ギュッとなったり。あとの3本はピタリとくっつき人差し指と連
動して動く。
初めのうちは<指>だと思っていたのに、その手はいつのまに
か性別を帯び、感情を見せ、所作を知り、意志を持っていた。
ときおり艶かしいんである♪
それは恋に胸を焦がす若い女そのもの。激しい情念と強い意志
で思いを遂げようとする女が目の前にいるようだった。
左遣いの手は動きが静かな時と、忙しく動いている時がある。
いろいろと仕事があるのだと人形付きで見てわかった。
足遣いは下にいて中腰だったりしゃがんだり、両手をシャカ
シャカさかんに交差させたり。
面白いのはこの3人がくっついたまま動くということ。ある場面
では横長の舞台の隅っこに固まっていた。主遣いと左遣いの体の
間を足遣いがくぐり抜けた時は一連の群舞を見ているようだった。
人形がなくても、3人がある法則にしたがって1つの有機体とし
て動いていることに今さら感動する。
うん、三位一体だ。
3人が舞台から通路に出てきたときが大コーフン!
わわ、泳いでるやんっ♪ 川が見えるやん~。
------自分用メモ------
足遣いの動きを見て思い出したこと。
下からゲンコツが勢いよく飛び出し、手がそそり立つ時がある。
(女性がすわった時の足遣いの手だと、昨年9月の勘十郎さんの
講演で説明された記憶がある。)
2007年に観たNODA・MAPの「THE BEE」の舞台で報道陣がマ
イクを暴力的に突き出すシーンがこれにそっくりなんである。
調べたところでは、勘十郎さんが初めてエア人形に挑んだのは
おそらく2005年、大阪倶楽部での上演がはじまりのようだ。
その後、何度か披露の機会があったわけだし、野田さんはこの
エア人形をかなり早い時期に見たことあるんじゃないだろうか?
------------------------
「髪も逆立ち波頭抜き手を切って渡りしは怪しかりける」
エアー人形の上演が終わり、舞台上の姫の息づかいが聴こえてき
そうなタイミングで、下手から剃髪の男が静かに登場。
赤の着物に藍の袈裟懸け・・・え! 安珍?と思わず息をのんだ。
人形遣いがそっと下手に引っ込む。
●浄瑠璃で舞踏を舞う 「病める舞姫」より
作曲・演奏:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友
振付・出演:由良部正美
文楽の余韻が残っている。
由良部さんの舞踏は安珍イメージで引き継がれた。
「言っておきたいことがある。もっと大事なことがある。
ずるずるずるっとだまされる。みすみすわかってだまされる。」
土方巽の言葉はなんて挑発的なんだろう。
今回はじめてそう思った。
舞い手。語り。2007年に観たものと同じなのに感じ方が違う。
とても義太夫っぽい。演出が違うせいだろうか。
(舞踏に合わせて語り、演奏するのはどういう点が違いますか?
音楽と比べて浄瑠璃は舞いやすいですか?ってアフタートーク
で聞けばよかった~。素朴な疑問すぎてとても聞けなかった。)
安珍は袈裟懸けを脱ぎ、赤い着物風の衣装だけになった。
由良部さんの手はつねにふわふわ、ひらひら動き、それは土方巽
の重力のある言葉にあえて逆らっているようにさえ見える。
ソフトだけれどその動きは明らかに挑発的だ。
花道代わりの中央通路までゆっくり歩み出て、観客の視線を集め
舞いながらまた舞台にもどる。白塗りの裸足のアシが艶かしい。
目の前にあるのは由部さんの所有物ではなく、客観的なうつわ。
そこに何かが宿っているのだ。
人形でもない、歌舞伎舞踊でもない、浄瑠璃の舞踏。
レクチャーのおかげか演出のせいか、不思議な観劇だった。
※プロフィールを見てビックリ。由良部さんはもと東方夜總会
(白虎社)の人。私が観たのは独立後の「身体の裏側2」だ。
<日高川入相花王 渡し場の段>
浄瑠璃:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友、鶴澤清公
出演:桐竹勘十郎 ほか
舞台には床と、この日初めての舞台セットが。
エアー人形だけだと思っていたので、もう一度同じ演目が人形で
観られると知って感激♪ やっぱり文楽はええなあ~。
さっき人形なしで動きを見ていたので、見方が違ってくる。
エアーの時に勘十郎さんの左手が何かを投げたように見えたのは、
人形が髪を振り乱しザンバラになった瞬間。後ろから前へ首を振っ
た動きだったんだー。
左遣いさんは姫の衣装を着替えたり、仕掛けを触ったり、いろい
ろお仕事があるんだね。よ~くわかりました。
足遣いさんはトーゼンながら見えませ~~~ん。
エアーでは通路が川になったが、文楽の舞台では浅葱色の幕を使っ
てアッという間に川ができる。姫が蛇になったり戻ったりしながら
泳いでゆくところはやっぱり面白い。
最後に正統派の文楽で終わったせいか満足。心地よい達成感♪
<アフタートーク>
勘十郎さんは人形があるほうがずっとラク、人形なしのほうが汗を
かく、と言っておられた。数年前に人形なしで観たいと言われた時
はけったいなこと言うなあと思ったけれど、人形なしでやると3人
それぞれの関係性がよくわかっていい。自分も正面で観てみたい、
とのこと。
大野一雄、土方巽の言葉を引用して「形が先か、魂が先か」という
質問に答えて。
英大夫さんは、考えてやるものではなく、気がついたら言葉が出て
いるような状態じゃないとお客様には伝わらない、と。
勘十郎さんは若い頃はひたすら形を勉強していたけれど、今は性根
をどう入れるかについて考えている、と。
由良部さんはどちらも結局同じことである、と言われたと思う。主
体であり客体であるのが踊りの醍醐味、と。
清友さんは、決まったことを繰り返しやるだけ。そのつもりでやって
いたら、今日は(英大夫さんが)違うことをやったりする、と笑いを
とっておられた。
最後に。
こんな凄い催しを企画してくださった伴野久美子さんにあらためて
ありがとうございました!
●関連の観劇メモ
現代詩を浄瑠璃で語る 観劇メモ (2007/8/29)
「現代詩を語り、舞踏を舞い、キリスト劇を演じる」観劇メモ
(2007/12/25)
4月文楽公演「桂川連理柵」観劇メモ (2008/5/5)
●舞踏に関するおもな記事
山海塾「金柑少年2005」観劇メモ (2005/10/4)
神戸チキンジョージのアンダーグラウンドな夜 (2005/11/18)
Kazuo Ohno Festival 2005と大野一雄さんのDVD (2005/12/2)
精華演劇祭は19日まで (2006/3/9)
山海塾「時のなかの時ーとき」観劇メモ (2006/3/19)
山海塾「遥か彼方からのーひびき」観劇メモ (2006/5/26)
第6回朝日舞台芸術賞グランプリは山海塾 (2007/1/11)
「大野一雄フェスティバル2007」まもなく開催 (2007/10/4)
山海塾「降りてくるもののなかで ー とばり」(2011/3/6)
まず、舞踏に関するレクチャー。
続いて、文楽「日高川入相花王 渡し場の段」を人形なしで上演
し、それを舞踏手が引き継ぎ、舞踏のパフォーマンスを披露。
最後に人形を入れて「日高川~」をもう一度見せる。
文楽と舞踏のコラボが感覚的に楽しめる演出にワクワク。

第二部 舞踏の源流・文楽
<講演 土方巽と芸術家たち>
建畠 哲(詩人・京都市立芸術大学学長)
文楽ファンの人たちといっしょに「舞踏」の映像を見て、土方巽
の話を聞く。かなり奇妙な感覚だった。
その日に見る映像に関して男性(お名前わからず)の解説が入る。
最初の映像は1968年の「肉体の反乱」から若き土方巽のずいぶん
挑発的でエロティックな舞台。つづく1970年代の映像は「疱瘡譚」
から。病や肉体的弱者の体の動きに着目したパフォーマンスという
ことだった。(白塗り、肌の露出、局部の誇張、空中移動、等々が
あるかと思えば、躍動とは対局にある奇異な身体表現もある。私が
持っているDVDは1973年の「夏の嵐 燔犧大踏鑑」なので、それ以
外の舞台映像が見られたのがウレシかった。)
伝統芸能との関係でいえば、音楽に義太夫や津軽三味線を使用した
ことがあった、とのこと。
彼の最後のパフォーマンスに間に合ったという建畠哲さんによれば、
人類は「土方巽を見たか否か」の2種類に分かれるそうだ♪
当時の熱狂的な観客の目線や熱気が話の端々から伝わってくる。
土方は三島由紀夫、細江英公、横尾忠則、澁澤龍彦、高橋睦郎ら
ジャンルを越えた芸術家、文化人たちと交流があったという。
細江英公と土方巽のコラボ写真集『鎌鼬』(かまいたち)からの
写真も数枚紹介された。
1965年に横尾忠則がデザインした暗黒舞踏の公演「バラ色ダン
ス―A LA MAISON DE M. CIVECAWA」のポスターもあった。
(こちらで見られます )
それまでの横尾忠則の作風が一変するきっかけとなったポスター
だと聞く。二人の出会いによって生まれた時代の落とし子的作品。
CIVECAWAとは澁澤龍彦のことだそうで、公演の出演者の中には
大野一雄・大野慶人の名前も見られる。
建畠さんの高尚な解説を勝手に噛み砕いてメチャクチャ平たく言
うとこうなるだろうか?
文楽は<人形>に人間を憑依させることによって人間以上に生々
しい存在になる。一方、土方の舞踏はオブジェとしての体、不自
由な肉体を意識することより結果として生々しいものを表現して
みせた。文楽と舞踏、そこに通じるものがあるのではないか。
(舞踏はいわば、自分で自分の体を人形の体のように客観的に扱っ
た、ということだろうか? 間違っていたらすみません。。。)
「舞踏」の表現の根本にある理論を「文楽」と結びつけて説明し
てくださったおかげで今までわからなかったことが感覚的にわかっ
たような気がする。
<創作と新演出による「舞踏と文楽のコラボレーション」>
●日高川入相花王 渡し場の段(人形なし)
浄瑠璃:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友、鶴澤清公
出演:桐竹勘十郎 ほか
舞台上に床が置かれ、浄瑠璃と三味線による出語り。
やはり、手摺や書割等のないシンプルな舞台。
下手から3人の人形遣いが全員黒衣姿で登場してくる。
黒ずくめで人形を持たないので、黒い長袖の先の露出した肌色
だけが目立っている。
人形を脱いで露になった勘十郎さんの左手、裸の指にゴクリ♪
一瞬、なんだか見てはいけないものを見てしまった気がした。
(やっぱり秘密クラブかもしれない。)
が、すぐにSな気持ちが打ち勝って、そこから先はほとんど舐め
るように見ていたと思う。
あ、これか。これなのか。
見てはいけないものを見てしまったー!という感覚は、白虎社
(舞踏集団)を初めて観た時の衝撃と興奮に通じる。
ところが、そんなヘナチョコな思いはすぐに吹き飛んだ。
勘十郎さんはじめ3人の人形遣いによる本物の力というか、伝統
芸能の持つ圧倒的なエネルギーに打ち砕かれた。
勘十郎さんの左手は胴串を握った形をしている。親指が上方に
開いて、人差し指は細やかに滑らかに動き、握り方がゆるんだり
ギュッとなったり。あとの3本はピタリとくっつき人差し指と連
動して動く。
初めのうちは<指>だと思っていたのに、その手はいつのまに
か性別を帯び、感情を見せ、所作を知り、意志を持っていた。
ときおり艶かしいんである♪
それは恋に胸を焦がす若い女そのもの。激しい情念と強い意志
で思いを遂げようとする女が目の前にいるようだった。
左遣いの手は動きが静かな時と、忙しく動いている時がある。
いろいろと仕事があるのだと人形付きで見てわかった。
足遣いは下にいて中腰だったりしゃがんだり、両手をシャカ
シャカさかんに交差させたり。
面白いのはこの3人がくっついたまま動くということ。ある場面
では横長の舞台の隅っこに固まっていた。主遣いと左遣いの体の
間を足遣いがくぐり抜けた時は一連の群舞を見ているようだった。
人形がなくても、3人がある法則にしたがって1つの有機体とし
て動いていることに今さら感動する。
うん、三位一体だ。
3人が舞台から通路に出てきたときが大コーフン!
わわ、泳いでるやんっ♪ 川が見えるやん~。
------自分用メモ------
足遣いの動きを見て思い出したこと。
下からゲンコツが勢いよく飛び出し、手がそそり立つ時がある。
(女性がすわった時の足遣いの手だと、昨年9月の勘十郎さんの
講演で説明された記憶がある。)
2007年に観たNODA・MAPの「THE BEE」の舞台で報道陣がマ
イクを暴力的に突き出すシーンがこれにそっくりなんである。
調べたところでは、勘十郎さんが初めてエア人形に挑んだのは
おそらく2005年、大阪倶楽部での上演がはじまりのようだ。
その後、何度か披露の機会があったわけだし、野田さんはこの
エア人形をかなり早い時期に見たことあるんじゃないだろうか?
------------------------
「髪も逆立ち波頭抜き手を切って渡りしは怪しかりける」
エアー人形の上演が終わり、舞台上の姫の息づかいが聴こえてき
そうなタイミングで、下手から剃髪の男が静かに登場。
赤の着物に藍の袈裟懸け・・・え! 安珍?と思わず息をのんだ。
人形遣いがそっと下手に引っ込む。
●浄瑠璃で舞踏を舞う 「病める舞姫」より
作曲・演奏:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友
振付・出演:由良部正美
文楽の余韻が残っている。
由良部さんの舞踏は安珍イメージで引き継がれた。
「言っておきたいことがある。もっと大事なことがある。
ずるずるずるっとだまされる。みすみすわかってだまされる。」
土方巽の言葉はなんて挑発的なんだろう。
今回はじめてそう思った。
舞い手。語り。2007年に観たものと同じなのに感じ方が違う。
とても義太夫っぽい。演出が違うせいだろうか。
(舞踏に合わせて語り、演奏するのはどういう点が違いますか?
音楽と比べて浄瑠璃は舞いやすいですか?ってアフタートーク
で聞けばよかった~。素朴な疑問すぎてとても聞けなかった。)
安珍は袈裟懸けを脱ぎ、赤い着物風の衣装だけになった。
由良部さんの手はつねにふわふわ、ひらひら動き、それは土方巽
の重力のある言葉にあえて逆らっているようにさえ見える。
ソフトだけれどその動きは明らかに挑発的だ。
花道代わりの中央通路までゆっくり歩み出て、観客の視線を集め
舞いながらまた舞台にもどる。白塗りの裸足のアシが艶かしい。
目の前にあるのは由部さんの所有物ではなく、客観的なうつわ。
そこに何かが宿っているのだ。
人形でもない、歌舞伎舞踊でもない、浄瑠璃の舞踏。
レクチャーのおかげか演出のせいか、不思議な観劇だった。
※プロフィールを見てビックリ。由良部さんはもと東方夜總会
(白虎社)の人。私が観たのは独立後の「身体の裏側2」だ。
<日高川入相花王 渡し場の段>
浄瑠璃:豊竹英大夫 三味線:鶴澤清友、鶴澤清公
出演:桐竹勘十郎 ほか
舞台には床と、この日初めての舞台セットが。
エアー人形だけだと思っていたので、もう一度同じ演目が人形で
観られると知って感激♪ やっぱり文楽はええなあ~。
さっき人形なしで動きを見ていたので、見方が違ってくる。
エアーの時に勘十郎さんの左手が何かを投げたように見えたのは、
人形が髪を振り乱しザンバラになった瞬間。後ろから前へ首を振っ
た動きだったんだー。
左遣いさんは姫の衣装を着替えたり、仕掛けを触ったり、いろい
ろお仕事があるんだね。よ~くわかりました。
足遣いさんはトーゼンながら見えませ~~~ん。
エアーでは通路が川になったが、文楽の舞台では浅葱色の幕を使っ
てアッという間に川ができる。姫が蛇になったり戻ったりしながら
泳いでゆくところはやっぱり面白い。
最後に正統派の文楽で終わったせいか満足。心地よい達成感♪
<アフタートーク>
勘十郎さんは人形があるほうがずっとラク、人形なしのほうが汗を
かく、と言っておられた。数年前に人形なしで観たいと言われた時
はけったいなこと言うなあと思ったけれど、人形なしでやると3人
それぞれの関係性がよくわかっていい。自分も正面で観てみたい、
とのこと。
大野一雄、土方巽の言葉を引用して「形が先か、魂が先か」という
質問に答えて。
英大夫さんは、考えてやるものではなく、気がついたら言葉が出て
いるような状態じゃないとお客様には伝わらない、と。
勘十郎さんは若い頃はひたすら形を勉強していたけれど、今は性根
をどう入れるかについて考えている、と。
由良部さんはどちらも結局同じことである、と言われたと思う。主
体であり客体であるのが踊りの醍醐味、と。
清友さんは、決まったことを繰り返しやるだけ。そのつもりでやって
いたら、今日は(英大夫さんが)違うことをやったりする、と笑いを
とっておられた。
最後に。
こんな凄い催しを企画してくださった伴野久美子さんにあらためて
ありがとうございました!
●関連の観劇メモ
現代詩を浄瑠璃で語る 観劇メモ (2007/8/29)
「現代詩を語り、舞踏を舞い、キリスト劇を演じる」観劇メモ
(2007/12/25)
4月文楽公演「桂川連理柵」観劇メモ (2008/5/5)
●舞踏に関するおもな記事
山海塾「金柑少年2005」観劇メモ (2005/10/4)
神戸チキンジョージのアンダーグラウンドな夜 (2005/11/18)
Kazuo Ohno Festival 2005と大野一雄さんのDVD (2005/12/2)
精華演劇祭は19日まで (2006/3/9)
山海塾「時のなかの時ーとき」観劇メモ (2006/3/19)
山海塾「遥か彼方からのーひびき」観劇メモ (2006/5/26)
第6回朝日舞台芸術賞グランプリは山海塾 (2007/1/11)
「大野一雄フェスティバル2007」まもなく開催 (2007/10/4)
山海塾「降りてくるもののなかで ー とばり」(2011/3/6)














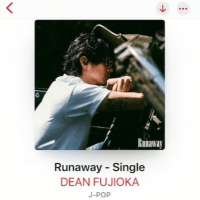
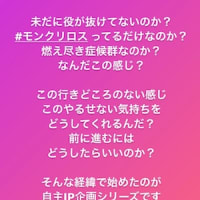
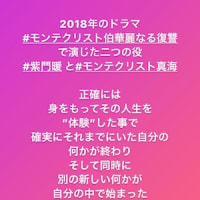


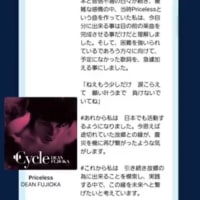












ツイッターではいつもお世話になってます、ぶんです。こちらは初めてかも…。
素晴らしいレポートありがとうございます!
今月、最も心の深くに響いた公演でしたが、舞踏は全く知らない世界だったのでうまく言葉で表せられなくて。。
まぁとにかくズドンとくる表現でした。
文楽も、人形遣いの動きだけで観ると不思議な色気がありますよねぇ。
伝統の積み重ね、人の身体の表現力に感動出来て、またその場にムンパリさまとご一緒させて頂き色々お話できて感謝でした!
また舞踏について教えて下さいませー
コチラにはたこやきパーティーの時に、ほら♪
いやー、ほんまに中身の濃い1日でしたね。
私も終日というのは初めてでした。
エアー人形は観られて本当によかったですねー。
で、文楽から逆に舞踏を知る機会でもあったのですね。
4月の文楽公演でもしお会いできたら土方巽のDVD
を持っていきますが・・・。
それから4月にお江戸で大駱駝艦の公演がありますわよ~。
http://www.dairakudakan.com/
http://www.dairakudakan.com/rakudakan/kochuten4/daiseikai.html
↓大駱駝艦の麿赤兒さんのインタビューです。
土方巽・唐十郎との出会いについても触れられてます。
http://interview.engekilife.com/05/
↓大駱駝艦と舞踏のことがわかるインタビュー。
http://www.performingarts.jp/J/art_interview/0506/1.html