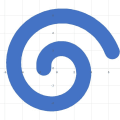2024年8月25日(日)、放送分。
興味ある人は、
NHKの聞き逃し配信から聞いてください。
多少省きましたが、メモ量は凄く多いです。
というか(メモというよりも)、ほとんど文字起こしかもしれませんが、
NHKさん目をつぶってください。
というか(でも思うに)、なぜラジオなんだろう?。
文章で公開してくれれば、凄く便利なのだが。
間違いあれば、
私の聞き間違いか、理解不足です。
また、" " 内は感想だったり私が追記したものです。
8.PTSDが考えさせること
・ストレス障害の原因となる深刻な体験をトラウマという。
・発端は、ベトナム戦争従軍兵から多く報告されたこと。
・4つの症状、
反復想起
トラウマを想起させることを回避する
刺激への反応が過敏になる
陰性な感情
・トラウマ体験後の一時的な場合はASD(急性ストレス障害)。
長期にわったり、時間が経ってから出てくるものがPTSD(心的外傷後ストレス障害)。
・適応障害は日常的なストレスによるもの、
PTSDは非日常のストレスによるもの。
・PTSDはいまに始まったものではなく、
大昔からあったことだろう、
例えば、太平洋戦争後には、
たくさんいたと思われる。
"『質屋』という映画がありましたね。"
"あと、ちょっと調べたら、
旧日本軍のPTSD患者の話が見つかりました。"
みんなが耐えているんだから、
自分も耐えなければならない、
という感じだったんだろう。
"それでも耐えられない人たちが、たくさんいたのでしょうか?。"
・↑PTSDという病気があるという認識がなければ、
病気とは見えない。
当然、治療しようと言うことにもならない。
PTSDという診断ができることで、
治療できるようになった。
・PTSDを考え出した国、人たちは、
米国である。
ベトナム戦争神経症などの名称で注目され検討された。
・戦場はベトナムだったのだから、
米国よりもベトナムの方がPTSDが多かったであろうに、
米国でPTSDが確立されたのは、
国が豊かで、復員兵のメンタルヘルスまで考える、余裕があったからであろう。
・エイブラハム・マズロー(米、20C)の、
欲求段階説。
1.生理的欲求、
2.安全の欲求、
3.社会的欲求、
4.承認欲求、
5.自己実現の欲求、
の5の階層に分けた。
低い段階の欲求が満たされると、
より上の欲求が起こるという説。
・PTSDは安全欲求よりも上の欲求を脅かすものだが、
まずは生理的欲求が満たされることが大事だ。
・衣食足りて礼節を知る、
恒産なくして恒心なし、
という言葉があるが、
おそらく同じ現実に注目したものだろう。
・健康と平和は切り離すことが出来ない。
(ウクライナやガザ地区などのことを引き合いに出した後)
・ヒステリーは、女性蔑視的な言葉として、現在では使われない。
・ヒステリーとPTSDは関わりが深い。
・解離症状や転換症状は、
ヒステリーや神経症、
PTSDはストレス障害として、
考えることが多かったが、
強いストレス体験が元となって起こるということは、
共通している。
・PTSDはベトナム戦争で作られた診断ではあるが、
昔は戦争神経症、
戦場神経症と言われていて、
第1次世界大戦のヨーロッパ戦線が最初であった。
・日本人にはなじみが薄いが、
世界に与えたインパクトは第2次世界大戦よりも大きかった。
"世界にとは、欧米に、でしょうか?。"
戦闘機、戦車、潜水艦、毒ガスなど最新兵器が登場した。
・戦場に慣れていないものが、
戦地に送られるので、
解離、失神、運動機能の障害などが、
多く発生し、
戦場ヒステリーという言葉も生まれた。
シェル(砲弾)ショックという言葉も生まれた。
・ヒステリーという言葉が、
女性特有であるという印象があり、
兵士にはそぐわないとして、
独仏共に、ヒステリーと診断することを避けていた。
また、
独仏とも、自軍にはヒステリーの発生はなく、
敵軍にはそれがあると牽制しあっていた。
・スペイン風邪(インフルエンザ)、
第1次世界戦末期の1918-1920年。
世界で5億人が罹患し、
日本でも38万人が死んだ。
死者の数では新型コロナを上回っていた。
参戦国は自国の被害を、
隠蔽したため、
実情が良くわからなかった。
スペインは参戦していなかったので、
隠蔽せずに公表したので、
スペインの被害報告が突出した。
スペイン風邪の最初の患者は米国で、
最も死者が多かったのはインドである。
・平時でもヒステリーは女性特有と思われており、
男性でも同様の症状があっても認識が遅れたり、
診断された人は蔑視されたりした。
・PTSDはこうした歪な状況を、
変化させるきっかけとなった。
・DSMでは、
PTSDの診断基準では、
トラウマ体験の反復想起の一つの形として、
解離があげられている。
トラウマ体験の現場に、
戻ったかのように行動してしまう。
・災害精神医学の専門家曰く、
震災などの大規模災害の被災者では、
典型的なストレス障害だけでなく、
転換性障害、解離性障害、うつ病、心身症などが、
混ざって現れる。
・子供の場合、
反復想起が、
遊びや描画で表現されるともいわれる。
・複雑性PTSD。
繰り返されたトラウマ体験、
父親の母親に対する暴力が、繰り返されるのを、子供が見て育ったり、
子供自体に対する暴言や虐待が繰り返されるなど、
により、
PTSDと類似した症状が出る。
・戦争体験とDVとの関連。
戦争に行った後、以前とは違い暴力的になり、
飲酒して暴力的になる例が、極めて多く報告されている。
というレポートがある。
日本でも太平洋戦争後にあったのではないのか?という指摘がある。
"webで調べるに、あるらしい。"
・DVの背景に戦争トラウマ体験があったならば、
DV対策とトラウマ治療の双方にとって、
有益なヒントを与えるのではないのか。
・PTSDは辛い記憶を反復想起させて、
その人の人柄までも変えてしまうと言うことは、
記憶が人の精神生活に、
重要な役割を果たしているということを示唆している。
・ルソー、エミールに、
同一性(アイデンティティ)は記憶によって保たれる。
と書いた。
・毎日の記憶が同一性の裏付けとなる。
トラウマ記憶が侵入し、同一性のあり方まで損なうのが、
PTSDの恐ろしさ。
・PTSDの治療法、
対処療法、抗不安薬、抗うつ薬の薬物療法。
トラウマ体験へのとらわれをなくすような精神療法も行われる。
トラウマ体験は過去の物であって、
現在の自分を損なうものではないということを確認してゆく。
症状が出る刺激に、少しづつ慣らしてゆく。
持続エクスポージャ療法。
辛い体験を心の底に埋めて、
時間と共に忘れてゆくことを、
支えることも良い場合もあるだろう。
・PTSDは辛いものだが、
人間にはトラウマ体験を克服して生きてゆく、
たくましさとしなやかさが備わっている。
・↑なぜそう言えるのか。
第2次世界大戦で日本は300万人が死に、
都市も破壊され、日本にいる人は、
巨大なトラウマ体験に飲まれていたはず。
しかし、人はそれぞれの人生を築き、
日本社会の復興をした。
日本よりも被害の大きかったドイツでも、
日本やドイツの被害者の国や人達でも、
世界のどこでも、戦争の惨禍から立ち直っている。
"第4回の放送では、精神疾患は、
遺伝と環境の両方だという話があったと思う。
多くの人は生理的欲求を満たすことで手一杯で、それ以上考えられなかったり、
周辺の人が見な同じで、仲間だったからとか、
あるのかもしれないと思った。
そして、弱い人はやっぱりPTSDになっていたのかもしれない、
とも思った。"
・人間は深刻なトラウマから、
立ち直れるのはなぜなのか?。
安心できる環境と、
支えてくれる人、見守ってくれる人の存在が重要。
・人と人とが支え合うとき、
驚くような、粘り強さとしなやかさを発揮するのではないのか。
そして、多くの人が時間が経つにつれPTSDから、
脱却したのではないのか。
"いや、でもその『時間』が人生の10%以上かも。
結構な時間だと思いますよ。"
・人間はトラウマを克服できるが、
だからと言ってそれを生み出す、
構造的な問題を放置してよいわけではない。
・予防に勝る治療無し、
はPTSDにも当てはまる。
自然災害によるストレス障害は、
予防しきれないかもしれないが、
せめて人為的なストレス障害を予防することを、
社会の目標として実践する必要がある。
"自然災害に対しては、
地震と洪水だったら、
社会が裕福ならば生き延びられる気がする。"
"問題は、火山の大規模噴火とか、
巨大隕石とかでしょうか。
大規模噴火は、いずれ必ず起きるので、
未来の人たちに丸投げでしょうか?。
それまで、無事でいられれば良いのですが。
巨大隕石は、運でしょうかね?。
ヨーロッパとアメリカは、
すでに隕石の軌道を変える実験とかやってたと思いますが、
やっぱり、金の力ですかね。
あと科学と技術力かな。"
"あと、未然の危機を感じ取る感性かも。"
・人の命と人間性を奪う、
巨大悪である戦争を抑止することは、
健康を維持増進する立場からも重要なテーマである。