
日本で公開されるアジア映画が韓国作品ばかりの中、やっとイラン映画が見られた。30年近くも前に制作された作品だが、今観ても全く古びていない。邦題は平凡だが、英題の“THE RUNNER”からつけたのだろうか。以下はチラシにあるストーリー。
―舞台は70年代初頭のイラン。ペルシャ湾沿岸の小さな港町。少年アミルは廃船にたった一人で暮らし、外国籍の船員が海に捨てた瓶を拾い集めたり、水兵の靴磨きや水売りなどをして何とか生計を立てている。アミルには好きなものが沢山ある。大きな白い船、飛行機、チャップリン、友だち、そして走ること。
ある日、アミルは自分が学校に行っていていい年齢なのに、読み書きができないことに気付き、猛然と字を覚え始まる…
いかにイランでも、11歳の少年がたった一人で暮らせるのか?とツッコミたくなるが、それが映画の世界だろう。この作品のコピーのひとつ、「生きる輝きがほとばしる!」どおり、アミル少年の笑顔は本当に輝いていた。子供の可愛さ目当てに見た観客もいただろうし、私の行った映画館ではやはりおばさん世代が多かった。
外国籍の船員が海に捨てた瓶を拾い集めるのはアミルだけでなく、他にも多くの少年たちが港で待ち構えている。瓶12本で27トマンという台詞があったが、現代の日本円にしてどれくらいなのだろう?イラン通貨は1トマン=10リアルのはずだが変動が激しく、まして70年代初頭と今では日本も物価基準が違っている。
外国船員の国籍は明らかにされてなかったが、欧米が主だろうか?飲料水の瓶を簡単に海に捨てるのは呆れたが、今ならペットボトルになっているのではないか。エコが叫ばれる21世紀、70年代よりも船員の意識改善が進んでいるのを願いたい。
アミルは水1杯を1リアルで売っている。氷を溶かした水をコップに入れただけだが、暑い季節には堪らないはず。水を求める大人にはズルい者もいて、食い逃げならぬ飲み逃げした男もいた。自転車で去る飲み逃げ男を必死に追いかけ、ついに追いつくアミル。根負けした男は1リアルを払う。まさに走る少年の粘り勝ち。
大きな白い船や飛行場から離着陸する飛行機にアミルが手を振って、追いかけるシーンは微笑ましい。友人の話でも幼稚園児の息子は乗り物に興味をもったそうで、少年が飛行機や船に関心を持つのはイランも同じらしい。対照的に乗り物に関心を示す少女は稀だし、男と女は子供の頃から興味の対象がこれほど違うのか。
好奇心の強いアミルは字が読めなくとも雑誌を買っている。雑誌上の写真を見るのが好きで、気に入った写真は切り取って住んでいる廃船内に貼っている。イランの雑誌は平均5リアルに対し、外国のそれは20~30リアルと値が張るとか。
この映画のクライマックスは天然ガスの炎が燃え盛る中、ドラム缶の上に置かれた氷の塊を取りに行く「火の競走」。少年たちは氷の塊を目指しひたすら走り続ける。大画面で見ると、炎を背景に走る少年たちの映像は迫力があった。この作品はナデリ監督の自伝的映画だそうで、インタビューサイトで監督は「火の競走」を次のように説明している。
―これは、黒澤明監督の『七人の侍』の雨中の決戦シーンをイメージしたものです。黒澤監督が「雨」を使ったのに対し、私は「炎」を使ったというわけです。
「火の競走」なので、つい私はルーツはゾロアスター教?と憶測してしまったが、どうも監督の創作のようだ。ペルシア湾岸の港町で逞しく生きる天涯孤独な少年の姿は、見る者を勇気づける。この映画が制作されたのはイラン・イラク戦争真っ最中だったため、本国でも「元気をもらった」と、とても喜んで見られたという。
蛇足だが、イランや国際社会で“ペルシア湾”と呼んでいる湾を、対岸のアラブ諸国では“アラビア湾”と呼称しており、国際名称をアラビア湾に変えるべきという主張を展開、イランと対立している(※ペルシア湾呼称問題)。これは日本海をめぐる呼称騒動から30年近く前から続いているそうだ。
よろしかったら、クリックお願いします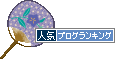
![]()



















