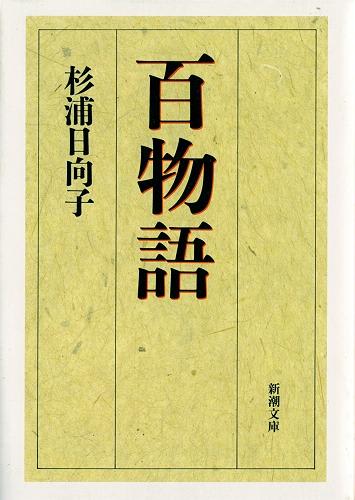
怪談のシーズンはとうに過ぎているが、今は亡き漫画家・杉浦日向子氏の『百物語』を読了した。題名こそ百物語だが、実際に収録されているのは99話なのだ。杉浦氏の絵や作品に描かれている江戸の風俗も素晴らしく、この怪談集も秀作だった。はじめに「古(いにしえ)より百物語と言う事の侍る不思議なる物語の百話集う処、必ずばけもの現れ出ずると」の一文があり、それ以後99話の怪談が続く。この『百物語』の中で、私が面白かった話を幾つか挙げたい。
先ず「其ノ二 障子の顔の話」。語り部が子供の頃、夜中に目を覚ますと土間に続く障子に、必ず小さな顔のようなものが浮かび上がっている。それは子供の拳ほどの大きさで、マス目はいつも決まっていた。朝になると跡形もなくなるが、年の瀬に紙を貼りかえても又同じように現れる。そうして何年も過ぎていき、ぞっとするほどのことは何もない。
ある夜、語り部はふと戯れに顔の上を墨でなぞった。翌日、そのマス目は切り取られ、何故だろうか、その日以来顔は消えてしまう。「その頃は何とも思わぬものの、今振り返ってみると不思議な気がする」と、語り部は述べている。
目目連のように無数の目がある化け物なら怖いが、顔は決まったマス目に現れ、しかもひとつだけ。顔もこけしの様で怖くはないが、障子に顔が現れるのはやはり不気味だ。もちろん我が家の障子にはそんな現象はなかったし、私も障子に浮かぶ顔を見たことがない。ただ、顔の浮かぶ障子があれば私も見たかった。
「其ノ十六 影を見た男の話」は奥州の話となっている。ある家の主人、外から帰ってみれば、彼の書院の文机に寄りかかっている人がいた。自分の留守中、かくも馴れ馴れしく振る舞うのは誰だろう、妻は母は客のあることを知っているのだろうかと怪しんで見ていると、着物や帯は自分が常に来ているものであった。更に髷の形、手指の様子、そのしぐさ…。己の後姿を見たことはないが、寸分違わぬように思われた。
主が顔を見ようと歩み寄ると、向こうを向いたまま一寸ばかりの障子の隙間から、その人は吸い込まれるように外に出てしまった。追って障子を開けたが、影も形も失せている。
主はそのことを妻に話すと、側で聞いていた母は何も言わずうちしおれている。そして主はその年の内に死んだ。これまで三代、父も祖父も死ぬ前に己の姿を見ていたのだ。母や家来は知っていたが、あまり不吉なことなので主には話していなかった。
西洋の怪談ならドッペルゲンガー現象とでも呼ばれるだろう。試にこの言葉をwikiで調べたら、何と江戸時代の北勇治という人物のドッペルゲンガーの話が載っており、杉浦氏が『百物語』でこれを取り上げていたとある。氏の創作ではなかったのだ。医学において自分の姿を見る現象は、「自己像幻視」と呼ばれるそうだ。
「其ノ三十 盆の話」は盆に亡き母が帰ってくる話である。迎え火を焚き、死んだ母が来るのを待っていた娘。その夜かすかな泣き声で目が覚めた娘は、声のした方に行って見ると母の顔をしたネズミがいた。つまり母は前世の行いが悪かったため、ネズミに転生したのだ。それを見て、「情けなや、おっかさん。おとっつぁんに恥ずかしくないのか、娘がいとしくはないのか」と責める娘。申し訳なさそうにネズミになった母は姿を消す。
翌日、隣人が母の好物だった「ずんだ餅」をお供えとして持ってくる。娘は餅を供えようともせず貪るように食べ、幼い妹にも食べるように勧めた。仏様の罰が当たると尻込みする妹に、「罰が当たるなら、姉ちゃんはきっと猫に生まれかわるよ」と言う娘だった。
輪廻転生など現代の日本人の大半は信じていないだろうが、江戸時代はそうではなかった。行いの悪い者は来世畜生道に落ちると本気で信じる人も多かったはず。そんな時代、母がネズミに生まれ変わったと知れば、子供が衝撃を受けるのは当たり前なのだ。盆で母が来るのを心待ちにしていたなら尚のこと。物悲しい話かもしれないが、ネズミよりも悲惨な生き方を強いられる人間は21世紀でも少なくない。迫害や貧困に打ちひしがれる不幸な人間よりも、野ネズミの方が自由に生きられ幸福ではないのか。
その二に続く
よろしかったら、クリックお願いします
![]()
![]()




















同じホラー漫画でも、杉浦氏のは好感がもてます。楳図かずおのようなのもおどろどろしくて面白いのですけどね。
貴方も杉浦氏の『百物語』を読まれていましたか。ネズミの母の話には「ずんだ餅」が出てくるので、東北人の私には妙に印象深かったです。wikiで見たら、宮城県や山形県だけの郷土食ではなかったことを知りました。
実は楳図かずおのホラー漫画も好きでしたね。子供の頃に気に入って見ていました。確かにおどろおどろしい話が多いですが、怪奇現象よりも人間の心理の複雑さの方が怖かった。楳図かずおの『恐怖』、以前記事にしています。
http://blog.goo.ne.jp/mugi411/e/26465c3e340d0fe84e0dc628e893a300