『妖怪の日本地図』(志村有広監修、青春新書)を先日読んだ。怪談は夏に付きもの、この時期になると妙にこの種の話が聞きたくなる。行き付けの図書館で、たまたま背表紙のタイトルが目に入り、つい借りてしまった。
私の本棚には水木しげるの『妖怪画談』『続 妖怪画談』『幽霊画談』(全て岩波新書)があり、元から妖怪話が好きなのだ。巻末の資料文献でも水木の著書が何点か載っている。
新書は序章にくわえ全6章構成となっている。相模女子大の大学教授を勤めた経歴を持つ怪奇文学研究者に相応しく、日本各地の妖怪の紹介や妖怪の歴史背景が描かれている。裏表紙では妖怪をこう解析していた。
―人々に恐怖を与え、さらには災厄をもたらす霊的存在もしくは怪異現象の総称。妖異、妖物、魔物、化け物などをさす。平安時代から、「物の怪」としての言及が見られ、民俗学者の柳田國男は、「零落した神」と捉えている。
妖怪は、基本的には邪悪な存在であるが、時と場合によっては、人間にとって好ましい行動をすることもある。何度、便所、門、神社、寺、村境など、境界をなす場所に現われることが多く、また「逢瀬が刻」と呼ばれた昼と夜の境の夕方と明け方に、この世界に出入りするとされている。
第1章「五大妖怪伝説!」で、鬼、河童、天狗、九尾の狐と共に大蛇が挙げられていた。蛇伝説の中でも最たるものは三輪山伝説というのは興味深い。「天皇家の信仰が深い三輪山の神が蛇体だったというのは、人々の蛇に対する思いが現れているといえよう」(40頁)、とある。
古代人が蛇に恐怖と神秘性を抱いていたのは無理もないが、金運に恵まれるよう蛇の皮を財布に入れたりする現代日本人も昔の人を笑えない。
九尾の狐の背景には、平安後期の宮廷において、天皇をも巻き込んで繰り広げられていた藤原氏の間の権力闘争があったようだ。「狐、政争の史実、陰陽道。これらが絡み合い、日本を揺るがせた妖怪の伝説を生み出したのである」(37頁)という解析には納得。九尾の狐の前世がインドや中国の悪女だったというのも、当時の日本人の世界観があった。
中世文学にも様々な妖怪は登場していたが、妖怪文学が確立したのは江戸時代という。妖怪絵画が発展したのも江戸時代。鳥山石燕は『画図百鬼夜行』で、それまでのおどろおどろしい妖怪と違い、親しみ易く人間的な表情をもつ愛嬌ある姿を描き、妖怪絵画の金字塔を打ち立てた。
怪談話や妖怪画と共に、妖怪を身近にしたのが妖怪演劇。妖怪演劇は室町時代に能の題材に登場していたが、江戸時代に歌舞伎で幽霊譚が演じられ、これが庶民の人気を集める。四谷怪談は現代でもドラマ化されているほど。
こうして妖怪は大衆の身近な娯楽となる一方、妖怪への恐怖、畏敬の念は薄れていく。現代では様々な漫画家や小説家が活躍して怪談を生み出している。新書では現代の妖怪ブームの火付け役となった人物に水木しげるを挙げており、これに異論ないはず。
本にある日本各地の妖怪では、やはり地元のそれが気になる。18~19頁の日本の妖怪地図を見ると、やはり京都の数はダントツだった。宮城県は1種だけで、仙台の「否哉(いやや)」がそう。仙台っ子の私だが、「否哉」など初耳だ。
「若い女性の姿をしていて、実は顔はいやらしい男。男性が声をかけると振り返り、その顔を見せて驚かせる」(173頁)と解説されているが、wikiにも載っていた。「いやや」と聞いて、主に特赦詐欺による消費者相談ホットライン188(いやや)を思い出してしまった。
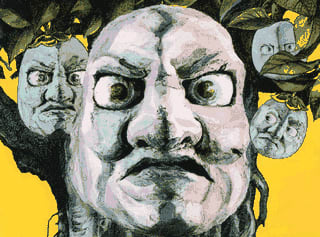
前にも水木しげるの『妖怪画談』で、地元の妖怪の名を初めて知ったことがある。「たんころりん」で、上の画像は『妖怪画談』から。「老いた柿の木が化けた妖怪で、柿の実を採らずに放置しておくと現れるという」(wiki)。
ならば、昨今は柿の実を採らずに放置しておく家が多いので、「たんころりん」が県内各地で出没するはず。しかし、“柿男”が現れたという話はまるで聞かない。
アマゾンには、「題名と著者の経験・知識から、もっと掘り下げたものを期待していただけに、中途半端感は拭えません」という辛口のレビューが一件のみだが、私的には満足させられた。新書の制限される頁数もあり、深く掘り下げる記述は難しいだろう。
◆関連記事:「二口女-民話に見る貧しさ」
「こんにゃく幽霊―食い物の恨み」
「日本の妖怪、外国の妖怪の違い」





















-------☆☆☆-------
映画『エクソシスト(ウイリアム・ピーター・ブラッティ原作)』で主人公に憑依して一家を苦しめる『悪魔パズズ』は本来はメソポタミアの『風の魔王』であり『蝗害の具神化』であるともいわている。
-------☆☆☆-------
本来はキリスト教伝播以前の異教の神であったものが、キリスト教の布教によって本来の神の地位から滑り落ち『悪魔』とされてしまったものは多数ある。
-------☆☆☆-------
有名なゴールディングの小説『蠅の王』------この本はオモシロイです。アンチ『十五少年漂流記』で、人間の心の闇を見せつけてくれます------の題名にもなった『悪魔ベルゼブブ』はペリシテ人の神『バアル・ゼブル(気高き王)』を蔑んで『バアル・ゼブブ(蠅の王)』と呼んだのが始まりとされている。
-------☆☆☆-------
三輪山のご神体が蛇であることを私が最初に知ったのは、諸星大二郎の『暗黒神話』を読んでのことだった。この漫画には三輪山のご神体『オオナムチ(大国主命?)』が実に爬虫類的に描かれている。タケミナカタの描写に至っては(タケミカズチに両腕を引きちぎられたため)全くの蛇である。
-------☆☆☆-------
勢力ある新しい神の支配によって旧世界の神々はクトゥルーの邪神のように恐ろしい姿に変貌してしまうのです。
-------☆☆☆-------
旧支配者のキャロル
https://www.youtube.com/watch?v=uMSRLCjbSh4
-------☆☆☆-------
こうした悪魔たちも後世名前やら特徴が整理され、果てはその肖像が描かれるようになると、恐ろしさは半減してしまう(何だか酒の相手に丁度良さそうである)。この辺りの変貌具合も日本の妖怪と似ているようです。
Wikipedia によると、九尾の狐についてはちょっと違うようですね。
中国の悪女(妲己)と同一視したのは中国で(『封神演義』が有名)それが伝わって、玉藻前も九尾の狐になったようです。
九尾の狐は現代でも大人気で「NARUTO」「ぬらりひょんの孫」などの漫画やポケモン(キュウコン)などに現れます。
個人的には、漫画の「うしおととら」を押します。
西洋の妖精も、かつては神や精霊でしたね。それがキリスト教化に伴い、妖精になってしまいました。映画『エクソシスト』の冒頭に『悪魔パズズ』の像は、いかにも悪魔そのものでした。元から悪霊で魔神だったにせよ。
『蠅の王』!懐かしいですね~~ 人間の心の闇を最も見せつけたのが聖歌隊の少年というのが何とも……『蠅の王』の正体も悪魔どころか、兵士の腐乱遺体。漂流少年たちを救出したのも軍艦というオチも皮肉でした。
諸星大二郎の『暗黒神話』は知りませんでした。かなり濃いストーリーのようですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E9%BB%92%E7%A5%9E%E8%A9%B1
『旧支配者のキャロル』という曲も初耳ですが、検索したらクトゥルフ神話のパロディー楽曲でしたか。ラヴクラフトのクトゥルフも傑作でした。今でもラヴクラフトは根強い人気があります。
インドの悪女とはマガタ国王子の妃・華陽夫人のことですが、名前からして中国風。九尾の狐と同一視したのも中国だった??仏教との繋がりで、九尾の狐伝説が時代と共に重ねられていったと思います。
最近のアニメや漫画は見ていないので知りませんでしたが、「NARUTO」やポケモンにも九尾の狐が登場していたとはスゴイですね。聊斎志異にはよく狐が登場しており、九尾の狐の物語は朝鮮やベトナムでも人気があるようです。