
岸辺から何度となく見ていた漁法がある。
舳先に網を付けた漁船が疾走して、網を水面に差し入れる。
水面に浮いているアユをとるというが、いったいどんな風にアユを見つけ、そして捕まえるのだろう。一度、間近に見たいと思っていた。
取材ではアユの多様な生態に呼応する漁法、をテーマとして選んでいる。川に遡上することなく生活する琵琶湖のアユ。そのアユを漁獲する網漁だ。
船の上に立てられた櫓の上。湖面は静かならご機嫌な高見の席だが、琵琶湖も時化れば恐怖感があるという。
そこから、湖面を見てアユの群れを探す。そして、ダッシュ。ゴムを押し出す力ですくい網を投入してアユを捕らえる。

かなりの速度。20ノットくらいで急に減速するから、両手放しての撮影はさすがに出来なかった。
勇壮な淡海(あま)駆ける舟人の漁だ。
漁船の全景

舳先に網を付けた漁船が疾走して、網を水面に差し入れる。
水面に浮いているアユをとるというが、いったいどんな風にアユを見つけ、そして捕まえるのだろう。一度、間近に見たいと思っていた。
取材ではアユの多様な生態に呼応する漁法、をテーマとして選んでいる。川に遡上することなく生活する琵琶湖のアユ。そのアユを漁獲する網漁だ。
船の上に立てられた櫓の上。湖面は静かならご機嫌な高見の席だが、琵琶湖も時化れば恐怖感があるという。
そこから、湖面を見てアユの群れを探す。そして、ダッシュ。ゴムを押し出す力ですくい網を投入してアユを捕らえる。

かなりの速度。20ノットくらいで急に減速するから、両手放しての撮影はさすがに出来なかった。
勇壮な淡海(あま)駆ける舟人の漁だ。
漁船の全景












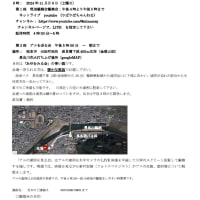














「環境漁協宣言 矢作川漁協100年史」 矢作川漁協100年史編集委員会 風倍社
上記の書籍に、1978年「月刊矢作川」滋賀県淡水養殖漁業組合監事(当時)寺田利美氏へのインタビューから、以下のような記述があります。
***以下一部引用***
~1975年、滋賀県漁業調整規則が改正され、体重0.5gのヒウオの漁獲が可能となる。網エリの目の制限が従来の6cmから0.9cmに緩和される。ガシャコンと呼ばれる沖すくい漁が始まる~
***以上一部引用***
琵琶湖では1960年代くらいまで、湖中で獲れたアユは食用とし、河川で獲れたアユは砂を喰っているので放流用にまわすという協定があったそうです。湖中のアユを生きたまま採捕する技術の発達や、河川を溯上するアユの減少によって1975年に調整規則が改正され今のような漁が可能となったようです。
湖中で獲れたアユは仕立てアユの元種苗として出荷されていたようです。同じく、1978年「月刊矢作川」滋賀県淡水養殖漁業組合監事(当時)寺田利美氏へのインタビューから、以下のような引用が上記の書籍にあります。
***以下一部引用***
~10年ほど前までの放流用の小アユは、河川で捕れたものと湖中で捕れたものが半々だったが、現在は最盛期の七割までもが湖中で捕れたものだという~
***以上一部引用***
この映像の漁船は堅田漁協の方のモノです。ボクが同乗しているのは中主漁協のMさんの船。
乗せてくれる船を探していて、MASAさんが読んだ本の著者、守山漁協の戸田さんが沖すくいをやってるというので、頼んでみました。でも今年はやっていないというので、紹介して貰ったのがMさんの船。
戸田さんとは琵琶博の外来生物展からのお付き合いですが、ボクのことを「怪しい、にせ漁師」と人に紹介したりしております。