この記事に書かれている内容について、「水田総合研究」の事例紹介者として琵琶湖博物館で講演したとき聞いていたのだけど、ネタバレなので紹介しないでいた。今回新聞発表となったので、ご紹介!
京都新聞 滋賀版 2006年7月19日
テクスト版
水田の魚、メタン発生を抑制
琵琶湖博物館が確認 富栄養化も防ぐ
水田で育つ魚が、地球温暖化の一因とされる温室効果ガスのメタンの発生を抑制し、琵琶湖の富栄養化も防ぐ働きをしていることが、滋賀県立琵琶湖博物館(草津市)の研究で分かった。魚がメタンガスの発生要因となるプランクトンなどを食べるためで、同館は「魚を育てる『ゆりかご水田』は、環境に優しい農業技術といえる」としている。2004年度から県がニゴロブナを放流したり、琵琶湖から遡上(そじょう)できる魚道を取り付けた、長浜市の「ゆりかご水田」で調査した。
昨年春、田起こし前の土壌を調べた結果、ゆりかご水田では、酸素を多く含む酸化層の厚さは25センチで、魚を入れなかった田(10センチ)の2倍以上あることが分かった。酸化層には富栄養化につながるリンが多量に蓄積されていた。
また、土壌の成分分析で、ガスの発生につながるメタン発酵が起きていないことも確認した。
同館の中島経夫上席総括学芸員によると、一般的に田に水を張ると、プランクトンやバクテリアの働きで酸素が減少し、酸素を嫌うメタン菌の活動が活発になって、メタン発酵が起きる。この時、土壌中の酸素も減り酸化層が薄くなって、封じ込められていたリンが水に溶け出すという。
しかし、ゆりかご水田では、魚がプランクトンを食べたり、土壌をかくはんするため、「酸素の減少が抑えられ、メタン発酵は進まず、余分なリンも流れ出ない」(中島学芸員)とみている。
地球のメタンガスの全排出量の4分の一に当たる年間700万トンが、水田から出ているという試算もあり、水田耕作が地球温暖化の一因とする研究者もいるという。
同館は今後、実際のメタン発生量などを調査する予定で、中島学芸員は「水田の生態系の中で、魚が果たしている役割を探りたい」としている。
京都新聞 滋賀版 2006年7月19日
テクスト版
水田の魚、メタン発生を抑制
琵琶湖博物館が確認 富栄養化も防ぐ
水田で育つ魚が、地球温暖化の一因とされる温室効果ガスのメタンの発生を抑制し、琵琶湖の富栄養化も防ぐ働きをしていることが、滋賀県立琵琶湖博物館(草津市)の研究で分かった。魚がメタンガスの発生要因となるプランクトンなどを食べるためで、同館は「魚を育てる『ゆりかご水田』は、環境に優しい農業技術といえる」としている。2004年度から県がニゴロブナを放流したり、琵琶湖から遡上(そじょう)できる魚道を取り付けた、長浜市の「ゆりかご水田」で調査した。
昨年春、田起こし前の土壌を調べた結果、ゆりかご水田では、酸素を多く含む酸化層の厚さは25センチで、魚を入れなかった田(10センチ)の2倍以上あることが分かった。酸化層には富栄養化につながるリンが多量に蓄積されていた。
また、土壌の成分分析で、ガスの発生につながるメタン発酵が起きていないことも確認した。
同館の中島経夫上席総括学芸員によると、一般的に田に水を張ると、プランクトンやバクテリアの働きで酸素が減少し、酸素を嫌うメタン菌の活動が活発になって、メタン発酵が起きる。この時、土壌中の酸素も減り酸化層が薄くなって、封じ込められていたリンが水に溶け出すという。
しかし、ゆりかご水田では、魚がプランクトンを食べたり、土壌をかくはんするため、「酸素の減少が抑えられ、メタン発酵は進まず、余分なリンも流れ出ない」(中島学芸員)とみている。
地球のメタンガスの全排出量の4分の一に当たる年間700万トンが、水田から出ているという試算もあり、水田耕作が地球温暖化の一因とする研究者もいるという。
同館は今後、実際のメタン発生量などを調査する予定で、中島学芸員は「水田の生態系の中で、魚が果たしている役割を探りたい」としている。











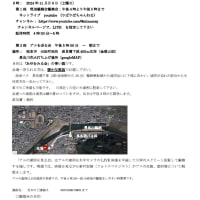














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます