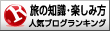写真①↑製糸場全体図(案内パンフレット)。
群馬県に旅行してきました、と言えばどこを思い浮かべますか?人口が最も多い約37万人の高崎市や県庁所在地の人口約33万人の前橋市、あるいは草津温泉や伊香保温泉や水上温泉、榛名山や赤城山や尾瀬、それとも保渡田縄文古墳群や群馬サファリパーク・・・。2024年(令和6年)6月14日に筆者は富岡市にある富岡製糸場(写真①↑製糸場全体図参照)を訪問してきました。

・写真②↑正面入り口。奥に見えるレンガ造りが国宝の東置繭所。
◇富岡製糸場の歴史
世界文化遺産「富岡製糸場」(正式には「富岡製糸場と絹産業遺産群」)は、2014年(平成26年)6月25日に、前年登録された富士山に次ぎ日本で18番目(現在全部で25か所)の世界遺産として登録されました。
西洋の製糸技術と機器を取り入れ、フランス人を指導者に招いて全国から10代の若い工女を募集し、日本初の本格的な機械製糸の工場として1872年(明治5年)に設立されました。世界最大級の規模で高品質の生糸が大量生産され輸出されて、その後の日本と世界の絹産業に大きく貢献したのです。そして115年の歴史を刻み、1987年(昭和62年)に操業を停止しました。その建物等は保存・改修され、現在世界遺産として観光することができます。

・写真③↑国宝の東置繭所。入口に総合案内所があり、中で展示パネルや映像ガイド等が見られます。

・写真④↑国宝の西置繭所。内部の半分は200人規模の多目的ホールとして講演会やコンサート、結婚式等に貸し出されています。

・写真⑤↑国宝の西置繭所の内側。壁や窓、天井のつくり等が見えます。
◇来場者数の推移
富岡製糸場が世界遺産に登録された2014年に133万人、翌年も114万人の観光客が訪れました。爆発的ブームが去り以降徐々に減少し、2019年(平成31年/令和元年)は44万人となりました。コロナ禍で年間来場者は10万人台まで落ち込みましたが、その後回復に転じて2022年(令和4年)は31万人を記録しています。筆者の訪問は平日午後でしたが、外国人観光客もほとんど見かけず、ゆったり見学して回れました。ブーム時はオーバーツーリズムで大混雑だったろう周辺の土産店や飲食店も空いていました。
なお、ご参考までに、現在富岡市の人口は4万5千人です。

・写真⑥↑敷地内にある高さ37.5mの煙突と蒸気窯所、鉄水留等です。
◇日本のものづくりの原点として
富岡製糸場を訪問して敷地内の建物や展示物、資料等から学び、ふと思い起こしました。明治政府が富国強兵・殖産興業・外交等の国策を推進し、日本は明治・大正・昭和を経て世界の工場となり、貿易立国として世界第二位の経済大国にまで成長した歴史です。今や少子高齢化と人口減少に直面している成熟した日本は、工場や販売拠点等の海外移転が進み、技術革新や新しい産業創出にも出遅れ、貿易黒字を稼げるものが自動車ぐらいしか無いと言われています。
そんな時代だからでしょうか、富岡製糸場にものづくりの原点を見たように思います。明治になって義務教育が始まりました。それを終えたばかりの少女たちが全国各地で募集され集まり集団生活をしながら、ひたむきに製糸工場で働きその後の日本の発展を底辺で支えたということです。そんなものづくりの歴史が、現在グローバルサウスと呼ばれる新興国の工場等で行われているのではないでしょうか。今は貧しくても、家族や自分のために働く場所とチャンスを国・政府や企業から与えられ、ひたむきに取り組む彼ら彼女らの誠意と努力が、未来に向け国を発展させる原動力だと感じます。
以上
◇おまけ
・写真⑦↓敷地内の旧社宅で飼われている蚕も見かけました。その大きさに驚きです(ビデオカメラと比較してみて)。