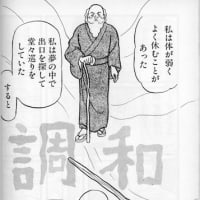コラム:世界の「脱ドル化」は誇張 今年も続く米債買い
https://jp.reuters.com/article/column-dollar-mcgeever-idJPKBN2WO06N
世界の各国がドルの保有を減らしているという説が大きな話題となっているが、実際の数字を見ると、中央銀行も民間セクターもドル建て債券の保有を増やし続けているのが実態だ。
各国中銀の外貨準備に占めるドルの割合は徐々に減ってはいるが、公的部門はドル建て資産を売るどころか、総合すれば買い越している。民間セクターも同様だ。
米連邦準備理事会(FRB)のエコノミスト、カルロ・バートート、ルース・ジュドソン両氏がまとめたデータ(バリュエーション調整後)によると、海外中銀と民間機関は今年1、2月に米国債を買い越した。
「脱ドル化とはドル買いが止まることだと考えているなら失望するだろう。
買う価格が下がるだけで、買いは続く」だろう。「ドル懐疑派の最右翼でさえ、ドル資産が壊滅的に売られるような事態は予想していない。実体を伴わない物事はまともに受け取れない」と語った。
国際通貨基金(IMF)のデータでは、世界の外貨準備に占めるドルの割合は昨年末時点で58.4%と、ユーロが誕生した1999年以来で最低だった。
ドルの卓越ぶりは色褪せていると言って差し支えないのかも知れないが、その変化は極めて段階的だろう。
IMF(国際通貨基金)が2021年5月6日に公表したレポートによると、2020年における世界の外貨準備高に占めるドルの比率は59%と、過去25年間で最低になりました。
アメリカの世界支配が崩壊に向かい、世界が多極化する事態を迎えています。
かって欧州の王族と貴族はシリング硬貨を作り通称「ドル」と呼ばれ、それを世界の通貨ドルとしましたが、やがてドルの権威は落ちて色褪せたことから、欧州諸国に統合を勧めてドル通貨に対抗出来るユーロ通貨を誕生させたことで、世界の通貨体制は多極化し始めたと言えます。
出版社トランス・アメリカ社(イスラエルに本拠)はかって、全米のマフィアを統一した〈金で殺人を請負う組織〉で、企業の形体を取ったフロント企業の金融部門ランベール銀行(ベルギーのイスラエル系)は、1999年にヨーロッパの共通通貨ユーロを創立しています。
現在は、スコットランド金融界の盟友、オランダ・ベルギー金融界の作った、ユーロ通貨が覇権を握りました。
1971年、金本位制を廃止したドルが世界の基軸通貨の地位を確立できたのは、石油貿易をドルで支配したからなのです。
2000年10月にイラク大統領サダム・フセインは、イラク原油の決済通貨をドルからユーロに切り替えると宣言した切っ掛け後から、為替市場でドルに対して10%以下であったユーロが上昇に転じたと思いきや、あっさりとドルを追い越してしまったのです。
それで、急所を突かれた米国は怒りと乱心して自ら9/11事件を捏ち上げて、アメリカ経済破綻の脅威(アキレス腱を狙った致命的一撃)となった、サダム・フセインを叩き潰して見せたのです。
今後は、大国ロシアや中国、EU、日本、統合された中東産油国の共通通貨、東アジアの共通通貨などが夫々に並び立つ、多極的な世界へと再編されて、アメリカは極の一つとして復活することになると言われています。

米ドルは基軸通貨であり続けられるか
ロシアによるウクライナ侵攻に伴う西側諸国による金融経済制裁は、国際通貨体制から発せられており中でもドルの使用の制限が、ドルの基軸通貨としての地位に影響するのではないかという議論を生んでいます。
ロシアのウクライナ侵攻は、米国が中央銀行の準備金を制裁する意思があることを示しました。
米国が<ドルを武器化>する用意があることを示した今、FRB(米連邦準備制度理事会)や欧米の銀行、その他の取引先が保有するドル準備は、政治的に没収されかねないということであるのです。
IMFのリポート「ドル支配のステルス(見えない)衰退」に記述された通り、この20年間で世界の外貨準備に占めるドルの比率は70%から60%へと緩やかに低下しています。
ロシアに対する制裁を受け、さらに低下が進む可能性があります。
米ドルは世界の基軸通貨の地位をこれからも維持するために、日本はアメリカの経済不況を救済する要望と圧力の必要性から、日銀は金融政策としてゼロ金利政策・量的緩和を継続していますから、ドル本位制は何とか持ち堪えて続いているとも言えます。
日本政府はこの様な、ミスリードの逆噴射とも言える政策を長年に渡り執って来たことから、金融・経済は「失われた30年」となり今も継続中で、欧米に大きく遅れを取り先進国でも低賃金のままで、韓国にも追い越される有様で経済は撃沈した侭となりました。
30年前に比べて、平均年収は少なくなった上に消費税は3%から10%に増税され、国民は四苦八苦し生活の質を落として堪え忍んでいる状況です。
それで、海外から出稼ぎで日本へ来る外国人は減少しました。
米国の経済力が低下していく中で「ブレトン・ウッズ体制」、または「金・ドル本位制」の問題点が徐々に表れています。
中国は経済力は大きいですが金融の力が弱く、自由に両替できない人民元をあえて取引に使おうとする国は少ない様です。
SWIFTを通じた国際決済シェアもドルが40%に上るのに対し、人民元は僅か3%以下に過ぎません。近い将来に人民元がドルの代わりになれるとは思えません。
かつて、前米大統領のトランプは、「私たちの通貨は暴落しており、間もなく世界標準ではなくなるだろう」と述べました。
一方では、BRICS諸国が「新通貨」を開発するなど、世界的な脱ドル志向が加速しているのが現状です。
ドルの大局は長期的な下落サイクルに入ったのかもしれません。それはドルの基軸通貨としての覇権が終わりに近づいてきていることを意味します。
1944年のブレトン・ウッズ会議以来、ドルは国家間の国際貿易収支の決済に使われる唯一の通貨でした。
一般的に、米国政府はこれまで債務不履行に陥ったことがないと、思われているようでありますが、これは真っ赤な嘘なのです。
米国政府は過去100年の間に2回、非公式ではあるものの債務不履行に陥っています。
一度目は、1933年4月に発せられた大統領令6102号です。
この大統領令は、米国民に対し保有する“有事の金”を全て差し出すように強制したもので、明らかに米国政府の債務不履行でありました。米国での金の所有は、わずかな制限を除いて、その後約40年間違法とされました。
大統領令6102号の下で、米国人は金1トロイオンスあたりを20.67ドルで没収されました。
政府が金を没収した直後、1934年の金準備法によって、金の価格は1トロイオンスあたり35ドルに引き上げられました。つまり、1トロイオンスあたり約15ドル、米国民は40%以上の富を収奪されたのでした。
今後、日本も膨大な赤字国債を解消する必要性から同様な事があるかも知れません。と言っても金は殆どの国民は所有してませんから、預貯金と有価証券が対象になりそうです。
それには先ず、個人資産(預貯金)を調べて把握する必要性からマイナンバーカードが必要になり、各自の金融口座と密かに紐づけ様と巧妙に誘導する為なのです。
しかし、庶民は低収入が続き思ったよりも預貯金額は少ないのかも知れません。
現在の相場はバブルというより、社会主義的な国家管理相場で、金融当局の自作自演の相場をみて、金融資本主義が続いているように錯覚しているのが今の市場であります。
成長のための資金を負債に依存していることを考えると、金利の上昇は本質的に破壊的であるのです。インフレは宴の終わりだと言えます。
それでも、ドルの基軸通貨としての地位はそう簡単には終わらないでしょう。
ドルの価値は金利を上げることで取り敢えずは、維持できます。
しかし、ペトロダラーの終わりの始まりから、ドルの長期的な運命はすでに決まっているのかもしれません。
ドル離れが顕著なのは、ロシアやトルコなど米国との対立が顕著な国であります。
ロシアはウクライナ問題を切っ掛けに米国から制裁を受けており、金融市場の混乱が続いています。
まだ大きな動きではないものの人民元の保有比率拡大は、一帯一路計画に象徴される中国の新興国支援が影響している可能性があります。
中国の最終的な狙いは、巧妙で狡猾な経済援助を通じて人民元の経済圏を確立することであり、ゆっくりとしたペースではありますが、中国の国際戦略もドルのシェア低下の一因となっています。
しかし、国際的な通貨としては信用が足りないため、一部の国を除いて人民元を大量保有するという選択肢はないでしょう。
現在では、人民元の最大の要因は金融資本取引では自由化されていないので、国際通貨という観点から見れば世界の基軸通貨になることは出来ていません。
一方、アルゼンチンのマサ経済相とか、マレーシアのアンワル首相とか、ブラジル政府などは中国との貿易に関して、ドル建て決済を停止して人民元建て決済を検討したり行うと発表しています。
中国は独自の取引決済システム(CIPS)を2015年に稼働させています。
その他、インドネシア、イラン、ロシアなど多くの国家が人民元を貿易決済通貨として、広く使用し始めているのが現状です。
CIPSを通じた貿易決済がこのまま膨らみ続けて、ドル一極体制が崩れ人民元がドルを脅かす存在となれば、それは結果として中国を中心とした新しい金融市場が大きく膨らむことを意味します。
これまで国際金融において大きな存在感を示し、巨額の利益を上げ続けてきた欧米金融機関にとって、収益基盤を奪われることを意味します。
それで、米国バイデン政権が対中強硬策を何かと企だてて、実行しようとしているとも言えます。
つまり、水面下で進む「人民元の国際化」が米中の利害対立を激化させているのです。
SWIFT(国際銀行間通信協会)によると、3月の世界の貿易決済における人民元のシェアは2.26%に過ぎません。ドルは41.74%、ユーロは32.64%、円は4.78%で、人民元は第5位となっています。