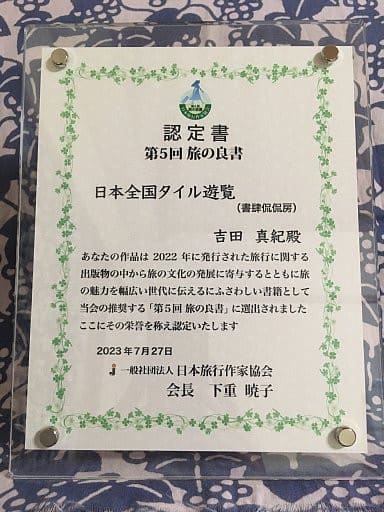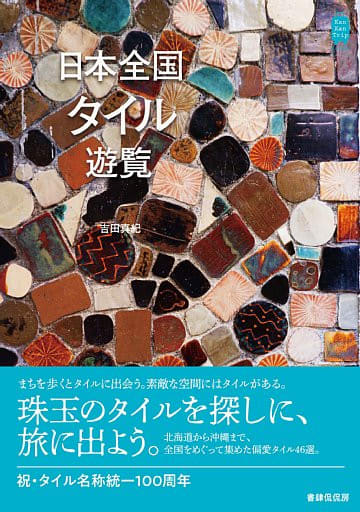嘉麻市、常盤館の続き。
この常盤館、素晴らしいのはお料理とお庭だけではない。二階にある部屋がすごいのだ!!
実はこの部屋の意匠を見ることが目的だった。友人がこの部屋をリクエストしてくれたのだが、
老朽化しているためここにはお客を泊めることはできないとのことで、見学させて頂いた。

魚の形をしたプレートに「ひこ」、いやいやこれは右から左に読むのだ。「こひ」=鯉の間である。
この形はあまり鯉っぽくないが・・・笑

中は一見何の変哲もない6畳間なのだが・・・

よく見ると、床柱に「鯉之間」という文字が浮き彫りされている。

そしてその下には、木目を水の流れに見立てた鯉の滝登り!木目も自然の」ものではなく完全に彫刻である。

床柱の足元は松かさのような意匠。

床脇っぽい部分の棚や床板もすべて彫刻されている。

床框は四方竹・・・と思いきや、これも木材を彫ったもの。竹の節も再現してあって、ぱっと見はだまされそう。

壁に直接固定された棚は花型というか雲形というか変わった形で、和歌のような文字が彫られている。

落とし掛けにも松の幹と松葉が彫ってあり、一部は着色されている。天井は網代模様の彫刻。

2段になった中央の床の間の床框は、これも皮つきの松を模しているのか?


天井は中央部がわずかに山型に傾斜がついた船底天井。そして窓際の半間分を区切る意匠的な垂れ壁がついており、
そこから天井の勾配が変化しているのは、茶室の掛け込み天井風のアレンジなのか??

その半間分の天井には、なんと将棋の駒が!?

窓のまぐさにも「ヒコ ヒコ ヒコ・・・」。


窓台にも鯉の姿が・・・どんだけ鯉が好きやねん!?笑
お客来い来いとか、滝登りで出世につながる縁起物として、また水とあわせて火事除けのまじないなど、
鯉は古い家によく見かけるモチーフだが、「コヒ」という文字まで装飾に使うとは、ここを建てたご当主が
相当変わり者だったのか、それとも任された職人が変わり者だったのか・・・笑

窓の外側についた欄干は波模様と網代。もちろんこれも木を彫ったもの。

2階には大広間もあって宴会もできる。こちらは特段風変りな意匠はなくまぁ普通の部屋だ。

あっ、ここにも鯉が!

常盤館の公式サイト→こちら
常盤館を出て少し走り、「みつあんきょ」を見に行く。平成筑豊鉄道の築堤に空いた3連アーチのトンネル。
正式名は「内田三連橋梁」、1895(明治28)年建造。そこをくぐるのは水路と道路だ。

上流側は石積みになっていてちょっといかつい雰囲気。水切りがついているのでもともとは全幅水路だったのだろう。

くぐって反対側へ出よう。


キツイ逆光!!こちら側はレンガ積みで、将来の拡幅を見据えてゲタ歯になっている。このレンガの外観は
未完成の断面なわけだ。
平成筑豊鉄道はもともと石炭運送のために敷かれた豊州鉄道であった。当時は筑豊地方の各炭鉱から石炭を
運び出すための鉄道が網目のように走っていたのだ。しかし石炭の時代は去り多くは廃止された。
3セクの旅客鉄道として残ったこの路線も複線化されることはなく、石積みの仕上げをされないまま今に至っている。


築堤にはいちめんカラシナの花盛り!!
若いつぼみを探して少し摘む。花もきれいだが、茹でて食べるとめちゃおいしいのだ(笑)

続く。
この常盤館、素晴らしいのはお料理とお庭だけではない。二階にある部屋がすごいのだ!!
実はこの部屋の意匠を見ることが目的だった。友人がこの部屋をリクエストしてくれたのだが、
老朽化しているためここにはお客を泊めることはできないとのことで、見学させて頂いた。

魚の形をしたプレートに「ひこ」、いやいやこれは右から左に読むのだ。「こひ」=鯉の間である。
この形はあまり鯉っぽくないが・・・笑

中は一見何の変哲もない6畳間なのだが・・・

よく見ると、床柱に「鯉之間」という文字が浮き彫りされている。

そしてその下には、木目を水の流れに見立てた鯉の滝登り!木目も自然の」ものではなく完全に彫刻である。

床柱の足元は松かさのような意匠。

床脇っぽい部分の棚や床板もすべて彫刻されている。

床框は四方竹・・・と思いきや、これも木材を彫ったもの。竹の節も再現してあって、ぱっと見はだまされそう。

壁に直接固定された棚は花型というか雲形というか変わった形で、和歌のような文字が彫られている。

落とし掛けにも松の幹と松葉が彫ってあり、一部は着色されている。天井は網代模様の彫刻。

2段になった中央の床の間の床框は、これも皮つきの松を模しているのか?


天井は中央部がわずかに山型に傾斜がついた船底天井。そして窓際の半間分を区切る意匠的な垂れ壁がついており、
そこから天井の勾配が変化しているのは、茶室の掛け込み天井風のアレンジなのか??

その半間分の天井には、なんと将棋の駒が!?

窓のまぐさにも「ヒコ ヒコ ヒコ・・・」。


窓台にも鯉の姿が・・・どんだけ鯉が好きやねん!?笑
お客来い来いとか、滝登りで出世につながる縁起物として、また水とあわせて火事除けのまじないなど、
鯉は古い家によく見かけるモチーフだが、「コヒ」という文字まで装飾に使うとは、ここを建てたご当主が
相当変わり者だったのか、それとも任された職人が変わり者だったのか・・・笑

窓の外側についた欄干は波模様と網代。もちろんこれも木を彫ったもの。

2階には大広間もあって宴会もできる。こちらは特段風変りな意匠はなくまぁ普通の部屋だ。

あっ、ここにも鯉が!

常盤館の公式サイト→こちら
常盤館を出て少し走り、「みつあんきょ」を見に行く。平成筑豊鉄道の築堤に空いた3連アーチのトンネル。
正式名は「内田三連橋梁」、1895(明治28)年建造。そこをくぐるのは水路と道路だ。

上流側は石積みになっていてちょっといかつい雰囲気。水切りがついているのでもともとは全幅水路だったのだろう。

くぐって反対側へ出よう。


キツイ逆光!!こちら側はレンガ積みで、将来の拡幅を見据えてゲタ歯になっている。このレンガの外観は
未完成の断面なわけだ。
平成筑豊鉄道はもともと石炭運送のために敷かれた豊州鉄道であった。当時は筑豊地方の各炭鉱から石炭を
運び出すための鉄道が網目のように走っていたのだ。しかし石炭の時代は去り多くは廃止された。
3セクの旅客鉄道として残ったこの路線も複線化されることはなく、石積みの仕上げをされないまま今に至っている。


築堤にはいちめんカラシナの花盛り!!
若いつぼみを探して少し摘む。花もきれいだが、茹でて食べるとめちゃおいしいのだ(笑)

続く。