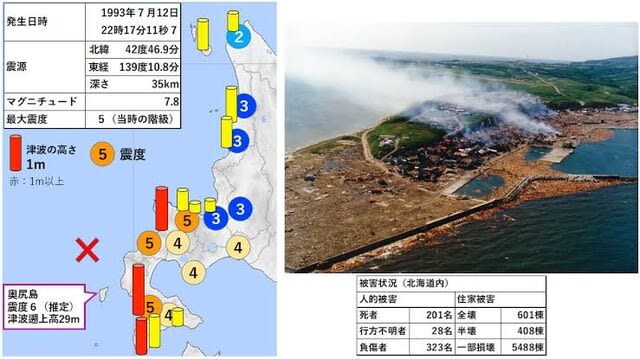224/11/28 thu
前回の章
れっこやうめちん、熊倉瑞穂などの出演立候補により、三章目から、この実在する人たちを使い物語を作るわけだが、二章から期間が空き過ぎた。
読み返してみると一章はどうしょうもないクソの話だけで、あまり面白くない。
コメディ小説を書いているつもりなのに、面白く感じない。
これは致命的である。
このままでは作品として成立しないと感じた俺は、二章をより破茶滅茶にしてみた。
続いて俺は二章もチェックする。
第二章《兄弟》
僕は一人っ子。
家は食堂である。
捻りハチマキを頭に巻いた常連客相手に、パパンが料理を作り、僕が運ぶ。
狭く小汚い店ではあるが、僕ら家族が食べていけるぐらいの収入はあった。
ママンは、一切お店にタッチしない。
どんなに忙しくても、二階で口笛を吹きながら涼しそうな表情をしている。
今日も忙しいのに、ママンはそ知らぬ顔。
食堂内は戦場と化していた。
「注文です。肉焼き一丁、茄子味噌一丁」
「おいす。肉焼き一丁、茄子味噌一丁! ウォンチュ!」
最後につく『ウォンチュ』の意味合いが未だよく分からないが、多分了解したという意味なのだろう。
毎度の事ながらいつも不思議に思う。
「おい、兄ちゃん、水」
「こっちも水、水」
「は、はい、只今」
あちこちのテーブルに水を注ぎながら、「たまにはコーラでも頼みやがれ」と心の中で悪態をついてみた。
「あ、水ちょうだい」
「こっちもちょうだい」
「はい、今行きます」
どいつもこいつも……。
「あらあら忙しいわね~」
階段のほうから声が聞こえたので振り向くと、ママンが目を丸くしてホール内を見ていた。
「ママン、ちょっと手伝ってよ」
「無理無理。私はこれからやらなきゃいけない事があるんだから。頑張ってちょうだい」
薄情なものである。
ママンは食堂という名の戦場の中を堂々と歩き、外へ出た。
ママンの歩き方の癖なのだろうが、お尻をプリプリさせながら歩く。
なので客の大半はママンのお尻に視線が釘付けになる。
「奥さん、いいケツしてるよな~。もうプリンプリンじゃんよ」
「あんなケツに、チクワぶっ刺したらどうなんだろうね?」
「そんな奴はいねえよ」
この平和ボケした馬鹿共め。
ママンはパパンの奥さんであり、僕のママンでもある。
おまえらみたいな汚い連中に、誰がチクワなど刺させるかってんだ。
ガラ……。
入口のドアが開き、うすらデカい大男が入ってきた。
「あっ!」
思わず声を出してしまう。
以前うちに来て、でっかいクソだけして帰った野郎だ……。
あの時は店内大パニックになり、営業ができなかったのだ。
何度流してもビクともしないデカいクソをしやがって、ボケが……。
呑気に大男はメニューを眺めている。
自分のしでかした事の重大さをまるで分かっていないのか?
まず何て言ってやるか……。
《お客さん、先日デカいクソをうちでしてったでしょ?》
いや、トイレだけしかしていないからお客さんではないか……。
《困りますよ、あんなデカいクソだけされたって……》
待てよ。
客じゃないのに、敬語を使うのもおかしいな。
《あのさ~、あんな巨大クソをされても困るんだよね》
ここまでタメ口だと、この大男が怒りだすかな?
喧嘩になったら嫌だし……。
何て言うか考えている内に、ママンが小松菜を鷲掴みにして戻ってきた。
やらなきゃいけない事って、小松菜を摘む事だったのかよ。
うちの店の横には、我が家自慢の大きな花壇がある。
ママンはそこで茄子やら小松菜を作っているのだ。
一日十八回ぐらいは様子を見に行くぐらい、ママンの可愛がりは常軌を逸していた。
「今日のおかずは小松菜のゴマ和えよ」
「他には?」
「何贅沢言ってんの。それだけあれば大丈夫でしょうが」
「え~っ」
ママンの料理はうまいが、いつだって一品しか作らない。
よくパパンは文句も言わず、黙々と食べ続けられるものだ。
口笛を吹きながら、ママンは呑気に二階へ上がってしまう。
「おい、肉焼きできてんぞ! 茄子味噌も」
「へ、へい!」
チクショウ。
この忙しさが恨めしい。
どれだけ忙しくたって、僕の給料には何の影響もないのだ。
早いところ就職口を探してこんなチンケな店から撤退しなければ、僕の未来は暗いままである。
「おい、さっきから注文って言ってんだろ」
巨大クソをした大男がクソ生意気なハスキー声で呼んでいた。
「忙しいから、おまえだけ見ている訳にもいかないんだよ」と怒鳴ってやるか。
ゆっくり息を吸い込みながら、大男に近づく。
「は、はい。何にいたしましょう?」
実際に喧嘩などした事のない僕。
目の前に来ると何も言えず、ただの小心者に過ぎないでいた。
今日も忙しかったなあ……。
仕事を終え、部屋へ戻るとドアの鍵を掛ける。
恒例のテッシュタイムだ。
毎日これだけが楽しみで生きているといっても過言ではない。
以前パパンから仕込みの手伝いをしろと、急にドアを開けられてしまい、恥ずかしい姿を見られた事が三回もあった。
そういった経緯を踏まえ、僕は鍵をつける決意をしたのである。
安月給の中から血を吐くような思いでつけた鍵。
しかしこれでもう安心だ。
さて今日は何をおかずにしようかな……。
『漏らしちゃうの、イヤン!』にするか。
これは何度見ても飽きがこない。
業界ではいまいちの人気だったらしいが、こんな名作は他にないだろう。
「駄目、あなた……。あん……」
「ゲッ……」
薄い壁の向こうから、ママンの声が聞こえてきた。
勘弁してくれよ。
いくら何でもオナニーの時に、実の母親の感じた声など聞きたくもない。
「ママンのお尻、プリンプリンしてて最高だよ」
パパンもいい年して何を言ってんだか……。
十八歳の年頃の息子がいるのもお構いなしに、隣でいきなりおっぱじめる両親。
とてもじゃないが、オナニーなどしていられない。
僕は窓を開け、ぼんやりと夜空を眺める事にした。
「ん……?」
僕の部屋の真下は、ママンが大事にしている花壇がある。
そこへオヤジ二人組が近づいてきた。
息を潜め、様子を伺う事にする。
オヤジ二人は辺りをキョロキョロ見回し、誰もいないのを確認すると、花壇から小松菜を引き抜きだした。
二階から見ている僕に気づく様子はない。
今日のおかずは小松菜のゴマ和えだった。
多分、明日も明後日も小松菜だろう。
うんざりするが、ママンは同じような料理を何日でも続ける。
このまま小松菜を引き抜いてくれれば、明日のおかずは別のものになるかもしれない……。
いや、朝になればママンが大騒ぎするだろう。
それに手塩に掛けて大事に育てた小松菜が可哀相である。
気付けば僕は下に降りて、外へ飛び出していた。
路地の先には、オヤジ二人組が小松菜を手に持ちながら、意気揚々と歩いている。
「待てっ! 待ちやがれ」
僕は慌てて追い駆けた。
小松菜泥棒を見て、知らんぷりはできない。
「何だ、このガキは?」
僕の言葉に振り向いたオヤジたちは睨んできた。
喧嘩などした事がない僕は、咄嗟に怯んでしまう。
「ま、負けないぞ」
「はぁ?」
「おまえたちが持っている小松菜はどうした?」
心臓が飛び出そうなぐらい怖かったが、絶対にママンの大事な小松菜は、この僕が取り返してやる。
「あ、これか? 道端に落ちていたのを拾っただけだ」
「う、嘘をつくな!」
ちゃんとこっちは、うちの花壇から盗んだのを見て知ってるんだ。
「うっせぇぞ、クソガキ」
「じゃあ、小松菜を返せ!」
自分のしている事は矛盾しているのかもしれない。
小松菜を取り戻せば、また明日や明後日のおかずも小松菜になってしまうのだ。
それでも僕は取り戻さなければならない使命感に燃えていた。
「分かったよ。ほら。うるせえガキだ」
オヤジは持っていた小松菜の内、一束だけ放り投げてくる。
ラッキーだ。一束だけなら、ママンもおかずにしないだろう。
いや、そういう問題じゃない。
こいつらは泥棒なのだ。
小松菜泥棒をこのままにしておく訳にはいかない。
「冗談じゃないぞ。その小松菜は、うちのママンが作った大事なものなんだ。とっとと返しやがれ!」
一対二で、圧倒的に不利な状況。
それでも男は背を見せてはいけない時がある。
「行こうぜ。こんなガキ、相手にしていてもしょうがねえ」
勝った……。
僕の気迫に押されてオヤジ二人に逃げていく。
いや、違う。
残りの小松菜も取り戻さなければ意味がないのだ。
「待てっ! 小松菜を返せ」
「け、勝手に拾いやがれ」
オヤジはもう一束を放り投げると、その場から駆け足で逃げ出した。
T字路の路地の突き当りを左に曲がると、姿は見えなくなる。
チクショウ。
僕はママンの大事な小松菜を二束した取り戻す事ができなかった。
次は絶対に承知しないぞ。
翌日になると、ママンが朝から大声を出しながら錯乱していた。
パパンは必死になだめている。
「小松菜が三束ほど花壇から消えている」と大騒ぎしているママンを見て、僕は昨夜の事を思い出していた。
あのオヤジ二人組は、また味をしめて小松菜を盗みに来るだろう。
その時はこの僕が捕まえてやる。
「今日はママンの機嫌が悪いから、おまえもあまり刺激するなよな」
「分かってるよ、パパン。ママンがどれだけ小松菜を愛してきたかぐらい、僕にだって分かるからね」
昨夜の出来事は、誰にも言わないでいた。
この手であのオヤジたちを捕まえてやるのだ。
ここ三日間ほど、小松菜泥棒は来なかった。
夜になりオナニーを我慢しながら、僕はひたすら泥棒が現れるのを待つ。
先日僕が怒ったのが利いたのだろうか。
だとすれば、これ以上、見張っていても意味がない。
今日はゆっくりオナニー三昧としゃれ込もう。
今まで力を入れ過ぎていたので、相当溜まっている。
ズボンを脱いで、畳の上に腰掛けた時だった。
下からガサゴソと物音が聞こえる。
もう両親は寝ているはずだが……。
僕は音を立てずに部屋を出て、忍び足で廊下を歩く。
階段のところまで来ると、「誰かいるのか!」と大声で叫んだ。
ガタッ……。ゴトゴト、バタンッ!
下の食堂に誰かがいる。
僕の声で、慌てて外へ逃げたんだ。
急いで下へ出ると、外からハスキーな声が聞こえてくる。
「誰かぁ~。泥棒よぉ~」
外へ出ると、どう見ても五十歳はいっているオヤジが、女装をした状態で大声を上げていた。
初めて見たが、これがオカマというものだろうか?
「今、お宅から泥棒が……。あっちへ逃げていったわよぉ」
「あっちですか?」
「ええ、じゃあ私は行くわね」
オカマはそう言って去って行った。
夜中なので、辺りを見ても人通りはない。
僕はオカマが路地を左折するのを見届けると、家へ戻った。
「酷いありさまだな……」
両親も降りていて、散らかった店内を見ていた。
しばらくして「あ、レジの金がないっ!」と、パパンが声を荒げ、ママンが「ちゃんと鍵を掛けていたの?」と追求しだす。
「いや、家の中だし掛けてない」とパパンが言うと、ママンは烈火の如く怒りだした。
僕が先ほどの状況を説明すると、ママンは「オカマの人がいた? どこに?」と聞くので、「玄関出てすぐそばにいたよ」と言うと、「ひょっとしたら、自作自演かもしれんな」とパパンが口を挟んできた。
自作自演とは、本来論争中、相手の意見に反論する人を少しでも増やそうとしたり、自分を擁護する意見を自分で行ったりする事。
それによって論争を打破し、自分の主張の正当性を際立たせるというものである。
ひょっとして、あのオカマオヤジが犯人という事だろうか?
「何が自作自演よ。一体いくらレジに入っていたのよ、このトウヘンボクが!」
「ひぃ~、許してママン……」
ママンがパパンの髪の毛を持ち引きずり回しているのを横目に、僕は警察へ電話をした。
警察の調べによると、指紋一つ残っていないプロの手口だと言われた。
結局犯人は見つからず、うちは泣き寝入りをするハメになる。
ママンは大泣きし、パパンはガックリと首を落とした。
冷静に思い出してみると、あのタイミングで外にオカマがいたのはおかしい。
他に誰一人いなかったのである。
四日前は小松菜泥棒。
今日は現金泥棒。
この一週間、うちは被害に遭い過ぎている。
警察に見張っていてほしいところだが、そこまで暇じゃないだろうし……。
「待てよ……」
僕は一つの共通点に気がついた。
小松菜泥棒のオヤジ二人組が逃げていった方角と、オカマオヤジが逃げていった方角は同じなのだ。
何か繋がりがあるかもしれない。
盗まれたものは違うが、盗んでいった人間に共通の匂いを感じたのだ。
だらしない管理をしていたパパンは、ママンに散々怒られ小遣いを減らされたらしい。
馬鹿なパパンは、食堂のメニュー全般を五十円値上げした。
「みんな、本当にすまない。実はうちに先日泥棒が入ってしまってな。値上げせざるえないんだ。申し訳ないが、五十円だけ全品値上げさせてもらった」
来る客に同じような言い訳をして、平謝りに頭を下げるパパン。
見ていて気の毒だった。
常連客の竹花さんは、「気にするなよ。いくらになったって俺は食いに来るって」と励ましてくれる。
「何、本当か? じゃあ、全品百円ずつ値上げとくか」
調子に乗るパパン。
「ふざけんじゃねえよ。これ以上高くなったら、もう食いに来ねえからな」
「何だと? さっきと言ってる事、違うじゃねえか」
「うるせえ。おまえは余計な事しないで、黙々と安い飯を作ってりゃあいいんだよ」
「ふざけるな、この野郎! 偉そうな事言って、この間なんかクソの匂いをちょっと嗅いだだけで逃げやがったじゃねえか」
「当たり前だろうが! 臭いもんは臭いんだよ。そのあとだってちゃんと食いに来てるじゃねえか。これ以上値上げすんじゃねえ」
パパンと竹花さんは、他の客がいるのも構わず、店内で取っ組み合いの喧嘩をしだした。
泥棒騒動から三日間が過ぎた。
僕の予想では、今日辺り何かありそうな予感がする。
夜中になると窓を開け、外の様子を伺った。
横ではまた、パパンとママンが卑猥な事をおっぱじめた声が聞こえる。
呑気なものだ。
息子の僕が家の為に真剣に見張りをしているというのに……。
「ん……。来たっ!」
うちの目の前にあるT字路から、二人の老夫婦が歩いてくる。他に人通りはない。
こんな夜中に歩いているのはおかしい。
案の定、老夫婦はうちの花壇の前に来ると、辺りをキョロキョロ見回しだした。
おばさんは背中にリュックを背負っている。
まさかと思っている内に、「今だ!」という声が聞こえ、おじさんはおばさんのリュックに花壇から小松菜を引き抜き入れだした。
「……」
怒鳴りつけたい衝動を懸命に抑え、僕はジッと様子を伺いつつ、デジカメで証拠写真を撮った。
よし、うまくファインダーに納まったぞ。
老夫婦は、小松菜をあらかたリュックに入れると、最初に来たT字路を戻りだす。
僕は急いで階段を駆け降りた。
警戒していないのか老夫婦の足取りは遅く、僕が外に出た時も、まだT字路を歩いている。
突き当たりまで来ると、老夫婦は左折したので、駆け足であとを追った。
「あれ、いないっ!」
すぐ僕もあとを追ったのに、老夫婦の姿は見えない。
T字路の角にある『居酒屋 兄弟』という店から笑い声が聞こえてきた。
夜中の三時だというのに『兄弟』は看板をつけ、堂々と営業している。
風営法などまるで関係なしといった感じである。
家から三十メートル先にある『兄弟』は、訳の分からない居酒屋であった。
近所の噂だと色々な店を出入禁止になった人間たちの唯一の溜まり場だと聞いた事がある。
幸いに窓が少しだけ開いていたので、覗いてみる事にした。
「……!」
思わず声が出そうになる。
『兄弟』の中には、先ほど小松菜を盗んでいった老夫婦だけでなく、前に小松菜を盗んだオヤジ二人組や、オカマオヤジまでいた。
仲良く同じテーブルに腰掛け、笑顔で酒を飲んでいる。
「あそこにまた小松菜あったからさ。また私らで引っこ抜いてきたよ。女将さん、これ調理してつまみにしてちょうだいよ」
「あそこってレジの鍵、掛けてないからやりたい放題なのよぉ。私なんか、用意周到に一回の見取り地図作っちゃったものぉ~」
オカマオヤジが口に手を当てて「オホホ」と笑った。
一連の騒動は、全部こいつらの仕業だったのか……。
僕は急いで家に帰り、両親の部屋を開けた。
「ば、馬鹿野郎! ノ、ノックぐらいしろ!」
パパンが裸のまま、ママンに布団をかぶせた。
でも僕は見てしまった。
黒い紐で全身を縛られたママンの身体を……。
「そ、それどこじゃないって。また泥棒が来たんだよ。今までの泥棒連中が、『兄弟』って店にいるんだ。パパンも一緒に来てよ」
「うるさいっ! 子供はもう寝なさい。早くドアを閉めろ! 閉めやがれ!」
駄目だ。
卑猥な行為を息子である僕に見られたパパンは、すっかり逆上して話を聞いてくれない。
僕はため息をついて、自分の部屋へ戻った。
確か窃盗罪って、現行犯じゃなかったかな……。
僕は悔しさの余り、朝までなかなか寝つかなかった。
昨夜の出来事を見てしまったからか、パパンは仕事中、一切口を利いてくれない。
「マスター、今日はたっぷり味噌の聞いた味噌チキンカツを作ってくれよ」
昨日喧嘩したはずの竹花さんは、懲りずにうちへ来ている。
いつもなら「息子にオーダーを通せ」と言うのに、今日は「おいっす。味噌チキ一丁。ウォンチュ!」と受けていた。
よほど僕と口を利くのが恥ずかしいのだろう。
「そういやさ、マスター。あの時の巨大クソ、本当に臭かったよな~」
「味噌料理を作っているのに、そういう話題はやめろ!」
この二人は昔からの同級生で腐れ縁らしい。
前にママンがそう言っていた。
ドアが開き、客が入ってきた。
「いらっしゃ……」
何と入ってきたのは『兄弟』の連中だった。
小松菜を盗み、この店のレジの金まで手をつけておきながら、堂々とした表情で入ってくる。
先頭が老夫婦。
次にオヤジ二人組。
そしてオカマオヤジ。
最後に店の女将らしい人間が来た。
女将の髪型は、昭和を彷彿させるような感じで、「それってカツラじゃないの?」と思わず突っ込みを入れたくなるようなものだった。
僕はパパンに小声で伝えようとするが、「仕事中、私語は禁止だ」と取り合ってくれない。
「ちょっと、お水ぐらい早く出しなさいよぉ~」
オカマが偉そうに言ってくる。
「い、いらっしゃいませ……」
唇を噛みながら、僕は必死に我慢した。
泥棒連中は、ビールやつまみをたくさん注文し、楽しそうに飲んでいる。
女将は老夫婦の男に酒を勧めていた。
一時間ほど過ぎ、その男だけを残してみんな帰ってしまう。
散々酔わせておいて会計を押しつけたのは見え見えである。
老夫婦の男は、気持ち良さそうにテーブルへ突っ伏して寝ていた。
その内、店も混みだしてきたので、パパンが「その客、叩き起こせ」と言ってくる。
言われなくてもそのつもりだ。
僕は男を乱暴に起こす。
「うにゃ…。あれ?」
「もうお連れの方たちはとっくに帰りましたよ。ここで寝られても困ります。お勘定だけしといてもらえますか?」
「あ、あ~……。女房が財布持ってんだよな……」
「払ってもらわないと、困るんですけど」
「多分、『とんかつ原田』へ行ってると思うんだ。兄ちゃん、一緒にそこへ付き合ってもらえんかのう?」
「はあ、何で僕がそんな事を?」
「会計はいくらだっけ?」
「一万二千円です」
うちの食堂で一万を超える会計なんて、滅多にない。
それだけ酒や食い物をたくさん頼んだからなのだが、それで金がないは通らない。
「高いのう……」
「大人数でそれだけ飲んで食ったからでしょうが!」
「分かった分かった。じゃあ、『とんかつ原田』へ付き合っておくれよ。そこに、うちのがいると思うから」
持っていない人間からはさすがに取れない。僕はパパンに事情を説明した。
「仕方ない。じゃあ、おまえ行って来い」
「お店、大丈夫?」
「しょうがないだろう。一万二千円、キッチリ取って来い」
「分かったよ、パパン。頑張ってね」
僕は後ろ髪を引かれる思いで、店をあとにした。
老夫婦の男の言う『とんかつ原田』は、歩いて百メートルぐらいの距離にある。
ここの揚げるとんかつはおいしいと近所でも評判であるが、うちの食堂でもとんかつのメニューがある為一度も行った事がなかった。
「そういやあ、おまえさん。原田のとんかつを食った事あるか?
「ありませんよ……」
どうでもいいけど、講釈垂れる前に金を払いやがれって感じである。
僕は早いところ金を徴収して、店に戻らなきゃいけないんだから……。
『とんかつ原田』へ到着すると、男は中へ入り、座敷に座り込んだ。
「ちょっと何をしているんですか? 奥さんは?」
「まあ、いいから若いの…。そこへ座れ」
何だ、こいつは……。
「座れじゃないですよ! 奥さんはどこにいるんですか?」
「いいから座れ! おう、オヤジ。酒を冷で二つ」
「飲んでいる場合じゃないでしょうが!」
「いいから座れって」
店にいる客が僕を白い目で見ているので、仕方なく座敷に上がる。
「ほれ、飲め」
男は金も払っていないのに、偉そうに酒を勧めてきた。
こんなところで時間を潰している暇ないのに……。
だけど金を徴収しないで帰ったら、パパンからもっと怒られてしまうだろう。
仕方なく僕はおちょこを手に取った。
「カンパーイ!」
ひょっとしてこの男、奥さんがここにいると言っていたが、それすらもデマなんじゃないか?
男はいい感じで酔いだし、目も虚ろになってくる。
「おい、若いの。おまえ、ここのカツ食った事ないって本当か?」
「え、ええ…。そうですね……」
その時、ヨボヨボのおじいさんが、ドアを弱々しく開けながら中に入ってきた。
「見ろっ!」
男は、ヨボヨボなおじいさんを指差しながら口を開く。
「あんな死に掛けのジジーだってな~。ここのカツ、食いてーんだよっ!」
「……」
あんな年取ったおじいさんに、何て酷い言い草を……。
こいつ、相当酒癖が悪いな。
「おまえも注文してみろ。ここのカツをよ」
「は、はぁ……」
そんな訳で金を取りに来た僕は、いつの間にか『とんかつ原田』のとんかつを食べる事になってしまった。
「どうだ。うめえか?」
「は、はぁ……」
「若いんだから、もっとシャキッとしやがれ」
「は、はい……」
「こんなうまい料理教えてやったんだから、ここはおまえ、出しとけよ」
「はあ?」
「俺っちはな、宵越しの金は持たない性格でよ」
「何を言ってんですか? うちでも料金を払っていないんですよ?」
「まままま……。細かい事は気にしなさんなって」
「気にしますよ! こうなったら『兄弟』の女将からもらうからいいです」
話にならない。
こんな馬鹿をまともに相手した自分が駄目だったのだ。
靴を履き、帰ろうとすると、肩を後ろから掴まれた。
「おい、ちょっと。会計まだだよ」
店のマスターが渋い顔で手を出してくる。
「あ、すみません。払います。でも、僕の分だけしか払いませんよ」
「一緒に来といて何を抜かしてんだ、あんたは?」
「だって、別に知り合いって訳でもないし……」
「お連れさんは、あんたが会計を払うって言ってるぜ」
「そ、そんな…。あっ……!」
座敷にいたはずの男の姿はいつの間にかいなかった。
僕が『とんかつ原田』のマスターと揉めている間に逃げたのだろう。
納得がいかないまま僕は二人分の会計を済ませ、店をあとにした。
怒り心頭で道を歩く僕。
はらわたが煮えくり返っていた。
うちの店では、六人で飲み食いして食い逃げ同然。
挙句の果てに『とんかつ原田』では、僕が金を払わされた……。
行く先は一つ。『居酒屋 兄弟』だ。
すぐ近所であんな真似をしといて、『兄弟』は堂々と店を開けている。
僕は乱暴にドアを押し、中へ入った。
「あっ!」
そんな強く押した訳でもないのに、入口のドアは、ガタンと外れてしまう。
何てボロい作りなのだろうか……。
「ちょっとあんた! 何、うちのドアを壊してんだい」
昭和の香りを持つ厚化粧の女将が、僕を睨みつけながら怒鳴ってきた。
他にはいつもの面子が座っている。
先ほどの老夫婦の男だけがいない。
「す、すみません……」
「キッチリと弁償してもらうよ」
「は、はい……」
待てよ。
何か立場がすっかり逆転していないか?
「手付けでとりあえず三万円ほど置いていきな」
「そ、そんなに持っていませんよ……」
「冗談はおよしよ。人の店の入り口を壊しておいて、そんなんで済むと思っているのかい?このすっとこどっこい!」
何で食い逃げした奴に、ここまで偉そうに言われなきゃいけないんだ。
もっとしっかりしなきゃ駄目だろ。
「分かりました。ドアは弁償します。だけど、うちで飲んで食べた会計がまだ払われていません。そっちを先にお願いします」
「知らないよ、そんな事は」
「え? だって一緒に来て飲んでいたじゃないですか!」
「たまたま別のお店で飲んでいて知り合っただけだよ。うちの客でもないしね。勘定なら、最後に残っていたオヤジから取るんだね~」
「嘘だ……」
「嘘なんかついたって意味ないだろ。まったくあんたは根性悪だね~」
この僕が根性悪?
言うに事欠いて……。
「ふ、ふざけるなっ! そこにいる連中、うちの小松菜を盗んだり、そっちのオカマオヤジはうちに泥棒に入ったりしただろうが!」
とんでもない連中だ。
僕は溜まっていた怒りを爆発させた。
「は、証拠でもあんのかい? 下手な事を抜かすと、訴えるよ?」
証拠……。
ある……。
老夫婦がうちの小松菜を盗んでいる時、デジカメで撮影しているのだ。
「ちょっと待ってろ。証拠を持ってきてやる!」
「ふん、何が証拠だよ。笑わせてくれるねえ」
女将はおろか、周りの泥棒連中までニヤニヤしている。
僕は猛ダッシュで家へ帰り、デジカメをポケットに入れた。
家の食堂は混雑して、パパンが一人できりきり舞いだったが、構わず僕は外へ出た。
背後から「おい、貴様。何をしてやがんだ!」と怒鳴り声が聞こえたが、あえて無視する。
食い逃げ同然の連中に、言いようにされたのが悔しかった。
あいつらの余裕を奪いたい。
それにはこのデジカメしかなかった。
『兄弟』へ再び戻ると、僕はデジカメの電源を入れ、老夫婦の写る場面を出した。
「ほら、これを見てみろ! 動かぬ証拠だ」
「ほう、ここからじゃよく見えないね~。よく見せてごらん」
女将にデジカメを渡す。
しばらく老夫婦の写る画像を眺めていたが、「あ、目眩が……」と言い、その場に崩れ落ちた。
ガチャッ……。
「あ、デジカメがっ!」
僕はハッキリ見た。
女将が倒れ込む際、デジカメを床に叩きつけたのを……。
作動状況を確認してみる。
しかしデジカメはまったく動かず、スイッチすら入らない状態だった。
「よくも僕のデジカメを壊しやがったな……」
「馬鹿言ってんじゃないよ。あんたが私を突き飛ばしたりするから、転んだんじゃないか」
「何だと?」
「ねえ、みんな。みんなも見てたでしょ?」
女将が客に促すと、みんなも「そうだ。俺たちは見たぞ」と言い出す始末。
あまりの悔しさで、目に涙が滲む。
「あそこの食堂の倅だろ? 今日のところは帰っていいよ。後日、ドアの請求に行かせてもらうから。さっさと帰んな」
食い逃げした金は取れず、大事なデジカメまでも壊され、しかもドアの弁償までさせられる。
僕は敗北感に打ちのめされながら家へ戻った。
メチャクチャ怒られると思っていたが、パパンは冷静に僕の話を聞いてくれた。
「そうか。悔しかっただろうな……。あとはこのパパンに任せておけ」
「ぼ、僕、ぐやじい……」
ずっと堪えていた涙が溢れ出す。
店内の客は、何だ何だと僕を見ている。
「おい、見世物じゃねえんだ。今日のお代はいらねえ! みんな、帰ってくれ」
パパン……。
これほどパパンが偉大に見えた事などなかった。
非常に頼もしい存在。
ガランとした店内には、常連客の竹花さんだけが残っていた。
「おい、竹花ちゃんよ。おまえも帰ってくれ」
「おいおい、冷たいじゃないのさ。俺とおまえの仲だろうが。俺も協力するぜ」
「竹花ちゃん……」
「久しぶりに『肥溜めブラザース』の再結成と行くか」
「ふむ、竹花の…。何年ぶりよのう……」
パパンは遠くを見るような目つきになり、口調まで変わりだした。
パチパチパチ……。
二階からママンが拍手をしながら降りてきた。
「そうよ。事情は上から聞いていたわ。ここはパパンに竹花さん。あなたたちの出番ね」
一体何だ、『肥溜めブラザース』とは?
ママンによると、昔々パパンと竹花さんは、手のつけられない悪ガキだったらしい。
この二人を敵に回すとロクな事にならないと噂され、いつからか『肥溜めブラザース』という異名を持つようになったという。
「腕は錆びついちゃいないぜ、竹花の」
「そうか。ならば『兄弟』とやら、相手にとって不足はないぜよ」
「竹花君、格好いい! さすが私が昔、抱かれた事だけはあるわ」
げ、ママン。
調子に乗って何て事を言うんだ……。
「何? 今、何て言ったんだ、ママン?」
パパンの顔つきが変わる。
「ん、何でもないわよ……」
「嘘をつくなっ! 竹花の奴に抱かれたとか言っただろうが!」
「言ってないわよ」
何だかマズい展開になりそうだ。
竹花さんはその光景を見ながらタバコを吸い、ニヤリと笑っている。
「おいおい、男のジェラシーはみっともないぜ」
「何だと、この豆泥棒がっ!」
「昔の事をレディに、グチグチと聞くもんじゃねえって事よ」
「貴様っ!」
ママンの余計なひと言で、十数年ぶりに復活した『肥溜めブラザース』は、すぐに解散となった。
うん、この章は中々反響があり、評判が良かった。
何しろ、ほとんど実話なのだから……。
まだ家の隣に、トンカツひろむがあった頃の話である。
うちの家から進んだ先に、T字路があり立門前通りにぶつかる。
その左角にきねや食堂という店があった。
豚顔のお姉さんが働いていて、二十歳前後の俺が食べに行くと、決まって「家は継がないの?」と声を掛けてきた。
何度同じ事を聞くのだろう、この人はと思いつつ、毎度「俺は継ぎませんよ」とだけ簡潔に答え、黙々と食べて帰るような食堂だった。
平成初期というのもあり、きねやは本当に安かった。
オムライス五百円、カレーライス四百円、トンカツ定食六百円。
そんなリーズナブルな値段。
当時金の無かった俺は、よくきねやを利用した。
俺が新宿歌舞伎町で裏稼業のゲーム屋をしている頃、きねやの主人が亡くなり、その奥さんと血の繋がっていない豚顔のお姉さんは、店を売って田舎へ引っ込んだと聞く。
そこへ新しく入ったのが『姉妹』という居酒屋だった。
当初俺はきねやが看板変えたのかなと思い、定食を食べに入る。
そこで初めて『姉妹』はきねやと別物であると知った。
安い定食だったので、数日後入ろうとすると、入口で昭和の香り漂うカツラの女将に止められ「うちはね、酒飲まない客はお断りだよ!」といきなり怒鳴られ出入禁止となった。
トンカツひろむへ行った時、俺は姉妹の話を岡部さんにしてみる。
すると「あの店、ほんととんでもねえんだよ」と答えた。
ここからは当時働いていた先輩の岡部さんからの話。
ひろむに、姉妹の昭和の香り漂う女将が五人ほど引き連れやってきた。
散々飲み食いしながら、一人一人席から消えていく。
不審に思った岡部さんが、最後に残った酔っぱらいオヤジにお勘定は大丈夫か聞くと、無一文だったらしい。
ひろむのおはざんに店を任せ姉妹へ走る岡部さん。
そこで会計を請求すると、あの残った客がご馳走するから行っただけで、払う義理は無いと追い返される。
頭に来た岡部さんは、酔っぱらいを車に乗せ、川越警察署まで無銭飲食で連れて行く。
警官の話では、このオヤジ無銭飲食の常習犯のようだ。
警察署へ連れて運転中に「おい、若造! このガキが」と散々岡部さんの頭を小突いていたオヤジ。
金を取れない事が分かった岡部さんは、警官に向かって「もう金はいいから、一発だけ殴らせて」と警察の目の前で堂々と殴って帰ってきたエピソードを聞いた。
小松菜泥棒事件も実話だった。
こちらは実家が被害に遭った話である。
当時まだ結婚していなかった弟の徹也は家の三階に住んでいた。
深夜外で物音がするので窓を開けると、おじいちゃんが花壇に植えて育てている小松菜を引っこ抜く輩を発見。
文句を言いに外へ出て捕まえるも、一束の小松菜を投げた間に逃げられたと俺に言ってきた。
この頃金のあった俺は、三十万円貯まる貯金箱へ、五百円玉のみ貯金してマックスまで金を貯めた。
日頃世話になっているおじいちゃんへプレゼントすると、嬉しかったのか「智一郎からもらった」と居間にその貯金箱を飾っていた。
俺が仕事で深夜新宿へいる頃、家に泥棒が入る。
その時も物音を聞いた徹也が一階まで駆け下り外へ飛び出ると、うちの敷地内の駐車場に一人のオカマのオヤジが立っていて「泥棒よー、泥棒よー」と叫んでいたそうな。
おじいちゃんへプレゼントした三十万円入った貯金箱は、一日で盗まれてしまう。
結局あとで警察の調べで分かったのが、そのオカマオヤジが犯人で窃盗の常習犯らしい。
そのオカマや小松菜泥棒は、すべて姉妹の常連客というのも後々判明した。
そこで岩上整体で暇を持て余していた俺は、その設定をパクって『パパンとママン』の小説に使ったのである。
二章に出てくるトンカツ原田。
ここも実はトンカツ楽天という名店が実際にあり、モデルにさせてもらった。
家の近所にある伊勢一酒店。
そこの店主である松田さんは早稲田大学出のインテリだが、酔うと連雀町一のヤバい酒乱に変わる。
以前提灯祭りの時、俺は変身した酒乱モードの伊勢一さんに捕まり、トンカツ楽天へ強引に連れてかれた。
その時ヨボヨボのおじいさんが楽天に入ろうとするのを見て「見ろ、智一郎! あんな死に掛けたジジイだって、ここのカツ食いてえんだよ!」と叫んだ。
そういった過去のエピソードを集めて書いたのがパパンとママンの二章兄弟だった。
実際に洒落にならない被害に遭ったので、せめてコメディ小説としてネタにしてやらないと、そんな思いが強かった。
岡部さんの店『とよき』の常連客の竹花さんは『パパンとママン』を読み「俺の扱い酷えなあ」と笑っていた。
頭を空っぽにして書く小説が、執筆していてここまで楽しいと思いもよらなかった。
そこで出演希望者を募集してみたのだ。
俺の生活は、大日本印刷印刷、望とのやり取り、執筆と変化する。
ある日仕事行くと、工場長であり課長から呼び出された。
「岩上さん、うちの社員になってくれないかな」
俺は即答できなかった。
大企業の社員。
生活は保証されるだろう。
しかしここで人生を決めてしまっていいのか?
また戦うという道は?
俺がもし本気で戦えば……。
いや、過度な期待を自分にするな。
俺は久しぶりの復帰戦でさえ、相手を気遣い本気で戦えなかったじゃないか。
何日か葛藤している内に、課長は諦めたのか誘う事はしなくなった。
まあ今はとりあえず生活できる金額を稼ぎ、家で小説を書ければいいと割り切る。
夜勤が終わり車で帰る時、飯野君が休みだと朝食へ誘い、彼の家の近くにあるガストで近況を話し合う。
時間が合えば望と会って抱く。
今の生活も、そう悪くないなあと思うようになる。
大日本印刷の社員の一人が、休憩中声を掛けて来た。
工場というただっ広い閉鎖された空間の中、各々がマイペースであり仕事中会話をするという事が無い。
そんな状況で声を掛けられるというのは、素直に嬉しかった。
社員の河村は俺より一つ上。
高校を卒業して大日本印刷へ就職し、現在へ至るらしい。
モサッとした閉鎖的な人間が多い中、河村はとても社交的で男から見ても、中々の色男である。
「岩上さんって他の派遣の方たちと違って、何て言うんですかね? 漂っているオーラが違うと言うか……」
俺はここ最近の一年を簡単に話す事にした。
整体、本、格闘技。
河村は目を丸くして驚き「やっぱり何かあるんじゃないかなって、最初見た時からずっと思っていたんですよ」と興奮している。
同じA班で休みも一緒なので、飲みに誘われた。
彼より二つ年上の彼女を紹介され、居酒屋で酒を飲み交わす。
次に河村お勧めのスナックへ行く。
入る前に言われたのが、河村と彼女は付き合っているというのを隠しているとの事。
狭いスナックだが、飲み屋の女は五名ほどいて、ほぼ満席状態。
この日河村の誕生日だったようで、ほとんどの飲み屋の女が彼にこっそりプレゼントを渡すのを見た。
三軒目の居酒屋へ入ると、河村の彼女は「自分の男が黙って見ていて、どのくらいモテるのかを知りたかった」と説明してくる。
俺にはいまいちピンと来ない感覚だったが、彼らカップルがそれでいいならと気に留めなかった。
有意義な休みを過ごし、家へ戻って明日へ備える。
時間調整だけが、大変な仕事だ。
望も続きを期待しているし、俺は『パパンとママン』三章の執筆を開始した。