パリ協定 (気候変動)
トランプ大統領の声明要旨 パリ協定離脱
米国と米国民を守る任務を果たすため、パリ協定から離れる。米国にとってより公正な協定に変えたうえで、再加入するか、全く新しい枠組みをつくる交渉を始める。交渉をして公平な協定ができるかどうか様子を見よう。それができれば素晴らしいし、できなくてもそれはそれで構わない。
パリ協定は米国に不利な合意に政府が参加してしまった代表例の一つだ。一方、他の国々が利益を得て、私の愛する労働者がコストを負担させられている。そして職を失い、賃金が下がり、工場が閉鎖させられている。
本日をもって米国はパリ協定実施をやめる。大きな負担だった緑の気候基金への拠出もやめる。
パリ協定は米経済にマイナスの影響を与えるだけでなく、環境保護という当初の目的も果たしていない。汚染に加担する国々を規制せず、保護が進んでいる米国を罰するような枠組みを支持できない。中国は温暖化ガスの排出を増やし続けることができる。インドは石炭生産を倍増できる。
パリ協定よりはるかに優れた協定をつくろう。それは米国民だけでなく、世界の人々が喜ぶものだ。それができるまで我々は加わらない。
米国が環境問題のリーダーの立場を維持するよう努める。それはあくまで公正で、負担や責任が世界のどの国も同じになるような条件でのみだ。
米国はいつから威厳を失い、笑われる存在となったのか。今後はそうした扱いを受けることはない。私はパリ市民でなく、ピッツバーグ市民を代表して大統領に選ばれた。今こそ離脱の時だ。米国民や企業を守る新たな協定を交渉し、米国を偉大にしよう。
(2017/6/2 日本経済新聞)
トランプ氏、パリ協定離脱を正式表明「米国に不利益」
トランプ米大統領は1日、ホワイトハウスで声明を読み上げ、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から離脱すると発表した。パリ協定は「非常に不公平だ」として「米国に不利益をもたらし、他国の利益となる」などと非難し、公約実現を正当化した。195カ国が署名した同協定から、世界第2位の二酸化炭素(CO2)排出国である米国が抜ければ、地球的課題の温暖化対策には大きな打撃となる。
トランプ氏は「(温暖化ガス削減の)国別目標の履行や、緑の気候基金(への拠出)を中止する」と表明した。オバマ前政権は温暖化ガスを「2025年までに05年比で26~28%削減する」との国別目標を表明し、途上国の温暖化対策を支援する緑の気候基金に30億ドル(約3300億円)の拠出を約束したが、いずれも白紙に戻した。
トランプ氏は米国民の税金が海外に流れていると指摘したうえで「もう他国の笑いものになりたくはない」と強調。逆に主要排出国の中国やインドは恩恵を受けてきたと批判した。
トランプ氏は先月末の主要国首脳会議(タオルミナ・サミット)など欧州の各国首脳から協定にとどまるよう説得されたが、これに応じず米国第一の主張を貫いた形だ。同氏はドイツのメルケル首相、フランスのマクロン大統領、英国のメイ首相らと相次いで電話協議し、パリ協定からの離脱決定を伝えた。首脳らは「遺憾の意」を示した。
トランプ氏は声明で離脱への意欲を示す一方で「再交渉を始めて公正な協定を結びたい」とも提案した。「米国と納税者を守る新協定」ができれば復帰する考えも示したが、具体的な条件は明らかにしなかった。
メルケル首相を含む独仏伊の3首脳は1日、即座に連名で声明を発表し、「パリ協定は再交渉できない」とトランプ氏の提案を拒んだ。協定に署名した194カ国との再交渉は現実的でなく、実現を疑う声は多い。
パリ協定の規定では、離脱が可能になるのは発効から4年後の20年11月となる。温暖化ガスの排出量で見ても世界2位の米国が離脱すれば、国際協調の機運に悪影響が出るのは避けられない。基金への拠出を中止したことで途上国に波紋を広げる恐れもある。
温暖化対策は世界全体が直面する共通課題として、日米欧などが1990年代から途上国を交えて時間をかけて合意をつくり上げてきた。現在のパリ協定は一律に削減目標を定めるのでなく、各国が目標設定と削減実行を継続的に進める仕組みだ。世界最大の経済大国である米国が「自国第一」を理由に同協定から抜ければ、排出削減の取り組みだけでなく世界的な政策協調の枠組みにも影を落とす恐れがある。
(2017/6/2 日本経済新聞)
米パリ協定離脱「歴史的過ち」 批判広がる
トランプ米大統領によるパリ協定からの離脱表明を受け、米国内外で1日、強い反発が広がった。
首都ワシントンでは抗議デモも発生。一方、炭鉱業が盛んな地域では歓迎の声も上がった。
国連のグテレス事務総長は「とても失望する」との声明を出し「環境問題で米国がリーダーであるのは重要だ」とクギを刺した。「持続可能な未来へ米政府や米国のあらゆる関係者との連携に前向きだ」と指摘した。
昨年の大統領選をトランプ氏と争ったヒラリー・クリントン氏はツイッターに投稿し「歴史的な過ち」と指摘。「離脱は米国の労働者や家族を置き去りにする」と批判した。オバマ前大統領も声明で、トランプ政権が「未来を拒む少数の国に加わった」と批判した。世界でパリ協定に加盟していない国はシリアとニカラグアの2カ国だ。
1日夕にはホワイトハウスの近くで環境団体の呼びかけによる抗議デモが起き、集まった人たちが「気候の危機に目覚めよ」「科学は命を救う」などと書かれたプラカードを掲げ、決断を翻意するよう求めた。
経済界でも批判が広がった。大統領への助言委員会委員を務めるテスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)はツイッターに「委員会をやめる」と改めて表明。「気候変動は真実だ。パリから離れることは米国、世界にとって良いことではない」と投稿した。
ゼネラル・エレクトリック(GE)のジェフ・イメルトCEOはツイッター上で「決定に失望した」とし、「産業界はいまや政府に頼らずに(温暖化対策を)リードしなければならない」と独自対策を進める決意を示した。IBMは「米国が協定に加わるか否かにかかわらず、温暖化ガスの削減に向けた長年の活動を続け、顧客も支援する」とする声明を発表した。
一方、温暖化ガスを多く出す石炭産出地では歓迎の声が出た。ウェストバージニア州のモリシー司法長官は地元メディアに「今回の発表は州内で働く家族にとり大きな勝利だ」と話した。同氏は他州の司法長官とともにトランプ氏に協定離脱を促す書簡を出していた。
(2017/6/2 日本経済新聞)
「間違い」「失望」米でSNSに批判 パリ協定離脱
「間違い」「失望した」――。トランプ米大統領が地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの離脱を発表したのを受け、米国を代表する企業経営者の批判の声がSNS(交流サイト)で飛び交っている。電気自動車(EV)メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)はツイッターで大統領への助言委員会委員を辞めると表明。他社も軒並みトップがコメントを発信し、ネット空間で拡散している。
「パリから離れることは米国にとっても世界にとっても良いことではない」。テスラのマスクCEOはツイッターで委員の辞任を表明しトランプ氏と“決別”。これにとどまらず、「パリ協定のもとで中国も2030年に向けてクリーンエネルギーの創出に動く姿勢を見せていたのに」と残念がった。
アップルのティム・クックCEOは「パリ協定からの離脱は我々の惑星にとって間違いだ。アップルは気候変動と戦い続ける」と訴えた。マイクロソフトのサティア・ナデラCEOも「我々は気候変動が地球規模で取り組むべき喫緊の課題だと信じている。今後もできることをやり続ける」とつぶやいた。
マスク氏同様に大統領助言委員の辞退をツイッターで表明したのが、ウォルト・ディズニーのボブ・アイガーCEOだ。「道義上の理由から辞めることにした」。簡潔な文章から憤りがにじみ出ている。
グーグルのスンダル・ピチャイCEOはツイッターで「今日の決定には失望した。グーグルはよりクリーンで、より豊かな未来のために全力を尽くしていく」と表明した。
フェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEOは「パリ協定からの離脱は環境や経済にとって良くない。我々の子どもたちの将来を危険にさらす」とフェイスブックで発信。「地球温暖化を止めることは世界的なコミュニティーでしか対応できない」としたうえで、「我々は手遅れになる前に一緒に行動しなければならない」と訴えた。
批判はシリコンバレーの企業にとどまらない。ゼネラル・エレクトリック(GE)のジェフ・イメルトCEOは「決定に失望した。産業界はいまや政府に頼らずに(温暖化対策を)主導しなければいけない」と表明。米金融大手のゴールドマン・サックスのロイド・ブランクファインCEOは「(離脱の決定は)環境問題と米国の世界における指導的立場の後退だ」と指摘した。
経済界以外からも離脱を批判するツイートが発信されている。環境問題に対する活動を続けている俳優のレオナルド・ディカプリオ氏は「今日、地球は被害を受けた。今こそ行動を起こすことが何よりも大切だ」と主張した。ドキュメンタリー映画で知られる映画監督のマイケル・ムーア氏は「トランプは全人類に対する犯罪に手を染めた」と激しくののしった。
昨年の大統領選をトランプ氏と争ったヒラリー・クリントン氏は「歴史的な過ちだ」としたうえで、「離脱は米国の労働者や家族を置き去りにする」と批判。雇用を生むと主張してきたトランプ氏の思惑とは逆の効果が生まれる可能性を指摘した。
(2017/6/2 日本経済新聞)










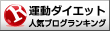

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます