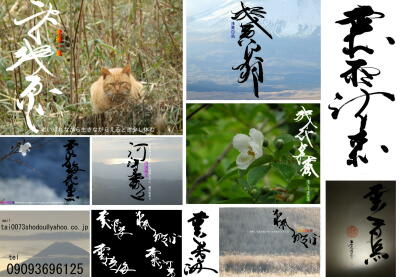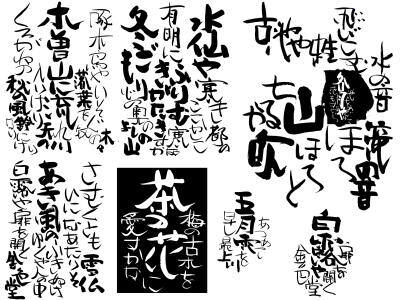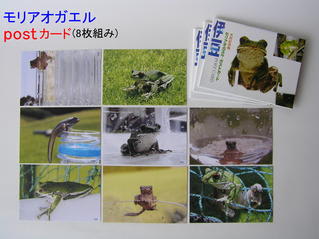箱根路と書
デザイン書道のご依頼はtel 09093696125 mel tai0073shodou@yahoo.co.jo TAIまでお気軽にご連絡ください。
箱根は古くから、江戸時代参勤交代の通過点として、知名度が高く東京の避暑地として、文人・墨客が多く訪れている。
箱根の老舗旅館では多くの書画が残されて、伊東博文・大久保利通・木戸孝允・福沢諭吉・北原白秋・樋口一葉、政治家、経済人、文化人が箱根に「書」を残しているそうで、これだけの有名人の書が残されている場所は全国でも珍しいそうである。チャーリーチャップリン・ビートルズのジョンレノンなど世界的なアーティストが訪れた場所でもあります。
又、軽井沢も避暑地としてイギリス人宣教師により発見され近代人気のリゾート地でよく知られていいる。
箱根は渡り鳥が種を落としていくのか、太平洋側は日差しが強く、又山全体の湿度が高い。
植物の種類が豊富で、鎖国をしていた頃の江戸時代、長崎に滞在していたオランダ商館の医師ケンペルは長崎から参勤交代の途中、箱根の多くの植物に着目し帰国後世界に紹介し日本の近代植物の基礎になっている。植物の種類は箱根だけで約1600種、ニュージーランドと同じぐらいの数があるそうです。
ハコネツツジ・ハコネランと言った独自の名前がついたものも多く、江戸時代鎖国をしていた日本にもかかわらず、富士山も含め箱根の自然は世界へと広く発信されている。
古代において物の利用、発達は居住地で産するものを利用していたようで、石・竹・木・皮など西欧では石が建材として主流で空気は乾燥している。日本では江戸城の基礎石は遠く伊豆半島より船で運ばれ、主たる建材は木であった。竹は高温多湿の気象条件に適し、西欧では育たない。日本は水と米の文化であり、米の生育には水と過去の経験が重要で先祖代々の知恵を親から子へ受け継がれ伝統を大事にし、その土地定住する民族である。西欧の水はまずく、飲めないところもありレストランでは有料で麦が主生産品である。
日本では皮は樹木から、植物より和紙や衣服に利用し、主なタンパク源は肉で、羊を家畜とする欧州では皮・毛で衣服・生活用品などを加工していた。基礎体温が高く、寒さ、乾燥に強い角質層を持ち筋肉量が多い、解りやすく言うと、日本はウエットで西欧のドライした気象環境の違い、演歌とロックと言えるかもしれません。
洋紙に書く筆字はすべりやすく滲みはほとんどないので濃いめの墨がいい、和紙は薄い墨は滲みが速やく、手漉きの古紙は柔らかな滲みが特徴です。湿度の高い気候に適しその調整ができる、和紙の文化と墨、日本の筆、中国の書(漢字)。
中国では古来領土を広げそれを移民族を統一し支配するため情報を共有するに適した漢字の原型・象形文字は読み方は違ってもその意味が伝わる広い国土の多くの人々を統制するのに都合がよかった。日本でも奈良・平安時代の律令政治は中央・地方に渡り、中央集権的官僚制運用のため、仏教・儒教・技術体系に文書主義を導入のため漢字は国家運営や諸国からの税徴収に必要であつた。
日本の筆に対し西欧のカリグラフィー、アルファベットの書形を基本とする、ペンという筆記具は古代、日本の木簡・竹に対し西欧の羊の皮が用紙として利用されていた。皮はペンの紙面に対して横の動き、左から右への平行移動にペンは適している。
竹は米と同じくらい日本文化を代表するもので食糧にもなり武器にもなり楽器にもなり、乾燥した西欧には育たない竹、湿度と高温に関係していると考えられる竹文化は言語伝達のルーツでもあるような気がする。
木・竹の筆記紙面は毛筆の紙面に対し上下筆圧(天地)の動きはクッションの働きに適している、又筆文字は左右の動きも加わりアルファベット(ペン)に比べ漢字(筆)は上下・左右・立体的でえ複雑な動きを必要とする。
西欧のフェンシングの突き・サーベルの切るに比べ日本剣術の動きは曲線的であり立体であるのと同じように漢字(書道)も立体である。
楷書から行書・草書を一つの線にしたとき日本のひらがなが出来上がり、漢字が一字一字その意味を持つている表意文字に対し英語・外来語と同じ表音文字の「ひらがな」は順応な日本独自の中国にはない文化の表だといえる。
又表意文字・表音文字同時に併用している日本人はアジアでも特異な民族といわれて、日本語の漢字ひらがなは立体的、空間描写に優れているように思う。
新聞を見たとき漢字を追うことで全体のイメージが理解できることも便利である。
ただ書道は和装きもの、茶道、弓道と同じく本来の機能から離れた伝統文化、非日常の時間でありノスタルジー又精神文化を魅了するもので、コンピューターのような日常不可欠な合理的道具ではない。
軽井沢に対し箱根は湿度が高い、乾燥した軽井沢が「ペン」とするならば箱根は「筆」と言えるかもしれません。
箱根強羅駅を登ると演歌歌手矢代亜紀さんの別荘があり大文字焼きの見える山並みには井上陽水さんの別荘がある。同じ伊豆半島の伊豆高原は湿度も少なくタモリさん、ジュディオングの別荘があり福山雅治さんはよく来てるらしい。
人もドライタイプ・ウエットタイプに分類できるかもしれません.