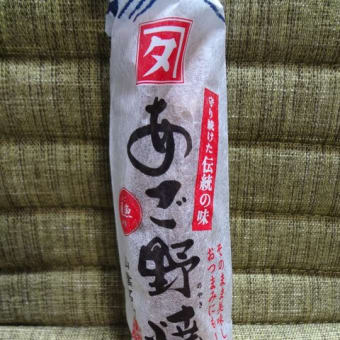第2回目になりました、出雲弁講座です。前回にもお伝えしましたが、この講座はあくまでも「島根県松江市に18年間住んでいた出雲弁ネイティブスピーカー」の私見がふんだんに盛り込まれています。地域により差異があることをご了承ください。
Ⅰ、だんだん‥これは出雲弁を語る上では避けて通れないワードです。意味としては「ありがとう」です。某連続テレビ小説のタイトルにもなりましたので、島根に縁遠い方でもご存じかと思います。
ただ、若い人はあまり使わないかと思います。50歳以上の、島根県でも比較的田舎の方でしたら日常使いされている方もいます。でも若い人達も使いはしませんが、「だんだん=ありがとう」だとわかるぐらいには認知度も高く、街中の広告等にもだんだんは溢れています。
ちなみに、「ありがとう」は”だんだん”と言い換えますが、「ありがたいことに」を”だんだんなことに”とは言い換えません。これは”あーがたい(ありがたいの訛化)ことに”となり、昔から”だんだん”という言葉しか無かったわけではなく、「ありがとう」という言葉もキチンと生活の中で地位を確立しており、各々が平行して発生したと思われます。
あと余談ですが、この方の「だんだん」という曲、とてもいい曲です。聞いてみてください。前の曲になりますが、島根県の方が歌手です。「だんだん」という言葉が持つ温かさを表現しており、出雲弁スピーカーが持つ出雲弁に対しての矜持であったり優しさを感じさせてくれます。もし気になりましたら聞いてみてください。
http://musia.net/loco&ichiugawa/loco_prof.html
Ⅱ、ちょうかんぼう‥これは、お腹に異変が出る風邪を指します。上記から急に趣が変わりましたが、これが自分が出雲弁だと知って一番ビックリした言葉です。たぶん漢字にすると、腸感冒になるかと思います。
感冒(かんぼう)とは風邪という意味なので、意味合いとしてはお腹にくる風邪で問題無いと思うのですが、それと腸がくっついた腸感冒という言葉は、医学用語にはもちろん国語辞典にもありません。完全に島根県内でのみ通じる言葉です。ですが、あまりにも私たちの生活に根付いていたので、お腹の調子が悪く病院へ行った際にはお医者さんに「お腹の調子が悪いので、”ちょうかんぼう”かもしれません。」とフツーに伝えていました。島根県外から赴任されたお医者さんだったら、さぞ意味不明だったことでしょう。
やはり体調を表す言葉には独特な方言が多く「ぞんぞがさばー」や「あいまちした」等があります。形の無いものは表現しずらいので、地域により特色のある方言になりがちですね。