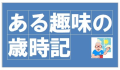江戸のころ‥‥
うなぎを食べるには
「店内での飲食」・「店頭での販売」・「出前専門店」がありました。
「寿司」「蕎麦」「天ぷら」とともに江戸4大名物であった「うなぎ」
しかし、江戸の庶民たちが気軽に楽しめる食材ではなかったようです。

【高級食材「うなぎ」をめぐる裏事情】
丼物の魅力は、ご飯とおかずが一緒に食べられることで
忙しい時に簡単に栄養のある食事をとることができます。

忙しいのに美味しいものは食べたいとアイデアを生み出したのは
「大久保 今助」文化年間(1804)に、考案したといわれています。
「大久保 今助」は、常陸(現茨城県)の農民で
江戸に出て水戸藩御用達として財を成し、歌舞伎の興行主となりました。
忙しくて食事に出かける時間がなかったので
うなぎを芝居小屋に出前させたのが始まりです。

しかし、「うなぎ(今の蒲焼)」だけでは
運んでいるうちに冷めてしまいます。
冷めてしまっては、あまりおいしくないうなぎ。
そこで、温かいご飯と一緒に注文することを思いつき
うなぎをご飯の間に入れたのが、始まりだといいます。

「うな丼」という呼び方も明治になってからのもので
江戸時代は、「うなぎ飯」や「どんぶり」といい
" うな重 " も江戸時代にはまだなく
この「うなぎ飯」は、よほど美味しかったようで
あっという間に上方まで伝わったと云います。

ただし、江戸で名のある高級店ではそのブライトが許さなかったのでしょうか
いくら人気があっても、この「うなぎ飯」を出さなかったといいます。
【江戸前とは】
「江戸前」というと現代人は、九分九厘「すし」を思い浮かべるでしょうが
江戸(現東京)のおひざ元の海で獲れた魚を使った握りずしという意味です。
実は、江戸前=すしとなったのは明治以降のこと。
江戸時代には、「江戸前」はうなぎを指す言葉でした。

【起源は】
古く、奈良時代の「歌人 大伴家持」が知人に勧めたという記録が残っています。

【さばき方】
当初はぶつ切りにして食べていましたが
上方は「腹開き」、江戸では「背開き」今も変わらぬ武士の作法です。

【どうして夏の「土用丑の日」に食べるのか?】
有名な逸話として、「幕末の学者・平賀源内」が
夏に売れないウナギ屋にすすめた宣伝方法が
大当たりしたのが始まりと言われています。
このころからうなぎを「江戸前」と呼ぶようになり
うなぎの人気が出て来たのかもしれません。

【江戸前うなぎは、どこでとれたものか?】
現在の品川から深川にかけて取れたものというのが一般的なようです。
ここ以外でとれたうなぎは、「旅うなぎ」といってワンランク落ちるものとされていました。

【江戸時代のうなぎの値段】
最近は様々な要因からうなぎは簡単に口にできる値段ではなくなりましたが
江戸時代もうなぎ飯は一般的な店で「1杯64文(約1920円)」
気軽に食べられる値段ではなく
「うなぎ飯」を出さないような、高級店ではもっとうなぎは高かったそうです。

このため庶民はもっぱら屋台で売っている「1串16文(約480円)」を買って
美味いうなぎを賞味したそうです。
ウナギの美味しいのは冬から、この時期がおすすめです。

🔴「趣味の歳時記」ここをクリックすれば、見ごたえあるもう一つのブログ。お待ちしています❣️❣️
◯「初版 ひとり ときどき ふたり散歩」は、こちらをクリック❣️❣️
下記リンクは、「ピクスタ(写真販売)」こちらをクリック!