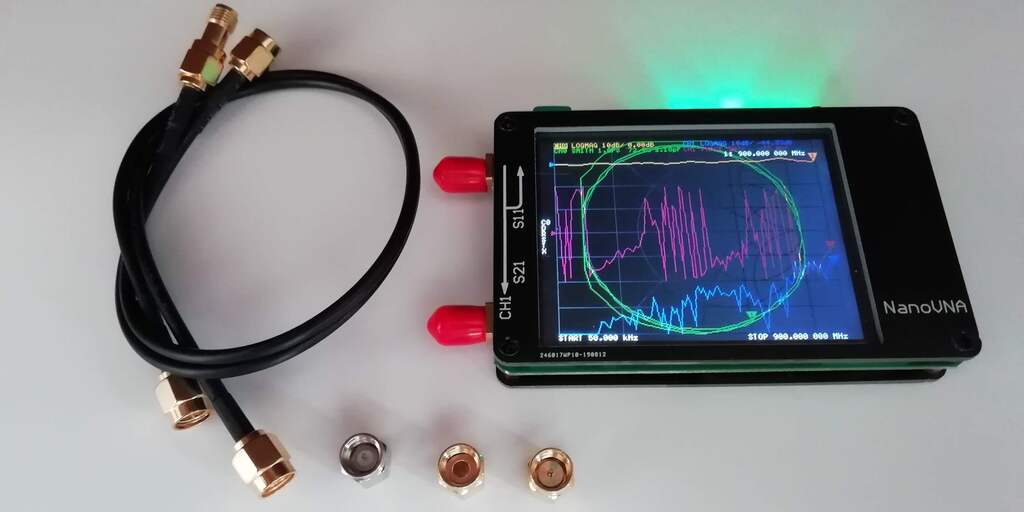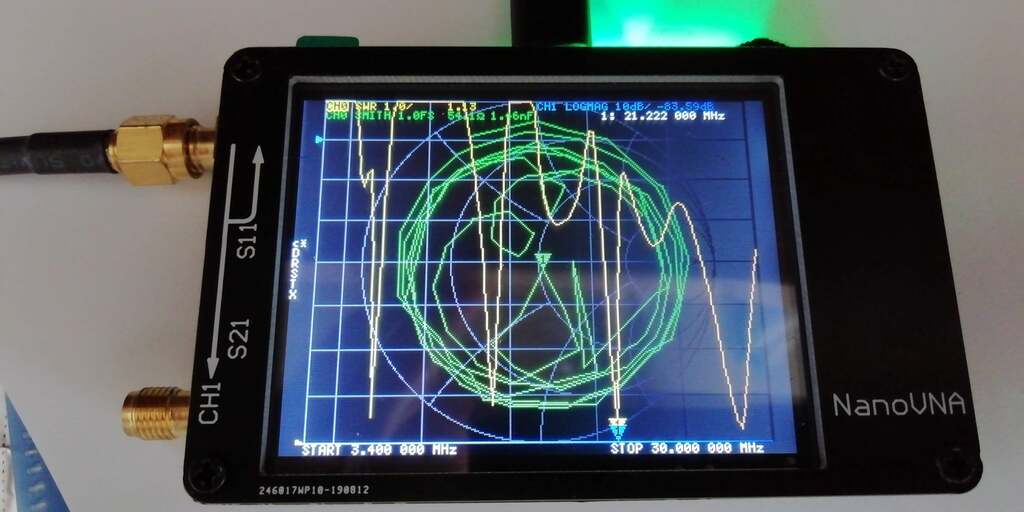局免許の変更申請のメモです。
私の場合、来年(2021年)の4月で現在の局面が切れるので、継続させるためにはその一カ月前までには更新手続きをしないといけません。今回は、新スプリアス規制の猶予期限が今回の次の更新期限までに来てしまうので、どっちにしても新スプリアス規制をクリアするRigで局面更新しないと、電波が出せなくなります。それに先立つ、変更申請のメモです。
(再免許の時には、原則申請に係る変更を同時にできません。軽微な変更は可能ですが、送信機とかの構成に係る変更はできません。なのでそれに先立って変更申請が必要になります)
方針:
(1) 新スプリアス規制に対応したRigに変更する。
(2) 現在申請してあるRigはすべて撤去して、新たにHF+50Mは、IC-756PROを50W改造して保証認定を受ける、V/UHFはIC-T90(新スプリアス対応品)を追加、すでに許可済のデジタル通信系認可を継続する。これで1.9から430MHzまでをカバーする。
(3) 保証認定は前回もIC-756無印の50W化保証認定でお世話になったTSSで行う。(保証認定をしてくれる組織にはTSS以外には、JARDがあります)
・IC-756PROの50W化
これは以前IC-756無印でやったことがあるので、OMさんから電力計をお借りして、ICOMサポートに連絡して100W→50W改造法を入手、改造、確認でやりました。IC-756無印とIC-756PRO(一世代違うだけ)では、改修する制御基板が異なる(回路が違う)ことが後でわかりました。改良されているようです。
ICOMサポートからは、すでに保守終了品なので、ご自分でやってください、とのメモが入っていました、、。チップ抵抗を二か所はんだ付けして、あとは電力計を見ながらVRをそれぞれ調整。あとは各周波数で最大電力が50Wになっているかのチェックと証跡取り。
これらの証跡をもとに、TSSへの保証認定依頼文書を作成し、TSSに依頼します。依頼文書には、学生の時の実験レポートみたいですが、何を依頼するか、いつ、だれがやったのか、何をもとに改造したのか、その結果はどうだったのか、などを記載します。私は依頼文書に貼付資料として、各周波数表示とその時の電力を写真に撮ったものを付けました。
ちなみにIC-756PROは新スプリアス規制に対応できる仕様を有していることがわかっています(総務省のホームページに記載あります)が、今回は50W化改造をするので、改造+新スプリアス規制対応の保証認定、という位置づけになります。
・TSSでの保証認定
TSSでの前回の保証認定時と変わっていたのは、今回は、総合通信局に申請する申請書を事前に作成して、それを添付して保証認定依頼をする方法になっていました。前回は、保証認定してもらいたいものだけを認定してもらった(あとの通信局との調整は自分でやる)記憶があったのですが、今回は、保証認定の結果が変更申請にどうかかわるかまでチェックしてくれました。自動車の運転免許更新でいうと、代書屋みたいな位置づけですかね、、使ったことはないですが。
今回の変更申請は、IC-756PROの50W改造とIC-T90の追加、がメインですが、TSSではその両方を含めて総合通信局への申請書をもとに資料の修正までやってくれました。(WEBで色々と先人の記事を見ると、TSSでは、単に現在申請済のRigの新スプリアス対応保証認定だけのものはやってくれないようです。今回はIC-756PROの改造と追加、IC-T90の新規追加なので問題なし。)
修正箇所は、1.9M帯の発射が許容される電波形式が3.5M帯と同じになったので、それを追加、IC-T90の送信電力は5Wなのですが、10W以下は10Wに整理されるとのことでその対応と、電波形式がFMだけなので一括符号の修正などでした。
10/30の夜(金曜日の夜)にTSSに提出して、11/10(火曜日)に上記の連絡があり、11/13(金曜日)に保証認定書が届きました。途中文化の日の祝日なども入っていますので、実質1Weekから10日程度かかったことになります。
変更内容の趣旨をきちんと理解してくれ、丁寧な仕事してくれたと思います。また機会があったらTSSさんを使おうと思います。
保証認定書が届いてすぐに関東総合通信局に変更申請を出しました。今日で申請して2Weekたちましたが、まだ処理中です。ほぼ同時期に変更申請をした友人は、すでに通信局から納付の通知が来たそうなので、間もなく来るのではと思います。
・変更申請時のTips
(1)変更申請は、総務省 電波利用 電子申請 lite というものを使っています。
前回までの申請情報の履歴および内容がDownloadできるので、何も変更がない時の更新手続きなどは至極簡単です。
(2)申請書類をローカルに見たい時がありますが、XML形式なので見ずらいのですが、「DLitePrinter」なる申請書のXMLをPDFに落としてくれるものを作ってくださった方がいらっしゃいます。それを探してDownloadして起動し、上記からDownloadした過去の申請書類のzipファイルをそのまま食わせると、その内容がPDF化されて表示されます。先駆者に感謝です。
(3)過去の申請書をDownloadして、zipファイルを解凍した場合に、解凍したファイルのファイル名が文字化けすることがあります。これは、Lhaplusなどのアプリで解凍すると、ファイル名がUTF-8を理解できないために文字化けをするようです。
文字化けする場合は、圧縮/解凍アプリが何かを確認して、ファイル名がUTF-8を理解するアプリを使ってください。WindowsのExpolerは文字化けしません。7-Zipも大丈夫です。
何かのご参考になれば。
2020/12/11以下追記:
2020/11/14にLite経由で変更申請を提出して、2020/12/8に変更完了の連絡が来ました。土日も入れて、約3.5週程度かかりました。
変更申請が完了したので再免許の申請をしましたが、変更してあるので、申請処理は、3分と掛かりませんでした。この調子でゆくと再免許処理の完了は年明けですかね。
2020/12/26以下追記:
局面再申請は、2020/12/11夜に申請Liteで申請し、翌営業日2020/12/14に審査終了、当日Payeasyで申請料送付、2020/12/17に審査終了、翌18日に返信用封筒を送付して、12/22消印で12/23に新しい免許状が到着しました。営業日で10日ほどで完了しました。ご参考まで。